社内アンケートの具体的な質問例を厳選7項目38問で紹介!作成時の注意点とは?
更新日: 2025.7.15 公開日: 2022.11.11 jinjer Blog 編集部

日々のなかでは、従業員が業務や自社についてどういった思いを抱いているかを知る機会が少ないものです。従業員の不安や悩みを引き出せないままだと、離職にもつながりかねません。従業員が定着する働きやすい職場にするためには、社内アンケートの実施が効果的です。
今回は従業員を対象にして社内アンケートの質問例と注意点を紹介します。
目次

人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」という人事担当者の方に向けて、ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法を解説した資料を無料配布しています。
従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 社内アンケートの質問を構成する2つの要素
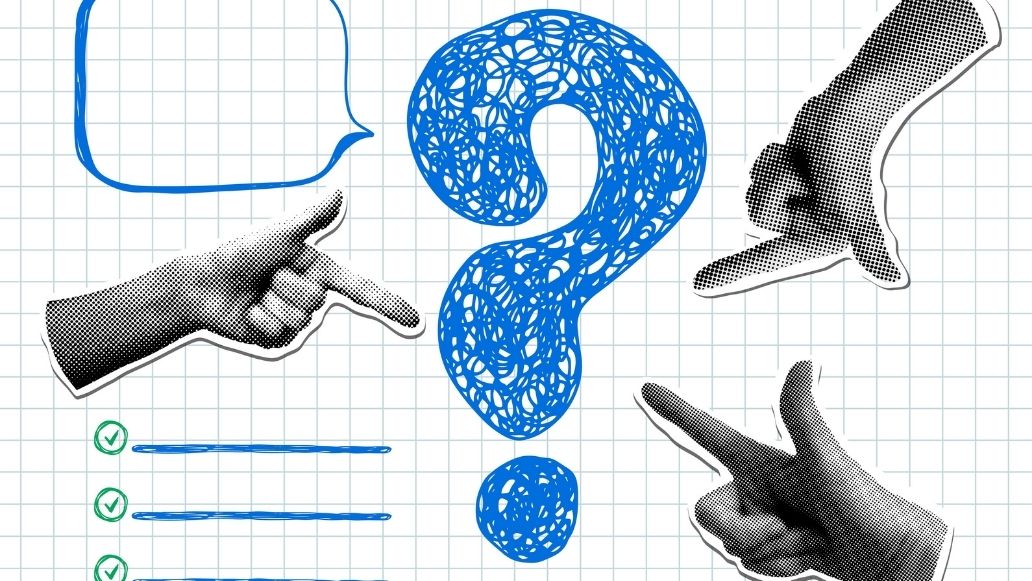
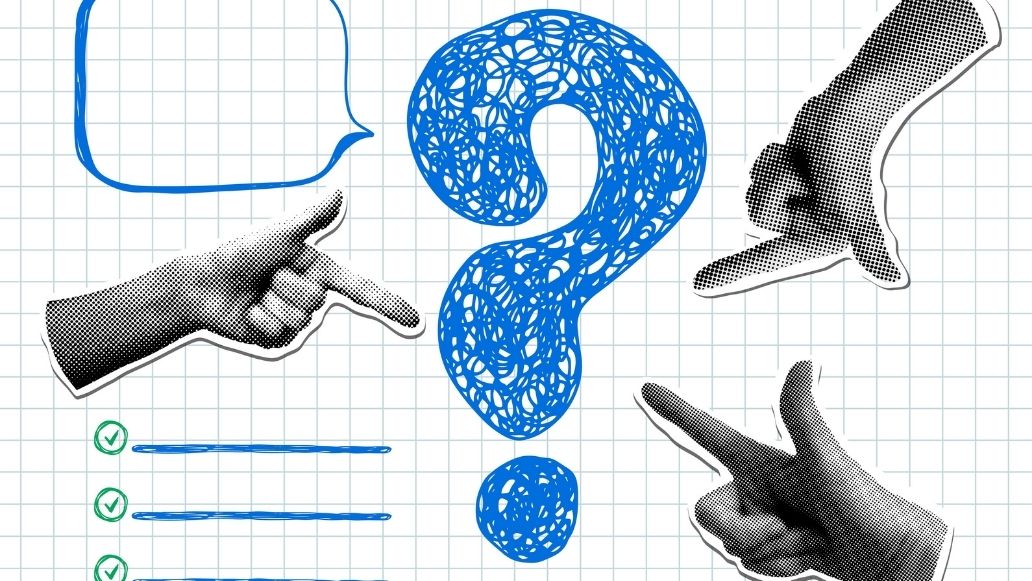
まず社内アンケートの質問例を考える前に、アンケートをおこなう目的から明確にしておく必要があります。社内アンケートをおこなう目的とは従業員満足度を計測することです。
そしてこの社内アンケートで測るべき従業員満足度は、「動機付け要因」と「衛生要因」に分けられます。両者をわかりやすく説明すると、次のように異なります。
- 動機付け要因:達成感や責任、昇進など満足度に関わる要因
- 衛生要因:職場環境や給与、人間関係など不満足に関わる要因
例えば、業務を達成したことで誰かから認められれば従業員は仕事に満足感を抱くでしょう。一方、給与に不満を感じている従業員を昇給したとしても、不満は解消されても満足感にはつながりません。このように、社内アンケートでは次のように動機付け要因と衛生要因で質問を作成し、何についてのアンケートにするか目的を明確にする必要があるのです。それぞれの要因について、詳しく説明します。
1-1. 動機付け要因とは
動機付け要因は、従業員が仕事に対してより高いモチベーションを持ち、ポジティブな姿勢で業務に取り組むための基盤を提供します。具体的には、達成感や承認、仕事内容そのものの魅力、責任の感覚、昇進の機会等が含まれます。
例えば、達成感は目標を達成することで得られるもので、仕事の重要性を感じる際に生まれる要素です。言い換えれば、従業員が自分の努力が認められる瞬間があると、さらに仕事への意欲が高まります。承認も同様に、上司や同僚からの評価が高まることで、自己肯定感が向上し、さらなる前向きな行動を促進します。
仕事内容そのものも大きな要因です。自分が興味を持てる業務や、チャレンジングな仕事は、従業員が自発的に取り組む原動力となります。また、責任感を持つことで、自分の役割の重要性を追求し、より良い結果を求めるようになります。昇進の機会があれば、キャリア成長の可能性を感じることで、日々の業務に対するモチベーションがさらに向上します。
このように動機付け要因に基づくアンケートを実施することで、従業員のモチベーションを引き出す施策を明確にすることが可能になります。このような結果を上司に提示することで、具体的な改善策を講じやすくなり、個々の従業員に対して適切なマネジメントをおこなうための基盤を築けます。社内アンケートを通じて得られたデータは、企業の成長戦略や従業員のエンゲージメントを高めるための一助となります。
1-2. 衛生要因とは
衛生要因(ハイジーンファクター)は、従業員が不満を抱える理由として広く知られており、そのため、職場環境を改善するための施策を検討する際には欠かせない視点となります。
具体的には、衛生要因には会社の経営状況やマネジメント、監督技術、給与、対人関係、就労条件、職場環境といった要素が含まれます。例えば、従業員が十分な給与を受け取っていない場合や、上司とのコミュニケーションが不足している場合には、仕事に対する不満が高まることがあります。これにより、離職率が上昇するというデータもあり、衛生要因に対策を講じることは非常に重要です。
しかし、衛生要因を改善しても、必ずしも従業員の満足度が向上するわけではありません。改善した結果、不満が解消されるためマイナスはゼロに戻りますが、満足感やモチベーションがの向上には結びつかないという特性があります。このため、衛生要因に基づいた施策を講じるとともに、動機付け要因を併せて考慮することで、真の従業員のモチベーション向上を図る必要があります。このようにして従業員の不満を特定し、改善策を実施することで、離職率の低下が期待されます。
2. 社内アンケートの具体的な質問例を7項目38問で紹介!


ここでは「動機付け要因」と「衛生要因」に分けて、具体的な質問例を7項目にわけて38問紹介します。
- 業務内容に関して:動機づけ要因
- 成長に関して:動機づけ要因
- 社風に関して:衛生要因
- 会社の制度や評価に関して:衛生要因
- ワークライフバランスに関して:衛生要因
- 心身に関して:衛生要因
- コンプライアンスに関して:衛生要因
2-1. 業務内容に関して
業務内容に関する質問は、従業員が与えられている業務に対してどれだけ満足しているかを測ります。この項目の数値が高い従業員であれば、意欲があり従業員満足度が高い状態にあるといえます。
業務内容についての質問として次のようなものが考えられます。
- 仕事にやりがいを感じている
- 仕事が自分の適性に合っている
- 仕事のなかで達成感や満足感を得ることができる
- 仕事が認められたうえで、適切な評価を得られている
- 仕事に自分の考えや意見を反映できている
- 仕事においてスキルや能力を高められる環境がある
2-2. 成長に関して
成長に関しては、日々の業務の中で成長を実感できているかどうかを確認します。この他にも、スキルの取得や成長スピードなどに関しても質問しましょう。
- 現在の業務が成長につながっていると感じる
- スキルアップが図れる仕事だと感じる
- 自分の適性や得意分野が活かせている
- 成長するために何をすべきか理解できている
- 仕事を通じて新しいことを学ぶ機会がある
2-3. 社風に関して
社風に関する質問では、コミュニケーションやチームワークがある環境か自主性を発揮できる環境かといった職場の雰囲気にどれだけ不満があるかを把握します。
- 自分の意見を自由に言い合える雰囲気がある
- 自主性を尊重してくれる
- 向上心や成長意欲が評価されている
- 社内の人間関係は良好で相談しあえる雰囲気がある
- 問題が起きた際に周囲からのサポートがある
2-4. 会社の制度や評価に関して
会社の制度や評価については、給与や評価制度が関わるため、衛生的要因のなかでも重要な項目です。給与や評価制度に加えて、キャリア支援についてもこの項目で質問しましょう。
- 給与は現在の業務内容や仕事に対して納得できる
- 自分は正当かつ公正に評価されていると思う
- 人事制度や評価について多くの社員は納得していると思う
- キャリア形成のための制度が整っている
- キャリア形成についての相談機会がある
2-5. ワークライフバランスに関して
業務量が多いことで、ワークライフバランスが崩れていないかを確認しましょう。
多様な働き方によって仕事と生活を調和させることが求められている現代では、重要な項目です。
- 過大な業務の負担を強いられることはない
- 自分に与えられる業務量は適正だと思う
- 残業時間は無理ない適切な範囲に収まっている
- 所定の休日・休暇は適正だと感じている
- やむを得ない欠勤や早退に対応してくれる
2-6. 心身に関して
心身については、日々の業務で心身を害していないかを確認します。会社の制度や評価に関する項目と同様、衛生要因のなかでも重要な割合を占める項目です。
業務に関してなにかしらのストレスを感じている人は多く、厚生労働省「令和4年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」では、82.2%もの人が仕事において「ストレスとなっていると感じる事柄がある」と回答しています。
心身に関しては、次のような質問を用意しましょう。
- 業務は身体的な健康に悪影響を与えない
- 自分の身体的な特徴を配慮したうえで業務ができている
- 現在の業務は体力的に余裕をもって進められている
- 現在の業務は精神的に余裕を持って取り組めていて、過度なストレスはない
- 仕事上の悩みや課題を解決する方法がわかっている
- ハラスメントを受けた、ハラスメントの現場を見たことはない
参考:「令和4年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」| 厚生労働省
2-7. コンプライアンスに関して
会社にはコンプライアンスの遵守が求められています。この項目では、法令遵守が軽んじられていないかを質問しましょう。
- 自分が知るすべての業務は法令を遵守している
- コンプライアンスについての教育指導や管理体制が整っている
- コンプライアンス違反に対しての相談窓口や相談できる体制が整っている
- 機密情報は適切に管理されている
- ハラスメント対策は適切におこなわれている
このように、社内アンケートをおこなう際には、改善すべき項目を理解するためなどの目的をしっかりと設定したうえで調査しましょう。
当サイトでは、適切な質問項目の設定の方法や、アンケートを取った後に企業がすべきことをまとめた資料を無料で配布しています。
社内アンケートをおこなう上で設問にお悩みの方は、こちらから「従業員満足度のハンドブック」をダウンロードしてご活用ください。
3. 実効性を高めるためのチェックリストとポイント


社内アンケートを「形骸化させない」ためには、質問設計の段階から「実効性」を意識する必要があります。
ここでは、従業員の本音を的確に捉え、具体的な組織改善に繋げるための、チェックリスト形式での質問設計のポイントと、その際に留意すべき点を解説します。
3-1. 質問設計チェックリスト:このアンケートは「本音」を引き出せるか?
社内アンケートの質問を設計する際は、以下のチェックリストを参考に、一つずつ確認をおこなうようにしましょう。
- 質問は客観的で中立的か?
- 質問は具体的で簡潔か?
- 回答形式は適切か?
- 質問数は最適か?
- 匿名性は確保されているか?
それぞれ詳しく解説します。
質問は客観的で中立的か?
特定の回答へ誘導せず、中立的な表現を心がけましょう。従業員が安心して本音を語れるよう、公平な立場で質問を作成する事が重要です。回答の信頼性を高めるために不可欠です。
質問は具体的で簡潔か?
曖昧な質問は避け、具体的な行動や状況に焦点を当てましょう。簡潔な表現で誤解を防ぎ、的確な回答を促せます。これにより、具体的な改善策を導き出しやすくなるでしょう。
回答形式は適切か?
目的に合わせ形式を選びましょう。定量把握には選択式、具体的な意見には自由記述が有効です。バランス良く組み合わせ、多角的な情報を収集します。従業員が回答しやすい形式を選ぶ事も大切です。
質問数は最適か?
質問過多は従業員の負担となり、回答率低下を招きます。回答時間の目安を設定し、質問数を厳選しましょう。本当に必要な情報に絞り込む事で、回答率向上に繋がります。
匿名性は確保されているか?
従業員が安心して本音を語るには匿名性が最も重要です。特定を恐れず率直な意見が出るよう、システム設定で匿名性を徹底し、事前に明確に周知しましょう。回答の信頼性と精度向上に不可欠です。
3-2. 本音を引き出し、実効性を高めるためのポイント
上記のチェックリストに加え、質問設計の質をさらに高めるためのポイントも押さえましょう。
- 質問は客観的で中立的か
- 質問は具体的で簡潔か
- 回答形式は適切か
- 質問数は最適か
- 匿名性は確保されているか
社内アンケートで従業員の本音を引き出し、その結果を組織改善に繋げるには、質問設計が鍵となります。
まず、質問は客観的で中立的におこない、従業員を特定の回答へ誘導しないようにしましょう。これにより、安心して率直な意見を得られます。次に、具体的かつ簡潔な表現を用いる事で、曖牲さをなくし、的確な回答を促すことが可能です。
回答形式は目的に合わせ、定量と定性(自由記述)のバランスに注意します。多角的な情報を引き出すために適切な形式を選びましょう。
また、不要な質問や重複する内容はなくすことで従業員の負担を軽減して回答率を上げられます。
そして最も重要なのは、回答の匿名性を確実に保証することです。従業員が安心して本音を語れるよう、システム設定と事前周知を徹底します。これらのポイントを押さえることで、社内アンケートは真の組織改善を促す強力なツールとなるでしょう。
4. 社内アンケートは目的に応じた質問を作成しよう


社内アンケートは業務内容についてか、社風についてなのかなど、目的を絞ったうえで質問を作成しましょう。質問が多くなりすぎると、回答する意欲を下げてしまい、アンケートの精度が落ちてしまいます。
正しくアンケートをとったら、その結果に対しての施策を講じて従業員が働きやすい環境を整えましょう。



人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」という人事担当者の方に向けて、ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法を解説した資料を無料配布しています。
従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
サーベイの関連記事
-


離職率の計算方法とは?厚労省方式と実務での算出・活用ポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.10.10更新日:2025.10.09
-


離職率が高い会社の特徴は?業界別ランキングと離職率を下げる施策を紹介
人事・労務管理公開日:2025.10.09更新日:2025.10.09
-


360度サーベイとは?概要と他制度との違い・導入メリットと注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.10.08更新日:2025.10.09






















