借入金とは?借入金の種類や意味、金利や返済まで網羅的に徹底解説
更新日: 2024.5.23
公開日: 2022.5.11
jinjer Blog 編集部

事業を進めていくうえで必要不可欠なのがお金です。自己資金で賄える場合もありますが、そうでない場合は人からお金を借りたり、銀行から融資してもらったりすることも珍しくありません。これが借入金です。借入金は貸借対照表では、借入金は負債に計上されます。
今回は借入金の詳しい解説や4つの種類、借入金のメリット・デメリットについて詳しく解説します。負債というとマイナスイメージがありますが、借入金にはメリットもあるため、しっかり理解しておきましょう。
目次
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 借入金とは?意味や目的などわかりやすく解説


借入金は他者からお金を借りたお金を意味しています。いわゆる借金です。個人や銀行からの融資、取引先から融資などお金を借りることを「借り入れをする」といいます。
具体的には、借用証書や約束手形、金銭貸借契約などに基づいてお金を借りることにより発生する債務が、借入金です。どこから借りたかは問題ではなく、兄弟や親族、知人、親会社に借りた場合なども、借入金になります。借入金には返済の義務があり、利息も支払わなければなりません。
1-1. 借入金は貸借対照表負債に計上される
貸借対照表は資産の部と負債の部が記載されており、それぞれの合計額が一致しています。借入金は資産の部と負債の部のうち、負債の部に計上される項目です。
例えば銀行から500万円の融資を受けるとしましょう。融資を受けると通常口座にお金が入金されます。その際、貸借対照表では資産の部の「普通預金」などの口座を表す勘定科目の残高が、負債の部では借入金の残高が、それぞれ500万円ずつ増える仕組みです。現金でお金を借りた場合は、資産の部の現金の勘定科目が増えます。
借入金には利子が発生するため、返済するときには借り入れした元本と利息に分けて会計処理をおこなわなければなりません。
関連記事:借入金勘定科目とは?2つの勘定科目で正しく使い分けるポイント
関連記事:固定負債に該当する長期借入金について基本からやさしく解説
1-2. 資本金との違い
資本金は会社を設立するために、株主が会社に出資するお金です。資本金は会社設立をする人が自己資金を出す場合と、株主が出資者となってお金を出す場合があります。資本金の場合は、出資者に対してお金の返済義務はありません。出資者は経営に参加し、利益が出た場合は配当金が支払われます。
人がお金を出してくれるという意味では、借入金と似ているように感じられます。しかし、返済の必要がない資本金は借入金とは似てはいるものの全く違うものであることを覚えておきましょう。
1-3. 短期借入金と長期借入金の違い
短期借入金と長期借入金の違いは返済期日の違いにあります。
| 借入金の種類 | 返済期間 |
| 短期借入金 | 1年以内 |
| 長期借入金 | 1年以上 |
短期借入金は返済期日が1年以内、長期借入金は返済期日が1年を超える借入金のことです。
一般的に銀行をはじめとした金融機関が借入先となり、短期借入金のほうが金利が低くなる傾向にあります。借入をするときは返済期日と金利のバランスを考え、調整することも必要です。
1-4. 運転資金と設備資金
借入金は上記のように短期、長期で分けるケースもあれば、資金用途によっても分けることができます。
| 借入金の種類 | 資金用途 | 具体例 |
| 運転資金 | 会社を継続していくための資金 | 人件費・賃貸費・通信費・仕入費など |
| 設備資金 | 事業継続のために必要な設備 | 増改築費・設備投資・賃借料など |
資金用途として一般的なのが運転資金と設備資金の2つです。運転資金は会社を継続して運転していくための資金です。具体的には社員の給与や日々の仕入れなどの資金のことです。設備資金とはその名の通り、事業運営を継続する上で必要な設備(工場や車両、機械など)にかかる資金のことをいいます。
2. 借入金の4つの種類


借入金には4つの種類があります。それぞれどのような性質の借入金なのか知っておきましょう。
2-1. 証書貸付
証書貸付は、融資する側とお金を借りる側が金銭貸借契約を結んだ上で、金銭消費貸付契約証書を差し入れておこなう借入金のことです。金銭消費貸付契約証書には、貸付金額や返済期日の他に、利率などさまざまな貸付条件が記載されます。
一般的に借入金という場合は、この証書貸付を意味していることが多いです。不動産などを担保にして、お金を借り、返済が滞ると担保に物を売却したお金で借入金が返済されます。
2-2. 手形貸付
手形貸付は金銭消費貸借契約証書の代わりに、銀行に振り出した約束手形を使って、手形に書かれている金額の融資を受けることをいいます。手形貸付の場合は、証書貸付のように担保は設定せず、比較的短期間の貸付がおこなわれます。
手形貸付は短期での返済という特徴から、会社の運転資金やつなぎの資金を融資してもらうときに利用されることが多いです。担保はありませんが、返済が滞ると不渡りとなり、会社の社会的信用は大きく失墜してしまいます。
関連記事:短期借入金とは?長期借入金との違いを踏まえて正しく扱うポイント
2-3. 手形割引
手形割引は、他人や他社が銀行で振り出した約束手形を、支払い期日より前に銀行や手形割引をおこなっている事業者で買い取ってもらうことです。手形割引は、他者から約束手形が振り出されているものの、その期日より前にお金が必要なときに利用するケースがほとんどです。
手形の振出人や企業の財務状況や実績によっては、買い取ってもらうときの手数料がかなり高くなることもあります。
2-4. 当座借越
前もって決めた融資限度額までであれば、いつでも自由に融資を受けたり、返済をしたりできる借入金の種類です。借入できる口座があるため、わざわざ金融機関に足を運ぶ必要はなく、限度額までなら融資の回数制限もありません。
カードローンは当座借越のひとつです。口座を作る人の返済能力や信用度で貸付をおこなうため、担保は設定されません。自由に融資が受けられるため借りる側としては使い勝手がいいのですが、そのぶん当座借越設定のための審査は非常に厳しくなっています。
3. 借入金利と借入金の返済


借入金は個人や金融機関などから借りているお金であるため、必ず返済しなければなりません。その返済について知っておきましょう。
3-1. 借入金利とは
借入をおこなう際には一般的に金利がかかってきます。当然会社が借りる借入金にも金利がかかります。
金利とはお金を借りることで発生する手数料のようなものです。借入先によって金利は大きく変動します。最も一般的なのが銀行などの金融機関、他にも政府系の金融機関やノンバンクなどがあります。政府系の金融機関が比較的利率が低く、ノンバンクなどの貸金業をおこなっているところは利率が高くなる傾向にあります。
3-2. 借入金の返済
借入金は期限内に返済する必要があります。そのため高額の資金調達や利率の高い借入をおこなってしまうと、返済が難しくなるため慎重に調整ことが重要です。
借入をした後は、借入金の利息の計算をしてしっかりとした返済計画を立てましょう。
それと同時に借入金の仕訳も正しくおこない、会社がどれくらいの負債を抱え、利益を出しているのかを把握しなければなりません。
4. 借入金のメリット


会社の負債となる借入金はマイナスの印象が少なからずあります。しかし、借入金にはどのようなメリットがあるのか理解しておきましょう。
4-1. 事業資金にゆとりができる
融資を受けると、それだけ事業資金にゆとりが生まれます。ビジネスの世界では「月末に入金があるはずだった会社が急に倒産してしまった」ということが起こることもあります。入金されるはずのお金がなくなると、取引先に支払いができなくなり、従業員への報酬も支払えません。事業資金にゆとりがある状態を維持していれば、万が一の事態が起きても、慌てずに安定した経営を続けられます。
4-2. 将来への投資ができる
融資を受けると会社の成長に向けて投資ができます。新しいシステムの開発や機械の導入ができる他、今までにない取引をするなど、将来に向けた投資をすることは、会社を成長させていくためには欠かせません。投資にはお金が必要不可欠ですが、融資を受ければまとまった金を工面できます。
4-3. 企業の信用度が向上する
銀行から融資を受ける場合、返済能力があるかを調べられ、厳しい審査が行われます。その審査をクリアして融資を受けられたということは、資金や利益面で信用されている会社であることの証明になります。会社が成長していることを実感できるため、事業主にとって自信にもつながるでしょう。
4-4. 節税効果が期待できる
借入金の利息は経費として計上できるため、利息分が節税となります。どの程度の節税になるかはケースバイケースですが、少しでも節税できるのであれば、多少なりともメリットがあると言えるでしょう。
関連記事:役員借入金を活用する節税対策のメリットやデメリットについて解説
5. 借入金のデメリット
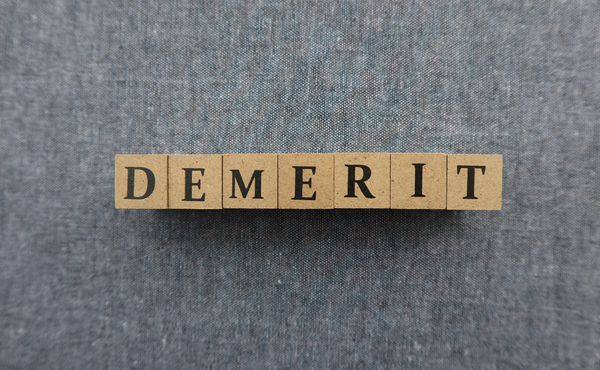
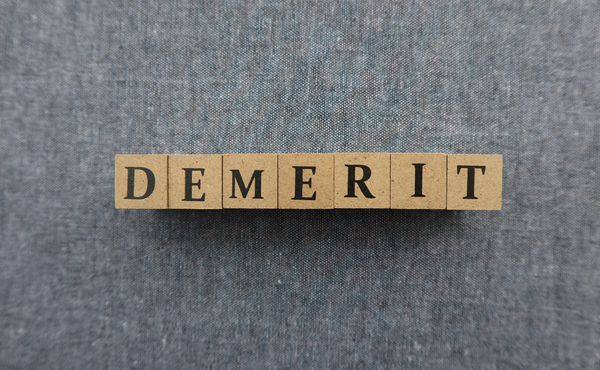
借入金のデメリットは月々確実に返済をしなくてはならないことです。知人や家族からの借入金なら多少は融通が効くかもしれませんが、金融機関からの融資は毎月の返済が大前提で、返済が滞ると信用を失ってしまいます。
融資を受けすぎると返済だけで手一杯になり、資金が足りなくなってしまうこともあるでしょう。資金がなくなると、取引先にも従業員にも支払いができず、事業を畳まざるをえなくなってしまいます。
無理のない計画を立てて借り入れないと、取り返しのつかない事態に陥ってしまう可能性もあることは理解しておきましょう。
6. 借入金はマイナスばかりではない!上手に活用して会社を発展させよう


借入金は銀行や取引先、知人や友人、家族、親族などからお金を借りることです。借入金を活かせば経営が安定しますし、会社が大きく飛躍できるチャンスもあります。ただし、借金であることに変わりはありませんから、無理しすぎるとメリットよりデメリットが勝ってしまうリスクもあります。
計画的に借り入れをして、借入金を事業に活かし、会社の成長を目指しましょう。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















