固定負債に該当する長期借入金について基本からやさしく解説
更新日: 2024.5.23
公開日: 2022.5.11
jinjer Blog 編集部
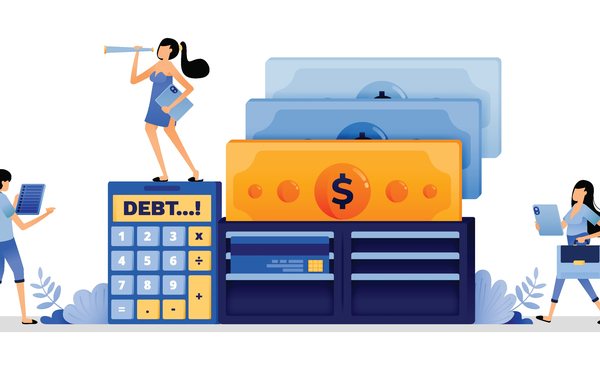
長期借入金は、借入金の中でも1年を超えて返済をする予定の借入金です。高額になりやすいことから、分割で返済することも多いでしょう。短期借入金との違いをしっかりと把握しておけば、仕訳も問題なくおこなえます。
ここでは長期借入金の特徴や仕組み、仕訳の際の具体例を見ていきます。
関連記事:借入金勘定科目とは?2つの勘定科目で正しく使い分けるポイント
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 長期借入金とは?


長期借入金とは、決算日の翌日から起算して1年を超えて返済する予定の借入金です。借入金は「ワン・イヤー・ルール」と呼ばれる1年基準を適用し、長期借入金と短期借入金の2つに区分されています。
1-1. 長期借入金の種類
長期借入金の種類は以下の通りです。
- 銀行からの借入金
- 役員からの借入金
- 親会社や関連会社からの借入金
- 個人からの借入金
種類を見てもわかるように、とにかく1年を超えて返済する予定の借入金であれば、長期借入金とみなされます。ただし何でもすべて長期借入金としてしまうと、どこから借り入れたものなのかわからなくなるので、注意が必要です。
会社の外部からの借り入れなのか、それとも内部からの借り入れなのかを区別するために「関係会社長期借入金」「従業員長期借入金」というような区分表示にすることが多いです。
関連記事:役員借入金を活用する節税対策のメリットやデメリットについて解説
1-2. 長期借入金と短期借入金はどう違う?
長期借入金と短期借入金の違いは、最初にもお話ししたように「返済期間」です。1年を超えるかどうかによって区別されています。では借入金として資金を調達する場合、どのような違いがあるのかも見ていきましょう。
長期借入金の定義
長期借入金は返済期日が1年を超える借入金であることが原則です。利益と減価償却費の計上によるキャッシュフローにて返済していくことになり、借入審査のハードルは高いでしょう。
以前は有担保でしか借り入れできないケースが多かったものの、最近は金融庁の指導もあり無担保での貸し付けにも積極的になった金融機関が増えました。優良企業に限っては、代表取締役の連帯保証も求められないことが多いです。
短期借入金の定義
短期借入金は、長期借入金と反対に1年以内に返済期日が到来する借入金です。金利は返済日が1年以内ということもあり、長期借入金よりも低くなる傾向があります。運転資金として借り入れることを想定している借入金なので、売掛金を回収できれば返済ができることを前提として金額を決めましょう。売掛金の範囲内なら、赤字でも融資を受けられる可能性があります。
関連記事:短期借入金とは?長期借入金との違いを踏まえて正しく扱うポイント
1-3. 長期借入金の区分
長期借入金は、貸借対照表の「固定負債」に分類されます。貸借対照表の負債の部には、返済期限が1年以内のものを流動負債、返済期限が1年を超えるものを固定負債として区分するのが一般的です。
流動負債か固定負債かを区分する方法は2つあります。
① ワン・イヤー・ルール(1年基準)
ワン・イヤー・ルールは、貸借対照表の決算日から1年以内に返済する負債を流動負債、1年を超える負債を固定負債として区分する方法です。
② 正常営業循環基準
正常営業循環基準は、営業循環過程にあるものを流動負債として分類する、という基準のことです。そのため、買掛金や支払手形は流動負債として区分されます。
まずは正常営業循環基準で流動負債を決定し、それ以外の物はワン・イヤー・ルールによって流動負債か固定負債かの分類をしましょう。
1-4. 1年内返済予定の長期借入金
長期借入金を返済する際は、一括ではなく分割でおこなうことがほとんどです。そのため、決算日から1年以内に返済期日が訪れる金額分は流動負債に分けられます。
長期借入金すべてを「長期借入金」と扱って残高管理をして、決算時に組み替え仕訳で流動負債に組み替える、という方法だと混乱せず管理できるでしょう。
2. 長期借入金のチェックポイント


ここでは、会社の経営に対する長期借入金の安全性やリスク度をチェックする財務指標として「自己資本比率」「固定比率」「固定負債比率」3つの財務指標を紹介します。
長期借入金を適切に管理できるように、それぞれの特徴や計算方法を把握しておきましょう。
2-1. 自己資本比率
会社の借入金が適正な範囲であるかどうかを判断する指標となるのが、自己資本比率です。
自己資本比率=自己資本╱総資本×100
総資本は自己資本と他人資本を足したものです。他人資本は会社が他人から調達した資金であり、返済する必要のない自己資本とは区別して考えます。
自己資本比率が高ければ高いほど、返済不要の資本が手元にあるということになり、会社の経営の安全性が高いでしょう。反対に他人資本ばかりだと会社経営が怪しいということがわかります。
2-2. 固定比率
長期的な視点で安全性を見る指標として扱われているのが固定比率です。
固定比率=固定資産╱自己資本×100
固定資産は一度購入すると数年間は使用します。そのため、固定資産によってお金が生み出される期間も長期です。そのため、設備投資による固定資産は借入金で賄わず、返済義務がない自己資金・株式からの出資が望ましいといわれています。
2-3. 固定負債比率
固定負債比率は、固定比率から流動負債を外して、自己資本で借入金をいくら担保しているかを表すものです。
固定負債比率=固定負債╱自己資本×100
体制強化のためにも、借入金は短期から長期へとシフトしていくのが望ましいです。しかし固定負債比率が高すぎる場合は、資本構造を見直さなくてはなりません。
3. 長期借入金の実際の仕訳例


長期借入金の特徴や仕組みを理解したところで、次は長期借入金のよくある仕訳例をチェックしていきましょう。複数の借入先がある場合は、どこからの借入金であるかを明確にするために、借入先ごとの勘定科目を設定します。
また借入時には契約書に必要な印紙・手数料・諸費用が先に引かれるため、区別して処理をする必要があります。
3-1. 借入期間が3年の借入金を返済した場合
① 設備機器の購入費用として借入期間3年で200万円を借り入れた
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 2,000,000円 | 長期借入金 | 2,000,000円 |
② 当月分の返済額である10万円を、利息1,000円とともに支払った
| 借方 | 貸方 | ||
| 長期借入金 | 100,000円 | 普通預金 | 101,000円 |
| 支払利息 | 1,000円 | ||
3-2. 長期借入金として諸経費を引いた金額が振り込まれた場合
① 金融機関から500万円を5年で借り入れ、印紙代と利息、信用保証料などが控除されて入金された
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 4,776,000円 | 長期借入金 | 5,000,000円 |
| 支払利息 | 4,000円 | ||
| 租税公課 | 10,000円 | ||
| 長期前払費用 | 200,000円 | ||
| 支払手数料 | 10,000円 | ||
② 長期借入金のうち、返済期日を迎えた50万円を利息5,000円とともに返済した
| 借方 | 貸方 | ||
| 長期借入金 | 500,000円 | 普通預金 | 505,000円 |
| 支払利息 | 5,000円 | ||
3-3. 返済期限1年を切った長期借入金を短期借入金へと振り替える場合
長期借入金200万円の返済期限が1年を切ったため、短期借入金へ振り替えた。
| 借方 | 貸方 | ||
| 長期借入金 | 2,000,000円 | 短期借入金 | 2,000,000円 |
長期借入金をいつ振り替えかるかのタイミングは、決算期において返済期限が1年以内となった時です。勘定科目の「短期借入金」または「1年内返済予定の長期借入金」へ振り替えをおこないます。
4. 長期借入金の返済時は元本と利息を確認しよう


また返済時は元本の返済と利息の支払いが同時におこなわれるため、返済予定表を確認してそれぞれの金額がいくらであるかチェックしましょう。また勘定科目を間違えないことも大切です。
関連記事:借入金とは?借入金の種類や意味、金利や返済まで網羅的に徹底解説
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















