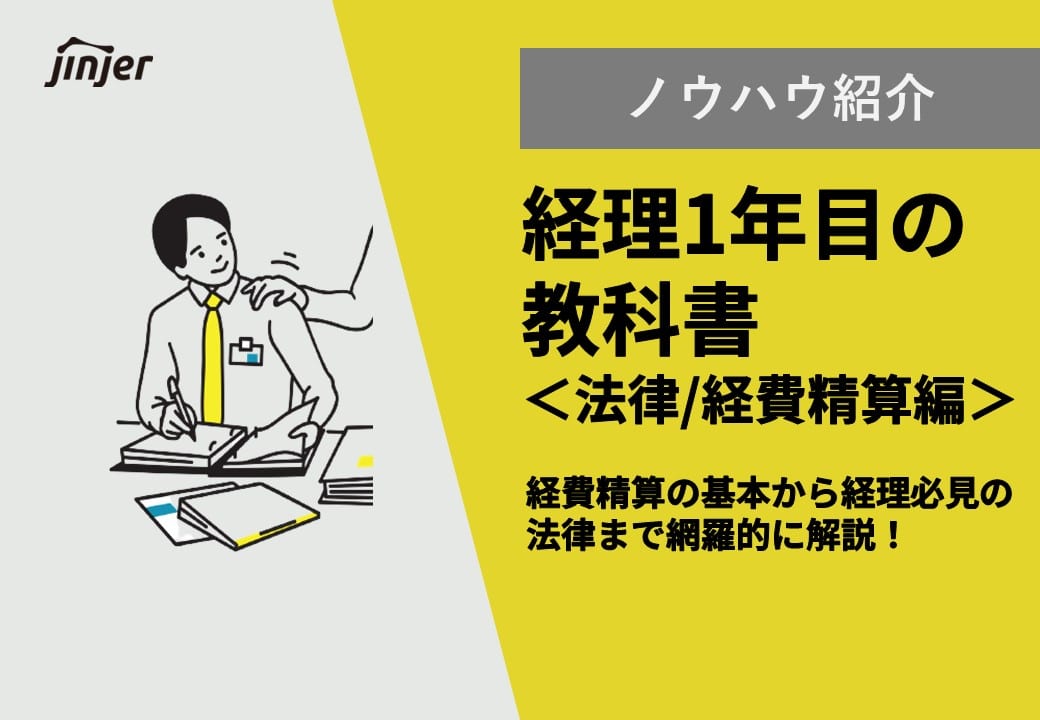法人税の軽減税率、中小企業が押さえておくべき内容は?わかりやすく解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2020.12.4
jinjer Blog 編集部

「中小企業者等の法人税率の特例」によって、中小企業は大企業よりも法人税率が優遇されています。大企業の場合、法人税率は一律23.20%ですが、中小企業は所得のうち年800万円以下の部分については法人税率が15%に減額されます。
中小企業の経営者や経理担当者は、「中小企業者等の法人税率の特例」を賢く活用し、財政基盤の安定化を図ることが大切です。
ここでは、中小企業が知っておくべき法人税の考え方、法人税の軽減税率の仕組みについて、わかりやすく解説します。
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安がある方必見の資料です。
経費精算は日々発生するため、流れ作業のように処理することもあるでしょう。しかし、経費精算業務は、社内規程や関連法に対応した細かいルールが存在するため、注意が必要です。
また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回Webで調べる時間や、本を買う費用も省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
1. 中小企業における軽減税率の要件や特例

大企業と中小企業では、法人税の計算方法が変わります。大企業などの普通法人は一律23.20%の税率がかけられますが、企業規模が小さい中小法人(中小企業者)は、より税率が低い「軽減税率(15%)」が適用されるためです。
ここでは、中小法人の要件や軽減税率の仕組み、制度延長の有無について解説します。
1-1. 税制改正によって中小法人の要件が変更
軽減税率の対象となるのは「中小法人(中小企業者)」のみです。平成31年度の税制改正によって、軽減税率の対象とならない大規模法人の範囲が拡大し、中小法人の要件が厳しくなりました。中小法人の要件は次のとおりです。
資本金もしくは出資金の額が1億円以下で、次の条件に当てはまらないもの
- 大規模法人の傘下にあり、発行株式数の2分の1以上が所有された法人
- 複数の大規模法人との間に支配関係があり、発行株式数の3分の2以上が所有された法人
- 常時雇用の従業員が1,000人を超えている法人
なお、「適用除外事業者」は所得のうち年800万円以下の部分についても、軽減税率ではなく「本則税率」の対象です。
国税庁によると、適用除外事業者は「その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人」が該当します。
適用除外事業者については次項で詳しく解説するため、合わせてご確認ください。
関連記事:軽減税率は全ての企業が対象企業です。求められる対応を徹底解説
1-2. 【一覧表】軽減税率を考慮した企業区分別の法人税率
上記の企業区分をふまえ、軽減税率を考慮した法人税の税率を一覧化しました。
| 区分 | 開始事業年度 | ||
| 平成31年4月1日以後 | |||
| 中小法人 | 所得のうち年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15%(軽減税率) |
| 適用除外事業者 | 19%(本則税率) | ||
| 所得のうち年800万円を超える部分 | 23.20% | ||
| それ以外の普通法人 | 23.20% | ||
このように区分が明確に分かれており、法人税を計算する際は自社の条件に合わせて正しく算出しなければなりません。
とくに中小法人は適用事業者と適用外事業者に分かれるため、この点にも十分に注意しましょう。
1-3. 令和5年度税制改正大綱で2年間延長された
もともと中小法人の軽減税率は2023年3月31日で終了する予定でした。しかし、令和5年度税制改正大綱で、2年間の延長が決定しています。
税率や区分には変化はなく、国内の経済状況や情勢から今後もさらに延長される可能性があります。
法人税率を計算する際は常に最新の情報を入手するようにし、期間や税率の変更にも迅速に対応するようにしましょう。
軽減税率に限らず、経理業務には法律で定められたルールに則らなければならない業務が多くあります。抜け漏れなく対応するためには、経理業務の基本を理解するだけでなく、各種関連法についても知識を深める必要があるでしょう。
当サイトで無料配布している「経理1年目の教科書」では、経理担当者が押さえておくべき業務の基本や法律について解説しています。ふと疑問が浮かんだときにすぐに読み返せるよう、ダウンロードして保管することをおすすめします。興味がある方は、ぜひこちらからご覧ください。
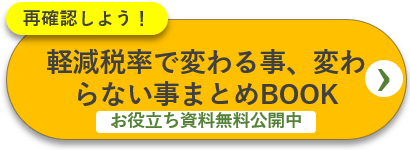
2. 軽減税率が適用されない適用除外事業者が存在する

法人税の軽減税率が適用されない事業者は「過去3年間の平均所得金額が15億円を超えている」ことが条件です。
この条件を満たしている場合は、中小事業者であったとしても、軽減税率が適用されずに一般税率で法人税が適用されます。
過去3年という基準は、事業年度開始日から計算します。事業年度3年分の所得金額を合計し、期間中の月数を合計した数字で割って12をかけて計算します。
【計算式】
(事業年度3年分の所得金額 ÷ 期間中の月数) ×12 =過去3年間の平均所得
この計算式で求められた数字が15億円よりも上回った場合は、軽減税率の適用除外者になります。
また、このほかにも細かい適用除外の条件があります。より詳しい情報は国税庁が公開している適用除外者の判定表を確認しましょう。
3. 法人税を計算する際は所得を基準にする

法人税の計算方法や税制について熟知しているかどうかが、企業の最終的な利益(税引後利益)に大きく影響してきます。
ここでは、法人税の計算方法の基本や、その際に関わってくる「税務調整」の考え方について詳しく説明します。
3-1. 法人税がかかる所得の計算方法
法人税の課税対象は「所得(税務上の儲け)」です。所得税では法人格のない個人の所得が課税対象ですが、法人税では株式会社などの法人の所得が課税対象です。税務上、所得の金額は「益金」から「損金」を差し引いて計算します。
所得(または欠損)=益金-損金
決算などで「利益(会計上の儲け)」を計算する際、「利益(または損失)=収益-費用」の計算式を使います。税務上の「所得」は、会計上の「利益」とは違います。
所得の計算に使う「益金」は税務上の収益、「損金」は税務上の費用(コスト)のことです。なお、益金=収益、損金=費用ではありません。
益金=収益+益金算入項目-益金不算入項目
損金=費用+損金算入項目-損金不算入項目
益金算入項目(または損金算入項目)とは、会計上は収益(費用)とならないが、税務上は収益(費用)となる項目を表します。
逆に、益金不算入項目(または損金不算入項目)とは、会計上は収益(費用)として勘定するが、税務上は収益(費用)として勘定しない項目のことです。
つまり、益金と収益、損金と費用はそれぞれ範囲が違うと覚えておきましょう。たとえば、会計上は法人税の還付金を「収益」として勘定しますが、税務上は「益金」として勘定できません。
このように会計と税務のズレを解消する作業のことを「税務調整」といいます。
年度末には決算が行われ、会計上の「利益(または損益)」が確定しますが、法人税は利益にかかるわけではありません。別途、税務上の「所得(または欠損)」を計算したうえで、さらに企業規模に応じて所得税率がかけられます。
3-2. 法人税の計算方法
法人の課税所得が計算できれば、あとは法人税率を掛けるだけで法人税を算出できます。
以下の条件で実際に計算をしてみましょう。
- 資本金:5,000万円
- 益金:3,000万円
- 損金:1,000万円
- 普通法人
【計算式】
課税所得:3,000万円 - 1,000万円 =2,000万円
法人税:800万円 × 15% =120万円、1,200万円 × 23.2% =278.4万円
法人税は課税所得800万円までは税率が15%、それを超えた分は23.2%になるため、このように分けて計算をします。
2つの法人税を合算した398.4万円が法人税として納める金額です。
4. 中小企業は自社に適用される軽減税率を知って法人税を正しく納めよう

ここまで、法人税の計算方法の基本や、中小企業などを対象とした法人税の軽減税率について解説してきました。
法人税の税率や軽減税率は改正されることが多く、複雑な区分が発生することもあります。計算する際は最新の情報を自社に適用し、正しく算出するように心がけましょう。
中小企業の経営者や経理担当者は、法人税の軽減税率について詳しく知り、事業基盤の安定化を図ることが大切です。
関連記事:軽減税率の対策。補助金の内容や手続きについて詳しく紹介
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安がある方必見の資料です。
経費精算は日々発生するため、流れ作業のように処理することもあるでしょう。しかし、経費精算業務は、社内規程や関連法に対応した細かいルールが存在するため、注意が必要です。
また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回Webで調べる時間や、本を買う費用も省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04