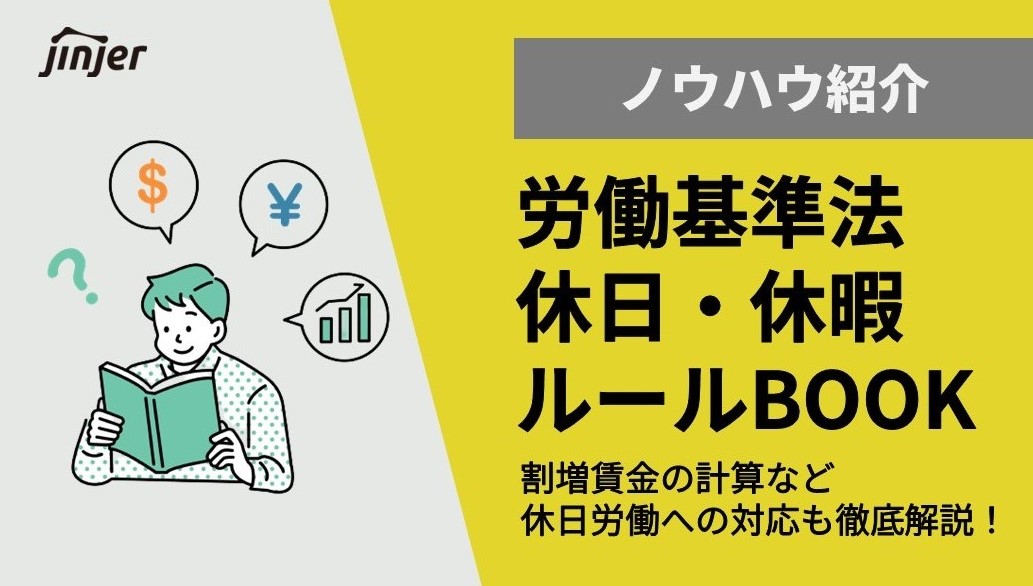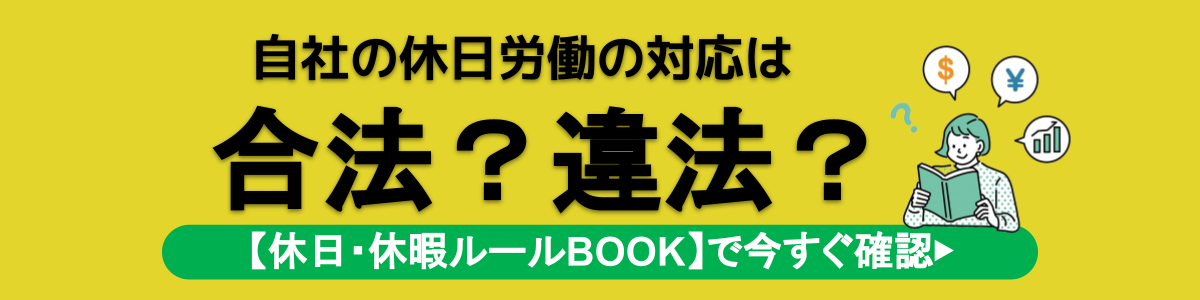代休の取得期限はどのくらい?今更聞けない休日管理のポイントを紹介
更新日: 2024.6.27
公開日: 2021.9.6
OHSUGI

休日出勤した労働者に対し、代わりの休みを与えることを「代休」といいます。従業員の健康管理のためにも、代休は休日出勤日の直後に与えることが望ましいです。
しかし、業務が忙しくてなかなか代休が取れないというケースは、決して珍しくありません。このような場合、取得することができない代休はいつまで有効なのでしょうか。この記事では、代休の取得期限や振替休日との違い、管理のポイントなどを解説します。
関連記事:代休の定義や振休との違い・運用のポイントを詳しく解説
目次
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
1. 代休の取得に期限はある?

そもそも代休とは、休日に出勤した場合に後日その代わりとして取得する休日のことです。企業において労働時間を柔軟に調整し、従業員のワークライフバランスを維持するために重要な制度です。
この代休の取得期限は、企業によってルールが異なります。ここでは、法律上の代休の取得期限と、実務上の代休の取得期限について紹介します。
1-1. 労働基準法上の期限は2年間
労働基準法上では、代休についての具体的な規定はありません。しかし、同法115代条には「賃金その他の請求権の時効」が2年であると記載されているため、代休の請求権も2年で時効を迎えると考えて差し支えないでしょう。
そもそも、労働基準法では労働者に代休を取らせることを義務付けてはいません。休日と勤務日をあらかじめ入れ替えて休日に勤務させる「振替休日」や、一定の条件を満たす従業員に対して付与することが義務付けられている「有給休暇」とは違い、代休は必ず取得させなくてはいけないものではないのです。
したがって、例え休日出勤をしても、会社の就業規則などに代休についての規定がない場合、労働者は代休を取得することはできません。
反対に、就業規則に代休についての規定があり、そこに自社ルールとして取得期限が記載されている場合は、そのルールが適用されることになります。
当サイトでは、本章で解説した代休と振替休日の定義の違いから、割増賃金の考え方までを解説した資料を無料で配布しております。給与の支払い不足等トラブルが起きやすい内容になるので、不安な方はこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1-2. 実務上では休日出勤の直後が望ましい
労働基準法における代休の時効は2年ですが、実務上でこの期限を採用している企業はなかなかありません。休日出勤をした2年後にさかのぼって代休を請求することは、本来の目的に反するためです。
そのため、企業は自社で代休についてのルールを設定し、そのルールにのっとって制度を運用するのが一般的です。
代休の取得期限は、1ヵ月や2ヵ月というように自由に設定できますが、可能な限り直後に設定することが望ましいでしょう。そもそも、代休は休日出勤をした従業員の体を休めることが目的の制度であるため、1週間以内の取得がもっとも適しています。
ただし、忙しい時期では休日出勤の直後に代休を取ることは難しいケースも多いため、余裕をもたせて1か月や3か月といった期間を設定する企業も少なくはありません。
代休の取得期限は企業が自由に設定できますが、従業員の健康管理を考慮のうえ、しっかりと取得できるルールを規定することが大切です。
2. 代休と振替休日の違い

振替休日は、代休と同じような意味で捉えられることがありますが、この2つには区別が必要です。その理由は、代休と振替休日とでは、申請方法や割増賃金の違いなど明確な違いがあるからです。
ここでは、人事担当者が対応を間違えやすい代休と振替休日の違いについて説明します。
2-1. 代休と振替休日の違いとは
「代休」とは、休日労働がおこなわれた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
一方で「振替休日」は、休日と勤務日をあらかじめ入れ替えることを指します。そのため、休日と勤務日を入れ替えて出勤させた従業員には、必ず入れ替えた勤務日に休みを取らせる必要があります。
つまり、代休は「休日労働が行われた事後に申請するもの」であるのに対して、振替休日は「休日労働が行われる前に、休日と勤務日を事前に入れ替えておこなわれるもの」という違いがあります。
2-2. 代休と振替休日の割増賃金の違い
代休と振替休日とでは、同じ法定休日に労働したとしても割増賃金に違いが生じます。
たとえば、普段、木曜日が勤務日で日曜日が休日の従業員がいるとします。
振替休日によって、従業員の勤務日と休日を事前に入れ替えて、従業員が日曜日に働き、木曜日を振替休日とした場合、従業員は労働時間に働いたという扱いになるため、休日労働の割増賃金は発生しません。
一方で、日曜日に休日出勤をさせた後に、代休で木曜日を休日とした場合、従業員は休日労働をしたことになるため、割増賃金が発生します。
割増賃金について、労働基準法32条と37条では、1日8時間、週40時間を超える労働を行なったとき、25%の割増賃金を支払う義務があると定めています。
また、法定休日に従業員を働かせたときは35%以上の割増賃金が発生し、所定休日の場合でも週に40時間を超える労働となった場合には25%以上の割増賃金が発生します。
代休制度を利用するときは、こういった割増賃金を正しく計算して支給する必要があります。賃金については自社のルールで運用することはできませんので、十分に注意しましょう。
法定休日と所定休日とは
法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、労働者に毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを指します。この法定休日は従業員に休息を確保するために設けられています。一方、法定外休日(所定休日)は、法定休日以外に会社が社員に与える休日を指します。
例えば、完全週休2日制の企業で日曜日を法定休日とした場合、土曜日が法定外休日(所定休日)となります。就業規則にはどの日を法定休日にするかを明示しておきましょう。これらの違いは特に代休の管理や割増賃金の計算において重要です。
従業員の休暇を適切に管理することで、労働環境の改善と企業の法的リスクの軽減が期待できます。
2-3. 代休と振替休日は給与の支払い方法が変わる
給与の支払い方法についても、適切なルールで運用することが求められます。同じ日に労働したとしても、振替休日を取得するか代休を取得するかによって給与の支払い方法が異なるため、必ず正しい処理方法を押さえておきましょう。
代休の場合は、取得期限によって給与の支払い方法が異なります。
代休の取得期限が同一賃金支払期間内であれば、休日出勤と代休で賃金を相殺できます。そのため給与計算の際は、休日労働割増賃金や時間外労働割増分の賃金を支払えば問題ありません。しかし締日をまたいで代休を取得させる場合、一度休日出勤の給与を支払い、代休を取ったのちに割増賃金を除いた基礎賃金を控除する必要があります。
したがって、代休をすみやかに取ることは、給与計算の手間を減らすという意味で非常に有効なことです。可能であれば、同一賃金支払期間内で代休を取得させるようにしましょう。
一方、振替休日は「あらかじめ休みと勤務日を入れ替える」制度であるため、事前に休日と入れ替える労働日を決めておかなくので代休とはなりません。つまり、給与の支払い方法は通常のままで良いというのが代休との違いになります。
例えば、「今週の日曜日に出勤する代わりに、来週の火曜日は休む」といったように決めてから勤務させるので、代休の取得期限などは関係ないのです。ただし、長期間振り替えた休日を取らせない場合は、制度の要件を満たせなくなってしまうので注意しましょう。
3. 代休期限が切れた場合はどうすればよい?

代休制度というのは、労働基準法で決められているものではなく、各企業が独自に決めている規則です。そのため、企業によっては「休日出勤から2ヵ月以内」というように、取得期限を決めていることもあります。
原則として、就業規則などで取得期限が決まっているのであれば、代休期限が切れた場合は取得できないため対応する必要はありません。ただし、代休の期限切れで取得できなかった場合には、休日労働をした日の割増賃金全額が残業代として発生するため、給与計算を間違えないようにしましょう。
代休分の割増賃金を支払わないと、労働基準法第24条に違反することになるので注意してください。もしも未払いになっている場合は、会社の不手際になるので早急に謝罪し、もし当人が賃金よりも代休を希望するようであれば対応するのが望ましいでしょう。
4. 代休を取得させないと違法になる?

従業員が代休を希望していても、「繁忙期で業務量が多い」「人員が不足している」などの理由で取得を許可できないこともあるでしょう。会社都合によって代休を取得させないのは、違法というイメージがあるかもしれません。
しかし、代休に関しては労働基準法で規定がなく、法律上の義務はないので違法にはなりません。就業規則などに則っていれば、代休を認めなくても大丈夫です。
休日出勤をしたのに代休を与えないというのは、従業員の不満や会社への信頼を失うなどのリスクがあるため、違法ではないとしても故意に取得させないようにするのは避けましょう。
5. 代休と有給休暇はどちらを優先すべき?

従業員に休日出勤をさせた場合、代休と有給休暇の取得についてどちらを優先すべきかを考える際には、以下のポイントを考慮することが重要です。まず、有給休暇は法律上従業員に保証された権利であり、従業員が希望する日時に取得する義務があります。これに対して代休は、法律上の義務ではなく会社のルールに基づくもので、取得させるかどうかは企業の裁量に委ねられます。
また、有給休暇は取得することで賃金が支払われますが、代休では賃金が発生しないため、従業員にとっては有給休暇を優先することが一般的です。特に、長時間労働を避けて従業員のモチベーション維持を図るためにも、確固たるルールが必要です。
さらに、有給休暇には取得にあたり2年の時効が設定されているのに対し、代休には法律上の取得期限がありません。これにより、有給休暇が期限切れを迎える前に優先的に利用されるべきです。
従業員の健康管理を促進する観点からも、休日出勤後に代休を勧めつつ、有給休暇の取得希望がある場合にはその希望を尊重することが望ましいです。企業は、これらの点を踏まえ、代休制度と有給休暇制度の運用を公平かつ明確にするルールを設定することが重要です。
6. 従業員の代休取得を管理するポイント

最後に、従業員の代休取得を正しく管理するためのポイントを2つ紹介します。
6-1. 代休の取得までが長期化しないようにする
企業は、従業員の未消化の代休が累積しないように気をつける必要があります。
企業には代休を取得させる義務はないと紹介しましたが、就業規則に代休が取得可能なことを規定しているにもかかわらず適切に代休を取得させない場合、従業員の健康やメンタルヘルスに悪影響を与えてしまう危険性が高まります。
法律上、代休の取得期限を延長したり代休の日程を再設定したりすることは問題ありませんが、長期間代休が取れない環境は問題です。
従業員の休日確保や健康管理のためにも、業務量を調整したり上司が声かけをしたりするなど、代休が累積・長期化しない取り組みをすることが大切です。
6-2. 代休ではなく振替休日で対応する
代休の取得を促進したり管理の手間を減らしたりしたい場合は、代休ではなく振替休日で対応することが有効です。
振替休日とは「休日と勤務日を入れ替える制度」のことで、あらかじめ休日労働の代わりに休む日程を決定して運用する点が大きな特徴です。いつ休みをとってもいい代休とは異なり、振替休日では必ず決められた日に休みを取ることが義務付けられるため、取得できずに累積することはありません。
また、あらかじめ誰がいつ休むのかを把握しやすくなるので、企業が管理する手間も省けます。振替休日は休日手当の支払いも不要であるため、企業側はコスト面の恩恵も受けられます。
関連記事:振替休日とは?定義や代休との違い、付与のルールを分かりやすく解説
7. 代休の取得期限は短めに設定し正しく運用管理を!

代休の法律上の時効は2年ですが、実務上ではなるべく休日出勤の直後に代休を取らせることが望ましいとされています。取得期限を短くすることは、労働者の休日確保や健康管理ができるだけではなく、給与計算や代休日数の管理にかかる手間を減らせるというメリットがあります。
代休に関するルールは、基本的に企業で決めて独自に運営することが可能です。
ただし、法定休日や割増賃金、給与支払いなど一部のルールは遵守しなければいけないため、運用時は十分に注意しましょう。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25