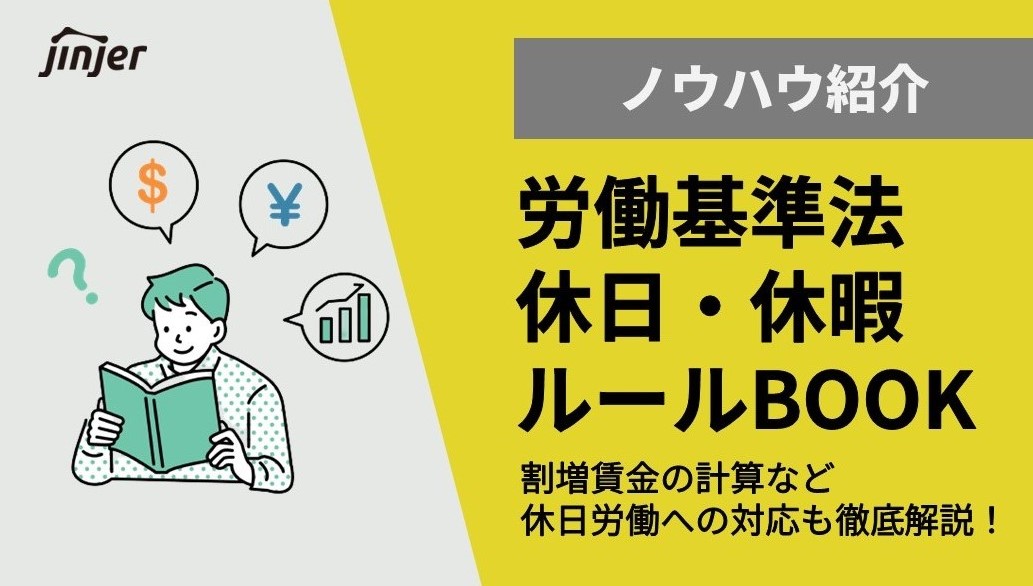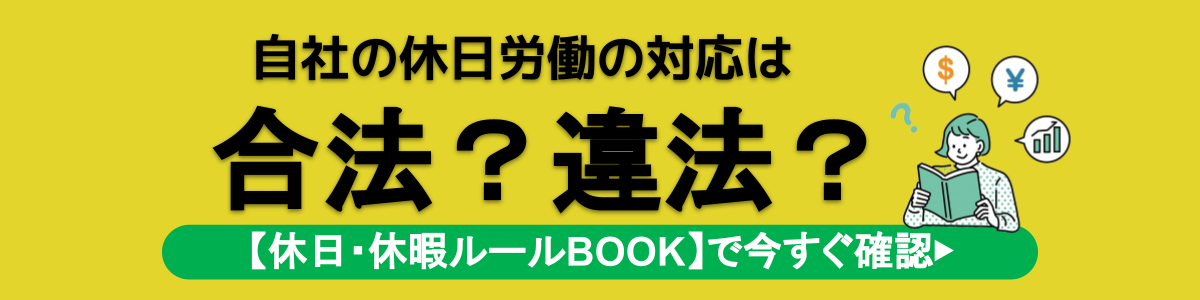代休とは?労働基準法上での定義や知っておくべき振替休日との違い

従業員に休日出勤してもらった代わりに、別の日に休ませることを「代休」といいます。
代休は法律上義務付けられているものではありませんが、労働者の健康を維持するためにも、休日出勤をさせたあとは取らせておくことが好ましいです。
この代休と似ている制度として、振替休日や有給休暇というものがあります。今回は、こういったほかの制度と代休の違い、適切な代休の運用方法について紹介します。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
1. 代休の定義

まずは代休の定義について正しく理解していただくために、代休についてと労働基準法との関係について紹介していきます。
1-1. 代休とは
そもそも、代休とは休日出勤した代わりに後日休ませることです。
厚生労働省によれば、代休は「休日労働が行なわれた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの」であると定義されています*。
例えば、「今週の日曜日に休日出勤をしたから、来週のどこかで休みをとろう」と考えているケースは、代休に該当するということになります。
1-2. 代休の付与は労働基準法で規定されている?
代休は、実は法律で取得が義務付けられているものではありません。そのため、労働者が代休を取らなくても問題はないのです。
ただし、労働基準法35条では週に1回もしくは4週に4回の法定休日を与えることについて定めているため、代休を取らないことによって法定休日を下回る場合は法律違反となります*。
企業は法定休日の要件を押さえつつ、労働者の健康を管理するために適切な代休の取得を推進する必要があります。
*参考:労働基準法第35条
2. 代休と振替休日・有給休暇の意味の違い

「休日出勤のあとに休みを取る」と聞くと、振替休日や有給休暇との違いがわかりにくいと考える人も多いかもしれません。この章ではさらに理解を深めるために、ほかの制度と比較しながら代休について見ていきましょう。
2-1. 代休と振替休日の違い
振替休日とは、「労働日と休日を入れ替える制度」のことです。
例えば、あらかじめ労働者に「今週の日曜日に出勤して、来週の月曜日を休みにする」と伝えた場合、振替休日に該当します。
この場合、単に労働日と休日を交換しただけであるため、代休の取得には該当しません。代休と振替休日では、以下の2つのポイントが大きく異なります。
- 休日を決めるタイミング
- 休日手当の有無
振替休日ではあらかじめ入れ替える労働日と休日を特定し、前日までに労働者へ伝える義務があります。したがって必ず休みを与える必要があり、労働もしくは休日とする前までにスケジュールを決定しておかないといけないのです。
あらかじめ休日出勤をしてもらうことになりそうであれば、振替休日を設けておくことが良いでしょう。振替休日は労働日と休日を入れ替えただけであるため、法定休日に出勤させた場合に通常の賃金に加えなければならない休日手当は不要です。
一方で代休は勤務後に代休の日程を決められ、法定休日の要件を満たしていれば休みを取らなくても問題ありません。
また、代休は休日出勤の代わりに与える休みであるため、法定休日に従業員を働かせたときは35%以上の割増賃金が必要になります*。
*参考:厚生労働省|時間外、休日及び深夜の割増賃金
関連記事:振替休日と代休の違いは?設定方法や法律違反になる場合を解説
2-2. 代休と有給休暇の違い
有給休暇は、給料が支払われる休暇のことを指します。労働基準法39条では、6ヵ月以上継続して勤務しており、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、勤続年数に応じた有給休暇の付与が義務付けられています。代休と有給休暇の違いは、以下の3つです*。
- 賃金が発生するかどうか
- 取得が可能になる条件
- 取得させる義務があるかどうか
そもそも、代休と有給休暇は「賃金が出るか出ないか」というポイントにおいて大きな違いをもっています。有給休暇は休んでも賃金が出ますが、代休をとったときは賃金が発生しません。
また、有給休暇は労働者が希望するタイミングで申請して取得できますが、代休は休日労働をおこなったあとでないと取得できない点も異なります。
労働基準法では労働者に代休を取得させることを義務付けていません。しかし、有給休暇は労働者の権利であり、従業員に希望された場合、企業は理由にかかわらず必ず取得させる義務があります。
このように代休を理解するためには、振替休日や有給休暇との違いを明確にすることが大事になります。そこで当サイトでは、そもそもとなる休日と休暇の違いから、それぞれの種類、取得のルールまでを解説した「休日・休暇ルールBOOK」を無料で配布しております。休日休暇の定義から対応方法まで一通り基本を理解したい担当の方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。
*参考:e-Gov|労働基準法
関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説
3. 代休を運用する上で抑えておくべき注意点と重要ポイント

この章では、企業が代休を導入する上での運用ルールについて5つ説明します。正しく運用するためにも注意点は抑えておきましょう。
3-1. 代休で時間外労働を相殺するときも割増賃金(手当)が必要
代休を取らせることで時間外労働分を相殺する場合は、時間外労働分の割増賃金を支払えば、可能です。
残業が多い企業では、代休を取らせることで時間外労働を相殺しようと考えることがあるかもしれません。
具体的には、月曜日から木曜日まで毎日10時間労働し、金曜日に代休を取ることで、法定労働時間からオーバーした分を相殺しようとするケースです。
代休で労働時間を相殺することは、じつは法律違反ではありません。そのため、こういった対応をおこななっても何ら問題ないのです。
ただし、代休を取得したとしても1日8時間の法定労働時間を超過した事実は消えないため、1日あたり2時間、合計8時間分の時間外労働に対する割増賃金は発生します。
労働基準法32条と37条では、1日8時間、週40時間を超える労働をおこなったとき、25%の割増賃金を支払う義務があると定めています。代休では割増賃金まで相殺することはできない点を、しっかりとおさえておきましょう。
3-2. 代休を月またぎで取得させる場合の給与計算に注意が必要
代休を月またぎで取得させる場合は賃金計算をする際に注意が必要です。同じ月内で代休を取得させる場合は、休日出勤日の割増賃金分を計算してその月の給与に加算するだけで給与計算をすることができます。
しかし、代休を月またぎで取得させる場合は、休日出勤日の賃金を加算したうえで、翌月の賃金から1労働日分の賃金を控除する必要があります。
例えば、9月に1日休日出勤して10月に代休を取得した場合、9月に1日増えた労働日分の賃金を10月分の給与として支給することはできません。9月分の給与に休日出勤の割増賃金込みの賃金を追加で支給した上で、10月分の給与から1日の労働日分の賃金を控除しなくてはなりません。
このように給与計算をおこなわなければならないのは、労働基準法第24条において、賃金支払いの5原則が規定されているからです。
労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。
このように、月またぎで代休を取得させることは賃金計算を複雑にすることを把握した上でおこないましょう。
3-3. 代休の買い取りはできない可能性が高い
代休は取得させなければならないものではないので、法定休日さえ与えていれば、付与するかどうかは企業の自由です。ただし、代休が発生するということは、休日出勤させているということなので、その分の賃金は支払わなければならず、割増賃金が発生するのであれば、そちらもあわせて支払わなければなりません。
法定休日を与えて、割増賃金込みの賃金を支払っていれば、買い取りをする必要性もありません。
ただし、法定休日を与えておらず、買い取ることで精算しようとすることはできません。
そのため、代休の買い取りは基本的に発生しないと考えておきましょう。
3-4. 許可なく欠勤を代休にすることはできない
休日出勤をしたあとに何らかの理由で従業員が欠勤した場合、会社が一方的にその欠勤を代休扱いにすることはできません。ただし従業員の同意がある場合は、欠勤を休日出勤に対する代休にできます。
この場合も、休日手当の支払い義務はなくならないため気をつけましょう。また、同意があれば欠勤があった日を「次回以降の休日出勤の代休」として取り扱うことが可能です。
関連記事:休日出勤した従業員に代休を取得させる際の基本ポイント
3-5. 希望がある場合は有給休暇を優先する
休日出勤をおこななったあと、賃金が発生しない代休を取る代わりに、有給休暇を取りたいと考える労働者もいるかもしれません。
もし、代休ではなく有給休暇の消化を希望された場合、企業はどちらを優先させればいいのでしょうか。代休を取得させることは義務ではありませんが、有給休暇を取得させることは会社の義務です。
そのため、企業は、相当の理由がない限りは従業員からの有給休暇の請求を拒否できません。つまり、希望がある場合は代休の代わりに有給休暇を優先させなければなりません。
4. 代休を運用するときに決めておきたいルール

代休の制度を導入しようとする企業は、就業規則などに運用ルールについて規定しておかなくてはいけません。あらかじめルールを明らかにしておかないと運用の根拠が不明瞭になり、トラブルに発展してしまう恐れがあります。
代休を運用するときに決めておきたいルールは、以下のとおりです。
- 代休取得の申請方法:所定の申請書を提出する、メールを送るなど
- 代休の取得期限:休日出勤の翌日から2ヵ月以内など
- 代休取得時の賃金:法定休日は35%以上など
また、代休を取ることで業務に支障が出る場合は、会社の指示でほかの日に変更できる旨を記載しておくといいでしょう。
運用ルールについては、労働者の不利益にならない限りは法的な制限がないため、自社で運用しやすい内容にしてかまいません。
4-1. 事後の振替申請は代休扱いになるため周知を徹底する
振休と代休の違いについては冒頭で説明しましたが、運用上でも注意が必要です。
振替休日を付与する場合は、事前に労使間で協議して代わりの休日を定めることが求められます。しかし、事後に振替休日の申請が行われた場合、それは代休として扱われます。具体的には、事前に定められた代わりの休日がない場合、従業員に条件によっては休日出勤に対する割増賃金を支払わなければなりません。これは法的な要件であり、遵守しなければならない重要なポイントです。
また、振替休日と代休では給与計算の方法も異なります。振替休日は事前に決めた場合であり、その日には通常の給与が支給されます。一方、突発的な事由により事後に休日を与える場合は代休とされ、条件によっては割増賃金が発生します。この区別を明確にし、適切に運用することが求められます。企業の人事担当者や管理職は、この規定に注意を払い、適正な運用を図ることが重要です。
4-2. 36協定を締結し就業規則へ記載する
代休を制度として運用する場合、その詳細を就業規則に明記しましょう。具体的には、代休の取得条件、手続き、代休と有給休暇の取り扱いの相違などを明確に記載することが、従業員とのトラブルを未然に防ぐために重要です。また、時間外労働や休日労働が発生する場合は36協定を締結する必要があります。法定休日を確実に確保するためには、振替休日と合わせて代休についてもルールを規定することが求められます。特に、労働基準法に則って取得条件、取得期限、賃金の取り扱いについて具体的な規定を設けることが労務管理の適正化に繋がります。これにより、企業は従業員の労働環境を整備し、スムーズな運用を実現できます。
5. 代休制度の定義を理解して正しく運用しよう

代休とは、休日出勤をした従業員を別の日に休ませる制度のことです。似ているように思われるかもしれませんが、振替休日や有給休暇とは全く異なる制度なので、しっかりと区別しましょう。
代休の取得は決して法律で義務付けられていることではありませんが、就業規則に定めることで、自社のルールにのっとって運用することができます。今回紹介したルールとポイントを踏まえ、労働者の健康管理をしながら適切に代休を運用しましょう。
関連記事:代休の取得期限はどのくらい?管理のポイントと併せて紹介
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちら「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25