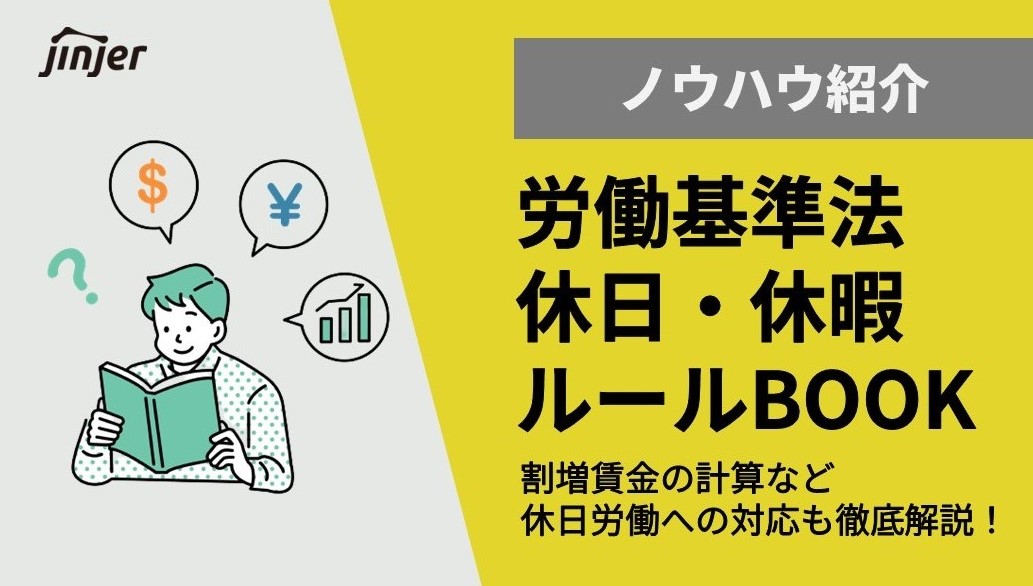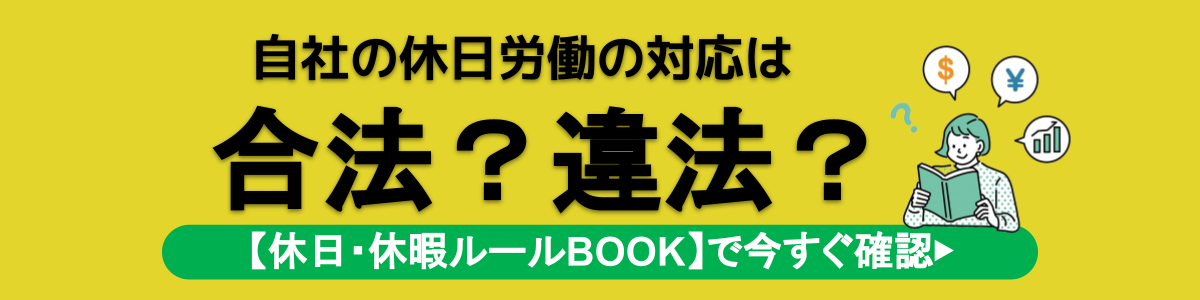振替休日とは?定義や労働基準法からみる代休との違い・給与計算の注意点を解説
更新日: 2024.6.28
公開日: 2021.9.6
OHSUGI

仕事をするうえで、休日に出勤が必要になることは多々あるかもしれません。休日と労働日を入れ替える場合、振替休日に該当して割増賃金の支払いが不要になるケースがあります。
この記事では、振替休日の定義について説明します。要件をしっかりと把握して、正しく運用しましょう。
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
1. 振替休日とは

振替休日とは、休日と決められていた日をあらかじめ労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にすることです。
例えば、休日と定められていた日曜日をあらかじめ「労働日」として、もともと労働日であった翌日月曜日を休みにするということが、振替休日に該当します。
そもそも労働基準法では、「週に1回または4週に4回」の法定休日を労働者に与えるよう使用者に義務付けています。振替休日は、この労働基準法のルールに則って休日を適切に運用するために設けられた制度です。
振替休日のポイントは、休みと労働日を入れ替えただけであるため、休日労働に対する割増賃金が生じない点です。休日出勤にならないことを理解しておきましょう。
2. 振替休日と代休の違い
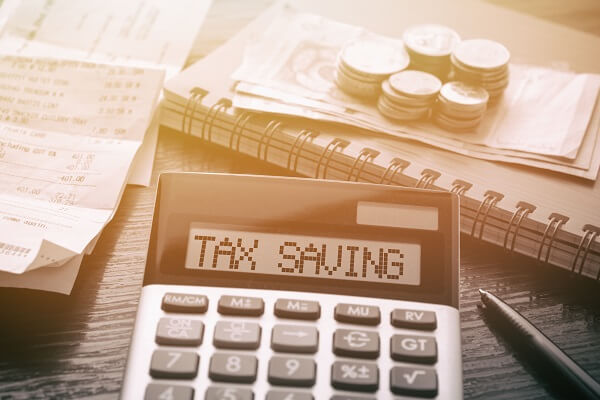
振替休日と似たような制度として「代休」というものがあります。代休とは、休日労働がおこなわれたときに、その代償として以後の労働日を休みとするものです。
一見すると同じに見えるかもしれませんが、両者には決定的な違いが2つあります。ここでは、それぞれの違いについて見ていきましょう。
2-1. 休日を決定するタイミング
両者では、休日を決定するタイミングが異なります。先述したように、振替ではあらかじめ労働日と振り替える休日を決定して、従業員に伝えておく必要があります。
一方で、代休は勤務後に任意の労働日を休みに設定できるため、事前に日程を決めておく必要はありません。計画的に休みと労働日を入れ替えるのが振替、急な休日労働にも対応できるのが代休というイメージです。
2-2. 給料の計算方法
両者では、給料の計算方法も異なります。
振替休日は「休みと労働日を入れ替える」と定義されているため、たとえ本来は法定休日あった日曜などに出勤しても、休日手当の支払いは不要です。通常の労働と同様の賃金で問題ありません。
代休には休日出勤手当(割増賃金)の支払いが必要
しかし、代休は「休日出勤をした代わりに休みを取る」と定義されているため、休日手当の支払いが必要です。法定休日に従業員を働かせると、35%以上の休日手当が必要になります*。
発生する給料は従業員にとって重大な問題であるため、企業はあらかじめ「どちらに該当するのか」をしっかりと説明し、従業員に納得してもらうことが大切です。
ここの内容を理解しなければ、給与の支払い不足が発生し多くのトラブルが発生しますので、定義から明確にしなければなりません。
そこで当サイトでは、本章でも解説した、代休と振替休日の定義の違いや割増賃金の計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。不安な点がある担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:振替休日と代休の違いは?設定方法や法律違反になる場合を解説
3. 振替休日を付与するための4つの要件

休みの日に出勤してほかの日に休むという働き方は、どのようなケースでも振替休日になるというわけではありません。この休日と労働日の入れ替えを「振替」として扱うためには、3つの要件を満たす必要があります。
ここでは、詳しい要件について見ていきましょう。
3-1. 就業規則に振替休日についての定めがある
振替休日を利用するためには、就業規則に「休日を振り替えることがある」旨を規定しておく必要があります。合わせて、振替休日のルールについても定めておかなくてはいけません。振替休日を利用する可能性がある企業は、しっかりと就業規則に記載しておきましょう。
また、就業規則への明記にくわえて、従業員への周知も義務付けられています。振替休日の制度を知らずに休日出勤の割増賃金を請求されるといったトラブルを避ける上でも、就業規則に定めるだけでなく、必ず従業員へ周知させましょう。
3-2. 振替休日にすることを前日までに従業員に伝える
振替休日を正しく運用するには、休日出勤させる前日までに出勤日と休日の入れ替えを済ませておくことがポイントです。そのため、従業員にも休日出勤をさせる「前日」の勤務終了までに振替休日を付与する旨を伝えなくてはいけません。
従業員に事前に知らせず、休日出勤させた代わりに休みを付与しても、振替休日としては扱えないため注意しましょう。
3-3. 振替休日となる日を明確に決める
もっとも大切なのは、休日をあらかじめ決めておくことです。どの休日と労働日を入れ替えるのかを決めてから休日出勤させることで、はじめて要件を満たせます。振替休日にすることだけを事前に決め、実際の日にちを指定しない場合は振替休日とみなされません。事前に振替休日と決めるだけでなく、必ず具体的な日付も指定しましょう。
日にちを決めていなかったせいで代休扱いに合ってしまうと、休日手当が必要になる可能性があり、想定外の人件費の出費が生まれてしまいます。
3-4. 法定休日の要件を満たしている
振替をおこなっても、週に1日もしくは4週4日の法定休日の要件を満たしていなくてはいけません。万が一、法定休日の要件を満たさないと労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
法定休日にのっとり、休みを設定する必要があるため、可能な限り労働日の近くに休みを取ることが理想的です。
4. 振替休日を取るときの注意点

振替休日を適切に付与しないと、給与計算に影響を及ぼすことや、労働基準法に抵触する恐れもあるため注意が必要です。
最後に、より正しく制度を運用するための注意点について見ていきましょう。
4-1. 事後の振り替えは代休となる
振替休日の処理でありがちなミスが、休日の付与タイミングを誤るケースです。
上述でも解説しましたが、振替休日は休日出勤の前日までに休日と労働日を入れ替えておかなくてはいけません。しかし、振替休日を「休みを振り替えるだけで良い」と認識していると、休日出勤した後に休日を付与してしまうというミスにつながります。
事後の振り替えは代休として扱わなくてはならず、振替休日とは異なり、休日手当の割増賃金支払いが必要です。
振替休日を誤って運用しないためにも、代休との違いについてしっかりと押さえておきましょう。
4-2. 給料の締め日までに振替休日を与える
振替休日はあらかじめ休みとする日を決定してからおこなわれるため、取得期限について意識することはあまりないかもしれません。
しかし、通常振替は同一賃金支払期間内でおこなわれることが一般的なので、給料の締日よりも前に休みを設定することを意識しましょう。
そもそも労働基準法には、労働によって確定した金額を全額支払わなくてはいけない「賃金全額払いの原則」というものが存在しています。そのため、もし休みを与える時期が締日をまたぐことになってしまうのであれば、一旦は休日出勤に対する給与を支払い、休みを取得してから控除をおこなう必要があるのです。
仮に相殺可能であっても「賃金全額払いの原則」のほうが優先されるため、上記の方法で精算することを推奨します。この場合は休日手当の割増賃金は不要ですが、後述する週に40時間を超える分の割増賃金は必要となるため、該当する場合は注意しましょう。
本来支払うべき給与を支払わないことは、法律で定められた義務を果たさないことであり、最悪の場合で信用に関わってくる問題でもあります。慎重に判断しましょう。
4-3. 週をまたぐ振替は割増賃金が必要になる可能性がある
振替休日の給料には休日手当が不要であると紹介しましたが、週を越えて休みと労働日を振り替えたときは、時間外手当として割増賃金が発生する可能性があるため注意しましょう。
労働基準法32条と37条では、1日8時間、週40時間以上の労働をおこなったとき、25%の割増賃金を支払う義務があると定めています。
たとえば月曜日から金曜日まで1日8時間、週40時間働いたのち、土曜日を労働日にしたときは週の労働時間は48時間です。このオーバーした8時間に対して、時間外手当として25%の割増賃金が必要になるというわけなのです。知らずに通常通りの給与を支払うと労働基準法に違反してしまうため、労働時間については慎重に管理しましょう。
4-4. 振替休日が累積することは法律違反
「休日に働いたけど、仕事が忙しくて休みが取れない」というケースは、非常に多いものです。しかし先述したように、振替休日はあらかじめ労働日と休日を決定してからおこなわれる必要があります。
そのため、休日の振替がおこなわれずに累積してしまうと、要件を満たせなくなってしまう可能性が高いのです。また、休日労働が生じたときは割増賃金が発生します。
振替休日では、労働した分の給料は代わりに休みとする日と相殺され、割増賃金のみが支払われることになります。振替がおこなわれない場合、取得してもいない休日と労働した給料が相殺されるため、労働基準法24条の「賃金の全額払いの原則」に違反してしまう点に注意が必要です。
休日出勤をさせたときは、すみやかに休みと取らせるようにしてください。
4-5. 企業側が法定休日を取得させていないと法律違反
振替休日が消化されないことは、従業員の満足度や労働環境を考慮しても避けるべきであり、なるべく早く消化させることが望ましいです。
そのためには適切な管理が求められます。とくに振替休日を取得させないことで週に1日取得が定められている法定休日を取得できていない結果になった場合、法律違反となってしまいます。
例えば、「休日出勤日から○日以内」や「代休日の前日までに指定する」などの具体的なルールを就業規則に明記することが有効です。
これにより、企業側も従業員も計画的に対応でき、不必要なトラブルを避けることができます。
4-6. 適切な割増賃金を計算して給与で支払う
振替休日で交換した労働日には休日労働に対する割増賃金は発生しませんが、代休をとらせた労働日は場合によって割増賃金の支払いが必要です。休日労働の合計時間によって、時間外労働分の残業代や深夜手当を考慮する必要があります。労働日が法定休日であれば、休日労働に対する割増賃金が必要になります。企業の人事担当者や経営者は、こうした計算を誤らないよう注意が必要です。
計算ミスが発生すると、未払賃金に繋がり、従業員からの請求や最悪の場合、裁判に発展するリスクが考えられます。特に、休日労働の取り扱いにおいて悪意なき誤った運用を避けるためにも、割増賃金の計算が適正に行われているか定期的に確認しましょう。これにより法的なトラブルを未然に防ぎ、適正な給与計算を維持することができます。
4-7. 年次有給休暇には変更しない
企業の人事担当者や経営者にとって、振替休日と念じ有給休暇の違いを明確に理解することは重要です。休日出勤をした従業員から「振替休日ではなく年次有給休暇として取得したい」との要望がある場合、対応には注意が必要です。
労働基準法には、休日出勤をした場合の休日取得に関する明確な規定はありませんが、就業規則に振替休日取得ルールを記載しておくことが重要です。振替休日を年次有給休暇に変更しても法的な問題はありませんが、そうすることで休日管理が複雑化し、コストが増大する可能性があります。そのため、「休日出勤時には振替休日を取得する」といった具体的なルールを就業規則に明記し、トラブルを未然に防ぐことが不可欠です。
適切なルール設定と明示により、休日管理の効率化と従業員の理解を深め、法的リスクを最小限に抑えることができます。
5. 振替休日は要件を満たして適切に運用しよう!

振替休日を導入するときは、あらかじめ就業規則に定めて休日と振り替える労働日を決定し、法定休日の要件を満たしている必要があります。
しっかりとこの3つを押さえて、適切に運用していきましょう。振替は代休と類似しているポイントも多いですが、休みを決定するタイミングと給料の計算方法が異なります。
振替をおこなったつもりでも、条件によっては否認されて割増賃金が発生する可能性があります。運用時は十分に注意してください。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
関連サイト:ホワイト企業ナビ
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25