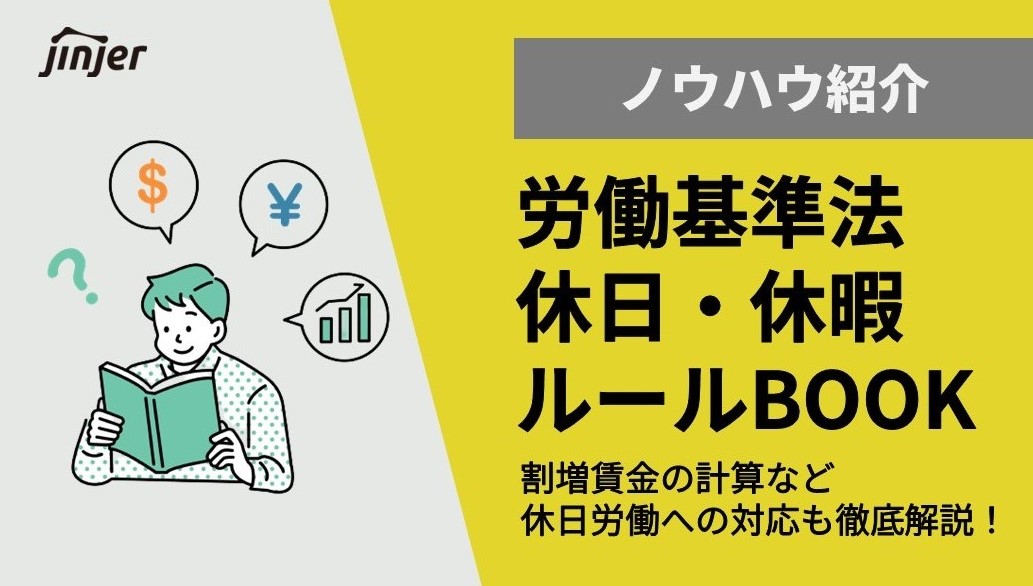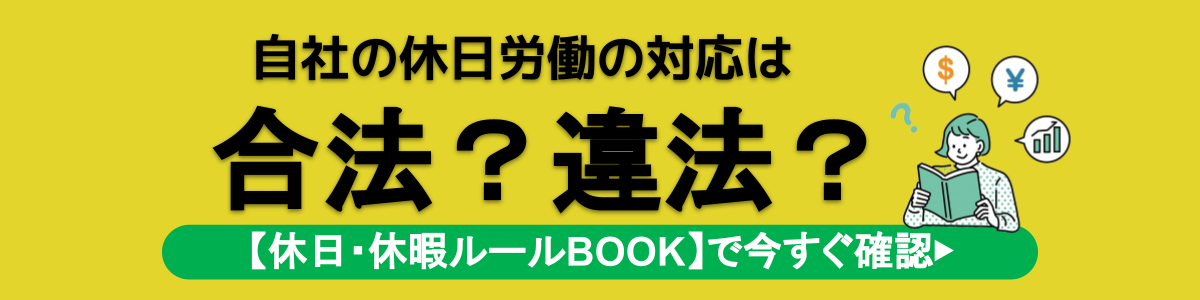振替休日に期限はある?週をまたいだ時の対応も解説

振替休日をおこなうときは休日と勤務日を入れ替えることになるため、勤務する日の前か後に休みを取らなくてはいけません。「休みを取らせないといけない」ということを理解している人は多いかもしれませんが、「いつまでに休ませればいいのか」「振替の期限はあるのか」ということを知らない企業の担当者もいるのではないでしょうか。
この記事では、振替休日の期限について解説します。取得期限や振替休日を運用するときの注意点を知って、正しく制度を活用しましょう。
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
1. 振替休日に取得期限はある?

振替休日は、休日と勤務日をあらかじめ入れ替えることを指します。そのため、休日と勤務日を入れ替えて出勤させた従業員には、必ず入れ替えた勤務日に休みを取らせる必要があります。
ちなみに、休日出勤した後にその労働分の休みを取るのは「代休」になります。振替休日はあくまで休日と勤務日を入れ替えているだけなので、休日出勤ではありません。
振休と代休では割増賃金の扱いが異なります。下記の記事では振休と代休の違いはもちろん、振休を取る際の注意点やトラブルの事例など網羅的に解説しておりますのでぜひご覧ください。
関連記事:振休(振替休日)と代休の違いとは?をわかりやすく徹底解説!
1-1. 振替休日の時効は原則2年間
労働基準法には、振替休日の取得期限について詳しい規定はありません。そのため一般的には、同法115条に記載がある「賃金その他の請求権の時効」が適用され、2年間で時効を迎えて休みを取る権利が消滅すると考えられています。つまり、振替休日の時効は原則2年であると言えます。
1-2. 振替休日はすみやかに取得させることが好ましい
振替休日の時効は2年間だと紹介しましたが、制度の性質上、できるだけすみやかに休みをとらせることが好ましいです。
会社によっては繫忙期が重なり、「振替休日が複数日程たまっている社員もいる」といった状況に悩まされてる人事担当者の方もいるのではないでしょうか。
しかし、そもそも振替休日は「あらかじめ休みと勤務日を入れ替える」制度であるため、事前に休日と入れ替える労働日を決めておかなくてはいけません。
具体的には、「今週の日曜日に出勤する代わりに、来週の火曜日は休む」といったように決めてから、勤務させる必要があるのです。したがって、長期間振り替えた休日を取らせないことになれば、そもそも制度の要件を満たせなくなってしまいます。
休みにする日を決めてから勤務させなければ、代休とみなされてしまう可能性があります。振替休日の時効は2年ですが、可能な限り早めに取らせるようにしましょう。
もし、振替休日が代休とみなされ法定休日に出勤をしたとなった場合、休日手当の支払いが必要となります。給与支払い時において時間外労働手当の過不足が生じることは、労使トラブルの種になりかねないので、振替休日や代休について正しく理解しておきましょう。
当サイトでは、振替休日や代休について不安な点がある方のために、休日出勤時の正しい対応やそもそもとなる休日や休暇の定義について解説した資料を無料で配布しております。休日出勤時の対応が正しいか不安な方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご覧ください。
2. 振替休日とは

振替休日の取得期限をより深く理解するためには、振替休日について正しく知っておくことが大切です。ここからは、振替休日の要件や代休との違いについて見ていきましょう。
2-1. 振替休日の要件
労働日と休日の入れ替えを振替とみなすためには、下記の3つの要件を満たす必要があります。下記の要件を満たさないときは、振替が否認されてしまう可能性があります。最悪の場合、労働基準法に違反していると判断されてしまうこともあるため注意が必要です。
①就業規則への規定
制度の採用や取得期限などを、就業規則で規定しておく。規定がないときでも、従業員から個別に同意を得ていれば問題ない。
②事前に休日と労働日を決め、休日出勤の前日までに伝える
あらかじめ入れ替える日程を具体的に決定し、休日出勤の「前日」までに従業員へ伝えておく。
③法定休日の要件を満たしている
週に1回、もしくは4週4回の休日を与えるという法定休日の要件を満たしている。
関連記事:振替休日とは?定義や代休との違い、付与のルールを分かりやすく解説
2-2. 振替休日と代休の取得期限の違い
振替休日と似た制度として、「代休」というものがあります。代休とは「休日出勤した代わりに休みを取らせる」ことで、振替休日とは定義が異なります。
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
厚生労働省では、「振替休日」について下記のような解説をしています。
「振替休日は労働日と休日を入れ替える制度であるため、たとえ休日であった日に勤務しても休日出勤には該当せず、休日手当も発生しません。」
しかし、代休は休日出勤に該当するため、休日手当の支払いが必要になるという違いがあります。
また、代休には「必ず取らせなくてはいけない」という義務がない点も大きな特徴です。
代休の権利は振替休日と同様に2年間ありますが、いつ取っても問題ありませんし、取らなくても法定休日の要件が満たされていれば違法になることはありません。
ここが、勤務日前後に休みを取る必要がある振替休日との最大の違いでしょう。休みの日程を決めずに振替をおこなったときは、要件を満たせず代休だとみなされてしまう可能性があるため注意してください。
振替が否認された場合、法定休日に従業員を働かせると35%以上の休日手当が必要になります*。
関連記事:代休の取得期限はどのくらい?管理のポイントと併せて紹介
2-3. 所定休日と法定休日の違い
振替休日・代休で休日労働をする際に、考えなければならないのが「休日の定義」です。
労働基準法では、原則として週に1日以上の休日を取らせることについて規定しています。
この原則を「法定休日」と呼び、この法定休日以外に企業が就業規則などで独自に設けた休日を「所定休日」と呼びます。
たとえば週休2日の会社は1日が法定休日、残りの1日が所定休日ということになるのです。なお、法定休日に従業員を働かせると35%以上の割増賃金が必要になります。
そのため、代休で休日労働させる際には、所定休日なのか、法定休日なのかを事前に確認する必要があります。
また振替休日と代休で、割増賃金の考え方が異なります。振替休日の場合は基本的に休日手当が適用されないのに対して、代休は休日手当が適用されるというように、休日出勤の管理には正しい知識が必要になります。
当サイトでは、振替休日や代休の定義から運用方法などをまとめた資料を無料で配布しております。振替休日に関して不安なことがある担当者様はこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説
3. 週や月をまたいだ振替休日の取得は可能なのか?
結論から述べると週や月をまたいでも振替休日の取得は可能です。ただし、割増賃金や賃金支払いの5原則などの給与に関するルールにおいて気を付けなければならない点があります。それぞれ詳しく解説します。
3-1. 振替休日が週をまたぐときは割増賃金が発生する
振替休日の期限は2年であるため、週をまたいだ振替休日の取得は可能です。ただし、割増賃金の計算に気を付けなければなりません。
労働基準法32条と37条では、1日8時間、週40時間を超える労働をおこなったとき、25%の割増賃金を支払う義務があると定めています。
振替休日の取得期限を長めに設定しているときは、割増賃金が発生する可能性があるため注意しましょう。
たとえば月曜日から金曜日まで1日8時間、週40時間働いたあと、土曜日を労働日にしたときの週の労働時間は48時間になります。このオーバーした8時間に対して、時間外手当として25%の割増賃金が必要になるというわけなのです。
もちろん割増賃金を支払えば、週をまたいだ振替は可能です。しかし、割増賃金の発生を避けたいのであれば、1週間の中で振替をおこなっておくことをおすすめします。
3-2. 振替休日が月や年度をまたぐときは一旦給与を支払う
振替休日の取得期限を2か月や3か月などと長めに設定している企業では、休みの取得が月や年度をまたぐこともあるでしょう。
このような時は、たとえ勤務日と休みで労働した分の給与が相殺されるとしても、一旦給与を支払わなくてはいけない点に注意しましょう。
労働基準法24条には、労働によって確定した金額を全額支払わなくてはいけない「賃金全額払いの原則」が規定されています。
そのため給与の締め日をまたいで休みを取るときは、一旦は休日出勤に対する給与を支払い、休みを取得してから控除をおこなう必要があるのです。
この場合は、休日手当に対する割増賃金は不要です。しかし、週に40時間を超えた分の割増賃金は必要なので、正しく給与を計算するようにしましょう。
4. 振替休日の期限に関して企業が注意すること

この章では、振替休日の期限に関して企業が注意しておきたいポイントを紹介します。適切な労働環境を整えるためにも、しっかりと目を通しておきましょう。
4-1. 就業規則に振替休日の取得期限を決めておく
振替休日をおこなうときは、必ず就業規則に自社で定めた取得期限を明記しておきましょう。労働基準法上の2年という時効はあまりにも長く、振替休日が長期化する原因となってしまうためです。
「振り替える日程は1か月以内」などといったようにあらかじめ取得期限を決めておくと、運用や管理がしやすくなります。
4-2. 振替休日の取得が長期化しないように気をつける
先述したように、振替休日は入れ替えた勤務日の前後で取ることが好ましいです。そのため、振替休日の長期化はできるだけ避けるようにしましょう。
しかし、なかには業務の繁忙さによって指定された日に休みを設定できないこともあるかもしれません。こういったときは、就業規則に規定されていれば、振替休日の再設定や取得期限の延長をおこなうことが可能です。
ただし、振替休日の長期化は管理が大変になるうえ、休日確保や健康管理の観点で望ましくありません。最悪の場合、なかなか休みが取れずに従業員が過労で倒れてしまう可能性もあります。
上司や管理者は、部下の振替休日の取得が長期化しないように配慮し、きちんと休みが取れるように業務量を調整することが大切です。
4-3. 再振替は可能だが割増賃金に注意する
もし振替休日として振り替えた休日にやむおえず業務をしなければならなくなった場合、振替休日の再振替は可能です。
振替休日の再振替は法的にも特に規制されていません。
一方で、再振替しやすい環境になってしまった場合、振替休日の蓄積や未取得など不適切な労務管理につながってしまう可能性があります。
そのため、振替休日に労働が必要となった場合は振替日の変更ではなく、振替日の労働を休日出勤として扱い、代休を取得させる運用方法が望ましいと考えられます。
従業員が利用しやすい制度であるかという観点も重要ですが、適切な労務管理が行える仕組みであるかという観点も重要です。制度を運用しながらバランスを見てルールの調整を行えるといいですね。
5. 振替休日の取得期限は短めに設定しておこう

振替休日には明確な取得期限がなく、労働基準法上に定められた権利の消滅時効である2年が適用されます。
ただし、あらかじめ振り替えている休日と勤務日を指定しておく必要がある振替休日の性質上、振替が長期化することは望ましくありません。
就業規則などに自社ルールを設定し、なるべく短い期間内で休みを取らせるようにしてください。振替休日の取得が長期化して週をまたいだり月をまたいだりしてしまうと、割増賃金や給与支払いに影響を与えます。可能な限り、労働日の直前直後の休みと振り替えることを推奨します。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25