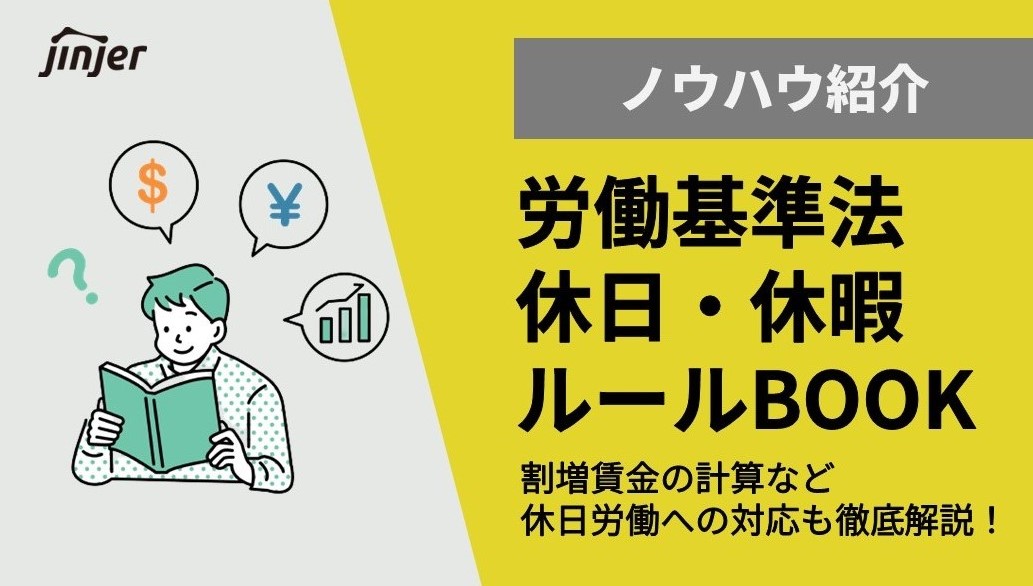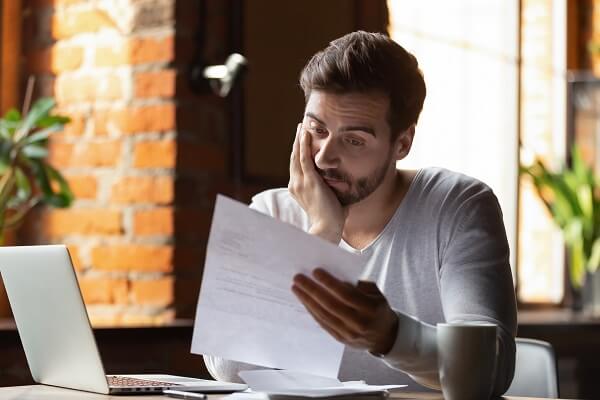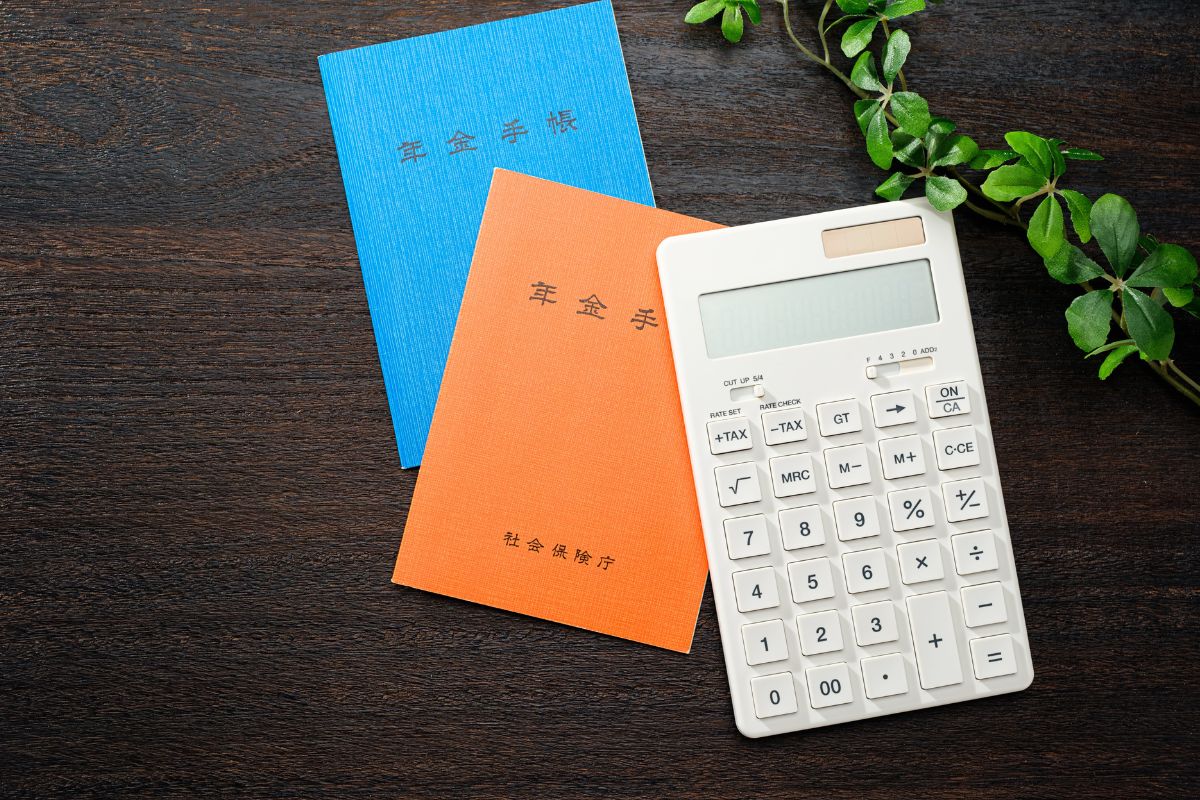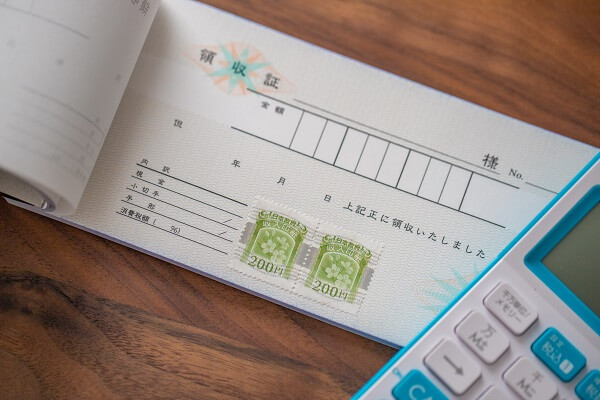連勤に関する労働基準法のルールや注意点を徹底解説

労働者の連勤や休日の規定は、労働基準法に定められています。規定では、原則1週間に1日の休日、もしくは4週間を通じて4日の休日が必要です。
ただし、設定している労働時間制度や休日の種類によっては、別のルールが発生するケースもあります。場合によっては割増賃金が発生するため、企業側は連勤の意味や休日の定義をよく理解しておく必要があるでしょう。今回は、連勤に関する労働基準法のルールと注意点を解説します。
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
目次
1. そもそも「連勤」とは

そもそも連勤とは、連続勤務あるいは連続出勤のことです。休日の翌出勤日から、次の休日までの日数が2日以上続く勤務状態を意味します。
法律用語ではなく、連日出勤している状態を表すときに使われる用語です。広く一般に使用される用語のため、本記事では休日を挟まず勤務する状態を連勤と表記します。
2. 連勤は何日を超えると違法?連勤に関する労働基準法のルール

労働基準法では、労働者に与えられる休日の日数が定められています。休日が与えられる要件によって、連勤の日数や割増賃金の有無が異なるため、休日の定義や種類を把握しておく必要があります。
2-1. 連勤に関する労働基準法のルール
労働基準法第35条では、会社(使用者)が労働者に与えるべき休日に関するルールを定めています。使用者は労働者に対して、以下のいずれかを選択して休日を与えなければなりません。
- 週1日
- 4週間を通じて4日
参考:労働基準法|労働局
この法定休日を遵守しない連勤は違法とされ、企業には厳しいペナルティが課せられます。
法定休日とは
法定休日とは、労働基準法で定められた休日で、休日とは労働義務のない日と定義されています。
法定外休日(所定休日)とは
また、法定外休日は労働契約や就業規則に基づいて付与されるもので、法定休日とは区別されます。例えば、週1日の法定休日を設ける会社で実際に週2日の休日がある場合、1日は法定休日、もう1日は法定外休日となります。
2-2. 連勤できる日数は原則12日まで(週休1日の場合)
このように使用者は、原則1週間に1日以上与える必要があるため、連勤できる日数は原則12日までとなります。また、例外的に4週間に4日以上の休日を労働者に与える方法もあります*。
就業規則や労働契約で企業ごとに定められた休日は、法定外休日と呼びます。祝日や創立記念日、お盆・年末年始の休日などに、法定外休日を設定しているケースが多いでしょう。
*参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov法令検索
2-3. 休日の種類
休日には、法定休日・法定外休日の他に「振替休日」「代休」もあります。振替休日とは、休日出勤が必要になったときに、あらかじめ休日と労働日を入れ替えて対応する休日です。
休日は労働基準法で1週間に1日と定められているため、法定休日に出勤すると割増賃金が発生します。しかし、前もって振替休日を指定し取得させることで割増賃金は発生しません。
また、代休とは休日出勤をした後に、別の労働日を休日に設定する休日です。代休の場合は休日と定められた日に出勤し、休みを別の日に取る設定のため、出勤した休日には割増賃金が発生します。
関連記事:振替休日と代休の違いは?設定方法や法律違反になる場合を解説
2-3. 休日と休暇の違い
休日と似た言葉に、「休暇」があります。日常生活では、休日と休暇を混同して使用しているかもしれませんが、労働基準法では休日と休暇はまったく異なる用語です。
休暇は事前の申し出により、就業規則や労働契約で定められた労働日に休むことを指します。まとめると、労働者が労働の義務を負わない日が「休日」、労働者が労働の義務を負っているが、免除された日が「休暇」です。
労働基準法第39条では、休日以外に年次有給休暇を与えなくてはならないことも明示されています。年次有給休暇を労働者に与えなくてはならない要件は、以下のとおりです。
- 雇入れ日から起算して6ヵ月間継続して勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
雇入れら6ヵ月を超えて継続勤務する労働者には、1年ごとに年次有給休暇の日数を加算しなくてはなりません。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
3. 連勤に関するルールで企業が注意すること

労働基準法に準拠した連勤であれば違法ではありませんが、いくつか気を付けたいポイントがあります。採用している労働時間制度によって連勤可能日数が異なったり、休日の種類によって割増賃金が発生したりするからです。
ここでは、企業側が理解しておきたい注意点を解説します。
3-1. 採用している労働時間制度によって最大連勤日数が異なる
連勤できる最大日数は、企業が定める労働時間制によって異なります。原則、使用者は労働者に1週間1日以上の休日を与える必要があります。
例外的に4週間のうち4日の休日をまとめて取得させても、労働基準法上は問題ありません。例えば、初日に出勤させ、最終週に4日まとめて休日を設定すれば最大24日の連勤も可能になります。ただし労働者の健康管理上、過度な連勤は避けましょう。
3-2. 雇用形態に限らずルールが適用される
パート・アルバイトなら、無制限に連勤させてもよいと勘違いしやすいですが、雇用形態に関わらず労働基準法第35条の休日ルールは適用されます。雇用形態に関わらず1週間に1日以上、あるいは4週に4日以上の休日が必要です。
特にシフト制では、労働者それぞれの休日を把握しにいため、労働基準法に違反する可能性があります。罰則を避けるためにも、労働者の連勤管理は重要です。
関連記事:法定休日と所定休日の違いや運用方法をわかりやすく解説
3-3. 振替休日で労働日を移動するときは連勤日数に注意
振替休日で労働日と休日を入れ替えるときは、連勤が労働基準法を超えていないかを確認しましょう。労働日と休日を振り替えた後に、1週間に1日以上の休日がなく、週40時間以上の労働となった場合は時間外労働に対して割増賃金が発生します。
また、振替休日を与えていたとしても、週に1日、もしくは4週に4日の休日がない場合は違法となるため、労働基準法に則って休日を計算する点に注意が必要です。
関連記事:振替休日とは?定義や代休との違い、付与のルールを分かりやすく解説
3-4. 代休を使うときは割増賃金が発生する
あらかじめ休日と労働日を入れ替えて代休とするときは、休日だった日に割増賃金が発生します。割増賃金とは、休日労働や時間外労働に対して通常賃金に割増して加算される賃金です。
休日労働に対する割増賃金は、通常賃金の35%、時給換算が1,000円の場合は、代休に伴う休日労働は時給1,350円です*。通常の労働日は定められた時間を超えて労働させると時間外労働となり、25%の割増賃金が発生します。
しかし、休日労働は労働時間が定められていないため、時間外労働の概念がなく、時間外労働分の割増賃金は発生しません。
*参考:法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省
関連記事:代休の定義や振休との違い・運用のポイントを詳しく解説
3-5. 連勤による未払い残業代が発生していないか確認する
長期間にわたって連勤している場合は、残業代がきちんと支払われているかどうかを確認しましょう。残業代請求権は、発生から5年(当分の間は3年)が経つと時効消滅しますが期間内は請求が可能です。(労働基準法第115条、同法附則第143条第3項)
参考:改正労働基準法等に関するQ&A
そのため、企業は従業員の労働時間を適切に管理し、未払い残業代が発生しないよう注意する必要があります。
4. 連勤において違法になるケース


それでは実際に連勤において法律違反になるケースとはどんなものでしょうか。該当するケースがないよう、先に把握しておきましょう。
4-1. 労働基準法違反となる連勤のケース
法定休日が週1日の場合は12連勤、4週間を通じて4日の場合は48連勤が上限です。この上限を超えて労働者を連勤させることは、労働基準法違反に当たります。
ただし、あくまでも法律上の話であり、労働者への負担を考えると、現実的ではないでしょう。また、常に12連勤(または48連勤)が認められるわけではなく、1週間に1日(または4週間を通じて4日)の法定休日を確実に与えなければなりません。さらに、時間外労働の時間数や休日労働(法定休日における労働)の日数は、労働者側との間で締結した労使協定(36協定)のルールに従う必要があります。36協定の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせている場合も、労働基準法違反です。労働基準法に違反する連勤を指示した場合、労働基準監督署による行政指導や刑事罰の対象となります。
4-2. 労働契約法違反となる連勤のケース
使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるように、必要な配慮をする義務を負います(労働契約法第5条)。
参考:労働契約法のあらまし|厚生労働省
これを「安全配慮義務」といいます。過度な連勤は、労働者が健康を害するリスクを高めます。労働基準法の上限は超えていなくても、あまりにも長期間の連勤を指示することは、使用者が安全配慮義務に違反している可能性が高いです。安全配慮義務違反となる連勤を指示した場合、使用者は労働者に対して損害賠償責任を負います。
4-3. 労働安全衛生法違反となる連勤のケース
労働安全衛生法により、使用者には快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保することが義務付けられています(同法第3条第1項)。
参考:労働安全衛生法|厚生労働省
労働者に対して過度な連勤を命じることは、上記の安全・健康確保義務に違反する可能性があります。労働安全衛生法に違反する連勤を指示した場合、労働基準監督署による行政指導などの対象となります。
5. 労働基準法に則った労働者の連勤管理を!

連勤や休日の理解できていない場合、故意でなくても労働基準法に違反してしまう可能性があります。罰則として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されるケースもあることを理解しておきましょう。
特に変形労働時間制を取り入れている企業や代休・振替休日を使う場合は、連勤を見逃しやすくなります。連勤の超過を防ぐには、労働者の勤怠管理の徹底が重要です。連勤の超過や代休による割増賃金コストを減らし、労働基準法違反を防げます。
特に労働者によって労働日・休日が異なる企業では、勤怠管理の一元化や簡素化して、業務の軽減を図ることも可能です。
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.11.26
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.11.20
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.11.15
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.11.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.10.31
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.11.19
勤怠管理の関連記事
-


勤怠管理システムの要件定義とは?基本の流れとポイントをチェック
勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.11.20
-

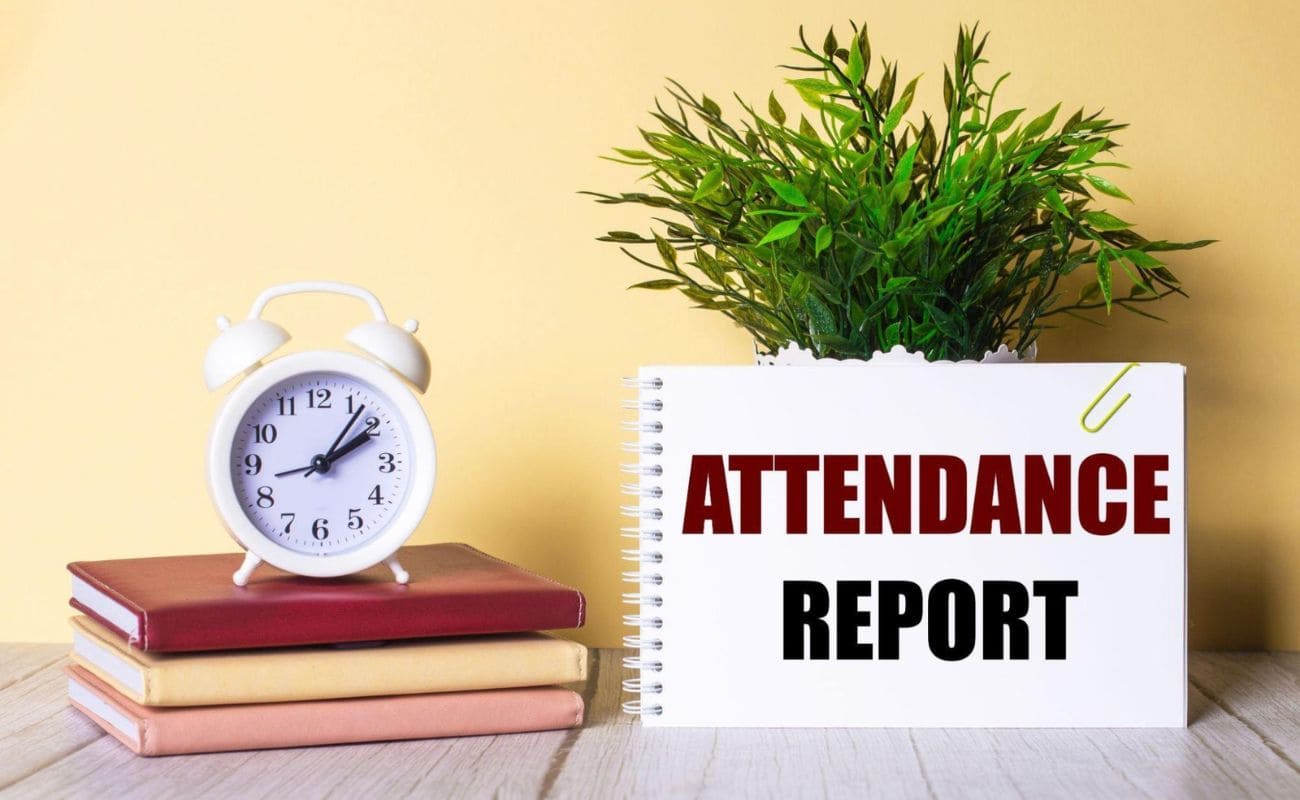
勤怠管理システムの費用対効果とは?判断方法を詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.11.10更新日:2024.11.20
-


タイムカードと勤怠管理システムの違いを詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.08.01更新日:2024.11.20