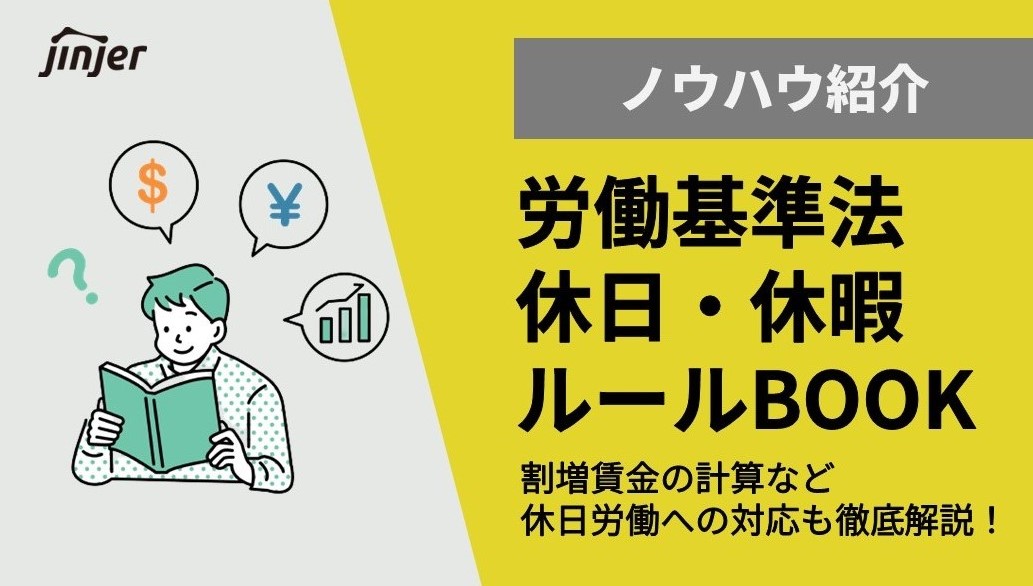法定休日と所定休日の違いは?運用方法や注意点をわかりやすく解説

休日は、法定休日と所定休日の2つに大きく分けられます。同じような休日に感じられますが、労働者を出勤させた場合の割増賃金など、大きく異なる点もあるため注意が必要です。この記事では、法定休日と所定休日の違いや運用方法などについてわかりやすく解説します。人件費などにも大きく関わるため、2つの休日の違いをしっかりと理解しておきましょう。
関連記事:法定休日と祝日の違いや割増賃金の計算法を詳しく解説
目次
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
1. 法定休日と所定休日の違いを簡単に解説


法定休日と所定休日の大きな違いは、法律によって定められているかどうかです。ここでは、それぞれの休日の定義について確認しておきましょう。
1-1. 法定休日とは労働基準法第35条で定められた休日
法定休日とは、労働基準法第35条で規定されている休日のことです。この条文には、使用者は労働者に対して、週ごとに最低1回、または4週間で4回の休日を与えなければならないことが記載されています*。
たとえば、1週間を月曜から日曜と定めている企業で、月曜から土曜まで出勤した労働者に対しては、日曜を法定休日として与えなければなりません。
*参考:e-Gov|労働基準法第35条
1-2. 所定休日とは法定休日以外に企業が定めている休日
所定休日とは、法定休日以外に、使用者が労働者に与える休日のことです。法定外休日とも呼ばれます。
前述のとおり、労働基準法第35条によると最低週1回の休日を与えればよいことになっていますが、実際には土日の2日間を休みとしている企業も多いでしょう。労働基準法第32条によって、労働時間の上限が定められているからです。この条文には、使用者は労働者に対して、1週間に40時間を超えて労働させてはならないことが記載されています*。
*参考:e-Gov:|労働基準法第32条
1日8時間労働とすると、月曜から金曜まで5日間働いた時点で労働時間の合計が40時間に到達してしまうため、土曜を所定休日としている企業が多いのです。
また、所定休日は企業独自の方針や業務の特性に応じて設定されるため、業種や職種による違いがあります。これにより、企業が労働者の働き方に対して柔軟な対応ができるようになり、労働者のモチベーションやワークライフバランスの向上にも寄与します。
さらに、所定休日を適切に設定することは、従業員の健康管理や、生産性の向上にもつながるため、重要な人事戦略の一環と位置付けられています。
関連記事:所定休日とは?その意味や設定のポイント・注意点を解説
2. 法定休日と所定休日と区別すべき理由
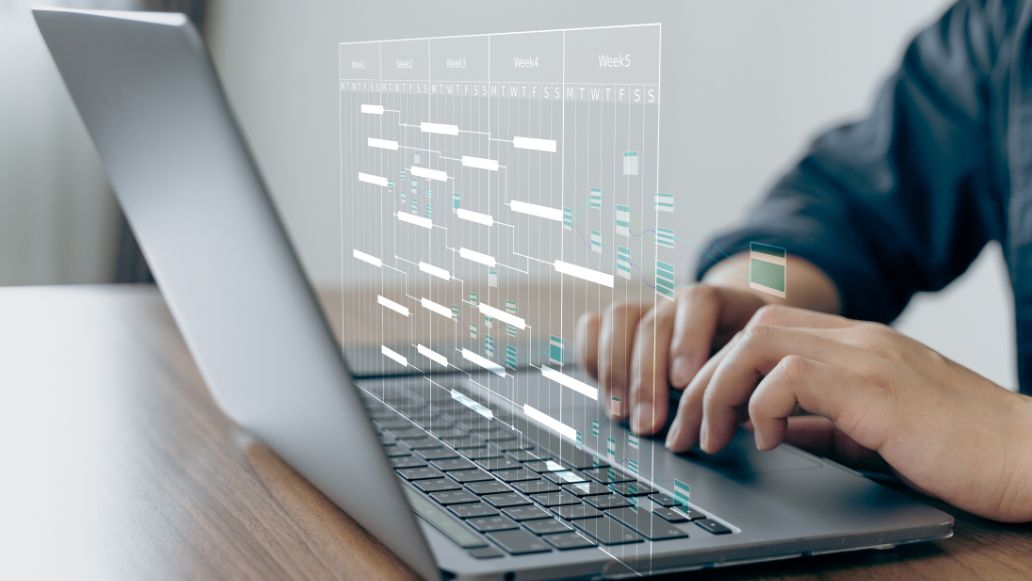
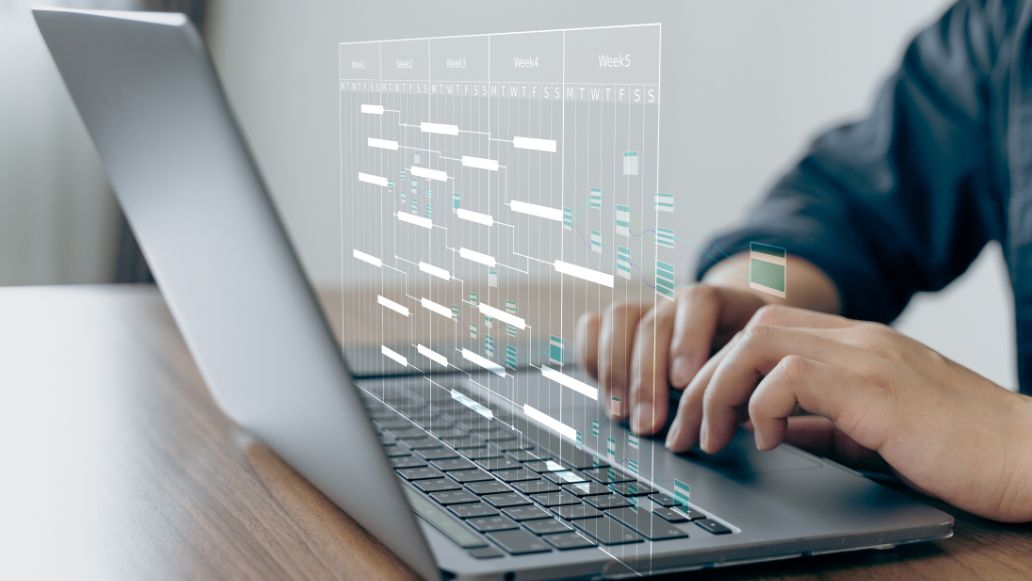
その理由は、所定休日か法定休日かによって、休日労働に対する割増賃金の計算方法が異なるためです。正確な給与計算を行うために区別した管理が求められます。企業が人件費を適切に管理し、労働法に則った運用を行うためにも不可欠です。
したがって、企業はこれらの休日の違いを把握し、適切な就業規則を定めることが重要です。
3. 法定休日と所定休日は賃金の割増率が異なる

法定休日と所定休日は、労働者にとってはどちらも自由に過ごせる休日であるため、大きな違いはありません。ただ、出勤した場合の賃金割増率が異なるため、企業側は2つの休日をしっかりと区別しておく必要があります。
3-1. 法定休日の割増率
法定休日に労働させた場合の割増賃金率は35%です。そのため、法定休日に労働させる場合は通常の1.35倍の賃金を支払う必要があります。
この法律は、労働者の休息を保護するために設けられており、事業主はこれを遵守しなければなりません。また、法定休日以外の所定休日においては、割増賃金率が異なるため、企業はそれぞれの休日の取り扱いを明確にして、適切な賃金計算を行うことが求められます。
3-2. 所定休日の割増率
所定休日に労働させる場合は、通常の労働と同様に扱われるため、週40時間を超えた労働に対して、1.25倍の時間外労働手当を支払わなければなりません。
人件費に大きく関わるため、法定休日と所定休日をしっかりと区別したうえで、社員の労働時間を管理することが大切です。特に、企業は法定休日に労働をさせた場合は1.35倍の割増賃金が適用されるため、賃金コストに与える影響が大きくなることを理解しておく必要があります。
また、休日の設定や運用に関しては、労働基準法の遵守を徹底し、就業規則に明記することが求められます。これにより、労働者の権利を保護しつつ、企業としての適正な運営が確保されます。
関連記事:法定休日と祝日の違いや割増賃金の計算法を詳しく解説
4. 振替休日と代休の違いとは
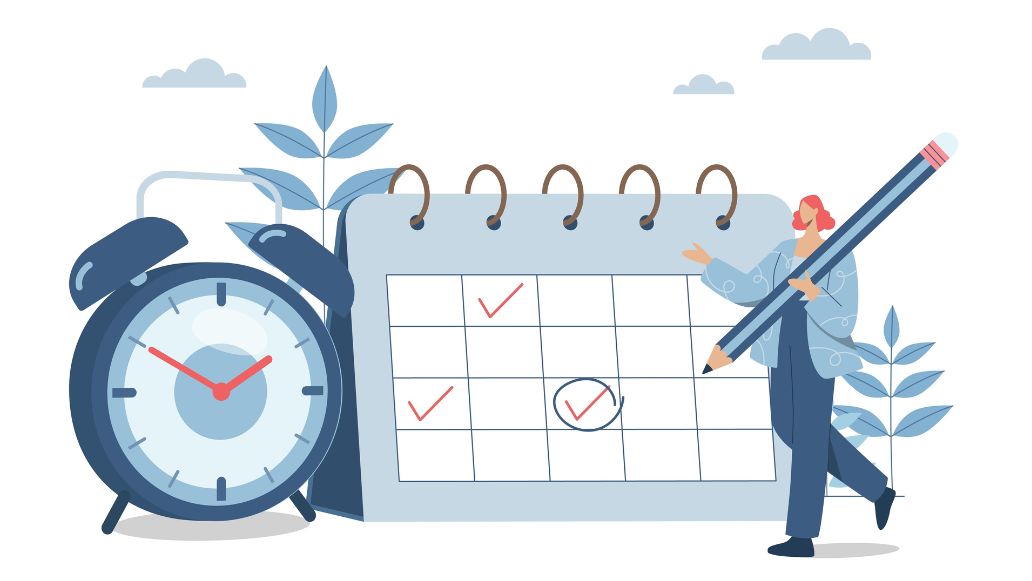
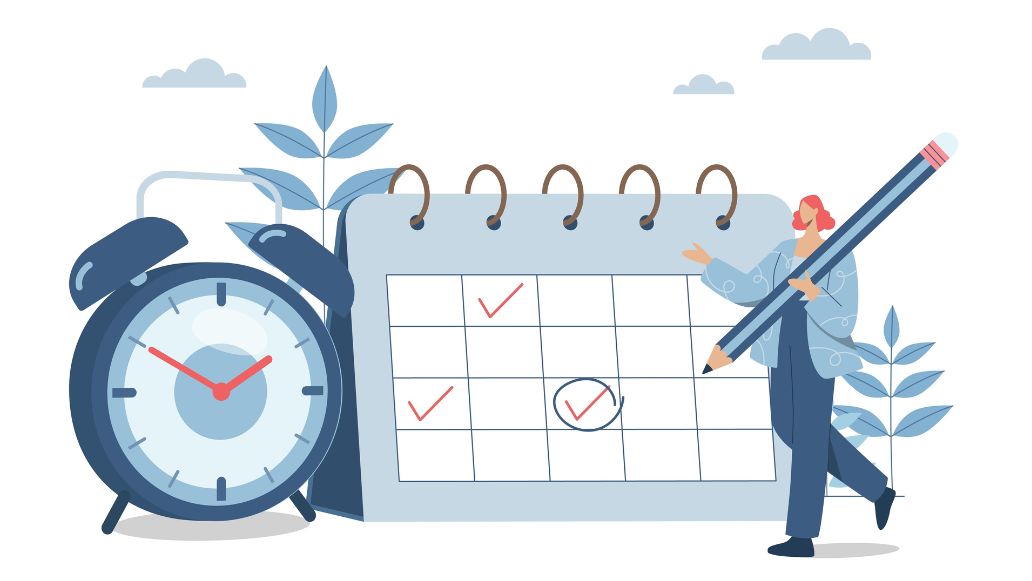
法定休日や所定休日に労働者を出勤させる場合、振替休日や代休を与えることが多いでしょう。2つの休日は同じように感じられますが、以下のように大きな違いがあります。
4-1. 振替休日とは
振替休日とは、出勤日と休日を事前に交換することで与えられた休日のことです。振替休日を与える場合は、出勤日と休日が入れ替わっただけであるため、休日労働という扱いにはなりません。
1.25倍や1.35倍といった割増賃金を支払う必要もないのです。ただし、休日を次の週に振り替えて、週の労働時間が40時間を超える場合は、超えた時間に対して1.25倍の割増賃金を支払う必要があります。
4-2. 代休とは
一方の代休とは、休日出勤をさせたあとで、別の日に与えた休日のことです。振替休日とは異なり、出勤日は休日労働として扱う必要があります。所定休日に出勤させた場合は割増賃金を含んだ1.25倍、法定休日に出勤させた場合は1.35倍の賃金を支払う必要があるのです。
割増率を誤ってしまうと給与未払いのリスクを負うことになるので、正しく理解しなければなりません。当サイトでは、休日や代休、振替休日などの特に認識の齟齬が起きやすい内容を、労働基準法に沿って解説した資料を無料で配布しております。代休や振替休日で不安な内容がある担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:振替休日と代休の違いは?設定方法や法律違反になる場合を解説
5. 法定休日や所定休日を運用するときの4つのポイント


法定休日や所定休日を運用するときは、休日の単位は暦日とする、休日に関する事項を就業規則に記載する、法定休日に出勤させる場合は36協定を締結する、といったポイントに注意しましょう。以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
5-1.休日の単位は暦日とする
法定休日や所定休日を与える場合は、原則として暦日としなければなりません。暦日とは、午前0時から午後12時までの24時間のことです。たとえば、所定休日である土曜日に1時間だけ出勤させた場合、休日を与えたことにはならないため注意しましょう。
また、午前6時を起点する24時間を休日とするといった設定方法も、基本的には認められません。ただし、旅館業や自動車運転者などの一部の業種については、条件を満たすことで、暦日ではなくても休日と認められるケースもあります。
5-2. 雇用形態や労働形態の違いに注意する
労働者の雇用形態や労働形態によって、休日出勤手当の取り扱いが異なるため注意が必要です。パートやアルバイト、契約社員は、正社員と同様に休日出勤手当が支払われるものの、契約社員に関しては派遣元との36協定が結ばれていることが重要です。
さらに、年俸制の場合は、休日出勤手当が年俸に含まれているかどうかにより支払いが異なります。また、フレックスタイム制では休日出勤を想定していないため、別途手当の支払いが求められます。このように、それぞれの雇用形態や労働形態の特性を理解しておくことが、適切な休日の運用に繋がります。
5-3.休日に関する事項を就業規則に記載しておく
使用者は、休日に関する事項を就業規則に記載して、労働者に対して明示しなければなりません。就業規則には、1週間の起算日などを記載しましょう。とくに規定を設けない場合は、日曜日が起算日となります。
無理に法定休日を特定する必要がないことにも注意しましょう。「できるだけ法定休日を特定する」という通達はありますが、法律的な義務はありません。
5-4.法定休日に出勤させる場合は36協定を締結しておく
法定休日に出勤させる場合は、36(サブロク)協定を締結しなければなりません。36協定とは、労働基準法第36条に基づいた労使協定のことで、法定労働時間を超えて働かせる場合に必要な協定です。
一般的には、労働者側と使用者側で内容を協議したうえで締結します。たとえば、法定休日を日曜日としている企業において、日曜日に労働させる場合は36協定を締結しておく必要があります。
また、36協定を締結したからといって、労働時間の上限がなくなるわけではありません。36協定を締結したあとも、時間外労働時間には上限規制があり、上限を超えて働かせると労働基準法違反となるため注意が必要です。
関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説
6. 法定休日と所定休日の違いを理解して正しく運用しよう!
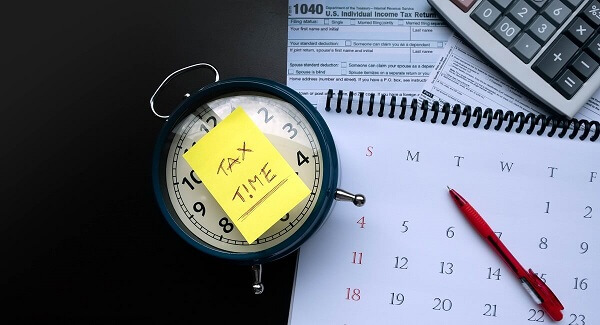
今回は、法定休日と所定休日の違いや、休日を運用するときのポイントについて解説しました。労働者にとっては同じような休日ですが、使用者にとっては大きな違いがあります。人件費などに大きく関わるため、違いをしっかりと理解したうえで運用していきましょう。
法定休日や所定休日を運用するときは、暦日単位で24時間連続した休みを与える、必要に応じて36協定を締結する、といったポイントに注意しなければなりません。労働基準法に違反することがないよう、理解を深めておきましょう。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちら「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
休日休暇の関連記事
-


休日出勤の振替休日は有給取得に変更できる?条件と注意点を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.22更新日:2024.10.09
-


法定休日に対する振替休日が認められる場合について解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.08更新日:2024.10.09
-


所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.08更新日:2024.09.17