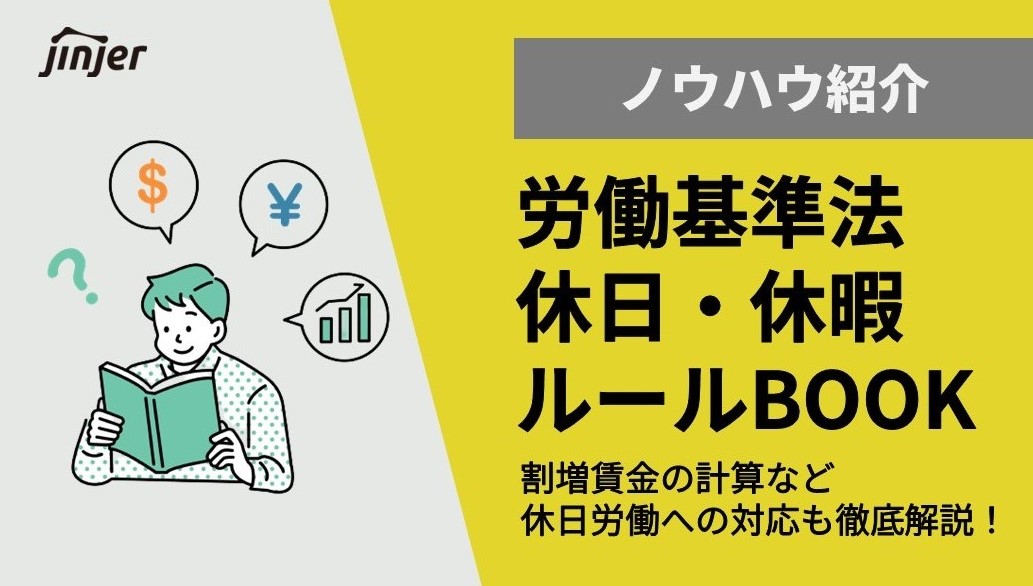法定休日に対する振替休日が認められる場合について解説
更新日: 2024.10.9
公開日: 2021.9.8
OHSUGI

急な仕事に対応するため、労働者に対して法定休日に出勤を求めるケースもあるでしょう。法定休日に出勤させた場合は、代わりの休日を与えるのが一般的ですが、法定休日に振替休日は適用されるのでしょうか?
この記事では、法定休日に対する振替休日が認められる条件や、振替休日を与えるときのポイントなどについて解説します。労働基準法に違反することがないよう、しっかりとチェックしておきましょう。
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
1. 法定休日に振替休日は適用される?

法定休日とは、労働基準法によって定められている休日のことです。この法律の第35条に基づき、使用者は労働者に対して、最低でも1週間に1回、または4週間で4回の休日を付与しなければなりません。労働者の健康状態を維持することは、業務の効率化や生産性の向上にもつながるため、適切な休日を与えることが大切です。
1-1. 法定休日にも振替休日は適用される!
法定休日にも振替休日は適用されます。たとえば、日曜日を法定休日としている企業において、日曜日に出勤してもらう代わりに、次の火曜日を振替休日とすることは可能です。ただし、振替休日として認められるためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。詳しくは後述しますので、参考にしてください。
関連記事:振替休日とは?定義や代休との違い、付与のルールを分かりやすく解説
2. 振替休日と代休の違いをわかりやすく解説

振替休日と似た言葉として代休がありますが、2つの休日は大きく異なります。ここでは、両者の違いをわかりやすく解説しますので、チェックしておきましょう。
2-1. 振替休日:出勤日と休日を事前に交換
振替休日を与える場合は、休日出勤をさせる前に、出勤日と休日を入れ替える必要があります。振替休日を与える場合は、出勤日と休日が入れ替わっただけであるため、仮に法定休日に出勤したとしても、36協定上の休日労働には該当しません。
(例)日曜日を労働日とする代わりに、水曜日に法定休日を事前に交換
| 変更前 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 法定休日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 法定外休日 |
| 変更後 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 労働日 | 労働日 | 労働日 | 法定休日 | 労働日 | 労働日 | 法定外休日 |
通常、法定休日に出勤させる場合は1.35倍の割増賃金を支払う必要がありますが、振替休日を与えるなら割増賃金を支払う必要はないのです。ただし、休日を翌週に移動して、1週間の労働時間の合計が40時間を超えるような場合は、超過した労働時間に対して1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。
2-2. 代休:休日出勤をさせたあとに別の休日を付与
休日出勤をさせたあとに別の休日を付与すると、その休日は代休という扱いになります。振替休日には該当しないため注意しましょう。
(例)日曜日に労働させた後で、水曜日に代わりの休日を付与
| 変更前 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 法定休日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 法定外休日 |
| 変更後 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 法定休日に労働 | 労働日 | 労働日 | 労働日に休む | 労働日 | 労働日 | 法定外休日 |
代休の場合は事後に休みを変更するため、休日に働いた分は36協定上の休日出勤としてカウントし、規定の割増賃金を支払う必要があります。
法定休日に出勤させた場合は1.35倍、法定休日以外の所定休日に出勤させ、週の労働時間が40時間を越えた場合は1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。法定休日の出勤であっても、振替休日にするのか代休にするのかで、割増賃金が発生するか異なります。また、時間外労働の割増賃金の支払い義務が追加で生じる可能性もあるので、定義から違いを明確にしておきましょう。
当サイトでは、振替休日や代休について、用語の定義やおすすめの使い分け方法、取らせる際の対応方法などを解説した資料を無料で配布しております。振替休日・代休の運用や計算で不安な内容がある担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:振替休日と代休の違いは?設定方法や法律違反になる場合を解説
3. 法定休日に対する振替休日が認められる条件

法定休日に対する振替休日を有効なものとするためには、就業規則に記載しておく、労働者に対して前日までに予告する、振替休日とする日を明確に指定する、といった条件をクリアする必要があります。それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。
3-1. 振替休日について就業規則に記載しておく
振替休日の制度を運用するためには、会社の就業規則に記載しておく必要があります。就業規則には、休日を別の日に振り替える場合があること、振り替える場合の手続き方法、告知の方法などについて記載しておきましょう。
3-2. 労働者に対して前日の勤務終了までに予告する
法定休日を別の日に振り替える場合、その労働者に対して前日の勤務終了までに予告する必要があります。
たとえば、法定休日を水曜日としている企業において、水曜日に出勤させて、翌日の木曜日に振替休日を与える場合は、火曜日の勤務終了までに予告しなければなりません。
また、水曜日に出勤させて、その前日の火曜日に振替休日を与える場合は、月曜日までに予告する必要があります。予告をせずに出勤させ、あとで休日を与えると、代休という扱いになるため注意しましょう。
当サイトでは、振替休日と代休で、割増賃金の金額がいくらかや休日出勤時の対応などがどのように異なるかをまとめた資料を無料で配布しております。そもそもとなる休日と休暇の定義から解説しておりますので、休日出勤時の対応で不安な点がある担当の方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご覧ください。
3-3. 振替休日とする日を明確に指定する
振替休日を与える場合は、その日を明確に指定する必要があります。たとえば、法定休日である日曜日に出勤させ、「別の日に休みを与える」といった曖昧な指示を出すことはできません。翌週の水曜日を休みとするなど、振替休日を明確に指定しましょう。
3-4. 週に1日もしくは4週で4日の休日が確保されている
法定休日に対する振替休日が認められるためには、当然ながら法定休日が確保されている必要があります。先述のとおり、労働基準法によって企業・事業者は、従業員に対して1週間に1日もしくは4週間で4日の法定休日を与えることが義務付けられています。
1週間に1日もしくは4週間で4日の休日を付与していない場合、振替休日が認められるどころか労働基準法違反にあたります。
4. 法定休日に対する振替休日を与えるときの注意点

法定休日に対する振替休日を与えるときは、法律や就業規則に従うだけではなく、労働者の働きやすさについても考慮しましょう。具体的には、休日を振り替える頻度はできるだけ少なくする、出勤日が連続しすぎないようにする、労働者の希望を考慮する、といったポイントに注意することが大切です。
以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
4-1. 頻繁に振り替えると労働者の負担が大きくなる
法定休日に出勤させても、条件を満たしたうえで振替休日を与えれば、法律上は問題ありません。ただし、労働者の負担が大きくなったり、ストレスを感じたりする可能性もあるため注意しましょう。たとえば、法律や就業規則に基づき、法定休日の前日に振替休日の予告をすると、労働者が休日の予定をキャンセルしなければならないケースもあります。
頻繁に急な休日出勤を求められ、休日の予定が立てられないと、有意義な休みを過ごせないでしょう。健康状態が悪くなったり、仕事へのモチベーションが下がったりする可能性もあるため注意が必要です。
4-2. できるだけ近接した振替休日を設定する
法定休日に出勤させる場合、できるだけ早めに振替休日を与えるようにしましょう。
おすすめは、同一週内に振替休日を与えることです。週をまたいでしまうと、法定労働時間である40時間を越えた労働になり、時間外労働分の割増賃金が必要になってしまうためです。
また、結果的には同じ日数の休日が与えられるとしても、連続して出勤することは労働者にとって大きな負担です。休日出勤した翌週に与えたり、出勤日が連続しすぎないようにしたりするなど、労働者の負担が減るように考慮しましょう。無理に働かせることで、労働者が体調を崩したり、生産性が低下したりするケースもあるため注意が必要です。
4-3. 振替休日の有効期限を決めておく
振替休日の有効期限を決めておくことは、労務管理において非常に重要です。振替休日が有効な期間は、就業規則に明記しておくことが推奨されます。
労働基準法第115条によると、休みを取得する権利は最長で2年間有効ですが、長期間にわたり振替休日の管理を行うのは困難です。そのため、労働者に適切なタイミングで振替休日を与えるためにも、定めた期限を設けることが効果的です。
特に、勤務日と振替休日との間が長くなると、労務管理が複雑になり、長時間勤務や割増賃金の未払いのリスクが増します。給料日の締め日までに振替休日を与えることで、賃金計算の負担を軽減し、労働者にも安心感を提供することができます。
4-4. 半日や時間単位での振替は不可
振替休日を半日や時間単位で付与することはできません。
労働基準法では、休日は原則として暦日(0時〜23時59分)で与えることが求められています。そのため、半日勤務とすることは、勤務時間の短縮に過ぎず、真の休日として認められません。企業が独自に「振替休日の半日取得は可能」と定めた場合でも、それは無効とされるため、注意が必要です。
一方、休暇に関しては半日や時間単位での付与が可能ですが、法定休日の振替においてはこの点を留意しておかなくてはなりません。
4-5. 未消化は労働基準法律違反になる可能性あり
振替休日を適切に付与せずに放置していると、未消化の振替休日に関して労働基準法違反になる可能性があります。
労働基準法第24条では、全ての賃金を正しく支払うことが求められており、特に振替休日を与えずに基礎賃金だけを支払うことは認められていません。
したがって、未消化の振替休日がある場合は、必ず給与で精算するなどの対応を行う必要があります。これを怠ると、企業は法律違反とみなされ、罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
5. 法定休日の振替休日管理には勤怠管理システムが最適

上述で解説のとおり、振替休日は週またぐ際に割増賃金が発生する可能性があること、法定休日の付与ルール「1週1回、4週4回」を遵守する必要があることなど、いくつか注意すべきルールがあるため、適切な休日管理が求められます。
しかし、従業員数の多い企業において、一人一人手作業により管理している場合、振替休日を正しく運用するには限界があるでしょう。
勤怠管理システムであれば、全従業員の振替休日の取得状況などがリアルタイムで把握できるため、適切な運用にくわえて、人事労務の負担も軽減させることが可能です。
特に、振替休日の通知が法定休日の前日の勤務終了までに行われることを確認する機能や、未消化の振替休日が労働基準法違反にならないよう自動的にリマインドしてくれるシステムを利用することで、企業は安心して労務管理を行うことができるでしょう。
休日も含めて勤怠管理全体を見直ししたいのであれば、勤怠管理システムの導入を検討してみても良いでしょう。
6. 法定休日に対する振替休日は適切に設定しよう!

今回は、法定休日に対する振替休日が認められる条件や、振替休日を与えるときの注意点などについて解説しました。振替休日を有効なものとするためには、就業規則に記載しておく、振り替える前日までに予告する、振替休日とする日を明確に指定する、といった条件を満たす必要があります。
法律や就業規則に従うだけでなく、労働者の負担が大きくならないよう考慮することも大切です。頻繁に振り替えると、休日の予定が立てられないだけでなく、労働者がストレスを感じたり、モチベーションが低下したりする可能性もあります。労働者の健康を維持しつつ、仕事の生産性を高めるためにも、振替休日は適切に運用していきましょう。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
関連記事:法定休日と所定休日の違いや運用方法をわかりやすく解説
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
休日休暇の関連記事
-


休日出勤の振替休日は有給取得に変更できる?条件と注意点を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.22更新日:2024.10.09
-


所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.08更新日:2024.09.17
-


法定休日と所定休日の違いは?運用方法や注意点をわかりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.08更新日:2024.09.11