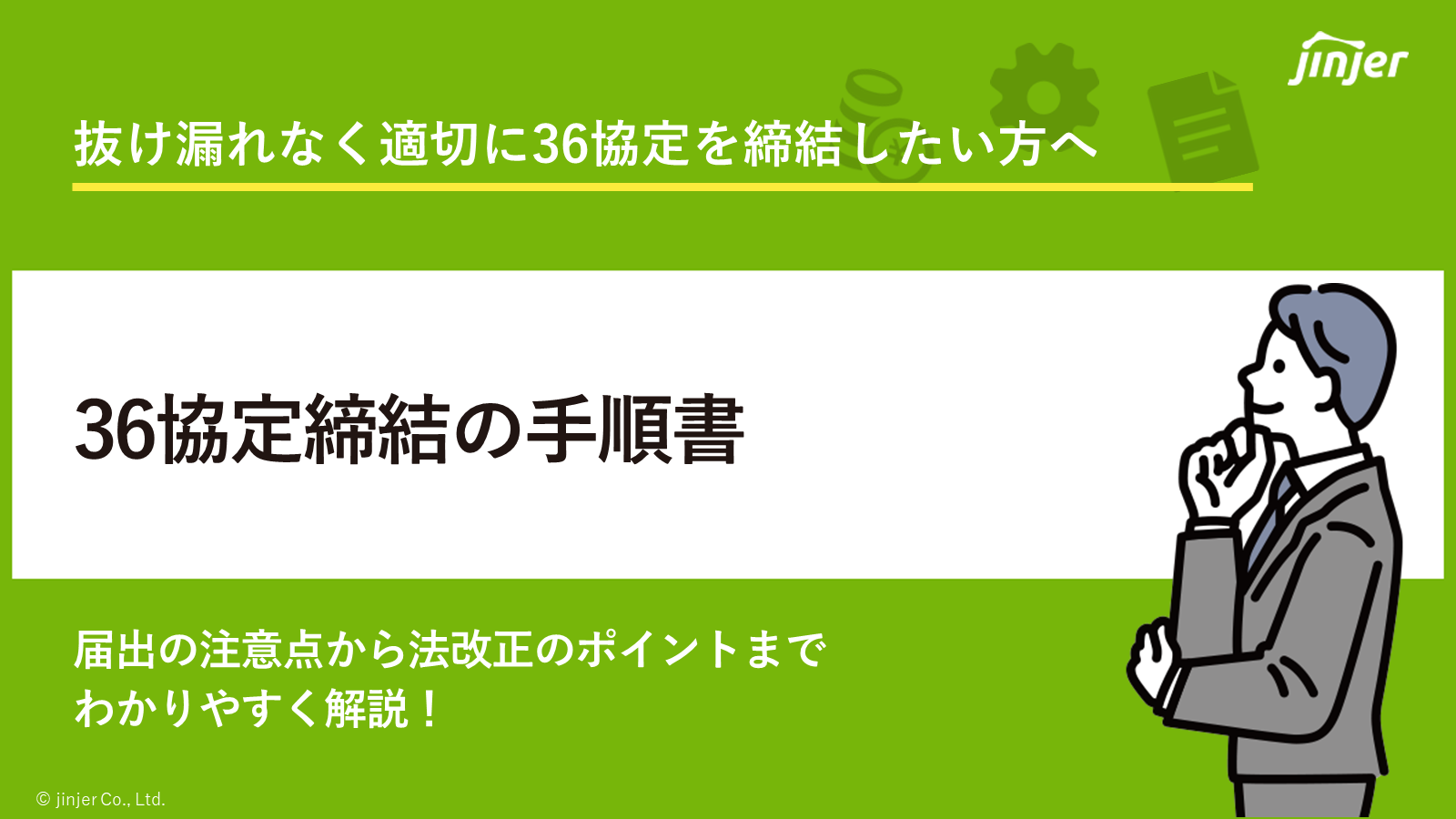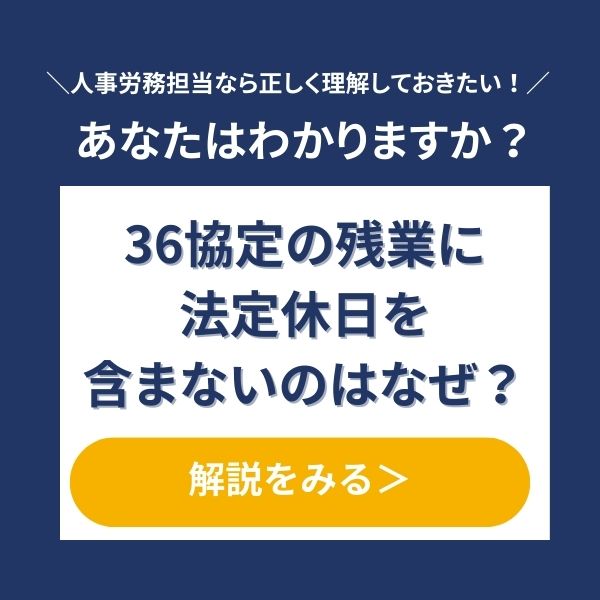36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

いわゆる残業にあたる時間外労働や規定された休日の労働などは当然のようにおこなわないほうがよく、労働時間はできる限り短くあるべきです。ですが、業務のなかで規定された労働時間以上の労働をしなければならないシーンもあるでしょう。
そのような場合に必要となるのが、36協定です。労働基準監督署に36協定を締結して届け出ることで、法で定められている時間以上の労働が認められるようになります。
今回は、36協定を届け出る方法や新様式と旧式との変更点といった基本ポイントについて解説します。36協定を無視して過剰な労働をさせてしまうと重い罰則が発生しますので、正しく届け出ましょう。
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
1. 36協定の届出の種類

36協定は、労働基準法の第36条に基づいて設けられたことに由来しています。働く側と雇用する側同士で締結します。日本の法律では、1週間あたり1日の休日があることを前提として、1週間で40時間、1日あたり8時間が労働時間として定められています。
この時間を超えて働くのであれば、36協定を締結して届け出る必要があります。締結せずに労働時間以上の労働をおこなうと、雇用する側に6ヶ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が科せられます。
36協定の書類にはさまざまな種類がありますが、これらは大きく2つに分類できます。
1-1. 一般条項のみ
一般条項のみの届出とは、36協定そのものを指しています。あらかじめ一般条項を締結しておくことで、1ヶ月で45時間、すなわち1年で合計して360時間の時間外あるいは休日の労働が可能となります。
1年単位の変形労働時間制の場合は条件が少し変わり、1ヶ月で42時間、1年で合計して320時間の時間外あるいは休日の労働を可能とするものとなります。
少しの違いですが、正しく把握しておきましょう。
1-2. 特別条項付き
一般条項で決められた時間以上の労働をおこなうためには、特別条項付きの36協定が必要となります。たとえば、決算による業務量の大幅な拡大や機械のトラブルに対する急な対応など、これらに当たるために一般条項で定めた時間以上働かざるを得ません。
ただし、特別条項付きといっても、残業時間を無制限にするものではありません。特別条項にも制限や適用するための条件がありますので注意してください。
2. 36協定の届出の作成方法

36協定を届け出る際は、以下それぞれの項目について協定する必要があります。
- 時間外労働をしなければならない具体的な事由
- 時間外労働をしなければならない業務の種類
- 時間外労働をしなければならない働く従業員の人数
- 1日のうち労働時間を伸ばせる時間
- 1ヶ月および1年における延長することができる時間数
- 協定の有効時間
また、特別条項を付ける必要がある場合は、さらに細かく協定しなければなりません。まず、基本の要件として定められた時間以上の労働の延長はできません。加えて、時間外労働をおこなうにあたり、働かなければならない事情について可能な限り具体的に定める必要があります。
時間外労働をしなければならない事情として、一時的あるいは突発的であること、1年の半分を超える労働に満たないと見込まれることが必要です。
2-1. 36協定の届出に必要となる代表者と要件およびその選出方法
36協定は、働く側の代表者と雇用する側の二者によって締結されるものです。36協定を締結するにあたり、働く側は代表者を選出しなければなりません。
もし、働く側の過半数によって構成された労働組合があるのであれば、こちらと協定をおこないます。労働組合がなければ、働く側の過半数のうちから代表者を選出します。労働組合がない場合の代表者は、選出にあたっていくつか要件があります。
まず、代表者は管理監督者でないものに限られます。これは、労働基準法の41条2号で触れられているものに該当しないという意味です。
選出は、協定の締結ためであることを周知したうえでの選挙または挙手によっておこなわれます。雇用する側による選出や親睦会の幹事などを勝手に代表者にしてしまうと、その協定は意味がないものとして効力を発揮しません。
関連記事:36協定の労働者代表とは?なる人の特徴や選出方法を解説
2-2. 届出の際の注意事項について
36協定を締結したら労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定を届け出る際は様式第9号の書類が用いられます。
なお、協定書そのものは出さなくても問題はありません。協定書は届出の書類と兼用することが可能です。届出の書類に労働所の署名あるいは押印をし、写しは5年間(当分の間は3年間)大切に保管します。
届出の書類は、労働基準監督署と控えの分の合計2部提出します。36協定は、届出が受理されて初めて効力を発揮します。協定のなかで定めた有効期限を迎える前に、必ず届出は提出しましょう。
協定の有効期限は、書類を作成するなかであらかじめ決めておくべき項目です。この期限は定期的な見直しを必要としており、どれだけ長くても1年が理想的とされています。
届出に必要な書類は、東京労働局のホームページから入手できます。
参考:厚生労働省東京労働局 | 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
関連記事:36協定の起算日について基本の考え方や注意点を解説
3. 36協定の届出の変更点

近年、日本では働き方改革が進められています。関連する法律が施行され、36協定に関する規定も変わりました。まず、気を付けたいのが書類の枚数です。一般事項で36協定を締結するのであれば、作成する書類は1枚のみとなります。
一方で、特別条項付きで締結する場合、2枚の書類を作成する必要があります。36協定に新しいルールが導入されたことで、特別条項により細かなルールが設けられるようになったためです。
細分化された項目のなかには「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保する措置」というものもあります。これまでの36協定と比較すると、働く側の健康状態をより鑑みた内容でなければなりません。また、これまでの36協定とは異なり、新様式では認められた時間外の労働時間にも制限があります。
- 1年で時間外の労働時間は720時間以内におさめること
- 時間外および休日における労働は1ヶ月あたり合計で100時間未満にすること
- 時間外および休日における労働は1ヶ月あたり合計が2~6ヶ月の平均で80時間以内であること
- 1ヶ月あたり時間外の労働が45時間を超えてしまってよいのは年間で6ヶ月まで
関連記事:36協定の新様式について旧式との変更内容や、いつから使うかを解説
4. 36協定は働く側を守る大切なもの

いきすぎた時間外労働は、誰のためにもなりません。働く側を守るために、36協定を締結して誰もが気持ちよく働ける健全な職場を作りましょう。36協定は、締結するにあたってその内容をより具体的に定めることがポイントです。
関連記事:36協定の提出方法3つと変更内容・注意点を分かりやすく解説
関連記事:36協定を本社一括届出にする方法やメリット・デメリット
関連記事:36協定の協定書とは?協定届との違いや書くべき項目を解説
残業時間の法改正!ルールと管理効率化BOOK
働き方改革による法改正で、残業時間の管理は大幅に変化しました。
当初は大企業のみに法改正が適応されていましたが、現在では中小企業にも適用されています。
この法律には罰則もあるので、法律を再確認し適切な管理ができるようにしておきましょう。
今回は「残業時間に関する法律と対策方法をまとめたルールブック」をご用意いたしました。
資料は無料でご覧いただけますので、ぜひこちらからご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25