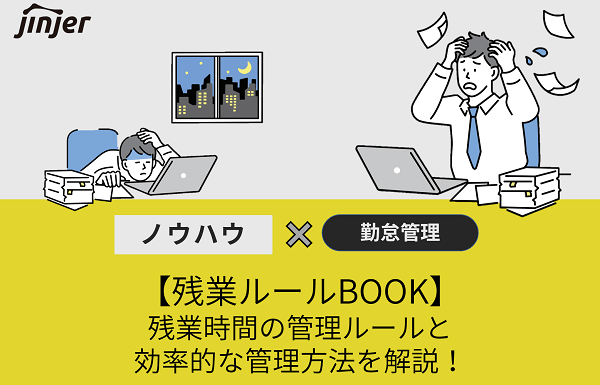外国人技能実習生の労働時間の上限について注意すべきこと
外国人技能実習生は外国から来て日本の高い技術を学んでいる人々で、将来的には母国に戻って習得した技術を生かして発展に貢献していきます。2017年からは外国人技能実習機構が設立されており、外国人の方がよりよい環境で働けるよう努力がはらわれています。
しかしその一方で、労働基準監督署がおこなった調査では実習先事業所のうち約7割で労働基準関連法違反が見つかるなど、外国人技能実習生の受け入れ先が必ずしも関連法に則って実習生を雇用しているわけではないことがわかっています。
知らないうちに労働基準関連法違反を犯さないためにも、外国人技能実習生の労働時間について詳しく見ていきましょう。
【関連記事】労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!
残業時間は労働基準法によって上限が設けられていますが、そもそも時間外労働の定義をきちんと把握していなかったり、しっかりとした勤怠管理を行っていないと、知らずに上限規制を超えてしまう可能性があります。
当サイトでは、自社の残業時間管理にお悩みの方に向け、時間外労働時間の数え方から、上限規制の内容、そして上限規制を超えてしまい罰則をうけないよう、どのように残業管理をしていけば良いのかや管理を効率化する方法まで解説した資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい方、罰則を回避したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 外国人技能実習生の労働時間の上限
まず外国人技能実習生の受入れ先となる企業や事業所が把握しておくべきなのは、外国人技能実習生の労働時間の上限でしょう。
違反した実習先のなかには一人あたりの1ヶ月の最長残業時間が、36協定の特別条項で定めた限度時間の70時間を超えて177.5時間になっていたという非常に悪質なケースもあります。
ここまでひどくはないとしても、労働時間の上限を超えて外国人技能実習生を働かせてしまうことはあり得るので、労働時間の上限を雇用主が把握しておくことが重要です。
1-1. 外国人技能実習生にも労働関係法令が適用される
外国人技能実習生に適用される法律は多くあります。なかでも労働については、日本人と同様、労働基準法や最低賃金法、雇用保険法などが適用されます。
そのため、労働時間の上限も労働基準法に定められている規定に則らなければなりません。
労働基準法では1日の労働時間の上限が8時間、1週間では40時間が規定労働時間として定められています。基本的にはこの労働時間を超えて働かせることは、従業員が日本人でも外国人技能実習生でもできません。
例えば、午前8時に始業した場合、1時間の休憩時間を含めて午後5時には仕事を終えなければならないということになります。
1-2. 外国人技能実習生の残業は36協定で可能
労働基準法には1日の労働時間の上限は8時間、1週間では40時間と定められています。しかし、実際には労働基準法の定める労働時間を超えて働いているケースは少なくありません。
なかには毎日残業しているという方もいることでしょう。ではこれは違法なのでしょうか。日本人であっても外国人技能実習生であっても、36協定が結ばれていれば所定労働時間を超えての残業が可能です。
36協定とは労働基準法の36条にある、雇用者と労働組合または労働者の代表者との協定のことです。企業や事業所は法定労働時間を超えて労働させる場合、この36協定を結んで労働基準監督署に届け出る義務があります。
36協定が結ばれていれば、外国人技能実習生に残業させることも可能です。ただし残業に関しては通常の時間給の25%増しの割増賃金を支払う必要があります。
1-3. 36協定があっても労働時間の上限はある
36協定を結んでいるからといって、残業時間が無制限というわけではありません。特に過労死が問題になったため、残業時間の上限も労働基準法によって厳しく定められているからです。
36協定を結ぶことで、労働時間を1ヶ月に最大45時間、1年間で最大360時間まで延長可能です。
しかし繁忙期などはこの上限を超えて労働させなければならないことも生じるでしょう。
そのため36協定の特別条項が設けられており、企業や事業所が届け出ることによってこの上限を超えた延長時間を設定できます。それでも時間外労働の上限は法定休日労働を除いて最大年間720時間と定められています。
さらに1ヶ月あたり45時間を超える時間外労働ができるのは年間最大6回までです。かつ法定時間外労働と法定休日労働を合わせて労働時間の上限は1ヶ月あたり100時間未満です。
外国人技能実習生についても労働時間の上限がしっかり決められているので、残業や残業時間を規定する特別条項を含めて詳しく知っておくようにしましょう。
残業時間の上限が設定されたのは、2019年の法改正のタイミングになります。改正前のまま残業時間に上限を設けていない企業の場合、罰則の対象になります。
2. 外国人技能実習生の労働時間管理での注意点
外国人技能実習生に限らず、労働時間の適切な管理は企業や事業所にとって非常に重要なポイントです。
労働時間が適切に管理されていなければ、どのくらい残業させたのか、労働基準法に違反していないのかなどを把握することは不可能でしょう。では外国人技能実習生の労働時間管理のやり方と、注意点について見ていきましょう。
2-1. 労働時間管理の方法
雇用主が実施しなければならない労働時間の管理方法も労働基準法によって決められています。2019年4月から改正労働安全衛生法が施行されたことにより、勤怠管理をすることが企業に義務付けられました。
雇用主は従業員の始業時間と終業時間を確認して記録しなければなりません。
しかもその方法は、雇用主が直接確認して記録する方法と、タイムカードや勤怠管理システムなどの客観的に記録する方法に限られます。外国人技能実習生の場合、こうした規定についてしっかり説明することが求められるでしょう。
日本語がわからない外国人技能実習生でも感覚的に操作してもらえるよう、勤怠管理システムによるタブレットやICカードでの打刻がおすすめです。勤怠管理システムでどのような管理ができるか知りたい方は、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをこちらからご覧ください。
【関連記事】勤怠管理の方法や方法別のメリット・デメリット、勤怠管理の目的を解説
2-2. 自己申告制の導入には十分な説明が必要
しかし業務形態によっては勤怠システムに常にアクセスできる状態ではない仕事もあります。そのような場合には例外的に自己申告による労働時間の把握が可能です。
しかし自己申告となると、雇用主が圧力をかけて労働時間を短く申告させることも可能になってしまいます。そのため、もし自己申告制を導入するのであれば、関係者全員に十分な説明をおこなうことが企業側に求められています。
外国人技能実習生に対して、労働時間を正しく申告するよう説明をおこないます。外国人技能実習生は日本語を十分に理解できないかもしれないので、可能であれば母語で説明できるように心がけるべきです。
さらに自己申告した労働時間と実際の労働時間との間に乖離がないか確認しなければなりません。たとえば1ヶ月あたりの労働日数に対して労働時間が明らかに多いなどのケースでは、必要に応じて労働環境を変えたり休ませたりすることが求められます。
【関連記事】労働時間管理を正確におこなうためのガイドラインを徹底解説
2-3. 法令違反がないかセルフチェックを
企業や事業所の多くが外国人技能実習生に関する労働関連法令を守っていないことを考えると、定期的に外国人技能実習生の働き方を見直す必要があるでしょう。
特に自己申告制による労働時間の把握をおこなっているのであれば、記録だけを見るのではなく実態を調査して、法令違反があれば速やかに是正するべきです。
もちろん適切な残業代の支払いなどもチェックすべきです。加えて自己申告制の場合、最大何時間まで申告できるといった上限を設けることはできません。もし関連法令に違反した場合、厳しい罰則が科せられ、事業の継続が難しくなる恐れもあります。十分に注意しましょう。
3. おすすめの労働時間管理方法
外国人技能実習生の労働時間を管理するには、勤怠管理システムを活用しましょう。勤怠管理システムを活用することで、残業時間の超過を防止可能です。
勤怠管理システムを選ぶ際は次のような点に着目するのがおすすめです。
- 多言語対応のシステム
- アラート機能が備わったシステム
- 有休管理が可能なシステム
3-1. 英語対応のシステム
外国人技能実習生の労働時間を管理するには、英語やインドネシア語、タイ語など多言語に対応した勤怠管理システムを導入しましょう。
勤怠管理システムはPCやスマートフォン、タブレットなどで打刻可能です。しかし、外国人技能実習生によっては日本語表記を不便に感じるかもしれません。そのため、多言語に対応している勤怠管理システムがおすすめです。外国人技能実習生が母国で勤怠管理システムを使用できれば操作ミスや打刻ミスも減少するでしょう。
3-2. アラート機能が備わったシステム
アラート機能が備わっているシステムであれば、外国人技能実習生の長時間労働を未然に防止可能です。週や月の労働時間、残業時間が超過する場合、従業員本人と管理者に通知が届くため、労働時間の上限超過を防げます。
3-3. 有休管理が可能なシステム
外国人技能実習生であっても条件を満たせば有休が付与されます。1年の有休が10日以上付与される場合、5日分取得することが義務づけられています。しかし、外国人技能実習生は、このルールを把握できていないかもしれません。そのため、有休の消化日数が足りない場合にアラートを発する有休管理が可能なシステムを導入しましょう。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説|厚生労働省
4. 外国人技能実習生を貴重な人材として適切に労働時間を管理しよう
外国人技能実習生は確かに日本の技術を学びに来ている人たちですが、企業や事業所にとっては人材不足を補う貴重な戦略です。できるだけ多くの外国人技能実習生を日本に迎え入れられるように、受け入れ先の企業や事業所が労働環境をしっかり整えるよう努力すべきでしょう。
長時間労働や過酷な労働を課しているといわれれば、日本にやってくる外国人技能実習生の数も減ってしまう恐れがあります。もちろん関連法令に違反している企業や事業所は罰せられるでしょう。
外国人技能実習生を安く雇える労働力を見るのではなく、貴重な人材と見るようにして労働基準法に則った労働時間の管理を心がける必要があります。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられていますが、そもそも時間外労働の定義をきちんと把握していなかったり、しっかりとした勤怠管理を行っていないと、知らずに上限規制を超えてしまう可能性があります。
当サイトでは、自社の残業時間管理にお悩みの方に向け、時間外労働時間の数え方から、上限規制の内容、そして上限規制を超えてしまい罰則をうけないよう、どのように残業管理をしていけば良いのかや管理を効率化する方法まで解説した資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい方、罰則を回避したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25