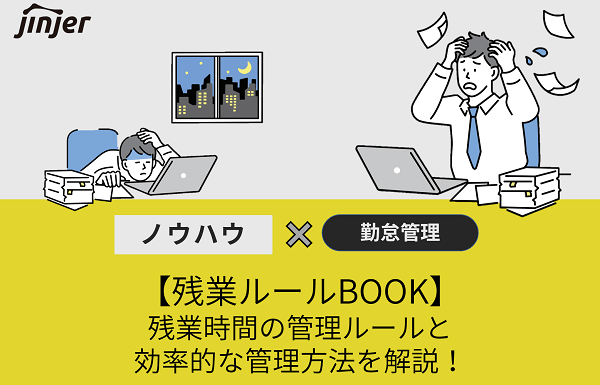法定内残業とは?法定外残業との違いや36協定、割増賃金の計算方法を解説
更新日: 2024.10.8
公開日: 2021.11.15
OHSUGI

法定内残業(法内残業)とは、法定労働時間の範囲内ではあるものの、企業の所定労働時間は超過した残業のことです。労働基準法上、法定内残業に割増し賃金の支払いは必要なく、残業代の扱いは各企業により異なります。この記事では、人事担当者向けに法定内残業の定義、残業の種類、残業代の計算方法を詳しく解説します。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 法定内残業とは

まずは法定内残業時間の定義を正しく理解するために「法定内残業時間とは」について解説します。
1-1. 所定労働時間以上だが、法定労働時間は超えない労働のこと
法定内残業とは、就業規則に定める所定労働時間は超えているものの、労働基準法の定める法定労働時間は超えていない労働のことです。法内残業、法定時間内労働などとも呼ばれることがあります。
労働基準法上、法定内残業に割増し賃金の支払い義務はありません。基本給に含むものとして対応することも可能です。ただし、就業規則や賃金規定で個別に定めている場合は、その規則に従い計算をおこないます。
所定労働時間とは、就業規則で定められた働く義務のある時間
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた、労働者が労働の義務を負う時間のことです。
始業から終業までの時間から、休憩時間を引くことで求められます。
例えば、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の場合、所定労働時間は8時間となります。
また、所定労働時間は、次に紹介する法定労働時間を超えて定めることはできません。
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の限度
法定労働時間とは、労働基準法第32条1項に規定されている労働時間のことです。[注1]
「使用者(会社)は原則として、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならない」という規定です。
上記上限を超えれば、時間外労働分の割増賃金が必要です。
[注1]e-Gov法令検索:労働基準法
所定労働時間と法定労働時間は必ずしも一致しない
以上のように、所定労働時間は法定労働時間の範囲内であれば、企業が自由に設定できます。
そのため、必ずしも、所定労働時間と法定労働時間時間が一致するとは限らない点に注意しましょう。
特に、所定労働時間が6時間など法定労働時間と比べて短いケースでは、法定内残業が発生しますが、割増し賃金を支払うか否かは各企業の定めによります。
そのため、残業代の計算では就業規則や賃金規定の確認が必要です。
2. 法定内残業と法定外残業の違い

法定内残業は労働基準法上、割増し賃金の支払い義務はありません。しかし、割増し賃金の支払い義務がないからといって、無給になるわけではありません。基本給として支払うか就業規則に従った金額を支払う必要があります。
対して法定時間外労働では、労働基準法上割増し賃金の支払いが必要です。1日8時間、1週40時間を超える労働では25%以上の割増となります。
さらに、月の労働時間が60時間を超えた場合、超えた部分については50%以上の割増が必要です。
法定時間外労働は、労働基準法で定められた残業のことを指しており、割増率を計算する場合に頻出になります。そのため残業に関しては、定義から明確に理解し、本章で解説している5つの用語の違いを明確にしておく必要があります。また、今までは残業時間の上限はありませんでしたが、2019年の働き方改革関連法により残業時間の上限規制が設けられました。
2-1. 法定外労働には36協定の締結が必要
なお、法定外労働は会社と従業員とで36協定を締結する必要があります。36協定を締結せずに法定時間外労働をした場合、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。36協定を結んだとしても、原則として月45時間、年間360時間(1年単位の変形労働時間制の場合には月42時間、年間320時間)が残業時間の上限です。
当サイトでは、残業時間の定義と上限規制について一緒に確認できる資料を無料で配布しております。残業時間について不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
3. フレックスタイムや変形労働制における法定外残業は?

フレックスタイムや変形労働制は次のとおり、通常の勤務体系とは異なります。
- フレックスタイム:従業員は始業時間・終業時間を任意で設定できる
- 変形労働制:労働時間を月や年単位で調整できる
このような通常の勤務体系とは異なる働き方であっても、法定外残業が発生します。フレックスタイム、変形労働制いずれも36協定を結んでいる場合は、月45時間、年間360時間が法定外残業の上限です。そのため、フレックスタイム、変形労働制どちらも法定外残業の上限に収めるようにしましょう。
また、フレックスタイム制の場合、コアタイム以外の労働時間では従業員自身が労働時間を調整できるため、実労働時間から法定労働時間を引いた差が法定外残業となります。具体的には、月の清算期間中に法定労働時間を超えた分が残業として計算されます。
同様に、変形労働制でも、所定の時間を周期的に見直して労働時間を調整することができますが、やはり法定労働時間を超えた分については注意が必要です。これにより、柔軟な働き方が可能でありながらも、法令に則った適正な労働時間の管理が求められます。
関連記事:フレックスタイム制で残業代は減る?残業の考え方や計算方法も紹介
関連記事:変形労働制でも残業代は出さないとダメ!知っておくべきルールとは
4. 時間外労働の種類と割増賃金率

残業代を正確に計算するには、残業の種類の理解が不可欠です。労働基準法上、賃金の割増しが必要な残業と合わせて解説します。
4-1. 深夜労働
午後10時から翌日午前5時までの労働は、「深夜業」に分類され、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
なお、上記時間帯に他の残業が重複する場合、合計した割増賃金率で残業代を計算します。
(例)法定時間外労働(25%)+深夜労働(25%)=割増賃金率50%以上
4-2. 休日労働(法定外休日)
休日には、会社で独自に定める「法定外休日」と、労働基準法上取得が義務付けられている「法定休日」があります。
法定外休日の労働では、その週の労働が法定時間内に収まる限り、通常の労働時間として処理します。そのため割増率は定められていません。
ただし、平日の労働で既に法定労働時間(1週40時間)を超えている場合は、法定外休日の労働は全て法定時間外労働として処理します。
法定外休日の労働や賃金について、就業規則で個別に定めている場合は、その規則に従います。
4-3. 休日労働(法定休日)
法定休日とは、労働基準法で定められた「毎週1日の休日または、4週間を通じて4日以上の休日」のことです。
法定休日の労働では通常の賃金に対して、35%以上の割増しが必要です。
なお、法定休日の労働は、残業(法定時間外労働)としてカウントしません。
ただし、深夜労働に当たる時間帯では、25%以上の割増は必要です。
5. 法定内残業の残業代の計算方法

法定内残業の残業代は、一般的に下記計算方法で求めます。
「法定内残業時間」×「1時間当たりの基礎賃金」
1時間当たりの基礎賃金は、就業規則や賃金規定に個別に定められているので確認しましょう。
例えば、下記のケースで1日の法定内残業代を計算します。
所定労働時間6時間、残業2時間、1時間当たりの基礎賃金1,250円。
2時間×1,250円=2,500円
また、法定内残業と法定外残業は異なりますので、次に紹介する、「法定時間外労働の残業代の計算方法」も合わせて理解するようにしましょう。
6. 法定時間外労働の残業代の計算方法

法定時間外労働の残業代は、下記の方法で計算します。
「1時間あたりの賃金」×「残業時間」×「割増賃金率」
それぞれのポイントを解説します。
6-1. 1時間あたりの賃金を算出
従業員の1時間あたりの賃金は、下記により求められます。
月給÷(1日の所定労働時間×月間所定労働日数)
「月給」に各種手当が含まれていれば、下記に該当するものは計算基礎から除外します。
- 家族手当(扶養手当・子女教育手当)
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、精勤手当など)
具体的には、「個人の事情により支給されている手当」が除外対象です。
上記に該当する手当であっても、「住宅手当 従業員一律5,000円」などとして支給している場合は、月給に含まれるものと解されます。そのため、手当は名称ではなく、個別の支給内容から判断します。
6-2. 残業時間を集計
残業時間は、割増賃金率の異なる種類ごとに分類すると理解しやすいです。下記を例にみてみましょう。
12:00~23:00勤務、休憩1時間、所定労働時間8時間
12:00~18:00→所定労働時間
18:00~19:00→休憩時間
19:00~21:00→所定労働時間
21:00~22:00→法定時間外労働
22:00~23:00→法定時間外労働+深夜労働
整理すると、
所定労働時間:8時間
法定時間外労働:1時間
法定時間外労働+深夜労働:1時間
となり、掛けるべき割増賃金率が判断できます。
6-3. 割増賃金率をかけ合わせる
最後に労働時間別の割増賃金率を確認します。
特に下記のように、割増賃金率が重複するものには注意しましょう。
・法定時間外労働+深夜労働:50%以上
・1ヵ月60時間を超えた法定時間外労働+深夜労働:75%以上
・休日労働+深夜労働:60%以上
以上により、残業代が計算できます。
7. 法定内残業を正しく理解して残業代を計算しよう
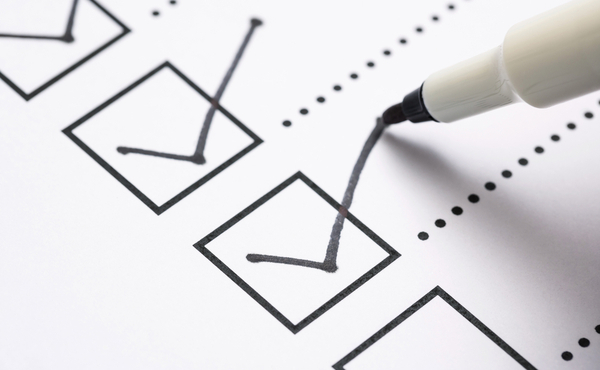
法定内残業とは、所定労働時間は超えるものの、法定労働時間は超えない労働のことです。
法律上、割増し賃金の支払い義務はないため、残業代の取り扱いは就業規則や賃金規定で確認するとよいでしょう。
また、残業代の計算では、深夜や法定休日の割増しも必要となるため、重複する場合は特に注意しましょう。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
残業の関連記事
-


残業代単価の計算方法と勤務形態ごとの考え方をわかりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.06更新日:2024.10.17
-


ノー残業デーを導入するメリット・デメリットと継続のコツ
勤怠・給与計算公開日:2022.03.05更新日:2024.01.15
-

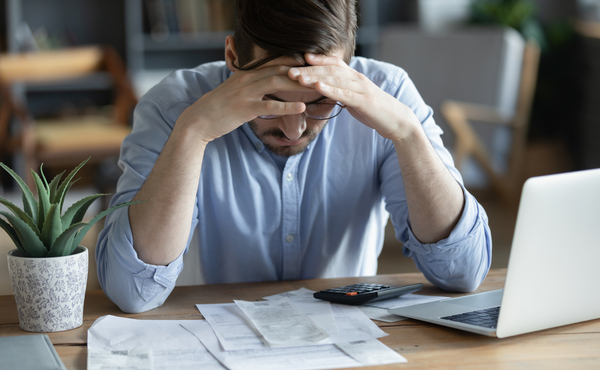
残業手当の計算方法や割増率、未払い発生時の対応を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.04更新日:2024.09.03