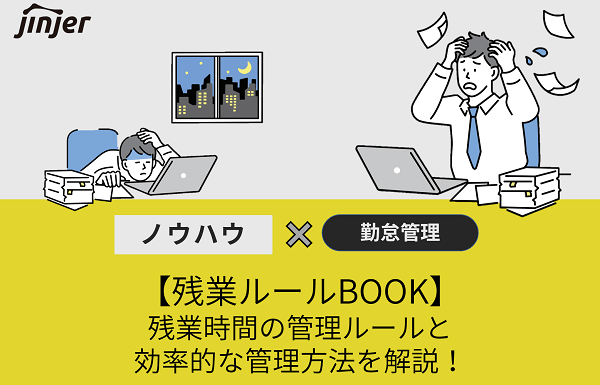【2023年-2024年】労働基準法改正による労働時間や増賃金率の変化を解説
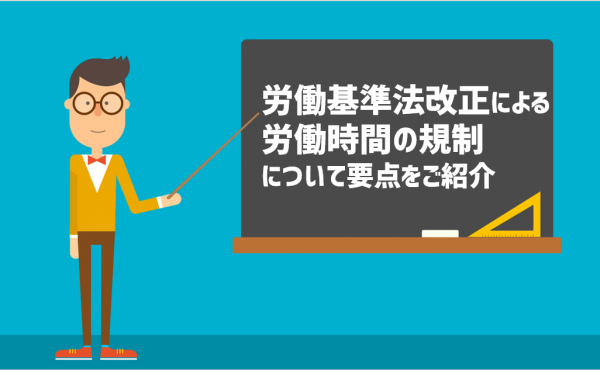
2023年までに労働基準法をはじめとした、さまざまな労働に関連する法律が改正されました。これまでは問題のなかった働き方が違法になるケースが発生しています。
2024年4月からは重要な法律の適用範囲が広がるため、現在までの改正内容と今後の予定を正しく把握しておく必要があります。
人事担当者として知っておくべき労働時間規制の変更点を押さえましょう。
目次
残業時間は労働基準法によって上限が設けられていますが、そもそも時間外労働の定義をきちんと把握していなかったり、しっかりとした勤怠管理を行っていないと、知らずに上限規制を超えてしまう可能性があります。
当サイトでは、自社の残業時間管理にお悩みの方に向け、時間外労働時間の数え方から、上限規制の内容、そして上限規制を超えてしまい罰則をうけないよう、どのように残業管理をしていけば良いのかや管理を効率化する方法まで解説した資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい方、罰則を回避したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 2023年までの労働基準法改正による変更点

労働基準法で定められている労働時間や賃金の支払いは、これまでにも改正がおこなわれてきました。まずは2023年までの時間外労働時間や有給休暇の取得、フレックスタイム制の清算期間など、大きな改正を確認していきましょう。
1-1. 時間外労働時間の上限
36協定を結び、届け出ることによって企業は従業員に対して時間外労働を命じることができます。
しかし、2019年に労働基準法が改正され、時間外労働時間の上限が設定されました。36協定を締結し、管轄の労働基準監督署に提出している場合でも、時間外労働時間は月45時間・年360時間が上限です。
法改正がおこなわれるまでは、特別条項付きの36協定を結んでいれば、この上限を越えて時間外労働を命じることができました。
しかし、多くの人間は過度の長時間労働に耐えられません。仕事によるストレスや劣悪な労働環境によって、過労死やうつ病の発症などの労働問題が起き、社会的な問題にまで発展しました。その結果、改正労働基準法では、「特別な事情があっても残業は年720時間まで」という制限が作られました。
ここまでテキストベースでお伝えしましたが、なかなか理解しづらい箇所もあるかと思います。当サイトでは、法改正で整備された6つの項目のうち「残業時間の上限規制」について詳細にまとめた資料を無料で配布しております。ブログの内容だけでは理解しづらい箇所がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1-2. 60時間を超える時間外労働の割増賃金率
2019年に施行された「働き方改革関連法」によって、企業の規模や業種を問わずに月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられています。
2023年3月末日までは、経営体力や支払い能力を考慮し、中小企業に対して猶予期間が与えられていました。しかし、猶予期間が終わった4月1日からは、すべての企業で50%以上の割増賃金を支払う義務が発生しています。
参考:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省
1-3. 有給休暇の取得義務化
改正労働基準法における大きな変更点の一つが、有休取得の義務化です。企業は年間10日以上の有休が発生する従業員に対して、最低でも5日以上の有休を取得させる必要があります。
本来、有休取得とは仕事を頑張っている従業員に与えられる権利です。しかし、企業側に時季変更権が認められていることもあり、実質的には権利を持っていても自由に休むことができない従業員が数多く存在しました。
「有休を取得するかどうかは企業や従業員に任せる」という従来の方針では、有休の取得率が一向に上がらないという現状を受けて、従業員に有休を取得させることが企業の義務になったのです。
なお、有給取得義務日数の消化期限は、従業員に有休を付与してから1年以内です。働き始めてから半年以上経過しており、営業日数の80%以上出社している場合は、正社員だけではなくアルバイトも有休を付与する必要があるため、注意が必要です。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省
【関連記事】有給休暇年5日の取得義務化とは?企業がおこなうべき対応を解説
1-4. フレックスタイム制の清算期間
フレックスタイム制とは、従業員が出社・退社時間を自由に決めることができ、自分で仕事量をコントロールできるようにした働き方のことです。
自由度の高いフレックスタイム制ですが、労働時間が法定労働時間を越えていれば、残業手当の支払いが必要になります。また、従来のフレックスタイム制では、清算期間の上限が1か月であったため、多少の変動があっても毎月の労働量を同じくらいにそろえる必要がありました。このシステムでは、数ヵ月単位で労働時間を割り振って、忙しい月は長時間勤務し、そうでない月は労働時間を減らすといった対応はできません。
しかし、法改正で、フレックスタイム制の清算期間が最大3ヵ月に延長されています。その結果、企業は最大3ヵ月の範囲内で従業員の残業手当を管理したり、繁忙期に合わせて労働時間を割り振ったりすることができるようになりました。
なお、フレックスタイム制の場合、1日8時間の法定労働時間の制限は適用されません。清算期間内の労働時間が超過しないようにする調整が必要です。
参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省
1-5. 高度プロフェッショナル制度の創設
働き方改革法では、高度プロフェッショナル制度が創設されました。高度プロフェッショナル制度の対象になる従業員は、労働時間・休憩時間・割増賃金などの労働基準法による定めの適用外になります。時間ではなく、仕事の成果で給与を決める労働形態を認める制度です。
対象職種は、金融商品の開発やコンサルタント、研究開発、士業などさまざまです。それらの業種のうち、以下の条件に当てはまる従業員は高度プロフェッショナル制度の対象になります。
- 高度で専門的な知識や技術を保有している
- 業務に従事した時間と成果の関連性が強い
- 仕事の範囲が明確になっている
- 1年間の賃金が最低1,075万円以上
対象になる従業員は、仕事が早く片付けば規定の労働時間を満たさなくても給与に変化はありません。しかし、それと同時に長時間の時間外労働も可能になります。健康に影響が出るような勤務を防ぐために、年104日以上の休日の確保や健康診断など、健康面を考慮した措置をとることも義務づけられています。
参考:⾼度プロフェッショナル制度わかりやすい解説|厚生労働省
1-6. 管理職を含む労働時間把握の義務化
過剰な長時間残業を問題視する改正労働基準法では、労働時間の把握も義務化されました。従業員の勤怠管理や働きすぎの予防は、あくまでも会社側の義務です。「社員が勝手に働いた」といい逃れをしても、実際に違法な長時間労働が発生していると企業が処罰の対象になります。人事担当者は確実に全従業員の労働時間を把握しておく必要があります。
なお、労働時間の把握が義務化されるのは、一般社員だけではありません。一般的には、労働基準法の制限がかからない管理職の労働時間も管理の対象です。
参考:働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)|厚生労働省
1-7. 勤務間インターバル制度の推奨
法律によって義務化されているわけではないものの、推奨されているのが「勤務間インターバル規制」の採用です。勤務間インターバルとは、「前日の退勤から翌日の出勤まで、最低◯時間以上空ける」というルールを指します。
人間が健康を維持しながら働くためには、適度な休息が不可欠です。「前日終電まで勤務をし、翌日は始発電車で出社をする」という過酷な状況では、疲労やストレスの蓄積を避けることができません。
その点、前日の退社時間に合わせて翌日の始業時間を繰り下げれば、十分な休息を取ることができます。始業・退社の管理が複雑になり、就業規則の変更も必要になりますが、制度自体は厚生労働省が推奨しているため、働き方改革の一環として自社での導入を検討してみることをおすすめします。
1-8. デジタルマネーによる賃金の支払い
デジタルマネーの普及により、2023年4月からは賃金もデジタルマネーによる支払いが可能になりました。これまでは金融機関の口座への振り込み、あるいは現金の手渡しに限定されていた支払い方法ですが、従業員の合意があった場合はデジタルマネーによる支払いができます。
利用できるデジタルマネーは、PayPayや楽天Edyなど2023年1月の時点では日本国内だけで83社ほど存在します。
参考:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について:厚生労働省
2. 2024年の猶予期間終了による時間外労働時間の変化

前項で紹介したように、時間外労働時間の上限規制は2019年から順次適用されていきました。しかし、一部の業種では5年の猶予期間が設けられ、義務化するのは2024年の4月からです。対象業種と猶予期間終了後の対応を確認しておきましょう。
2-1. 猶予期間が設けられている業種
以下の業種は業務の内容や特殊性から、即座に対応することは困難であるとされ、猶予期間が設けられています。
- 建築業(工作物の建設の事業)
- 運送業(自動車運転の業務)
- 医療業(医業に従事する医師)
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
これらの業種では、2024年3月末日まで時間外労働の上限規制が適用されません。猶予期間中に労働時間の管理方法や人員補充をおこない、時間外労働の上限を厳守できる体制を整えることが求められています。
2-2. 猶予期間終了後の対応
猶予期間が設けられていた業種も、2023年4月からはほかの業種と同様に時間外労働の上限が適用されます。原則として月に45時間、年に360時間の時間外労働の上限を守れるように労働時間の管理と調節をする必要があります。
3. 労働基準法の改正において企業に求められる対応
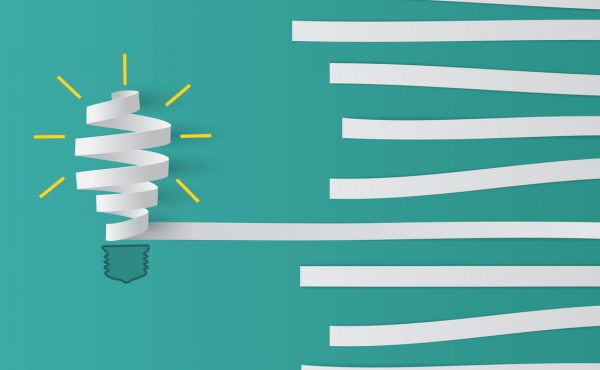
労働に関連するさまざまな法律が改正される中で、企業はその都度対応をしなければいけません。現在施行されている、および予定されている法律に対応するには、以下のような対処をしていきましょう。
3-1. 代替休暇(有給休暇)の付与
時間外労働が発生した場合は、割増賃金を支払う必要があります。しかし、月60時間を超える時間外労働については、従業員の同意があり、労使協定も締結している場合は割増賃金の代わりに代替休暇を付与することが可能です。
代替休暇の単位は、1日・半日・1日または半日のいずれかです。一部を代替休暇にし、残りを割増賃金で支払うことも可能であるため、従業員の健康確保の観点からどのように割り振るか決めましょう。
なお、代替休暇を与えられる期間は、時間外労働が60時間を超えた月から2ヵ月以内です。
3-2. 労働時間の可視化
労働安全衛生法により、雇用主には従業員の労働時間を把握する義務が発生しました。これに対応し、従業員の健康を守るためには労働時間の可視化が必要です。
退勤管理システムの導入や出社・退社を確実に把握できる方法への転換など、労働時間が第三者から見ても明らかになるようにしましょう。労働時間の可視化は企業の健全性を上げるとともに、会社の財産である従業員を守ることにもつながります。
勤怠管理システムは様々な方法で打刻が可能なため、外出の多い従業員の労働時間を把握することも可能です。また、労働時間をリアルタイムに把握できるため、残業時間の上限規制を守るためにも有効です。
勤怠管理システムでどのようなことができるか気になる方は、以下のリンクから勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをご覧ください。
▶クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをみる
【関連記事】法改正による「労働時間把握の義務化」の内容と対応方法
【関連記事】管理職の労働時間・休憩時間についての基礎知識を徹底解説!
3-3. 時間外労働時間の上限や割増率の改正への対応
労働に関連する法律は改正が多く、労働時間の上限や時間外労働の割増賃金率が変更されたり、新たな義務が発生したりします。猶予期間がない場合でも、企業は法律が施行されるまでに対応する準備をしなくてはいけません。どのような理由があっても、違反した場合には罰則が発生する恐れがあります。
迅速に対応をするためには、勤怠管理システムや給与システムなど、オンラインで自動的に更新がおこなわれる環境を整えることも重要です。
3-4. 時間外労働の削減
時間外労働を法定時間内に収めるためには、企業と従業員双方に労働時間を削減する工夫や努力が必要です。業務を効率的に進めるために、人員やシステムを見直したり、仕事が特定の人や部署に偏らないように調節したり、できることは決して少なくありません。時間外労働を削減する文化が浸透すれば、時間外労働の上限に困ることも減るでしょう。
労働時間の削減は、人事や上層部が主体にならないとなかなか進みません。ノー残業デーの設定や上司が定時で帰ることを促すなど、会社が労働時間の削減を目指しているという姿勢を明確にしましょう。
4. 労働基準法の改正内容を正しく把握して早めに対応しよう

労働基準法の改正によって、長時間労働に罰則付きの上限ができました。ほかにも、有給休暇の取得が義務化されたり、フレックスタイム制度が拡充されたりしています。これまで違法ではなかった労働環境も、法改正に伴って違法とされる場合が出てくるため、人事担当者の責任は重大です。
ただし、法律の求める基準を完璧にクリアするのは簡単ではありません。労働基準法の改正に合わせて勤怠管理自体をアップデートできるように、勤怠管理システムを取り入れて、人事担当者の労働時間管理の手間を軽減しましょう。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25