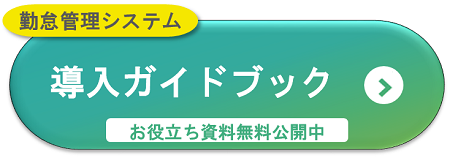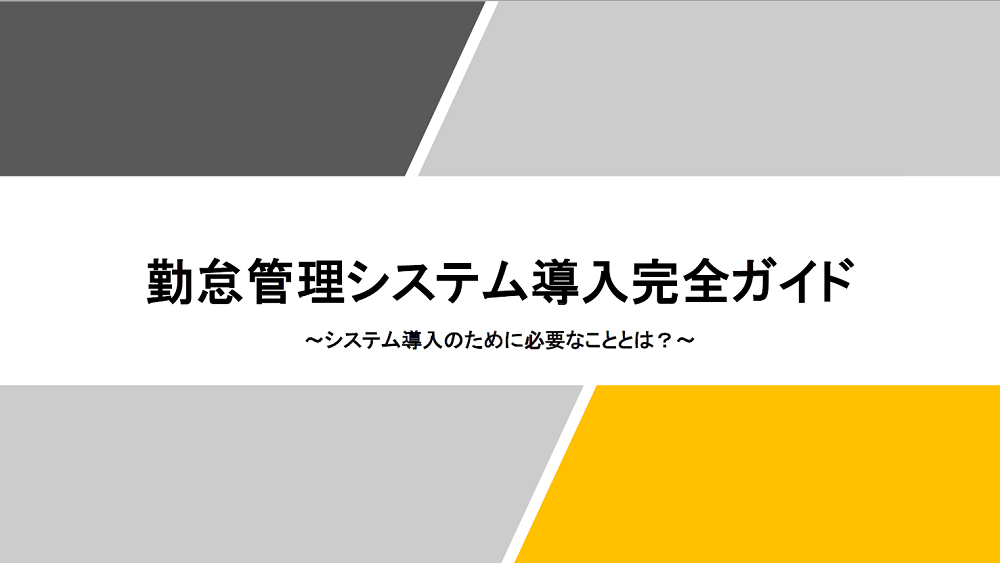労働時間の把握が義務化!法改正の内容と対応方法とは?
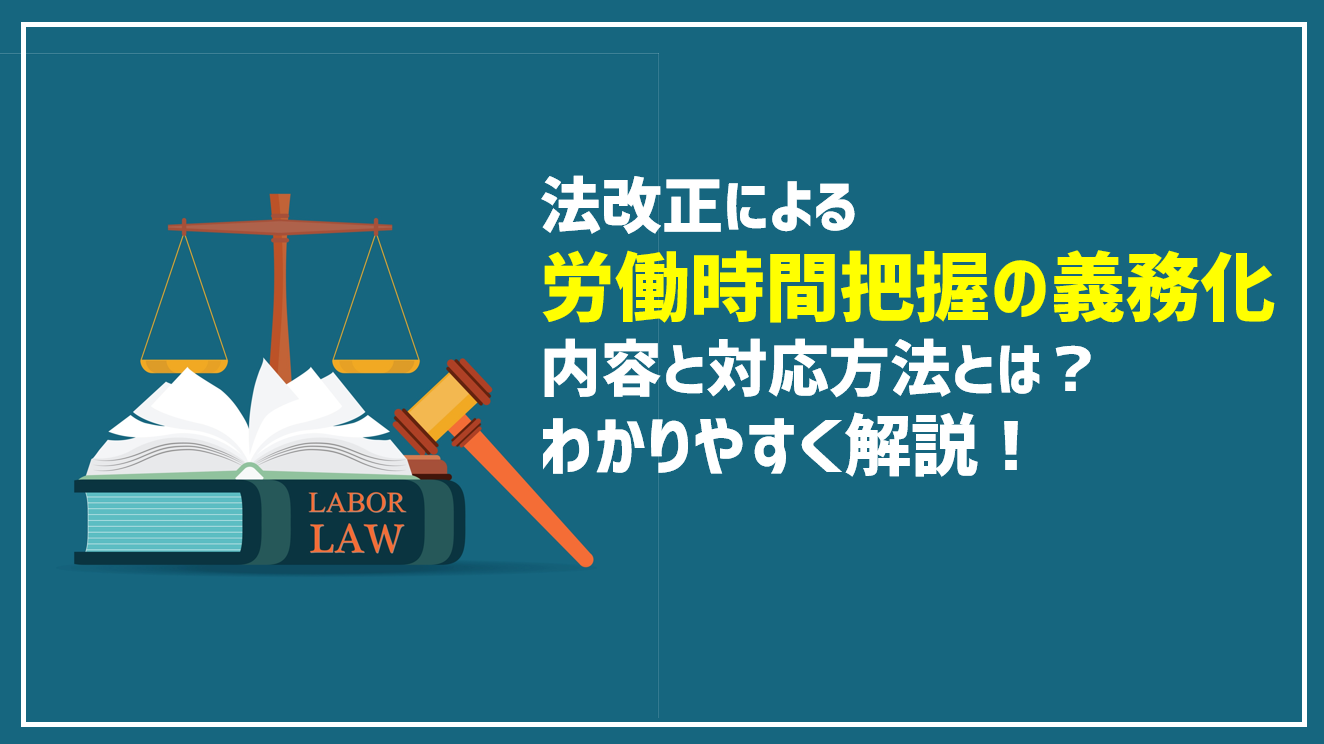
2019年の4月以降、働き方改革の一環としておこなわれた労働関連法の法改正によって決められたのが、「労働時間把握の義務化」です。
労働関連法の法改正によって、それまで罰則のなかった長時間労働・過度の残業に対する法的な罰則や上限が設定されました。
今回は、労働時間把握の義務化の概要や、義務化された理由、従来の勤怠管理との相違点など、基礎的な内容を押さえていきましょう。
【関連記事】労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!
目次
この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。
ジンジャーは、人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をご参考ください。
1.労働基準法とは

労働基準法とは、労働条件に関しての最低基準を定めた法律で、昭和22年に制定されました。
主に、以下の労働条件に関する規定が定められています。
- 賃金の支払の原則
- 労働時間の原則
- 時間外・休日労働
- 割増賃金
- 解雇予告
- 有期労働契約
- 年次有給休暇
- 就業規則
労働基準法は、労働環境や時代の変化に合わせて改正がおこなわれています。近年では、働き方改革などに伴い、2019年に改正労働基準法が施行されました。この施行に伴って、2020年以降も労働関係法の改正がおこなわれているため、労働時間などを管理する部署は定期的な法改正の確認が必要となっています。
2.2023年までの主な法改正について

昭和22年の労働基準法制定後、数々の法改正がおこなわれていますが、ここでは2023年までの主な法改正について紹介します。
参照:働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
2-1.時間外労働(残業)の上限時間
大企業は2019年4月1日から、中小企業においては2020年4月から、時間外労働(残業)の上限規制が適用されています。上限は月45時間、年360時間と定められていて、特別な事情がない限りは超えることができなくなるという法改正です。
ただし、業種によってはどうしても上限を超えてしまうというケースもあるかもしれません。そのため、労使で合意した場合は「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働は年720時間まで可能」という例外は認められています。
上限が守られなかった場合は、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が課せられます。これは労使で合意している上限を超えた場合でも適用される罰則となっています。
2-2.年次有給休暇の取得日数
2019年の改正労働基準法では、年次有給休暇の取得日数に関する改正も施行されています。
雇入れの日から6ヵ月間、継続的に勤務し、すべての労働日の8割以上を出勤している従業員に対しては、通常の労働者は10日の年次有給休暇を付与することになっています。
改正後は必ず取得させなければいけない年次有給休暇の日数が決まっている点が、法改正のポイントです。
具体的には、年に10日以上の年次有給休暇がされる場合は、最低5日の有給休暇を取得させることが義務付けられているため、会社側からも働きかけが必要になるかもしれません。
また、パート・アルバイトなど全労働日の8割以上を出勤できない雇用形態の場合も、「所定の労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること」と定められています。
会社が年次有給休暇の取得日数を適切に付与しなかった場合は、30万円以下の罰金という罰則が課せられます。
2-3.時間外労働の割増賃金率
2023年4月1日からは、時間外労働の割増賃金率の改正が施行されました。
今回の改正では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上となります。
今までは中小企業の支払い能力が考慮されていたため、50%以上というのは大企業のみの割増賃金率でした。しかし、法改正により中小企業に対しても、大企業と同じ割増賃金率にすることが義務化されています。
3.関連法令の改正

法改正は労働基準法だけでなく、労働基準法に関連する法令も改正されています。
ここでは、労働時間把握義務に関係する改正を紹介します。
3-1.勤務間インターバル制度の導入
労働時間等設定改善法が改正され、雇用主には「勤務間インターバル制度の導入」が努力義務化されました。この仕組みは、労働者に十分な生活時間や睡眠時間を確保することを目的としています。
終業時刻から次の始業時刻までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けるというのが「勤務間インターバル」で、平成31年4月1日から施行されています。
3-2.労働時間の把握義務
労働安全衛生法の改正により、雇用主には「従業員の労働時間を把握すること」が義務付けられました。義務化されたことで、雇用主は従業員の勤怠時間や時間外労働など、全労働時間を客観的な方法で記録する必要があります。
客観的な方法はいろいろありますが、労働安全衛生規則第52条の7の3ではタイムカードの記録やパーソナルコンピュータなど電子計算機のログインからログアウトまでの時間を記録することが推奨されています。
また、把握した労働時間の記録を作成し、「三年間保存するための必要な措置を講じなければならない」ことも義務付けられているので、退職や休職などで記録を破棄しないように注意しましょう。
参照:昭和四十七年労働省令第三十二号 労働安全衛生規則|厚生労働省
4. 労働時間の把握義務化の目的

法改正がおこなわれる前から、政府によって労働時間の把握は推奨されています。
しかし、企業の勤怠管理方法に関する統一の基準や法的根拠がなかったため、実際には「どのような勤怠管理をするのかは各企業の自由」となっていました。
そのため、給与計算の根拠となる労働時間の把握状況があいまいになり、「勤怠時間を勝手に15分単位で区切る」「残業時間を勝手に減らしてサービス残業を強制する」といった問題が発生しました。
また、「企業が労働時間を正確に把握できていない」という状況で起きるのが、労働時間計算の不正です。「労働基準法を守っていたら会社が成り立たない」という意見もあるかもしれませんが、長時間労働による健康被害が出る可能性もあります。
このような問題を解決することを目的として、労働時間把握が義務化されました。
5. 労働時間の把握義務化への対応

労働時間把握の義務化の主な変更点は、タイムカードをはじめとした客観的な勤怠管理システムの導入による厳密な労働時間の把握があげられます。
とはいえ、単に客観的な勤怠管理をすればよいというだけではないので、どのような対応すれば良いのか、具体的に解説していきます。
5-1. 客観的な勤怠管理システムの導入
法改正によって義務化された労働時間を正確に把握するためには、「タイムカードに労働時間を刻印する」など客観的な勤怠データが必要になります。
ただし、職場の事情からタイムカードを利用できない場面もあるかもしれません。例えば、テレワークなどで在宅勤務をしていたり、直行直帰で通勤してこなかったりする場合は、労働時間を自己申告してもらうことになります。
新たな勤怠管理システムを導入する場合、社員全員を集めて口頭で説明するのは大変なので、事前にマニュアルを作っておくことをおすすめします。また、就業規則や労使協定を見直して周知を徹底できるように段取りを進めていきましょう。
5-2. 労働時間は1分単位で把握する
労働時間把握の義務の内容として、重要なポイントのひとつが労働時間把握の厳密化です。
本来、企業が従業員を雇用する場合、1分単位で細かく労働時間を把握して給与を支払う必要があります。
しかし、「出社後、着替えてからタイムカードを押す」「30分以下の残業は残業として報告しない」「昼食休憩を取っても構わないが来客があれば事務員が対応すべき」など、本来給与が発生する時間を無給扱いにしてしまっている企業も少なくありません。
労働時間の把握義務化では、今までグレーゾーンになっていた労働時間を厳密に把握することが求められているので、1分単位で把握できるようにしましょう。
5-3. 管理職に対する労働時間管理の拡大
労働時間把握の対象は、管理職も含まれています。
労働時間の把握義務化は「会社で働く従業員の健康を守るため」のルールです。そして、長時間労働によって体調を崩すのは一般社員だけではありません。
管理職が一般社員より緩い残業規制の対象になるという点は法改正以前と同じです。しかし今回の法改正によって管理職に対しても労働時間把握が義務化されています。
一般社員も管理職も、アルバイトやパートであっても、長時間労働が認められた場合は医師による面接が必要なので、注意しておきましょう。
【関連記事】管理職の労働時間・休憩時間についての基礎知識を徹底解説!
5-4. 労働時間の長い従業員に対する医師の面接指導
もともと、長時間労働をする従業員に対しては、医師による面接指導が義務付けられていました。
しかし、労働時間把握の義務化によって産業医の権限が強化されています。そのため、残業時間と休日出勤の時間が週40時間を越えた場合、職種に関係なく医師の面接を受けさせるかどうかを検討する必要があります。
参考:長時間労働者への医師による面接指導制度について|厚生労働省
6. 労働時間を適切に把握し管理するためのガイドラインとは

「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置」にはガイドラインが発表されており、このガイドラインに沿って対応が必要になります。
上記のガイドラインに基づいて、使用者が勤怠管理について対応が必要なことについて簡単に説明いたします。より詳しい内容を知りたい方は、上記のリンクからガイドラインを確認してみてください。
【参考】労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
【関連記事】労働時間とは?社会人が今さら聞けない基本情報を徹底解説!
6-1. 始業・終業時間を確認し記録すること
使用者は労働時間を適正に把握するため、労働者の始業・終業時間を客観的な方法によって記録しておかなくてはなりません。客観的な記録とはタイムカードやICカード、パソコンの使用時間などが挙げられます。
6-2. 始業・終業時間を確認する方法
始業・終業時間を確認する方法は、原則として次のいずれかの方法が推奨されています。
- 労働時間管理担当者が自ら現認することにより確認し記録する
- タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録する
労働時間管理担当者が現認する場合、該当労働者からも確認できるような方法が望ましいです。
6-3. 始業・終業時刻が自己申告制の場合の措置
職種や仕事内容などにより、客観的な記録ではなく自己申告によって始業時間・終業時間を記録する場合は、従業員への説明をおこないます。その際、実態との乖離があった場合は調査をおこなうなどの措置が必要です。
また、自己申告を阻害する制度を設けてはならないとされています。
6-4. 賃金台帳の適切な調整
使用者は、労働者ごとに労働日数や労働時間、時間外労働時間(残業時間)、休日出勤・深夜労働の労働時間などを賃金台帳に記入しておかなくてはなりません。
上記の内容が記入されていない場合や虚偽の内容が記入されていた場合、30万円以下の罰金に処されるため、注意しましょう。
【関連記事】労働時間管理を正確におこなうためのガイドラインを徹底解説
6-5. 労働時間を記録する書類の保存
労働時間を記録する書類は、労働基準法第 109 条に基づいて5年間(当分の間は3年間)保存することとなっています。
労働基準法第109条では「その他労働関係に関する重要な書類」の保存を義務化していますが、労働時間の記録に関する書類もこれに該当するのです。
具体的には、労働時間管理担当者が始業・終業時刻を記録したもの、タイムカードなどの記録、残業命令書及びその報告書、労働者が労働時間を記録した報告書などが保存対象となります。
なお、5年間の起算点は、書類ごとに最後の記載がなされた日となるので、保存期間の間違いに注意しましょう。
6-6. 労働時間管理者の職務について
労働時間管理や労務管理をおこなう部署の責任者は、「労働時間の適正な把握など労働時間管理の適正化に関する事項を管理しなければならない」とされています。つまり、過剰な長時間労働がおこなわれていないか、労働時間が適正に把握されているかなどの確認が職務となります。
また、労働時間管理をするうえで問題点があった場合は、どのような措置を講ずるべきか、問題解消を図ることも重要な職務です。
6-7. 労働時間等設定改善委員会の設置
労働時間管理の状況によっては、必要に応じて「労働時間等設定改善委員会」などの労使協議組織を設置することとされています。委員会の設置は、労働時間管理の現状を把握した上で、労働時間管理上の問題点やその解決策などの検討をおこなうことが目的です。
7. 労働時間の把握義務化に必要なツール

厳格化された労働時間を確実に把握する方法としては、『始業・終業・残業の考えのマニュアル化』『手軽にタイムカードを打刻できる勤怠管理システムの採用』がおすすめです。
パソコンの表計算ソフトを使ったり、紙製のタイムジャードを使ったりして労働時間を管理するという方法もありますが、従業員の負担が多いとミスが発生しやすく、人事や事務社員に負担がかかってしまいます。
特に、企業の人事担当者は、労働時間を把握する以外にも法改正に併せて日々の業務を調整する必要があるため、少しでもほかの社員やシステムに協力してもらえるような環境づくりに力を入れましょう。
7-1. 始業・終業・残業の考え方のマニュアル化
多くの従業員は、正確な労働時間の定義や残業が発生するかどうかの基準などをそもそも知りません。基準を知らない従業員に対して、一方的に「今後は正確にタイムカードを押すように」と周知をするだけでは、押し忘れなどが生じるかもしれません。正確な労働時間を把握するには、「始業・終業・残業」のルールを理解してもらう必要があるので、まずは勤怠管理のルールをマニュアル化しましょう。
- 出退勤はパソコンのログイン状態で記録する
- 出社したら着替えや朝礼をする前にタイムカードで打刻する
- 残業を申告制にする
- 個人でタイムカードを押してからおこなう業務は残業の指導の対象とする
- 直行直帰をする場合の出勤・退勤の扱い
- 月間の残業時間制限
上記のような内容を盛り込み、「始業・終業・残業」に関する正確な報告ができるように、人事主導でルールを作りましょう。ただしルールを作っただけだと、細部まで読まない人も出てくる可能性があります。そのため、必要に応じて就業時間中に従業員を集めて説明を設けたり、各部署の管理職を集めて現場の上司が適切な指導をできるようにしたりすることも考えましょう。
7-2. 手軽にタイムカードを打刻できる勤怠管理システムの採用
社内ルールの整備と並行して進めたいのが、勤怠管理システムの導入です。出社したときに出社時刻を紙に記入するなど、個々人の作業に依存した方法だと、どうしてもミスや手違いが起きてしまいます。従業員や管理職がミスした場合、人事担当者がミスを見つけて修正をお願いすることになるため、二度手間です。
勤怠管理システムには、『出社後に各自のパソコンを使って1クリックで打刻できる』『スマホのアプリを使って出退勤を記録できる』『職場の入り口に端末を置き、ICカードをタッチして勤怠をつける』など簡単にタイムカードを打刻できる機能が搭載されています。そのため、労働者の打刻ミスも防げますし、労働時間管理担当者も手軽に出勤時刻や退勤時刻を管理できます。
勤怠管理システムを導入することで、「勤怠を付ける」という作業の負担を減らせますし、直行直帰の場合でも勤怠をつけることが可能になります。クラウド型の勤怠管理システムなら、月額課金制なので初期費用を安く抑えられるのもポイントです。
登録したデータは強固なセキュリティーで保護されますし、バックアップも充実しています。勤怠管理以外の機能が搭載されている勤怠管理システムなら、人事としての仕事も一部削減することができるでしょう。
勤怠管理システムでどのようなことができるか気になる方は、以下のリンクから勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをご覧ください。
▶クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページを見る
8. 便利なシステムの導入や社内ルールの整備で労働時間把握の義務化に対応しよう

労働関連法の改正によって、企業はこれまで以上に厳しく従業員・管理職の労働時間を把握する義務を負いました。労働時間が一定を越えた従業員に医師の面接を受けてもらったり、正確な勤怠状況を記録して長時間残業を防いだりするためには、社内ルールの整備が必要不可欠です。
人事担当者や各従業員が直接おこなう作業が多ければ多いほど、ミスや誤解が生まれやすくなるため、法改正に対応できるように使い勝手のよい勤怠管理システムの導入をおすすめします。
近年、人手不足などの背景から、バックオフィス業務の効率化が多くの企業から注目されています。
タイムカードの集計は、集計時にExcelに入力する工数がかかりますし、有給休暇の管理は、従業員ごとに管理することが煩雑で、残有給日数を算出するのにも一苦労です。
どうにか工数を削減したいけど、どうしたらいいかわからないとお悩みの方は、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤をWeb上で管理できるシステムのことです。勤怠管理システムの導入を検討することで、
・多様な打刻方法により、テレワークなどの働き方に柔軟に対応できる
・リアルタイムで労働時間を自動で集計できるため、月末の集計工数が削減される
・ワンクリックで給与ソフトに連携できる
など、人事担当者様の工数削減につながります。
「導入を検討するといっても、何から始めたらいいかわからない」という人事担当者様のために、勤怠管理システムを導入するために必要なことを21ページでまとめたガイドブックを用意しました。
人事の働き方改革を成功させるため、ぜひ「勤怠管理システム導入完全ガイド」をご参考にください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25