65歳以上から介護保険料はどう変わる?計算方法や制度をわかりやすく解説
更新日: 2025.8.28 公開日: 2024.12.22 jinjer Blog 編集部

65歳を超えると介護保険料は制度上の区分が変わり、保険料の支払い方法や計算方法が65歳未満とは異なります。また、納付も従業員がおこなうようになるため制度の詳細を理解することが大切です。
収入や居住地によって負担額が増減する可能性がありますし、逆に免除や減免対象となることもあるので、従業員は介護保険料について正確に把握しきれないかもしれません。
そもそも、今まで給与から控除されていたものが、65歳を超えると本人が納付しなければならないので、担当者に質問が来ることも考えられます。
本記事では、65歳以上の介護保険料の仕組みや計算方法、免除や減免制度について詳しく解説します。
目次
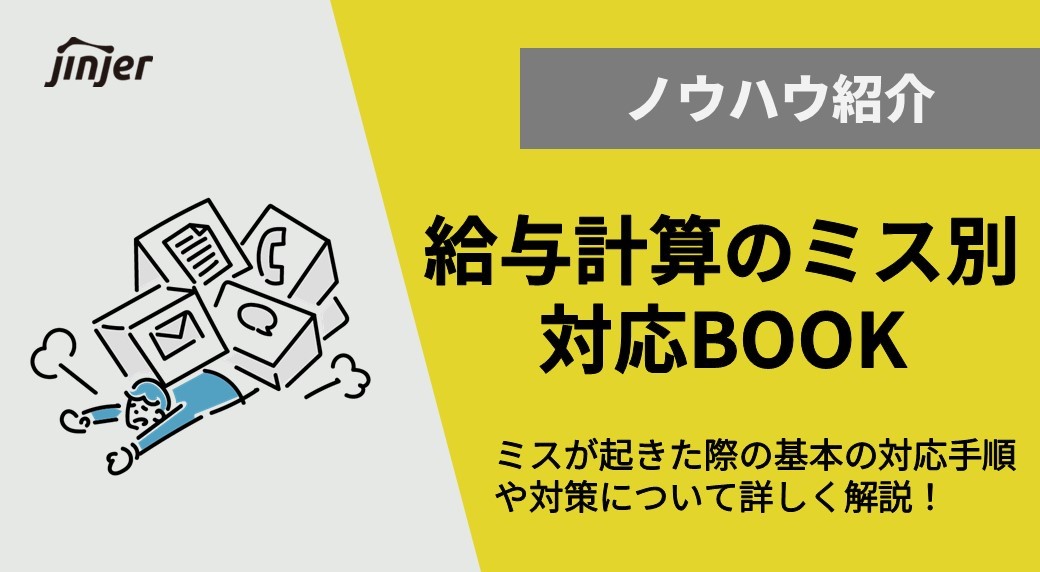
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
当サイトでは、万が一ミスが発覚した場合に役立つ、ミス別に対応手順を解説した資料を無料配布しています。
資料では、ミス発覚時に参考になる基本の対応手順から、ミスを未然に防ぐための「起こりやすいミス」や「そもそも給与計算のミスを減らす方法」をわかりやすく解説しています。
◆この資料がおすすめできる方
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・ミスをしないために、給与計算業務のチェックリストがほしい方
・根本的に給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
いずれかに当てはまる担当者の方は、ぜひ「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、日々の実務にお役立てください。
1. 介護保険とは?

「介護保険」は、介護が必要となる人を社会全体で支えるための公的な制度です。介護保険の運用者は市区町村となっており、被保険者はその地域に居住する40歳以上の人です。
運用者となる市区町村は、管轄内に居住している40歳以上の住民から介護保険料を集め、被保険者に介護が必要になった場合に介護サービスを利用できるよう整備していきます。
介護保険制度では、40~64歳までを「第二号被保険者」、65歳以上を「第1号被保険者」として定めており、65歳を超えると保険料の仕組みが変わります。
2. 65歳以上で変わる介護保険料の仕組みとは

65歳以上の場合、介護保険の制度上の区分が「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
年齢の切り替えは、65歳の誕生日の前日が設定されていて、その日を境に第2号被保険者としての保険料徴収が終了するのです。翌月分からは、第1号被保険者として新たに介護保険料の負担が始まります。
40歳から64歳までは健康保険料と共に介護保険料が給与から天引きされ、企業が保険料の一部を負担していました。しかし、65歳以上では居住している市区町村が介護保険料を管理するため、基本的に全額自己負担となります。
2-1. 介護保険料は65歳以上いつまで払う?
介護保険料は、65歳を過ぎたらいつまで払えばいいのか、知らない人は少なくありません。
70代や80代など、「高齢者」と呼ばれる年齢になれば払わなくていい、というイメージを持っている従業員もいるかもしれませんが、実は一生涯払う必要があります。つまり、「生きている間が納付期間」となるのです。
また、65歳以上で生活保護の受給を受けたとしても、第1号被保険者は公的介護保険の被保険者となるため、介護保険料の支払いが必要です。
3. 65歳以上の介護保険料はどう変わるのか

65歳以上の介護保険料は、以下の4つの変更点があります。
- 介護保険料の金額が全額自己負担となる
- 介護保険料の支払い方法が変わる
- 介護保険料の計算方法が変わる
- 被扶養者でも介護保険料を支払う必要がある
ここでは、これらの変更点について解説します。
3-1. 介護保険料の金額が全額自己負担となる
65歳以上になると、介護保険料の金額が全額自己負担となります。
65歳未満の場合、介護保険料は事業者との労使折半(半額負担)でしたが、65歳以上は第1号被保険者になるので、保険料の管理は居住している市区町村です。
つまり、65歳以上では事業者側の負担がなくなるため、従業員の収入状況によっては保険料の負担感が大きくなるかもしれません。例えば、定年後も働き続けている方は、65歳前と比べて負担額が増加することが多いので、年金受給と合わせた収入計画を立てることが重要です。
3-2. 介護保険料の支払い方法が変わる
65歳以上になると、介護保険の支払い方法が変わります。
40歳から64歳の第2号被保険者は、会社が提供する健康保険と一緒に給与から介護保険料が天引きされていました。
しかし、65歳以上の介護保険料の徴収方法は、年金の受給金額により特別徴収と普通徴収の2つの方法にわかれます。
それぞれの違いは、下記のようになります。
| 項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
| 対象者 | 年金受給額が年間18万円以上の人 | 年金受給額が年間18万円以上の人 |
| 支払方法 | 年金からの自動天引き | 納付書や口座振替での個別支払い |
| 徴収回数 | 年6回(偶数月に年金支給時に天引きされる) | 市区町村による指定の頻度 |
| 手続き | 不要(自動的に天引きされる) | 納付書の受け取り後、指定の金融機関などで支払う |
| 開始期間 | 65歳になった直後は一時的に普通徴収(6ヵ月程度) | 年金額が増加した場合、後に特別徴収に変更されることがある |
65歳以上の介護保険料は健康保険制度の枠外で、年金や収入に応じた形で支払う必要があるため、従業員の支払い方法に応じた対応が求められるでしょう。
3-3. 介護保険料の計算方法が変わる
65歳以上の介護保険料は、主に以下の項目にもとづいて計算されます。
- 本人の所得
- 同じ世帯の人の市町村民税課税状況
- 地域の65歳以上の人口
- 介護サービスに必要な費用の見込額
高齢者が多い地域や介護サービス費用がかさむ地域では、保険料が高く設定される傾向があるでしょう。また、所得によっても負担額が段階的に変動するため、年金などの収入が多い人はより高い保険料が課せられることがあります。
65歳以上の介護保険料の計算例
例えば、世田谷区の令和6年度〜8年度の介護保険料額の基準額は月額6,280円(年額75,360円)です。さらに、収入や所得、世帯の課税状況をもとに以下のように18段階に分かれています。
【世田谷区の介護保険料額(令和6~8年度)】※抜粋
| 保険料段階 | 対象者 | 年間保険料額 |
| 第1段階 | ・生活保護や中国残留邦人など生活支援給付を受けている
・本人と世帯全員が住民税非課税で、公的年金など収入金額の合計が80万円以下 |
21,478円 |
| 第5段階(基準額) | ・本人が住民税非課税である
・本人の公的年金収入および、ほかの所得の合計が80万円を超え、かつ同一世帯に住民税課税者がいる |
75,360円 |
| 第6段階(基準額×1.15) | ・本人が住民税課税である
・所得合計が120万円未満 |
86,664円 |
| 第10段階(基準額×1.9) | ・本人が住民税課税であり
・所得合計が420万円以上、520万円未満 |
143,184円 |
| 第14段階(基準額×2.9) | ・本人が住民税課税である
・所得合計が1,500万円以上、2,500万円未満 |
256,224円 |
| 第18段階(基準額×4.9) | ・本人が住民税課税である
・所得合計が5,000万円以上 |
369,264円 |
参考:世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例 | 世田谷区高齢福祉部
また、介護保険料額は3年ごとに保険料が見直されるため、65歳以上の従業員がいる場合、定期的に保険料を確認しておきましょう。
3-4. 被扶養者でも介護保険料を支払う必要がある
65歳以上になると、被扶養者であっても個人で介護保険料を支払う必要があります。
40歳から65歳未満の被扶養者は、扶養者が加入している健康保険に介護保険料が上乗せされるため、被扶養者個人からの保険料支払いは発生しませんでした。しかし、65歳以上になると、被扶養者も「第1号被保険者」として市区町村から直接保険料が徴収される仕組みに変わります。
例えば、夫が協会けんぽに加入しており、その妻が65歳未満の被扶養者である場合、妻個人から介護保険料の支払いは発生しません。しかし、妻が65歳になると、市区町村に直接保険料を支払う必要が出てきます。
被扶養者の保険料支払いに関しては勘違いが生じやすいため、変更について従業員に事前に説明し、円滑な移行をサポートしましょう。
4. 65歳以上の介護保険料の免除と減免制度

65歳以上の介護保険料には、特定の条件を満たす場合に支払い免除や減免措置が適用される制度があります。
介護保険料の免除条件が適用される主な対象者・条件は次のとおりです。
| 免除対象者 | 免除条件 |
| 海外居住者 | ・日本国内に住所を有さない場合、介護保険料の支払いが免除される |
| 短期滞在の外国人 | ・3ヵ月未満の滞在の外国人は支払い免除される ・3ヵ月以上滞在の場合は加入が必要になる |
| 特定施設の入所者 | ・障害者支援施設やハンセン病療養所など、適用除外施設に入所している場合 |
| 生活保護受給者 | ・生活保護法に基づく生活扶助費で介護費用が補填され、実質的に保険料は免除される |
介護保険料の減免条件が適用される主な対象者・条件は次のとおりです。
| 減免対象者 | 減免条件 |
| 災害で損害を受けた場合 | ・地震や台風などで被害を受けた場合、保険料の減免が適用される場合がある
・被災程度や損害の内容に応じて減免額が決まる |
| 失業、病気などで収入が大幅減少した場合 | ・長期の入院、失業、事業の休止などで収入が著しく減少した場合、減免が受けられる場合がある
・各自治体が定める収入基準にもとづき判断される |
| 所得が低く生活が困難な場合 | ・所得基準に基づき減免が適用される場合がある
・自治体により、資産状況や扶養関係など追加条件が設定される場合がある |
| 各自治体で定める減免条件に該当している場合 | ・各自治体が独自に定める減免基準に該当している |
介護保険料の免除・減免制度は、介護保険料の支払いが困難な状況にある高齢者を支援し、生活の安定を図ることを目的としています。
ただし、具体的な適用条件や減免率は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の介護保険担当課に確認しましょう。
5. 65歳以上の介護保険料は年末調整で社会保険料控除できる

介護保険料は社会保険料控除の対象となるため、年間t調整をすることによって65歳以上の介護保険料でも控除を適用できます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金などから差し引かれた金額の全額です。
控除手続きの方法は、特別徴収と普通徴収で異なります。
| 支払方法 | 必要書類 | 主な手続きの方法 |
| 特別徴収 | ・公的年金などの源泉徴収票 | 源泉徴収票に記載されている介護保険料の金額を、年末調整時に「保険料控除申告書」に金額を記入して勤務先に提出する |
| 普通徴収 | ・通料(口座振替)
・領収書(納付書払い) ・アプリケーションの履歴情報(キャッシュレス決済) |
支払った保険料を証明する書類を準備し、年末調整や確定申告時に支払った額を申告する |
納付書の控えや口座振替明細など、支払いを証明する書類は確定申告時に必要になる可能性があるため、必ず保管しておくことが推奨されます。
6. 65歳以上の介護保険料を滞納するリスク

介護保険料には納付期限があるので、期限内に支払いをしなければなりません。
正当な理由があれば、申請をすることで延滞が認められることもありますが、支払いを放置したまま滞納すると下記のようなペナルティが課せられます。
| 滞納期間 | ペナルティ |
| 納付期限から1年未満の滞納 | 納付日までの延滞金や督促手数料が上乗せされる |
| 1年以上の滞納 | ・介護サービスを利用した場合、全額(10割)を支払いとなる
・滞納分を納付、給付の申請をおこなえば、利用料の9~7割が払い戻される |
| 1年半以上の滞納 | ・介護サービスを利用した場合、全額(10割)を支払いとなる
・滞納分を納付しても払い戻しはない |
| 2年以上の滞納 | ・未納確定となるため後払いはできなくなる
・介護サービスを利用する際、自己負担が3~4割上がる ・高額介護サービスを受けた場合の払い戻しがない |
これらのペナルティを見ると、「介護サービスを利用しなければ問題ない」と思う従業員がいるかもしれません。
しかし、どんなに健康であっても、介護サービスを受けるような状況になる可能性はゼロではないので、滞納のリスクをしっかり理解してもらいましょう。
7. 65歳以上の介護保険料の制度を正しく理解しよう

65歳以上では、介護保険制度における被保険者の区分が変更となるので、介護保険料の仕組みも大きく変わります。
保険料は市町村が定める基準額にもとづいて所得段階別に設定され、主に年金からの特別徴収や個別の普通徴収で納付されるためです。また、3年ごとの見直しがあるため、定期的に保険料を確認することが重要になります。
65歳以上の介護保険料の制度を理解することで、従業員の負担額や支払い方法の変化を把握し、適切なサポートができるようになるでしょう。
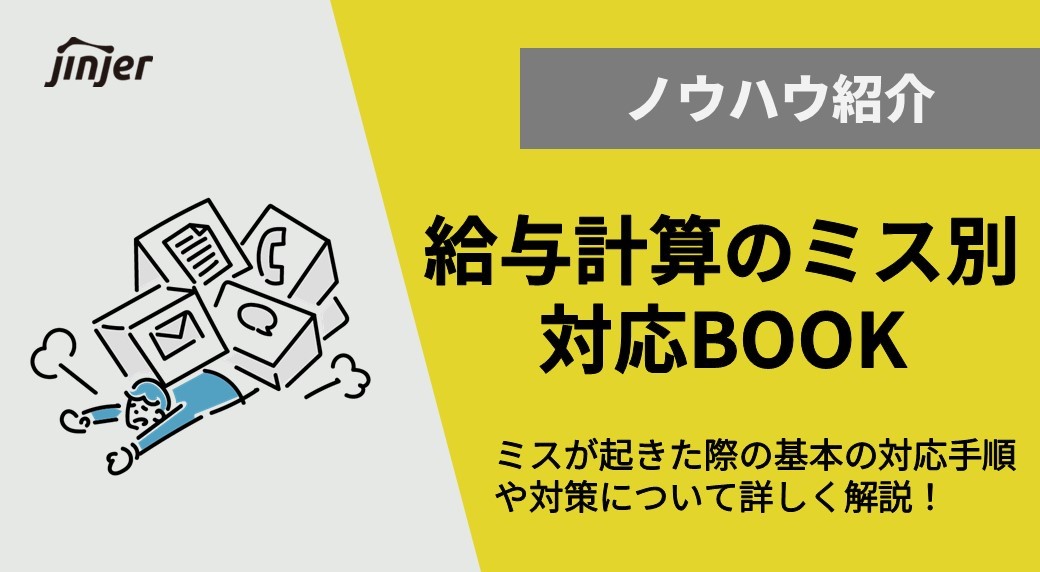
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
当サイトでは、万が一ミスが発覚した場合に役立つ、ミス別に対応手順を解説した資料を無料配布しています。
資料では、ミス発覚時に参考になる基本の対応手順から、ミスを未然に防ぐための「起こりやすいミス」や「そもそも給与計算のミスを減らす方法」をわかりやすく解説しています。
◆この資料がおすすめできる方
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・ミスをしないために、給与計算業務のチェックリストがほしい方
・根本的に給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
いずれかに当てはまる担当者の方は、ぜひ「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、日々の実務にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
給与計算の関連記事
-


雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28
-


パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28
-


休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28






















