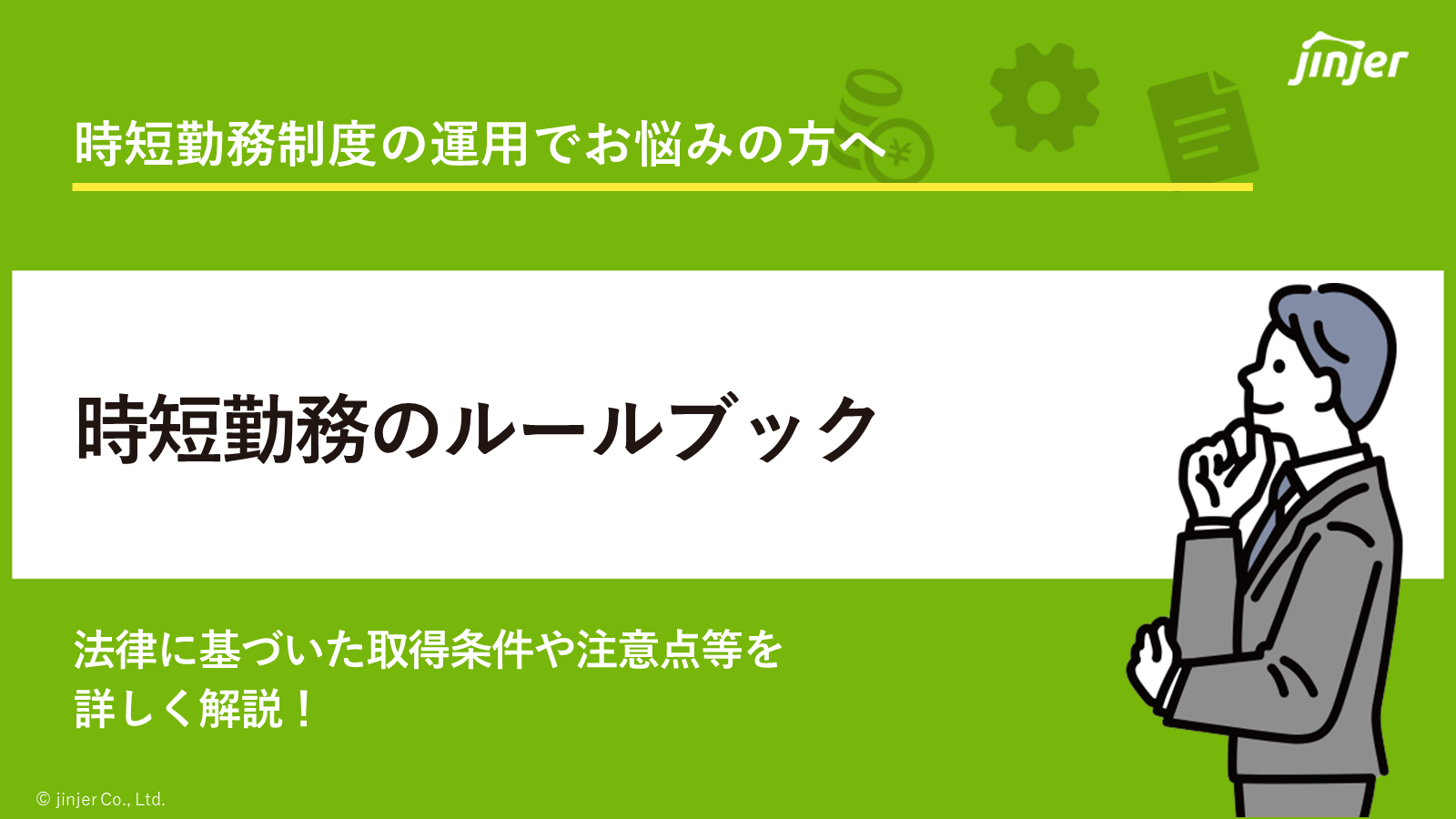時短勤務者の休憩時間は?その上限や短時間勤務制度の注意点を解説
更新日: 2024.7.4
公開日: 2021.11.12
OHSUGI

あらゆる面で価値観の多様化が進む昨今では、育児や介護のほか従業員のさまざまな生活環境を考慮した、柔軟な働き方をサポートする姿勢が各企業に求められています。こうした動きの一つにあるのが時短勤務で、従業員の働きやすさを守るためにも、しっかりと制度として整えていくことが不可欠です。
実際の就業時間など考慮すべき点は多々ある中で、時短勤務の休憩時間についても、従業員を管理する側にとっては気になるポイントでしょう。休憩時間は適切に取り入れていかないと、従業員の負担になるだけでなく、場合によっては違法となるケースも。
そこで今回は時短勤務における休憩時間の導入方法について、以下から詳しく解説していきます。まずは時短勤務の基礎知識から見ていきましょう。
▼時短勤務についてより詳しく知りたい方はこちら
時短勤務とは?導入するための手順と問題点を解説
目次
「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。
「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 時短勤務(短時間勤務制度)とは


時短勤務とは正確には「短時間勤務制度」といって、主に育児や介護にあたる従業員が通常の勤務よりも労働時間を短縮して働ける仕組みを指します。時短勤務の制度を設けることは、育児・介護休業法で定められている法的義務で、従業員からの請求があった場合には必ず適用しなければなりません。そのため企業側には、あらかじめ時短勤務の制度を用意しておくことが求められます。育児や介護をする従業員にとって、柔軟に利用できる体制にしておくことが必要です。
1-1. 短時間勤務制度が導入された背景
短時間勤務制度は、少子高齢化や働き方改革の一環として導入され、主に育児や介護といった家庭の事情に対応するための制度です。
従来、出産や育児、介護などで就業を諦めざるを得ない状況が多く見られました。しかし、家庭と仕事を両立できる環境を整えることが社会全体の緊急課題となり、政府は1991年に育児・介護休業法を制定しました。
この法制度は、働く人々が家庭と仕事の両立をよりスムーズに行えるようにする目的で設けられ、当初は「子が1歳未満の労働者」に対する時短勤務、フレックス、始業終業時刻の変更などの選択肢を提供するものでした。
2002年には対象者を「3歳未満の子を養育する労働者」に拡大し、2012年には1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度がすべての事業主に義務付けられました。これにより企業は、従業員が希望すれば短時間勤務制度を適用する義務があります。この制度の導入により、従業員のワークライフバランスの向上と企業の生産性の向上が期待されています。
2. 時短勤務における基本ルール
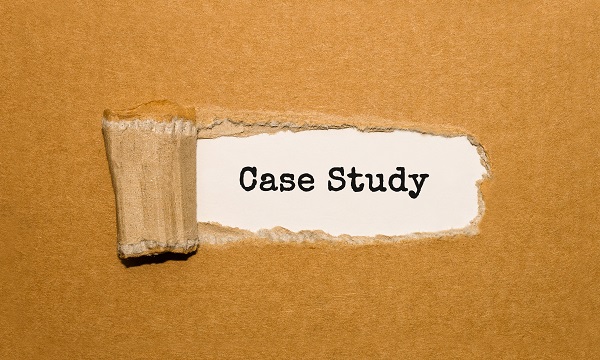
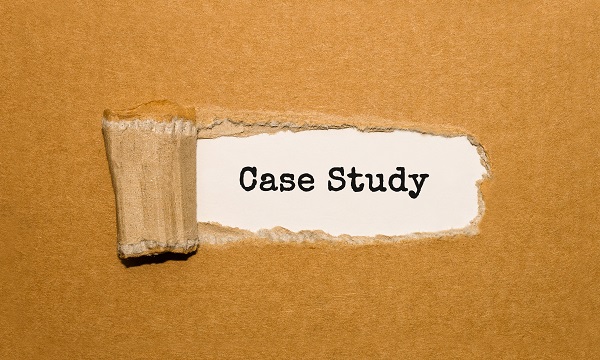
育児や介護をする従業員の希望に応じて利用できるといっても、すべての人を対象にしなければならないわけではありません。育児・介護の双方において、日々雇われる労働者のほか、入社1年未満・週2日以下の従業員も労使協定によって対象外にできます。
2-1. 介護による時短勤務の場合
介護での短時間勤務制度では、所定労働時間の短縮・フレックス勤務の適用・始業や終業時刻の調整・介護サービス費用助成のうち、いずれかを利用開始から3年以上の間で2回以上利用を可能とする措置をとる必要があります。所定労働時間を短縮する場合には、通常時が8時間なら2時間以上・7時間以上なら1時間以上を努力義務としています。
2-2. 育児による時短勤務の場合
育児における短時間勤務制度の法的義務は、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することです。そのためそもそも勤務時間が6時間に満たない従業員には、適用しなくても問題ありません。
さらに育児での時短勤務では3歳未満の子を持つ従業員が対象で、配偶者が専業主婦・主夫であっても適用するのがルールです。また業務の性質もしくは実施体制上、導入が困難な場合には、例外的に労使協定によって対象外にできるケースもあります。
時短勤務の導入事例(始業・終業時間の前後させる)
例えば単純に終業時刻を早める運用のほか、始業・終業をそれぞれ前後させる方法があります。もしくは日によってシフト制にすることも可能で、1週間の業務状況に応じて設定するのも一つの手でしょう。
関連記事:時短勤務はいつまで取れる?気になる基準と就業規則の決め方
3. 時短勤務者の休憩時間はどうする?


それでは実際に時短勤務をしてもらう際には、どのように休憩を取ってもらうのが適切なのでしょうか。
3-1. 6時間未満の時短勤務なら休憩時間がなくても問題ない
仮に時短勤務が6時間を超えない場合には、休憩時間はなくても違法ではありません。
労働基準法では、1日6時間を超過する場合には最低45分・8時間を超過する場合には最低1時間の休憩時間を義務としています。例えば時短勤務にて9時~15時で勤務してもらい、休憩なしで退勤としても問題はありません。
ただし時短勤務での休憩方法決めるときには、以下のような部分に注意しておかなければなりません。
4. 時短勤務における休憩時間で気を付けたいポイント


6時間以下の時短勤務であれば、休憩時間の設置は法的な義務ではありません。しかしより良い労働環境のためには、ある程度まとまった勤務時間数になる際には、本来なら休憩時間を設けるのが理想です。そこで次からは、適切な休憩方法にしていくためのコツをご紹介していきます。
4-1. 6時間を超過した勤務での休憩なしは違法
もし6時間勤務にしていたとしても、場合によっては数分超過してしまう日があるかもしれません。労働基準法では、6時間から1分でも多く労働するのであれば、最低45分の休憩が必要になります。休憩を取らせずに6時間を超えて勤務させてしまうのは違法なので、定時上がりを保証できないのであれば、45分以上の休憩時間を設けておくのが無難です。「6時間」は労働基準法での休憩規定の限度となるため、十分に注意しなければなりません。
関連記事:労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説
4-2. 育児時間との違いに注意
1歳未満の子を持つ女性労働者には、休憩時間とは別に、1日2回各30分以上は業務から離れられる育児時間を求める権利が認められています。もし対象者からの請求があれば、必ず応じなければならないため、休憩時間とはきちんと区別して運用していくことが必要です。
なお休憩時間は途中付与が原則で、当然ながら労働時間の前後に持ってくることはできません。一方で育児時間は、どのタイミングで取っても基本的には問題ないため、遅出・早上がりにも使えます。それぞれには大きな差があるので、併用する際には注意しましょう。
関連記事:労働基準法に定められた育児時間の考え方と請求方法を解説
4-3. 休憩時間を設ける際には「自由の原則」を忘れずに
労働基準法による休憩とは、使用者の指揮命令から完全に離れて、自由に過ごせる時間を指します。時短勤務には限りませんが、例えば電話番をしていたり指示待ちをしていたりするケースは、休憩には値しません。しっかりと休息が取れなければ意味がないので、きちんと休憩時間の過ごし方にも配慮する必要があるでしょう。
4-4. 拘束時間とのバランスにも配慮する
労働基準法での45分や1時間といった休憩時間は、あくまで最低ラインです。多くなる分には特に問題はないため、業種や職種によっては少し長めの休憩時間にしているケースも見られます。
時短勤務でも同様の休憩にしても違法ではありませんが、拘束時間が長くなってしまうのは問題です。例えば短く分割して休憩を設定するなども可能なので、時短勤務者にとってなるべく働きやすくなるように、しっかりと工夫するのがベストでしょう。
5. 法的な設置義務がある制度を理解して柔軟な休憩時間の確保を


時短勤務とは、従業員が私生活と無理なく両立していくための制度です。短い労働時間の中でも本来のパフォーマンスをしっかりと発揮してもらうためには、企業側にもさまざまな配慮が求められるでしょう。時短勤務における休憩時間も同様に、各従業員がきちんと日々の業務に集中しやすいよう、工夫しながら運用していくことが必要です。
ぜひ本記事を参考に、なるべく各自の負担を軽減できるような体制づくりを進めていきましょう。
「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。
「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25