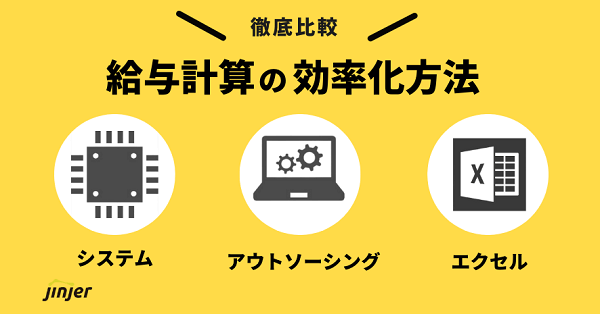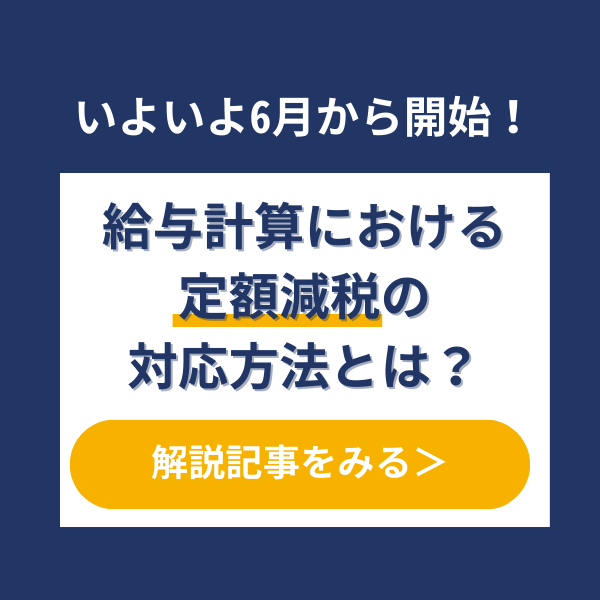賃金規程の変更後に届出が義務付けられているケースや変更手続きの流れ
更新日: 2024.5.22
公開日: 2022.2.12
OHSUGI

就業規則には賃金に関する項目があるため、新たに作成する際や変更を加える際は、労働基準監督署に届出をおこなう必要があります。賃金規程は労働基準法の中でも重要な項目なため、手順の誤りは認められません。
今回は、賃金規程の変更後に届出が必要となる理由や変更手続きの流れ、注意点などについて詳しく解説していきますので、変更したい方はぜひご一読ください。
目次
1. 賃金規程を変更した後には労働基準監督署へ届出が必要
賃金については就業規則に必ず記載しなければならない、絶対的必要記載事項です。就業規則は作成および変更時に労働基準監督署に届出をおこなう必要があるため、賃金規程に変更を加える場合も労働基準監督署に届出をしなければなりません。
就業規則とは、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律など、そこで働くすべての労働者について定めるものを指します。記載する項目のうち必ず表記しなければならない項目は、労働時間、退職に関することなどさまざまですが、賃金も必ず表記しなければならない項目のひとつです。
また、賃金規程の中でも、退職手当や賞与など臨時の賃金などについては、定めをした場合には記載をしなければなりません。
▽絶対的必要記載事項の賃金規程(必須項目)
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
▽相対的必要記載事項の賃金規程(事業場ごと規則を作成する場合は必須)
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
ただし、労働基準法に反する規則は就業規則として定めることができず、仮に労働者の同意を得ていても労働基準監督署に認められません。また、企業が一方的に作成し、提出することはできず、労働者の過半数を代表する労働組合または代表者からの意見書を添付してから提出する必要があります。
2. 賃金規程の変更手続きの流れ
賃金規程を変更する流れは次のとおりです。
- 賃金規程の変更案を作成し、労働者代表に意見を求める
- 労働者代表に意見書を提出してもらう
- 就業規則変更届を労働基準監督署に提出する(2番の意見書添付)
- 労働基準監督署が就業規則を受領する
- 正式に採用された就業規則を労働者に周知する
まずは、就業規則の変更案を作成し、労働者代表に意見を求めましょう。労働者は変更案をもとに意見書を作成しますが、意見書は労働者の過半数を代表する労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者が作成します。
労働者から受け取った意見書は、就業規則変更届に添えて労働基準監督署に届出をおこないます。労働基準監督署が受領した後は、変更後の就業規則を労働者全員に周知しましょう。周知する際は労働者全員の目につきやすい部分に掲示する方法と、書面を交付する方法を併用するのがおすすめです。
関連記事:労働契約法10条の規定による就業規則の変更の条件や方法
3. 賃金規程変更時の注意点
賃金規程を変更する際には、下記の注意点に留意する必要があります。
- 必ず労働者の意見を聞くこと
- 労働者が就業規則の内容を知っていること
- 労働基準監督署に届出をおこなうこと
- 労働者にとって不利益な内容に変更する際は合理性があること
- 法令を遵守しているか
- 自社の環境に適合しているか
また、さらに重要な注意点が2つあるのでチェックしておきましょう。
関連記事:就業規則の変更届出の方法と気をつけるべき4つの注意点
関連記事:就業規則の不利益変更とは?実施する際の4つの注意事項
3-1. 労働者の意見書を添付する
注意点の中に「必ず労働者の意見を聞くこと」とありますが、単に意見を聞くだけではなく、賃金規程を変更する際は労働者の意見書を添付しなければなりません。
労働基準法90条により、就業規則の作成または変更を労働基準監督署に届出する場合、従業員側の意見を記載した書面を提出することが義務付けられています。賃金規程は就業規則の記載項目となっているため、意見書を提出する必要があるのです。
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
意見書は、部署もしくは事業場ごとに従業員代表者を選出し、記載してもらいます。ただし、従業員の過半数が加入する労働組合がある場合は、労働組合に記載してもらっても問題ありません。
3-2. 労働者だけが不利益にならないようにする
就業規則は労働者の意見書の添付と、労働者への周知が義務付けられていますが、必ず労働者の同意を得なければならないというわけではありません。ただし、「労働者だけが不利益にならないようにする」という点には注意をする必要があります。
もしも、労働者にとって不利益な内容に変更する場合は、変更に対する合理性が求められます。万が一、不利益な内容に変更する際は、下記の内容を従業員に周知しましょう。
- 不利益の範囲や程度
- 変更する際の理由
- 労働者との交渉状況
また、労働者と使用者の間で締結される就業規則でも、労働基準法を違反する内容を定めることはできません。従って、法律で定められている最低賃金を下回る賃金規程は、就業規則でも定められないことになっているので注意してください。
4. 賃金規程を変更して賃金の引下げをおこなうこともできる
先ほども少し触れましたが、賃金規程の変更では賃金の引き下げをおこなうこともできます。賃金の引き下げは労働者にとっての不利益変更となるので、計算方法の変更や支給方法の変更よりも、注意しなければなりません。
賃金規程の変更で賃金を引き下げるには、以下の条件があれば認められます。
- 変更に合理性がある
- 就業規則を周知する
変更の合理性とは、具体的に以下の要素によって決まります。
- 従業員に対する不利益の程度ができる限り少ない
- 会社の存続など変更が必要である
- 他企業と比較して、不利益変更が妥当である
- 労働者(労働組合または代表者)と交渉がスムーズに進んでいる
4-1. 賃金規程変更による賃金引き下げの種類
賃金を引き下げる際に参考になるのが、賃金引き下げの種類です。賃金の引き下げには以下の3種類があり、それぞれ意味合いと賃金の引き下げ方法が異なります。
- ベースダウン
- 賃金カット
- 減給処分
ベースダウンというのは、賃金表そのものを改定して賃金水準を引き下げることを指します。一見平等に思える変更方法ですが、労働者全体の基本給が下がるため、退職者が続出し労働力不足に陥る可能性があります。ベースダウンをする際は、やむを得ない場合以外は避けるのが賢明です。
賃金カットは欠勤、遅刻などをした場合にその時間分を控除することをいいます。賃金を控除するのであれば、あらかじめ規定を定めておく必要があります。
減給処分は、賃金カットよりも重いペナルティとして用いられます。会社の規定を違反した労働者に対して適用されることが多いのですが、自由に指定できるわけではないので、注意が必要です。賃金カットと同じように、減給処分を適用する際には、あらかじめ就業規則で規定を定めておきましょう。
関連記事:労働基準法第24条における賃金支払いのルールを詳しく紹介
5. 賃金規程を変更する際は労働基準監督署への届出が必要!
賃金規程は就業規則の一種なので、変更する際は作成時と同じように労働基準監督署に届出をする必要があります。また、就業規則は労働者と会社の間で締結するため、変更には労働者の過半数を代表する労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて提出しなければなりません。
また、賃金規程の変更で賃金の引き下げをおこなう際は、不合理な理由で一方的に変更せず、労働者としっかり交渉し納得してもらうことも重要です。
就業規則は労働者が安心して働くための大切なルールなので、トラブルにならないよう労働基準法を遵守して運用していきましょう。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25