労働基準法第24条の内容や違反した場合の罰則を詳しく解説
更新日: 2024.7.19
公開日: 2021.10.3
OHSUGI
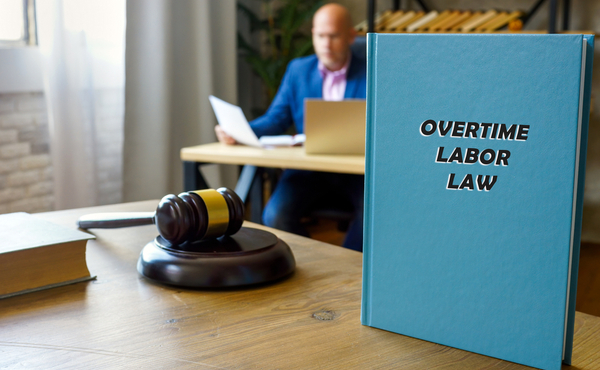
日本では労働基準法第24条において賃金支払いのルールが定められています。経営者は法令を遵守し、自社の従業員に対して適切な方法で賃金を支払わなければなりません。法令違反が発覚した場合は30万円以下の罰金刑に処される可能性もあるため、十分注意しましょう。
この記事では、労働基準法第24条で定められる賃金支払いの5原則について詳しく解説します。「通貨以外で賃金支給はできるのか?」「賃金の分割払いはできるのか?」など、賃金の支払方法に疑問がある方はぜひ参考にしてください。
そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
労働基準法総まとめBOOK
1. 労働基準法第24条は賃金支払いのルールを定めた法律


労働基準法第24条とは、労働者に対する賃金の支払いルールについて記載された条文です。条文の中では5つのルールが定められており、一般的に「賃金支払いの5原則」と呼ばれます。
1-1. 労働基準法第24条の条文
労働基準法第24条に定められている条文の内容は以下の通りです。
労働基準法第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条の適用の対象となる「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与など名称に関わらず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものを指します(労働基準法第11条)。ただし、実費的な性格を持つ旅費の支給や交際費の支給は通常「賃金」には該当せず、賃金支払い5原則の適用を受けません。要するに、賃金とは広範な概念であり、労働者が労働に対して受け取る全ての報酬を含むと理解されます。
1-2. 賃金支払いの5原則とは
【賃金支払いの5原則】
- 通貨支払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上の原則
- 一定期日払いの原則
賃金支払いの5原則は不当な搾取や賃金の未払いから労働者を守り、その生活を安定させるための取り決めです。これらの原則により、日本では現金以外(貴金属や商品券など)で賃金を支給することや、従業員の代理人に賃金を支払うことなどが禁止されています。
5原則は労働基準法に定められた法令であり、経営者はこれらを遵守した上で従業員への賃金支給をおこなわなければなりません。
ただし、賃金支払い5原則には例外もあります。経営者は5原則を正しく理解して実践すると共に、例外となる事例についても把握しておくことが大切です。
2. 労働基準法第24条における賃金支払い5原則の内容と例外


労働基準法第24条で定められる賃金支払い5原則について、その内容を1つずつ詳しく解説します。それぞれの原則には例外となる事例もあるため、合わせてチェックしておきましょう。
2-1. 通貨支払いの原則
従業員の賃金は、日本で流通する通貨(日本円)で現金支払いをしなければなりません。労働基準法第24条では、社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払いが義務付けられています。小切手や商品券を賃金の代わりとすることや、貴金属や腕時計等による現物支給は法令違反です。
ただし、例外として賃金の口座振り込みは認められています。この場合は事前に労働者の同意が必要です。現代社会において賃金の現金支給はかえって不便であり、口座振り込みが定着しています。
2023年の法改正では、一定の要件を満たした場合に限定して電子マネーによる給与の支払いも可能になりました。給与の支払い方法は、今後も時代とともに変化していく可能性が高いです。
また、法令で例外と認められており、かつ労使協定が締結されている事項に関しては現物支給も可能です。例えば定期券による通勤手当の支給や、小切手による退職金支払いなどが該当します。
2-2. 直接払いの原則
賃金は必ず従業員本人に直接支払わなければなりません。従業員本人が指定した任意代理人への支払は法令違反です。また従業員が未成年の場合でも、その両親など法定代理人への支払も禁止されています。
直接支払いの原則は、第三者による賃金の中間搾取を防ぐために適用されるものです。従業員の希望があったとしても、経営者は労働を行った本人以外に賃金を支払うことはできません。
例外として、従業員の「使者」に該当する人物に対しては賃金の支払いが認められています。従業員の配偶者や秘書などは「使者」に該当するため、本人に代わって賃金を支払うことが可能です。代理人と使者の区別は困難な場合もありますが、社会通念上本人に支給するのと同等の効果を生ずる者か否かで判断します。
2-3. 全額払いの原則
その期間の賃金は、全額まとめて一括で支払う必要があります。全額払いの原則は、賃金の一部の支払いを保留とし、従業員の転職の自由を阻害することを防ぐための決まりです。
また、直接払いの原則と同様、労働の対価を全て本人に帰属させることを目的とします。目的が定かではない不当な控除は禁止です。
賃金から控除できるのは法令で定められた名目のみです。社会保険料や源泉所得税といった公益上の必要があるものや、物品購入代金など明白な理由があるものについては控除が認められます。
また、従業員の過半数を代表する労働組合との労使協定によって同意が得られている項目についても控除が可能です。社内旅行積立費や親睦会費、社宅費などは労使協定の締結があれば賃金から天引きできます。
会社から労働者に金銭を貸し付けている場合はどうする?
会社が労働者に対して金銭を貸し付けている場合でも、賃金支払いにおいては「全額払いの原則」が適用されます。この原則により、貸付金と賃金を相殺することは基本的に認められていません。賃金は、労働者がその労働に対して受け取るべき正当な対価であり、これを貸付金で相殺することは労働者の生活を脅かす可能性があるため、違反行為とみなされます。
ただし、例外として労働者が相殺に同意し、その同意が労働者の自由な意思に基づくと認められる合理的な理由がある場合には、合意による相殺が認められます。この場合、会社は労働者からの書面による明確な同意を得ることが重要です。また、その同意が強制されていないことを示す証拠も必要です。もしこれを無視して相殺を行うと、賃金支払いに関する法律に違反し、罰則を受けるリスクが生じます。従って、会社は十分な注意を払い、法令遵守を徹底する必要があります。
賃金を過払いしてしまった場合はどうする?
全額払いの原則に基づき、賃金を過払いしてしまった場合の対応について説明します。まず、賃金の過払いとは誤って労働者に多くの賃金を支払うことを指します。そして、過払い分を翌月以降の賃金から差し引く手続きを「調整的相殺」と呼びます。この手続きを行うには、①過払い発生時期と賃金の清算調整時期が合理的に近接していること、②労働者に事前の予告があり、その額が多額で経済生活の安定を脅かさないこと、という条件が必要です。これらの条件を満たせば全額払いの原則に違反することなく、適切な対応が可能です。人事担当者や経営者の皆様には、これらの法律的要件を理解し、適切に対応することが求められます。
2-4. 毎月1回以上の原則
賃金は、最低でも月に1回以上の頻度で支払いが必要です。たとえ支給額が同じであったとしても、2ヶ月分をまとめて隔月で支払うということはできません。なお、この場合の1ヶ月とは暦の上での毎月1日から月末最終日までを指します。
毎月払1回以上の原則は労働者の生活上の不安を軽減することが目的です。特に十分な貯蓄がない若年層では、賃金の支払い間隔が開くと衣食住が満足に賄えない可能性もあります。
年俸制を採用している企業の場合は、最低でも年俸を12分割して毎月ごとに分けて支給しなければなりません。1年分の報酬をまとめて先払いすることも違法とされます。
例外として、毎月の給与とは別に発生する賃金については不定期での支払が可能です。いわゆるボーナスと呼ばれる年2回の賞与や、結婚手当のような臨時で発生する手当てが該当します。
2-5. 一定期日払いの原則
賃金はあらかじめ指定された一定の期日で支払われなければなりません。「月末締めの翌月25日払い」のように、毎月決まった期日を設定する必要があります。
「毎月第3金曜日」のような毎月の日付が一定にならない期日設定は違法です。また、「毎月20日から25日」のように支払期日に幅を持たせることも禁止されています。
一定期日払の原則は、毎月一回以上の原則と同様に労働者の生活を安定させるための取り決めです。支払日が毎月変動すると計画的な生活を送ることが困難になります。
例外として挙げられるのは支払日が休日の場合です。
支払日と休日が重なってしまった月は、該当月に限り支払日を変動することができます。その際は、休日前最後の平日に支払われることが一般的です。
関連記事:給料の締め日とは?支払日との違いや決めるポイント・変更の注意点を解説
3. 労働基準法第24条の違反となる行為と罰則
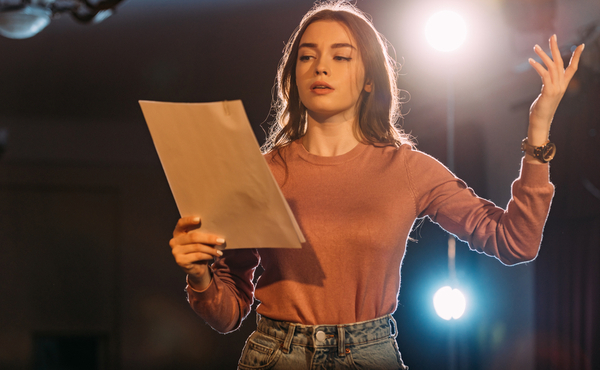
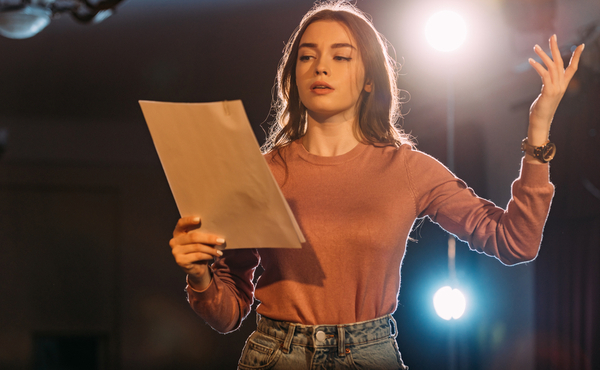
労働基準法第24条の違反行為が発覚した場合、労働基準監督署による監査や指導が実施されます。最悪の場合は経営者が罪に問われ、30万円以下の罰金刑に処されることもあるのです。
ここでは、労働基準法第24条の違反例を紹介します。
3-1. 違反例① 月末に入社した従業員の給与を翌々月に支給した
月末間際に採用して勤務実績が少ない従業員の賃金を、翌月の勤務分と合算して翌々月に支払うことは違法です。たとえ少額の賃金であったとしても、毎月1回以上の原則に従い各月ごとに賃金を支払わなければなりません。
3-2. 違反例② 従業員の希望に従い税理士に賃金を支払った
従業員が個別で契約している税理士は任意代理人にあたります。直接支払いの原則に従い、賃金は必ず従業員本人に支払いましょう。本人の希望があったとしても、従業員以外の第三者に給与を支払うことできません。
3-3. 違反例③ 給与の支払手数料を天引きした
賃金の支払いに関する各種手数料の天引きは全額払いの原則に反します。賃金からの控除が認められているのは源泉所得税や社会保険料、もしくは物品購など明白な理由があるもののみです。例え少額であったとしても、労使協定で同意を得られていない項目の控除はできません。
4. 労働基準法第24条において賃金からの天引きは違法?


労働基準法第24条において、賃金から天引きすると違法になるものと、ならないものが存在します。具体的に見ていきましょう。
4-1. 賃金からの天引きが認められるもの
賃金からの控除が認められているのは源泉所得税や社会保険料、もしくは物品購など明白な理由があるもののみです。例え少額であったとしても、労使協定で同意を得られていない項目の控除はできません。
法令で認められた税金・社会保険料
健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税など、法令で定められた税金・社会保険料は、賃金から天引きすることが可能です。これらの天引きは労働基準法第24条1項但書に明確に定義されています。この法令により、従業員の賃金からこれらの支払いを自動的に行うことが認められています。これにより、企業は法定の社会保険料や税金の適切な管理が可能となり、就業規則や労働契約の透明性を保つことができます。
労使協定で控除認められた社宅料・社員旅行の積立金など
上記以外に賃金からの天引きが認められるものとして、社宅料や社員旅行の積立金があります。これらは労働基準法第24条1項但書に基づき、労使協定で控除が認められるものです。企業がこれらの控除を実施するためには、労使協定を締結することが必要です。
労使協定を締結するだけでなく、就業規則や雇用契約書にも明文化しておく必要があります。これにより、従業員の賃金からの天引きが合法的に行えます。実際に適用される範囲や方法は企業ごとに異なるため、具体的な内容を記載することが重要です。
違反した場合には、労働基準法に基づく罰則が課される可能性があり、企業の信頼性や労使関係にも悪影響を及ぼすことがあります。したがって、これらの規定を遵守し、定期的に見直すことが推奨されます。
4-2. 賃金からの天引きが認められないもの
賃金からの天引きが認められないものとして、業務上で必要になる費用や労働者が会社に与えた損害金額、さらに給与における振込手数料について詳しく説明します。
業務上で必要になる費用・損害金額
まず、労働基準法に基づき、労働者の賃金から業務上必要な費用や損害を天引きするには、労働者の事前の合意が必要です。この合意がない場合、たとえ会社側にとって全く正当な理由があるとしても、それらを賃金から差し引くことは法律で認められていません。違反した場合、企業は労働基準法違反として罰則の対象となり、行政指導や罰金のリスクがあります。特に経営者や人事担当者は、こうした法律を遵守し、労働者との間に明確な契約や合意を形成することが重要です。賃金の天引きに関するルールを徹底することで、企業は法的リスクを最小限に抑えることができます。
給与における振込手数料
給与からの振込手数料の天引きは、前章でも紹介した通り、基本的には認められていません。従って、給与から振込手数料を控除することは違法となり得るため、企業は手数料の負担を自社で行うか、事前に労使協定を明確に定め適切に対処する必要があります。
5. 法律に則った賃金の支払いに関連して抑えておくべきルール


またその他にも会社から従業員へ賃金を支払う上で、法律に関連して抑えておくべきルールのポイントを解説します。
5-1. 労働時間は1分単位で給与計算をおこなう
企業が賃金支払いに関する法律を適正に遵守するためには、労働時間を1分単位で給与計算することが重要です。労働基準法上、労働時間を15分や30分単位で切り捨てて計算することは「全額払いの原則」に反し、違法とされています。そのため、割増賃金の計算も含め、労働時間は1分単位で処理することが求められます。
ただし、法律には一部例外も認められています。例えば、1時間あたりの賃金や割増賃金に円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げられます。また、一ヶ月における時間外労働や休日労働、深夜業の総額に1円未満の端数が生じた場合も同様の処理が認められています。同じく、一か月の時間外労働、休日労働、深夜業の合計時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることが可能です。
これらのルールを遵守し、適正な給与計算を行うことで、企業は法的リスクを回避し、労働者の権利を保障することができます。
5-2. 法改正により賃金のデジタル払いに対応する
令和5年4月1日から施行された労働基準法施行規則の改正により、賃金のデジタル払いが可能となりました。この変更により、特定の電子マネーを用いた賃金支払いが合法化されましたが、全ての電子マネーが利用できるわけではなく、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の電子マネーのみが利用可能です。例えば、大手資金移動業者であるPayPayや楽天、auなどが申請中です。また、現金化できないポイントや仮想通貨の利用は認められません。
賃金のデジタル払いのメリットとしては、銀行口座を持たない労働者への給与振込が容易になり、ATMから出金する手間の削減やポイント還元キャンペーンを利用することができる点が挙げられます。しかし、デジタル払いには受入上限額(100万円以下)があるため、超過分を別の方法で支払う必要があり、二重の手間やセキュリティリスク、資金移動業者の破綻リスクが存在します。さらに、導入コストも考慮すべき点です。
デジタル払いの導入には、労使協定の締結と労働者の個別同意が必要です。労働者の同意は書面で取得することが望ましく、詳細に説明を行った上で同意書を収集することが推奨されます。この新制度を活用する際には、企業は法的要件をしっかりと理解し、適切な対応を行うことが重要です。
6. 労働基準法第24条を遵守して適切に賃金を支払おう


労働基準法第24条は賃金の未払いや不当な搾取から労働者を守るための法令です。法令違反は経営者自身が罪に問われるばかりか、従業員の不信を招きます。労働基準法第24条の5原則を正しく理解し、従業員に対する適切な賃金支払いを実施しましょう。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08






















