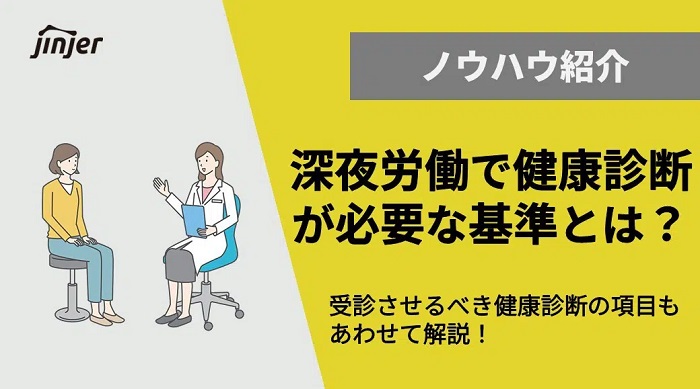夜勤による不眠症は労災の対象となる?企業が取るべき対策を紹介
更新日: 2025.6.10 公開日: 2024.12.23 jinjer Blog 編集部
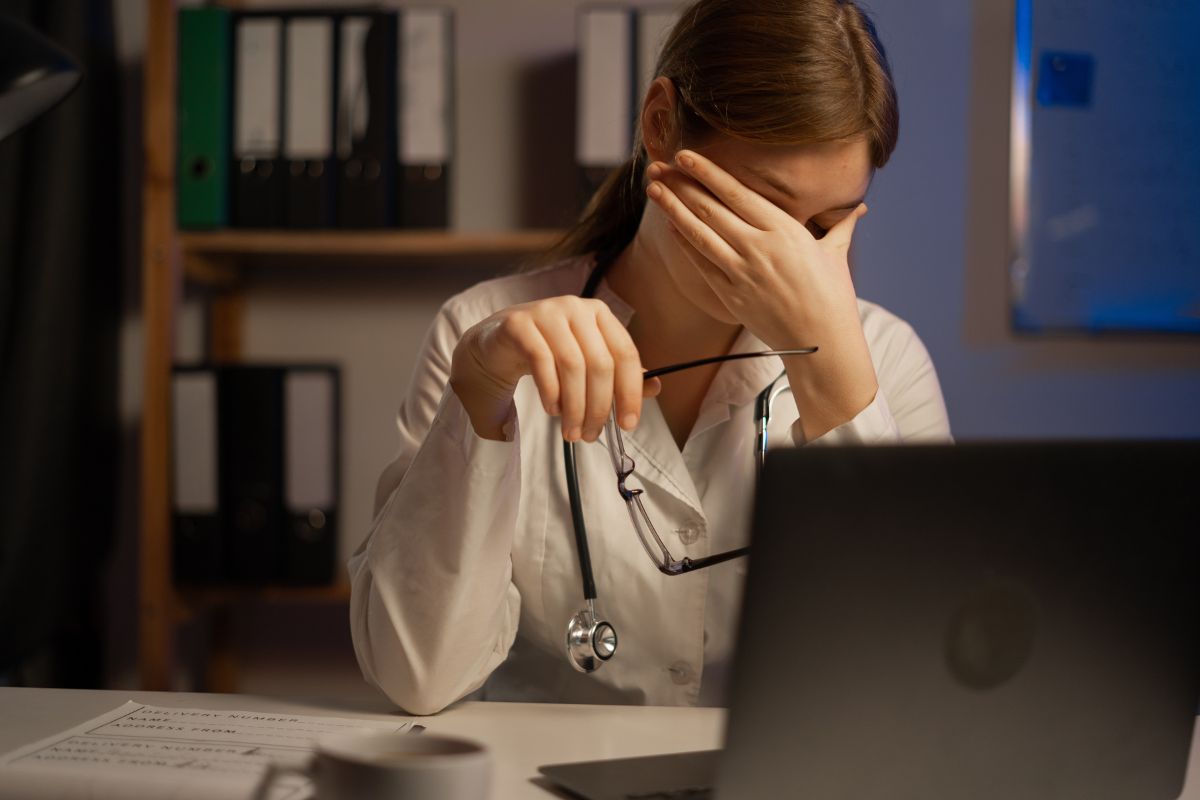
夜勤による不眠症は、労災の対象となる可能性があります。
労災認定されると、従業員からの損害賠償請求や労災保険料が上がる可能性があるので注意が必要です。また、労災のリスクだけでなく、従業員の健康や業務効率にも悪影響を及ぼすため、早めの対策が欠かせません。
本記事では、夜勤による不眠症が労災の対象となる理由や従業員・企業にもたらすリスク、企業が取るべき対策などを解説します。
目次
深夜労働では健康診断が必要と知っていても、「どれくらいで必要になるの?」「深夜労働がメインではなく、残業が深夜帯に及んでしまった場合も必要?」など、具体的な基準を把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは深夜労働・深夜残業で健康診断が必要になる基準や、受けさせるべき健康診断の項目について、本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。
また月80時間を超える時間外・休日労働を行い、さらに疲労の強い従業員から申し出があった場合も、過重労働者として医師による面接指導も必要も必要になります。
深夜労働に対する健康診断や、過重労働に関する面接指導の扱いに不安のある方は、こちらからダウンロードしてご確認ください。
1. 夜勤による不眠症は労災の対象となる


夜勤による不眠症は、労災の対象となる可能性があります。
その理由は、厚生労働省が定める脳・心臓疾患の労災認定基準では、長時間労働に加え、深夜業務が重なる場合に労働認定が考慮されるためです。
基本的な脳・心臓疾患の労災認定基準は、以下のとおりです。
- 発症前1ヵ月に100時間以上の時間外労働
- 2〜6月の時間外労働の平均が月80時間を超える場合
このように長時間労働が最も重視されるのは確かですが、近年は労働時間以外の負荷要因も考慮されることになっています。
労働時間以外の負荷要因は、以下の5つです。
- 勤務時間の不規則性
- 事業場外における移動を伴う業務
- 心理的負荷を伴う業務
- 身体的負荷を伴う業務
- 作業環境
上記のうち、夜勤は「勤務時間の不規則性」に該当します。
長時間労働に加えて、頻繁に夜勤がある場合、十分な睡眠を確保するのは難しいでしょう。
睡眠を取れないことにより体調を崩した場合、夜勤による不眠症が業務に起因するものと認められ、労災の対象となる可能性があります。
2. 夜勤による不眠症が従業員にもたらすリスク


夜勤による不眠症が従業員にもたらすリスクは、以下のとおりです。
- 精神の不調を引き起こす可能性がある
- 生活習慣病の発症リスクが高まる
ここでは、これら2つのリスクについて解説していきます。
2-1. 精神の不調を引き起こす可能性がある
夜勤による不眠症が続くと、精神の不調を引き起こす可能性があるでしょう。
夜勤が続くと体内リズムが乱れ、夜勤後に眠ろうとしても寝付けないことが多く、睡眠の質が低下してしまいます。睡眠の質が低下すると、うつ病などの精神障害を引き起こす可能性が増加すると言われているので注意が必要です。
国立精神・神経センターの亀井雄一氏の文献「気分障害における睡眠異常とその治療」によると、1年以上の不眠が続くと、うつ病が発症するリスクが通常の40倍に高まるとされているのです。
夜勤による不眠が長期間続くと、うつ病などの精神的な不調へとつながる可能性が十分にあるでしょう。
参考:うつ病治療 その1|日本を元気にする光療法の総合サイト
2-2. 生活習慣病の発症リスクが高まる
夜勤による不眠症は、生活習慣病の発症リスクを高める要因ともなります。
十分な睡眠による休養は、健康維持に重要な役割を果たしているため、十分な睡眠が取れない夜勤は生活習慣病になりやすいのです。
事実、日本の調査により、肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病と睡眠不足との関連が明らかになっています。また、心筋梗塞や狭心症、心不全などの心血管疾患のリスクも高まると言われています。
夜勤による不眠症を放置すると、生活習慣病を含むさまざまな健康リスクが増大する可能性があるでしょう。
3. 夜勤による不眠症が企業にもたらすリスク


夜勤による不眠症が企業にもたらすリスクは、以下の3つです。
- 生産性が低下する
- 事故のリスクが高まる
- 休職者や退職者の増加につながる
ここでは、これら3つのリスクについて解説していきます。
3-1. 生産性が低下する
夜勤による不眠症の従業員が増えると、生産性が低下する可能性があります。睡眠不足が続くと、集中力が低下し、作業効率が悪くなるため生産性が低下してしまうのです。
ある調査によると、集中力の維持が改善されることで、年間約25.8兆円の経済的効果が創出されるとも言われています。
また、不眠による疲労の蓄積も問題です。十分な睡眠を取れないと、脳の機能が適切に働かないので判断力の低下を招きます。このような状態は、重要な意思決定に支障が出る可能性もあり、業務の効率化にも悪影響が生じかねません。
慢性的な睡眠不足は従業員のモチベーションも低下させ、組織全体のパフォーマンスに大きな悪影響を与えるリスクもあるということです。
参考:Dropbox 職場における集中力の途切れがもたらす 労働生産性損失のグローバル調査結果を発表|Dropbox
3−2. 事故のリスクが高まる
夜勤による不眠症は、事故のリスクも高めます。
睡眠不足が続くと、判断力や認知能力に大きな影響を及ぼします。特に運転や機械操作などでは、重大な事故につながる可能性が高いので注意しなければなりません。
事故が発生すると、従業員自身だけでなく、周囲の人も巻き込む可能性があり、被害はさらに拡大するおそれがあります。また、労災が発生すると企業の評判も大きく低下しかねません。
3−3. 休職者や退職者の増加につながる
夜勤による不眠症は、休職者や退職者の増加にもつながる可能性があります。
身体的にも精神的にも疲弊した従業員はモチベーションが低下し、仕事に対する気力が沸かず、離職を考えてしまうことが多いのです。
離職者が増えると、ただでさえ人員が不足しがちな夜勤には、さらに大きな負担がかかるでしょう。
また、離職した従業員が多ければ、そ分の人員を補充しなければなりません。採用や研修などのコストがかさみ、企業にとっても大きな負担となります。
そのため、従業員の健康状態を注視し、不眠症の影響が出ていないか確認することが重要です。
4. 夜勤による不眠症で労災認定されないために企業が取るべき対策


夜勤による不眠症で労災認定されないために企業が取るべき対策は、以下のようなことが挙げられます。
- 従業員に睡眠指導を実施する
- 勤務間インターバルを十分に取る
- シフトを見直す
- 仮眠スペースを用意する
- 従業員にヒアリングを定期的におこなう
ここでは、この5つの対策について解説していきます。
4-1. 従業員に睡眠指導を実施する
従業員に睡眠指導を実施し、夜勤による不眠症での労災認定を防ぎましょう。睡眠リテラシーを向上することで、従業員の睡眠不足を予防する効果が期待できます。
例えば、睡眠に関するセミナーの実施は有効な施策の一つです。他にも、健康管理システムを活用すれば、睡眠不足が続く従業員を早期に把握できるので、不眠症を予防できます。
産業医などの専門家と相談しながら、効果的な睡眠指導を従業員に提供しましょう。
4-2. 勤務間インターバルを十分に取る
夜勤による不眠症での労災認定を予防するには、勤務間インターバルを十分に取ることが重要です。
勤務間インターバルとは、退勤から翌日の出勤時間までの休息時間を指します。この時間は疲労回復にとって非常に重要です。
インターバルが短いと、睡眠の質が低下し、労働能力が低下するリスクが高まります。特にインターバルが12時間未満の場合、睡眠不足を感じる従業員が増えるでしょう。
働き方改革においても、勤務間インターバル制度の導入は、企業の努力義務とされています。十分な勤務間インターバルを確保し、従業員の健康に配慮しましょう。
参考:勤務間インターバル制度をご活用下さい|厚生労働省 東京労働局
4-3. シフトを見直す
夜勤による不眠症での労災認定を防ぐためには、シフトの見直しも検討しましょう。勤務スケジュールの改善により、睡眠の質の向上が期待できます。
例えば三交代勤務の場合、日勤・準夜勤・深夜勤の順にシフトを調整すると、生体リズムの乱れが少なくなり、不調を感じにくくなるとされています。
シフトの見直しすることで、従業員のストレスや疲労を軽減できるでしょう。
4−4. 仮眠スペースを用意する
仮眠スペースを用意することも、夜勤による不眠症を防ぐ有効な施策です。夜勤中の仮眠は、疲労を効果的に押さえる効果があると言われています。実際に30分程度の仮眠時間を導入したことにより、従業員のパフォーマンスが向上した例もあります。
質の良い睡眠を取るためには、環境を整備することが大事なので、静かでリラックスできる個室が望ましいでしょう。
ただし、仮眠時間を「休憩時間」としてしまうと、結果的に拘束時間が長くなってしまうのでゆっくり休むことができないかもしれません。
従業員が安心して仮眠を取るには、仮眠時間を労働時間として認めることも大切な対策だと覚えておきましょう。
4−5. 従業員へのヒアリングを定期的におこなう
夜勤による不眠症で労災認定されないように、従業員へのヒアリングを定期的におこないましょう。
「しっかりと睡眠が取れているか」「疲れやだるさはないか」「体調に変化はないか」などこまめに確認することで、不調の早期発見・予防につながります。
なお、月80時間を超える時間外労働がある従業員には超過時間の情報を通知し、本人からの申し出があれば、医師による面接指導を実施しなければなりません。
定期的なヒアリングを通じて、従業員の睡眠状況を確認し、労災リスクを減らしましょう。
参考:長時間労働者への医師による面接指導制度について|厚生労働省
5. 夜勤による不眠症を予防し労災リスクを下げよう


夜勤による不眠症は、従業員の健康に深刻な影響を与えるだけでなく、業務中の事故や怪我などの労災リスクも高めます。労災は、企業全体の生産性にも大きな影響を及ぼすことにもつながります。
また、優秀な人材が休職するだけでなく、最悪の場合、退職にもつながる可能性があるので、無理のない夜勤シフトにすることが重要です。
さらに企業が取るべき対策としては、睡眠指導や勤務間インターバルの確保、仮眠スペースを用意する、定期的な面談などが有効です。
会社のためにも従業員のためにも、夜勤シフトの健康管理に積極的に取り組み、夜勤による不眠症を予防して労災リスクを下げましょう。
深夜労働では健康診断が必要と知っていても、「どれくらいで必要になるの?」「深夜労働がメインではなく、残業が深夜帯に及んでしまった場合も必要?」など、具体的な基準を把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは深夜労働・深夜残業で健康診断が必要になる基準や、受けさせるべき健康診断の項目について、本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。
また月80時間を超える時間外・休日労働を行い、さらに疲労の強い従業員から申し出があった場合も、過重労働者として医師による面接指導も必要も必要になります。
深夜労働に対する健康診断や、過重労働に関する面接指導の扱いに不安のある方は、こちらからダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-



雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30