労働基準法上は退職2週間前通知で大丈夫?スムーズな手続き方法
更新日: 2025.7.1 公開日: 2021.10.2 jinjer Blog 編集部

働き方の多様化に伴い、職場には多様な価値観や生活環境を持つ人材が集まるようになっています。それぞれが事情を抱えながら働いていれば、急な退職の申し出が発生するケースも少なくないでしょう。
ただし、会社としては業務の都合上、すぐに受け入れるのが難しい場合もあるかもしれません。できるだけ早めに願い出てもらうのがベストですが、実際のところ、従業員からの退職の申し出にはどのように対応するべきなのでしょうか。本記事では、退職について知っておくべき法律知識と、実務で役立つ運用例・注意点を解説します。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
関連記事:労働基準法とは?法律の要点や人事が必ず押さえたい基本をわかりやすく解説
目次

人事担当者であれば、労働基準法の知識は必須です。しかし、その内容は多岐にわたり、複雑なため、全てを正確に把握するのは簡単ではありません。
◆労働基準法のポイント
- 労働時間:36協定で定める残業の上限時間は?
- 年次有給休暇:年5日の取得義務の対象者は?
- 賃金:守るべき「賃金支払いの5原則」とは?
- 就業規則:作成・変更時に必要な手続きは?
- 40年ぶりの大改正:人事担当者が押さえておきたい項目は?
これらの疑問に一つでも不安を感じた方へ。
当サイトでは、労働基準法の基本から法改正のポイントまでを網羅した「労働基準法総まとめBOOK」を無料配布しています。
従業員からの問い合わせや、いざという時に自信を持って対応できるよう、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 労働基準法に基づく退職・解雇の原則とは


「労働基準法では退職の2週間前に通知が必要」という話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実はこれは正確ではありません。労働基準法には退職の2週間前ルールといった条文は存在せず、その規定は民法によって定められています。
しかし、労働基準法にも退職や解雇についていくつか別の規定があります。ここでは、労働基準法や実質的に法律と変わらない判例によって規定されるルールを解説していきます。
1-1. 30日前までの解雇予告(労働契約の終了)
会社が従業員を解雇する場合、労働基準法第20条により、少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分以上の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。
また、一定の場合については解雇が禁止されています。主なものとして、労働災害のため療養中の期間とその後の30日間、産前産後の休業期間とその後の30日間、労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇などがあります。
加えて、裁判の判例では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効」と判示されており、解雇には厳しい制約がある点に留意が必要です。
1-2. 整理解雇
会社の業績悪化や事業縮小など、経営上の理由による人員削減を「整理解雇」といいます。整理解雇は労働基準法に規定はありませんが、判例により厳格な要件が示されています。一般的に「整理解雇の4要件(要素)」と呼ばれ、以下のようなものがあります。
- 人員削減の必要性:会社の経営悪化などにより人員削減が真に必要であること
- 解雇回避努力:配置転換などあらゆる努力をしても解雇以外に手段がないこと
- 解雇対象者の選定の妥当性:誰を解雇するかの基準が客観的かつ公正で、合理的であること
- 手続の妥当性:事前に労働組合や従業員に説明・協議を行い、納得を得るよう努めるなど、解雇に至るまでの手続きが適切であること
1-3. 退職勧奨
解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは、従業員に自主的な退職を促し、合意の上で労働契約を終了させることをいいます。これは、従業員の意思とは関係なく会社が一方的に労働契約の解除を通告する解雇とは異なります。
退職勧奨自体は違法ではなく、現に業績不振や問題のある従業員に退職を促すことは多くの会社でおこなわれています。ただし、その進め方が行き過ぎると違法になる可能性があります。例えば、「退職に応じなければ解雇する」と迫ったり、長時間にわたり執拗に退職を強要したりすると、違法な退職強要とみなされる可能性があるため注意が必要です。
2. 無期雇用者がおこなう2週間前までの解約申出


次に、従業員から退職する場合の法律関係を確認します。ここでは期間の定めのない無期雇用契約(正社員など)を前提とし、民法第627条に基づく退職の申入れについて解説します。民法627条は、退職予告期間やタイミングに関する基本ルールを定めた規定です。
ポイントは「退職の2週間前」という期間ですが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
2-1. 根拠となる法律|民法627条1項
民法第627条第1項は、期間の定めのない労働契約について従業員・会社双方に「いつでも解約の申入れ(退職の申出)ができる」権利を認めています。その場合、申入れの日から2週間後に労働契約が終了すると規定しています。
つまり、正社員など無期雇用の従業員は、2週間前に退職の意思表示をすれば退職できます。これは退職の自由を保障する趣旨の規定であり、会社の同意がなくても退職が成立する点が重要です。会社側がそれを拒否したり一方的に延長したりすることはできません。
2-2. 月給者の対応方法|民法627条2項
民法627条第2項・第3項では、賃金の締め日など労働契約の報酬支払い期間に着目した特則が定められています。内容を平たく言えば、使用者(会社)からの解約申し入れについて「賃金計算期間の途中で解雇予告をする場合のタイミング」についての規定です。
例えば、月の前半に労働契約の解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に退職となるルールです。ただし現実には、会社からの解雇には特別法である労働基準法20条の30日前までに予告というルールが優先します。
3. 就業規則や社内規定との関係性


就業規則や社内規定で「退職は◯◯日前までに申し出ること」などのルールが定められている場合、民法の2週間ルールとどちらが優先するのでしょうか。この章では、会社独自の退職ルールと法律の関係について解説します。
3-1. 退職申出の期限を独自に定めた場合
多くの会社では就業規則などに「退職希望日の◯ヵ月前までに退職願を提出すること」などの規定があります。社内ルールは従業員との労働契約の一部となりますが、法律上の権利である2週間ルールを超えて、従業員の退職の自由を制限できるかどうかが論点となります。
結論からいうと、社内ルールの退職予告期間は「従業員へのお願い・社内手続き上のルール」であって、従業員が社内ルールを守らずに民法627条上の退職の申し入れを主張すれば、2週間ルールの効力は発生します。
社内ルールを設けて、従業員に対して退職予告期間を義務づけたとしても、それを根拠に従業員の退職を拒んだり、退職を認めずに働かせたりすることはできません。
ただし会社側としては、円滑な引継ぎのため就業規則である程度の予告期間を求めることは合理的です。双方の合意の上の退職を前提とした予告期間として、あまりに長すぎる期間を定めないよう留意し、従業員に周知しておくことが望ましいでしょう。
4. 有期雇用労働者に対する退職2週間前の考え方と実務


前述の通り、民法上はいつでも退職が認められるとされていますが、このルールが適用されるのは正社員などの期間の定めのない労働契約の従業員に限ります。契約社員やアルバイトなどの有期雇用では取り扱いが異なるので注意しておきましょう。
有期雇用では、期間を定めた労働契約が結ばれているため、「期日まで勤務すること」は従業員の原則的な義務です。そのため、仮に契約期間中に退職の申し出があったとしても、原則は会社の了承なしに退職することは認められません。
4-1. 契約期間の途中解雇はできない
しかしながら、例えば本人が重い病気になってしまった場合など、やむを得ない理由でどうしても勤務を続けるのが難しい際には、契約期間内であっても退職を受け入れる必要があります。
ただし、法律上では、具体的にどのような場合が「やむを得ない」と判断されるのか、明確には示されていません。それぞれの状況に応じて、やむを得ない事情であるかどうかを判断することになるので、どうしても迷う時には専門家に相談するのがおすすめです。労働局や労働基準監督署の相談窓口か、弁護士などから助言を受けると良いでしょう。
4-2. 契約期間中に従業員から辞めたいと言われた場合
では、特段やむを得ない理由がないにもかかわらず有期契約の従業員から「契約途中で辞めたい」と申し出があった場合、どのように対応すべきでしょうか。
会社としては従業員の法的義務を説明し、退職を拒否することも可能です。しかし、現実には無理に引き止めても、モチベーション低下による生産性悪化や別のトラブルにつながりかねません。そのため、実務上は当事者間で話し合い、合意の上で契約を途中終了(合意解約)することが多いです。
例えば「引継ぎ期間としてあと1ヵ月働いてもらう代わりに◯月◯日付で契約を終了する」などの合意を書面で取り交わし、円満に退職させる対応が現実的でしょう。
4-3. 契約期間中でも解雇できる場合
有期雇用では、労働契約によって一定期間は労働者を拘束することになるため、労働基準法による例外的な措置がされています。特例として労働契約が1年を超える長期の有期雇用では、労働基準法附則第137条にて「契約の初日から1年経過している」ケースでは、時期に関係なく退職することが可能です。
期間の定めのない契約の従業員と同じ扱いとなり、通知から2週間で労働契約終了します。
なお、何かの事業完了に向けた有期の労働契約は、上記には該当しません。例えば、特定のプロジェクト遂行に応じた期間が定められているケースなどです。
そのほか、厚生労働大臣が定めた高度な専門業務や、満60歳以上の労働者における有期雇用についても、この例外は適用されません。
また民法626条によって、仮に期間の短い労働契約であっても続けて5年を超え雇用されている場合には、期間の定めのない契約の従業員と同様に退職の自由が認められます。例えば契約期間は3ヵ月でも、これまでに毎回更新して5年を超え勤続している場合には、いつでも退職することが可能です。
そのため、期間の定めのない契約の従業員と同じく、退職の通知があってから2週間が経つと労働契約は終了してしまいます。
参照:民法|e-Gov法令検索
4-4. 契約期間途中の退職と損害賠償請求
上記のような例外に当てはまらないケースにおいて、有期雇用の途中で退職する労働者に対しては、場合によっては損害賠償請求ができます。
ただし、労働者の一方的な過失で退職となり、その因果から損害が生じた場合のみです。実際には非常に判断が難しいため、退職による損害賠償請求が認められたケースは少なく、よほどのことがなければ難しいとされています。多少の業務混乱や採用費程度では損害の算定も難しく、訴訟コストに見合わないでしょう。
5. 急な退職申出に備える方法


民法上では退職の申し出から2週間で労働契約が終了となるため、会社側は拒否できません。しかしながら、業務の引き継ぎや人員補充のことを考えると、退職までの期間に余裕を持たせて欲しいのが本音でしょう。
ここからは、法律を踏まえた上での、退職通知の手続きをスムーズにする方法についてご紹介します。
5-1. 就業規則で独自の退職ルールを定める
民法上では、あくまで退職通知から2週間で契約が切れるというだけで、双方の合意を前提に就業規則で「1ヵ月前までに願い出ること」というように定めることも認められています。
しかし、就業規則にあるからといって、必ずその規定が優先されるとは限りません。状況に応じて、従業員の意思表示が民法(労働契約の解約の申し入れ)なのか就業規則(合意退職の願い出)なのか見極めなくてはいけません。前者であれば、2週間後には労働契約は終了であると認識しましょう。
5-2. 従業員に周知する
就業規則は、定めるだけでは十分ではありません。従業員に対して就業規則を周知することが効力発生の要件の一つになっていますので、必ず周知しましょう。
退職時の手続きをよりスムーズにするためには、入社時のオリエンテーションや研修などの機会において、退職に関するルールと手続きを適切に説明し、理解を促進しておくとよいでしょう。
5-3. 急な退職申出の際は話し合いをおこなう
実際に急な退職の意思表示があった場合は、まず冷静に対応し、従業員との話し合いの機会を設けることが重要です。退職の理由を聞き、改善可能な問題であれば解決策を検討し、従業員の引き留めを図ることも一つの選択肢です。
ただし、引き留めをおこなう際は、従業員の自由意思を尊重し、過度な圧力をかけないよう注意が必要です。「なぜ辞めたいのか理由を聞かせてください」「改善できる点があれば検討したい」といった姿勢で臨み、従業員が話しやすい環境を作ることが大切です。
退職の意思が固い場合は、業務の引き継ぎや後任者について具体的な相談をおこないます。「重要な業務については詳細な引き継ぎ資料の作成をお願いしたい」「後任者への直接指導をお願いしたい」といった依頼をして、業務への影響を最小限に抑えると良いでしょう。
5-4. 労使双方で合意のうえで退職日を決める
最終的な退職日については、双方の合意により決定することが理想的です。法的には従業員からの2週間前の通知で労働契約が終了しますが、業務の引き継ぎや後任者の確保を考慮し、可能であれば合意のうえ退職日の調整を図りましょう。
退職日の調整をおこなう際は、従業員の事情も十分に考慮する必要があります。転職先の入社日が決まっている場合や、家庭の事情による退職の場合など、従業員側にも譲れない事情があることを理解し、双方にとって最適な解決策を見つけることが大切です。
5-5. 急な退職が発生しても影響を最小限にするための準備をおこなう
そもそも、会社としては「従業員はいつでも辞められる」という認識を持っておくことが必要です。いつ誰が辞めても困らないよう、業務を特定の従業員しかできない状況を作らないなど、属人性を解消することが重要でしょう。
属人性の解消にはドキュメンテーションの徹底が不可欠です。従業員が退職しても、他のメンバーが見ることができる共有フォルダなどにマニュアルを置いておき、参照すれば業務を続行できるようにしておけば、知識やノウハウが失われることを防げます。
また、社内Wikiやクラウド上の情報共有ツール・タスク管理ツールなどナレッジ共有ツールの活用も有効です。タスク管理ツールによっては、メンバー間の業務のやり取りの履歴が残るものもあります。各自のナレッジが蓄積・共有されることで、誰かが突然不在になっても他のメンバーが情報にアクセスして対応できます。
ほかにも、1人の担当者だけが知識やノウハウを独占しないよう、業務の複数担当制やジョブローテーションを導入することも有効でしょう。日頃からチーム内で業務内容を共有し合い、緊急時に代理で対応できる人材を育成しておくことが重要です。
6. 急な退職トラブルと注意点
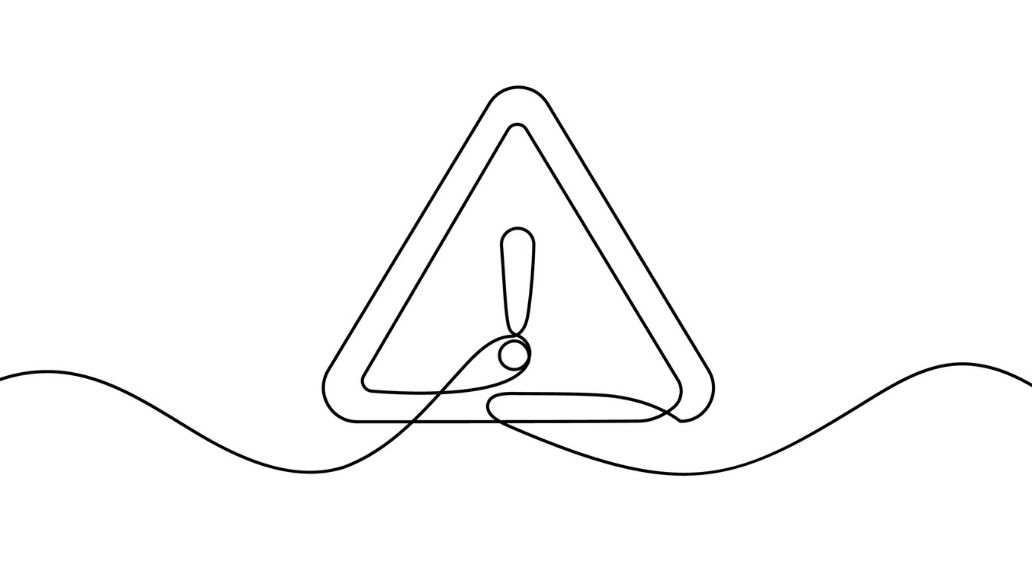
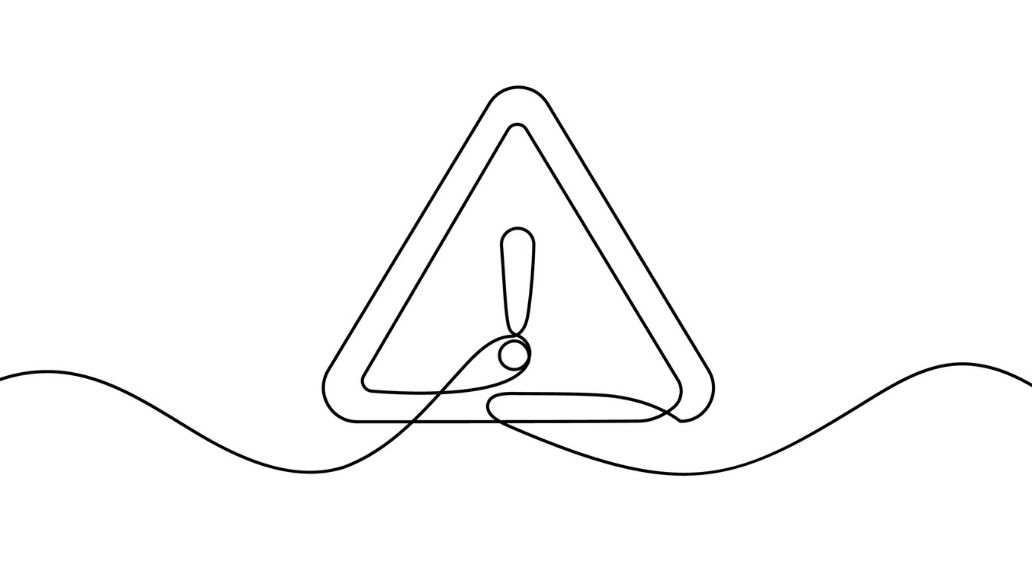
急な退職申し出があった場合、対応によっては深刻なトラブルに発展する可能性があります。法的なリスクを避け、適切な対応を取るために注意すべきポイントを詳しく解説します。
6-1. 退職通知の方法による拘束は原則不可
従業員からの退職の通知は、会社に意思さえ伝わるものであれば法律的な制限は特にありません。民法上では口頭でも問題はなく、例えば「規定の書式による通知でなければ認めない」というように、退職を引き延ばすことは基本的にはできないと考えておきましょう。
なお、退職通知の方法についてもルールとして就業規則に定めることは可能です。トラブルを防ぐためにも、定めておくのがベストです。
6-2. 退職代行を利用された場合
昨今、退職代行サービスの利用が増加しており、会社側も適切な対応方法を理解しておく必要があります。
弁護士でない退職代行サービス会社は、法律上は従業員の意思を伝達する「使者」としての役割しか持てません。弁護士でない者が退職条件について会社と交渉することは、弁護士法72条に違反する非弁行為に当たり違法となるということを認識しておきましょう。
まずは退職意思が本人の真意に基づくものかを確認します。必要に応じて委任状や本人確認書類のコピー提出を求め、本当に従業員本人の依頼なのかをチェックします。本人の意思が確認できたら、正式な退職届(書面)の提出を依頼します。代行業者からの口頭やメールでの連絡のみでは、のちの紛争防止のためにも不十分です。
実務上は、代行業者に「〇〇さんの署名押印入りの退職願原本を郵送してください」と依頼するか、会社から本人宛に退職届フォームを郵送し、署名捺印のうえ返送してもらう対応がとられます。
退職願が届いたら、申し出の受理と今後の手続きを記載した回答書を作成し、記録の残る方法で送付します。貸与品があれば返却方法なども指示しましょう。
このようなやり取りの内容(日時、相手、内容、提出書類、応答など)はすべて詳細に記録を残しましょう。のちの証拠となります。
6-3. 2週間以内に退職されると業務に支障が出る場合
従業員が「今日までで辞めます」など、2週間より短い予告で退職を申し出るケースもあります。この場合、法律上は労働契約の終了は2週間後になるため、2週間の法定義務を説明し、可能な限り勤務するよう説得します。
それでも本人が勤務しなければ、欠勤として扱いつつ2週間後に退職とする対応が一般的です。法的には、従業員がこのように無断欠勤で辞め損害が出た場合、損害賠償を請求することが可能ですが、実際に訴えて認められる金銭的損害が発生していない限り、あまり現実的ではありません。
6-4. 2週間以内の退職で有給休暇を使わせないのはNG
労働基準法39条に基づき、従業員は取得日を指定して年次有給休暇を取得する権利があり、使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」以外はその申請を拒めません。
会社にはやむを得ない場合に取得時季を変更する権利(時季変更権)が認められますが、それは他の時季に振り替え可能な場合に限られます。退職が決まっている従業員については、退職日以降に振り替えることが不可能なため、実質的に時季変更権は行使できないと解されています。
7. 労働基準法や民法に従って適切に退職手続きをしよう


2週間前予告による退職は従業員の基本的権利であり、会社側の都合でこれを制限することはできません。
ただし、双方の合意があれば退職までの期間を伸ばしてもらうことが可能です。。就業規則に「1ヵ月前までに願い出」など定め、周知しておくといいでしょう。この記事では、法律と判例、実務の観点から解説しました。退職にまつわるリスク管理に不安がある方はぜひ参考にしてください。
関連記事:労働基準法による退職届は何日前までに必要?法的ルールを解説



人事担当者であれば、労働基準法の知識は必須です。しかし、その内容は多岐にわたり、複雑なため、全てを正確に把握するのは簡単ではありません。
◆労働基準法のポイント
- 労働時間:36協定で定める残業の上限時間は?
- 年次有給休暇:年5日の取得義務の対象者は?
- 賃金:守るべき「賃金支払いの5原則」とは?
- 就業規則:作成・変更時に必要な手続きは?
- 40年ぶりの大改正:人事担当者が押さえておきたい項目は?
これらの疑問に一つでも不安を感じた方へ。
当サイトでは、労働基準法の基本から法改正のポイントまでを網羅した「労働基準法総まとめBOOK」を無料配布しています。
従業員からの問い合わせや、いざという時に自信を持って対応できるよう、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労働基準法の関連記事
-



勤務間インターバル制度の義務化はいつから?労働基準法改正の最新動向と企業への影響
勤怠・給与計算公開日:2025.12.16更新日:2026.01.29
-



2026年の労働基準法の改正は見送り?施行時期や議論中のテーマを解説
人事・労務管理公開日:2025.12.15更新日:2026.01.29
-


35歳未満の定期健康診断の基本項目は?省略可能な項目も解説
人事・労務管理公開日:2025.01.31更新日:2025.04.30











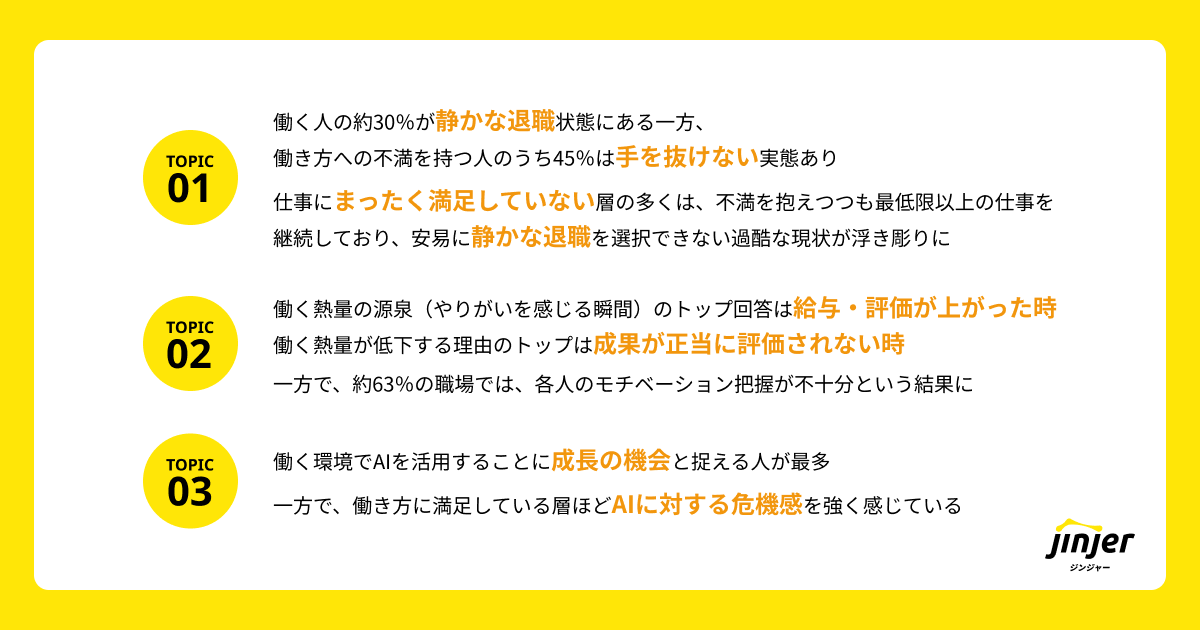








.png)