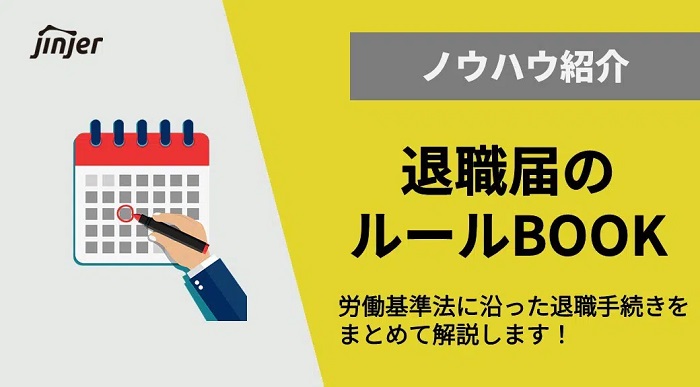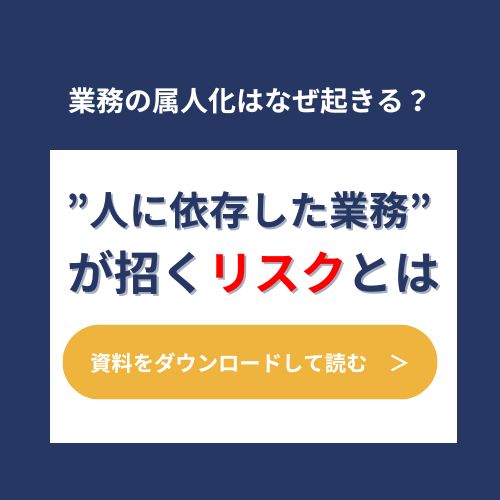労働基準法による退職届は何日前までに必要?辞める際の法的ルールを解説
更新日: 2024.7.19
公開日: 2021.10.4
OHSUGI

近年では1つの会社で定年まで勤め上げるという人は少なくなり、よりよい職場や働き方を模索するための転職も当たり前となってきました。
従業員が退職を希望しているのであれば、あとあと問題が起きないよう円満に手続きを進めることが重要です。企業の人事担当者は退職届提出の時期に関するルールを必ず把握しておきましょう。
この記事では、労働基準法による退職届の提出が何日前までに必要かを解説していきます。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。
そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法について、本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。
「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。
目次
1. 労働基準法による退職届は2週間前の提出でも大丈夫?


従業員が退職を決意した場合、その意志を会社に伝えるために退職届を提出するのが一般的です。
労働条件に関する基準を定めた労働基準法には、具体的に退職までの期間を区切るような項目はありません。退職の期間は、民法で規定されています。
雇用形態によって退職届の提出タイミングが異なりますので、雇用形態ごとにチェックしていきましょう。
1-1. 正社員など雇用の期間が定められていない従業員の場合
正社員のように雇用の期間が定められていない従業員については、退職届の提出タイミングは次のとおり考えられています。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法|e-Gov法令検索
民法の第627条1項には、解約の申入れはいつでもすることができ、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了するとの記載があります。
つまり、正社員など雇用の期間の定めがない労働者の退職については、申し入れから2週間という期間が定められているのです。とはいえ、引き継ぎなどのことを考えれば、1ヵ月前くらいまでに退職届を提出してもらったほうが安心です。
▼より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
労働基準法上は退職2週間前通知で大丈夫?スムーズな手続き方法
1-2. 年俸制などの方法で雇用している従業員の場合
年俸制など期間に応じた報酬を定めている従業員が退職する場合のルールは、次のとおり民法第627条3項に書かれている規定に準拠します。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索
つまり、年俸制のような報酬制度を定めており、契約期間が半年以上にわたる場合には、会社側は3ヶ月前に意思表示をしなければなりません。従業員からの退職の意思表示は2週間前で足ります。
1-3. 契約社員など雇用期間が定められた従業員の場合
民法第627条1項は、正社員など雇用の期間が定められていない従業員に適用されるルールです。 パートや契約社員など期間が定められた雇用契約の場合には、雇用契約書や就業規則において退職の定めをおこなう必要があります。
1-4. 会社側から退職の勧告をおこなう場合
退職には、従業員が退職を申し出るケースと企業側が解雇するケースの2種類があります。企業側が解雇するには次のようなルールを守りましょう。
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
引用:e-Gov法令検索 労働基準法
会社側から解雇の申し入れをする場合には、上記の引用文の通り、労働基準法第20条に従って30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。この場合でも、会社は勝手に解雇の予告をしていいわけではなく、解雇を言い渡す正当な理由や相当性が必要となります。
2. 退職届の提出時期に関するルールを就業規則で定めてもいい?


労働力の確保は多くの企業を悩ませる大きな問題です。中には離職率を下げるために「退職する場合には2ヵ月前までに申し出ること」といったオリジナルの規定を作るような会社もあるといいます。この場合、労働基準法で定められた2週間前の退職の意思表示ルールはどうなるのでしょうか。
2-1. 就業規則ではなく労働基準法が優先される
退職に関するルールを就業規則で定めることはできますが、その規定が労働基準法に反する場合は労働基準法が優先されます。
例えば、就業規則に「退職する場合には2ヵ月前までに申し出ること」と規定されていても、法律上は2週間前の通知で足ります。これは労働基準法が従業員の権利を守るために定めた最低基準だからです。
実際の判例でも「1ヵ月前までに退職の申し出をすること」と規定した就業規則を無効とし、2週間前までの申し出によって退職が可能とされた例があります。
会社が就業規則にオリジナルのルールを定めても、基本的には無効とされると考えたほうがよいでしょう。
従業員と会社双方にとって公正な取り決めを維持するため、就業規則に基づくルールの設定には十分な注意が必要です。
3. 退職届を受理してから従業員が退職までのスケジュール


続いて実際に従業員から退職届を受理した場合に、どのような手順で退職まで進めるべきなのか、スケジュールを整理します。
3-1. 従業員から直属の上司へ退職する旨の報告が入る
従業員が退職の意思を固めた場合、まず直属の上司にその意思を伝えることが一般的です。この報告は正式な退職届提出の前に行われることが多く、上司との面談を通じて退職の理由や意思を確認する場となります。
退職届は法的には2週間前に提出すれば足りますが、会社の事情や業務の引き継ぎを考慮して、可能な限り早めに報告することが望ましい旨をあらかじめ周知しておきましょう。また、退職日が具体的に決まっている場合は、その日程を明確に確認することが重要です。
3-2. 後任者への業務引継ぎを開始する
退職の報告が完了した後、次に重要なのは後任者への業務引継ぎです。引き継ぎ期間として少なくとも1か月を見ておくのが望ましいです。引き継ぎが短期間で行われると、後任者に過剰な負担がかかり、業務に支障が出る可能性があります。引き継ぎをスムーズに進めるためには、マニュアルや作業フローを事前に整理し、必要な情報やノウハウを後任者に漏れなく伝える工夫が必要です。これにより、業務の継続性を保ち、会社全体の運営にも支障をきたさないようにすることができます。
3-3. 有給休暇消化の期間に入る
通常、退職日が確定した後、有給休暇が残っている場合はその消化に入ります。例えば、10日の有給休暇が残っている場合、その期間を最終勤務日の前に設定し、最終出勤日は有休消化開始日の前となります。これは従業員にとって、退職前の休息や次のステップへの準備期間を提供する大切な時間です。しかし、有休消化中でも引き継ぎが完了していない場合、急遽対応が必要となることもあります。これを避けるためにも、最終勤務日までに全ての引き継ぎを終えるよう調整することが重要です。
4. 引継ぎをしない退職者への対応とトラブルの対処法


退職時に労働者との関係がこじれていると、退職者による業務の引継ぎが十分におこなわれない可能性があります。
このようなケースの際に、引継ぎをしない労働者に対して退職金を支払いたくないというご意見や退職者に有給が残っていても使わせたくないというご意見もあるかと思います。
では、どのように対応するのが適切なのか、トラブルへと発展しやすい3つのケースをもとに解説します。
4-1. 退職金の減額はかならず就業規則の記載が必要
退職金を支払うかどうかについて議論をする前に前提の話になりますが、退職の際引継ぎをおこなうのは信義則上の義務であると考えられているため、引継ぎをおこなわずに退職することは義務違反です。
しかし退職金の全額不支給は、基本的に認められません。
退職金は退職するまでの勤続に対する報償という側面があり、最後に引継ぎをしないだけで、今までの功績が全て否定されるということは、考えにくいためです。
一方で、一切の引継ぎがされないなど悪質なケースについては、退職金の一部減額が認められる可能性があります。
その場合は根拠が必要になりますので、就業規則などに「退職する労働者は適切に引継ぎをおこなう義務がある」「引継ぎをおこなわなかった場合は、退職金が〇%減額されることがある」というような規定を作っておくことが望ましいでしょう。
関連記事:労働基準法に退職金の規定はある?金額の決め方を詳しく解説
4-2. 有給消化の希望があれば断れない
また、退職時には有給休暇取得を巡るトラブルが発生しやすくなります。特に多いのは、溜まっている有休を一気に取得してから辞めたいという労働者にどう対応すればよいのかという問題です。
退職日が決まっている上で有給取得を希望された場合、基本的に労働者が取りたいと言えば取らせるほかなく、例外的に事業の運営に支障が出る場合に、取得の日時をずらしてもらうことができますが、このような場合だとそれ以後に有休取得をずらしてもらうことはできません。
したがって有休を一気に消化したいという申出を断ることは難しく、引継ぎなどの問題が発生する場合は、退職日をなんとかずらしていただけるよう退職者にお願いするくらいしか対応策がないのが現状です。
4-3. 損害賠償請求はできるが、承認されるのは困難
最後に損害倍層請求の可否についてです。引継ぎがおこなわれなかったことにより仕事の遂行に支障をきたし、会社が経済的な損失を被ってしまったというようなケースが考えられます。
しかし損害賠償は非常に困難です。
損害賠償を請求するには、「引継ぎをしなかったこと」と「損害」との因果関係を事実をもとに立証しなければならず、誰しもが納得する事実と因果関係を立証するための資料の2つを用意する手間まで考えると、現実的には難しいといえます。
5. 退職届と退職願、辞表の違いとは?


企業の従業員が退職を申し出るときには、企業側が退職届の提出を求めるのが一般的です。書類提出という形で退職の意思表示をしてもらうことは、トラブルを避けて円満に退社の手続きをおこなうために大切なステップといえます。
退職届とよく似たものに退職願や辞表があります。退職届や退職願、辞表はたびたび混同されますが、それぞれの書類が果たす役割は違っているので注意しましょう。
退職願とは労働契約の解除を従業員が会社に願い出るための書類で、退職の承諾を得るために提出します。これに対して退職届とは、従業員が退職を一方的に意思表示できるという意味合いをもつ書類です。
また、辞表は社長や取締役といった役員が役職から離れるときや公務員が組織を離れるときに提出する書類です。一般的な企業の従業員が退職するときには辞表が使われることはないので気をつけましょう。
従業員とその上司、または人事担当者などが話し合って退職の合意が取れたときには、退職届の提出を求めるとよいでしょう。
6. 労働基準法による退職届の正しい形式


民法や労働基準法などには、退職届の形式や書き方についてのルールは定められていません。退職の意思表示が正しくおこなわれていれば、退職届はどのような形式であっても構わないのです。とはいえ、あとあとの問題を避けるためにも、一般的なテンプレートやフォーマットに合わせて退職届を記載してもらったほうがよいでしょう。
退職届は手書きするほか、パソコンで作ってもらっても構いません。パソコンで作成し、自身の名前の部分のみ手書きで署名するという方もいます。
一般的な退職届にはまず慣例として「私儀」または「私事」と記載します。この言葉には「わたくしごとですが」という意味があります。
次の行には退職の理由について記載していきます。従業員の自己都合退職の場合には「このたび、一身上の都合により○年○月○日をもって退職いたします」とし、退職の理由を具体的に記載しないのが一般的です。なお、会社都合退職の場合に「一身上の都合により」と記載すると、自己都合退職として扱われることがあるので気をつけたいものです。会社都合退職の場合には、退職の理由について詳しい記載が必要となります。
本文の次の行には従業員の所属部署と氏名、提出日を記載していきます。最後の行には企業の名前と代表者名を記載します。
7. 退職届の提出方法


退職届には宛名として企業の代表者を記載することになります。しかし、提出先は従業員の直属の上司または人事担当者となることがほとんどです。
従業員はまず直属の上司または人事部に退職の意思を伝え、承認を得られたあとに退職届を提出します。
退職届の提出に気まずさを感じる従業員もいるかもしれません。しかし、退職届を相手のデスクの上に置く形で提出すると、ほかの書類に紛れるなどして上司や人事部の担当者の手元に届かない可能性があります。退職届はできるだけ面と向かって提出してもらいましょう。
従業員が怪我や病気などやむを得ない事情で出勤できない場合には、まずは電話やメールなどでやり取りをおこないましょう。退職届は、退職に関する話し合いができた段階で郵送してもらえば問題ありません。
退職届を郵送する際に、退職届の封筒に直接宛先を書くのは避けたいものです。郵送を選んだ場合には、退職届を入れた封筒を一回り大きな封筒に入れ、宛名を書いて送ってもらうのが最適です。
8. 従業員の退職を引き留めたい場合


また従業員から退職届を受け取った際に、イレギュラーケースとして引き留めたい場合はどのように対応すべきなのでしょうか。対応方法を紹介します。
8-1. 待遇の改善を提案する
上司が従業員の退職理由が待遇にあると判断した場合、給与の引き上げや希望する部署への異動などの提案を行うことがあります。これにより、従業員の不満を解消し、退職の意思を翻意させることが目的です。ただし、提案内容が実現可能であることを明確にし、文書で証明しておくことが重要です。不確実な約束は逆効果となる場合もあるため、具体的で信頼性のある改善策を提示することが求められます。
8-2. 高評価を伝える
「高く評価している」と伝え、会社がその従業員を必要としている旨を示すことも有効な引き留め手段です。しかし、評価を伝えるだけでは待遇や働き方に具体的な変化が生じないこともあります。従業員が評価を受けても退職の意思が変わらない場合は、引き留めは困難です。重要なのは、感情に流されず、評価の裏付けとなる具体的な対応を伴わせることです。従業員のキャリア目標や希望に沿った対応を示すことで、引き留め成功の可能性が高まります。
9. 退職届は労働基準法や民法の定めに応じて適切な時期に提出してもらいましょう


民法では退職の申し出に関して14日前までという期間を設定しています。従業員が退職するときには2週間前を目安に退職届を提出してもらえるよう促すとよいでしょう。
退職に関する企業と従業員の行き違いはときに大きなトラブルに発展することもあります。トラブルを防ぐためにも、従業員が退職を申し出たときには誠実に対応することが大切です。
関連記事:労働基準法における退職の定義と手続き方法を分かりやすく解説
労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。
そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法について、本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。
「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08