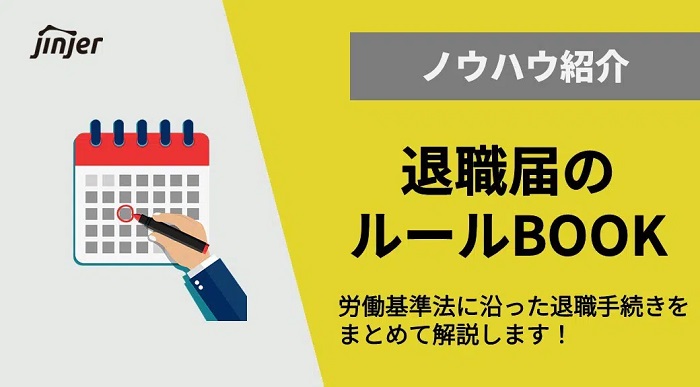労働基準法上は退職2週間前通知で大丈夫?スムーズな手続き方法
更新日: 2024.4.24
公開日: 2021.10.2
OHSUGI

働き方が多様化している昨今では、さまざまな生活環境や属性を持つ人材が在籍している職場もどんどん増えてきています。それぞれがあらゆる事情を抱えながら働いていれば、急な退職の申し出が発生するケースも少なくないでしょう。
ただし、会社としては業務の都合上、すぐに受け入れるのが難しい場合もあるかもしれません。できるだけ早めに願い出てもらうのがベストですが、実際のところ、労働者からの退職通知はどのように認めるべきなのでしょうか。今回は、退職を願い出てもらう方法について詳しく解説していきます。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。
そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法まで網羅的に解説しています。
「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。
目次
労働基準法総まとめBOOK
1. 基本的に労働者からの退職通知はいつでも認められる


まず労働者からの退職については、労働基準法ではなく、民法によって定められています。そもそも労働基準法とは、あくまで労働者の権利を守るものです。そのため労働基準法で制限があるのは、使用者側からの退職通知、つまり「解雇」や「退職勧奨」のみなので、覚えておくと良いでしょう。
なお、労働者からの退職は、「退職の自由」にもとづき、事前の意思表示さえあれば時期に関係なく認められるのが原則です。さらにその意思表示から2週間が経つと、例え使用者が認めていなくても、民法627条1項の規定に基づき労働契約は終了します。退職通知の「2週間前まで」のルールが知られているのは、この民法上の規定があるためです。
参照:民法|e-Gov法令検索
関連記事:労働基準法に定められた「退職の自由」の意味を分かりやすく解説
2. 使用者からの解雇予告は通常30日前まで


ちなみに、先ほども出てきた労働基準法のルールでは、使用者からの解雇予告は厳しく制限されており、少なくとも30日前までには通知すべきとされています。もし30日以内の退職を命じる場合には、不足日数分に応じた賃金を支払わなければなりません。これを「解雇予告手当」といい、平均賃金×不足日数分が支払い金額となります。
産休や労災療養などの休業、育児・介護休業の申し出といった理由では解雇できません。
関連記事:労働基準法第20条に定められた予告解雇とは?適正な手続方法
3. 有期雇用の場合は期間終了まで勤務するのが義務


前述では「民法上は時期に関係なく退職が認められる」としていますが、このルールが適用されるのは、基本的に期間の定めのない労働者に限ります。要するに正社員や無期雇用の場合のみで、パートやアルバイトなどの有期雇用では取り扱いが異なるので注意しておきましょう。
有期雇用では、期間を定めた労働契約が結ばれているため、「期日まで勤務すること」は労働者側の原則的な義務です。そのため仮に契約期間中に退職の申し出があったとしても、時期を引き延ばしたり拒否したりするのは、基本的には認められています。
4. 有期雇用であっても退職を認めるべきケース


しかしながら有期雇用だからといっても、基本的に使用者側は労働者を守る義務を忘れてはいけません。仮に以下のようなケースに当てはまる際には、期間の定めのない労働者と同様に、退職通知の時期に関係なく受け入れることが求められます。
4-1. やむを得ない事情がある
例えば本人が病気になってしまった場合など、どうしても勤務を続けるのが難しい際には、契約期間内であっても退職を受け入れる必要があります。
ただし、法律上では、具体的にどのような場合が「やむを得ない」と判断されるのか、明確には示されていません。それぞれの状況に応じて、やむを得ない事情であるか判断することになるので、どうしても迷う時には専門家に相談するのがおすすめです。労働局や労働基準監督署の相談窓口か、弁護士などから助言を受けると良いでしょう。
4-2. 1年以上の契約期間で初日から1年経過している
有期雇用では、労働契約によって一定期間は労働者を拘束することになるため、労働基準法による例外的な措置がされています。特に労働契約が1年以上になる長期の有期雇用では、労働基準法附則第137条にて「契約の初日から1年経過している」ケースでは、時期に関係なく退職することが可能です。期間の定めのない労働者と同じ扱いとなり、通知から2週間で自動的に労働契約は解約になります。
なお、何かの事業完了に向けた有期の労働契約は、上記には該当しません。例えば、特定のプロジェクト遂行に応じた期間が定められているケースなどです。そのほか、厚生労働大臣が定めた専門業務や、満60歳以上の労働者における有期労働契約についても、この例外は適用されません。
4-3. 有期雇用であっても5年以上勤続している
こちらは民法626条によって、仮に期間の短い労働契約であっても続けて5年以上雇用している場合には、期間の定めのない労働者と同様に「退職の自由」が認められます。例えば契約期間は3ヶ月でも、毎回更新して5年勤続している場合には、いつでも退職することが可能です。
そのため、期間の定めのない労働者と同じく、退職の通知があってから2週間が経ってしまうと、民法上の契約自体は終了してしまいます。
参照:民法|e-Gov法令検索
5. 有期雇用の期間内における退職では損害賠償請求ができる


今までに出てきた例外に当てはまらないケースにおいて、有期雇用で退職する労働者に対しては、場合によっては損害賠償請求ができます。
ただし、労働者の一方的な過失で退職となり、その因果から損害が生じた場合のみです。実際には非常に判断が難しいため、退職による損害賠償請求が認められたケースは少なく、よほどのことがなければ難しいとされています。
6.退職通知のルールを踏まえたスムーズな手続き方法


民法上では退職の申し出から2週間で労働契約が解消となるため、会社側は法律にしたがって退職の申し出を受理しなくてはいけません。しかしながら、業務の引き継ぎや人員補充のことを考えると、日数に余裕を持たせて退職を申し出て欲しいのが本音でしょう。
そこでここでは、法律を踏まえた上での、退職通知の手続きをスムーズにする方法についてご紹介します。
6-1. 就業規則で「2週間以上前」からの退職通知を促すことは可能
民法上では、あくまで退職通知から2週間で契約が切れるというだけで、双方の合意があれば、もちろん「1週間後」などに短縮することは可能です。また、就業規則にて「1ヶ月前」というように定めることもでき、会社のルールとして早めの退職通知を促すのも認められています。
そのため、退職の通知については、あらかじめ規則を決めて周知しておくとスムーズな手続きができるでしょう。
しかし、就業規則にあるからといって、必ずその規定が優先されるとは限りません。就業規則は、会社のルールです。就業規則で完全に拘束できるわけではなく、また状況に応じて、優先すべきなのが民法なのか就業規則なのかも異なります。
ただ、基本的には民法が有効だと考えておくのが無難です。もしどうしてもやむを得ない事情がある場合には、即時の退職を認めることが求められるでしょう。
6-2. 日頃から労働者との良好な関係を築く
労働者が突然退職を申し出てくる理由には、会社に対して不満を抱えているケースが少なくありません。予期せぬ退職の申し出を未然に防ぐという意味でも、普段から労働者と良好な関係を築いておくことが大切です。
上司が部下とのコミュニケーションを積極的に図ることに加え、長時間労働の是正や福利厚生の拡大、人事評価の見直しなど労働環境や制度の改善を図ることも有効です。
労働者からの突然の退職通知を減らすだけでなく、離職防止にも効果が期待できるでしょう。
7. 退職通知の方法による拘束は原則不可


労働者からの退職の通知は、使用者に意思さえ伝わるものではあれば、法律的な制限は特にありません。民法上では口頭でも問題はなく、例えば「規定の書式による通知でなければ認めない」というように、退職を引き留める行為も基本的にはできないと考えておきましょう。
なお、退職通知の方法についても、会社のルールとして就業規則に定めることは可能です。トラブルを防ぐためにも、きちんと何か形に残る方法で、規則を作っておくのがベストです。
8. 労働基準法や民法のルールに従って適切に退職願を受理しよう


労働者からの退職の通知時期は、特に何の決まりもなく、互いの要望もなければ「2週間前」が原則です。
ただし、必ず2週間前までというわけではなく、双方の合意があれば、即日の通知でも退職はできます。その反対にできるだけ事前の通知を必要としている場合には、就業規則に定めることが可能です。
法律による制限はないため、滞りなく退職の手続きを進めるには、使用者と労働者の認識を合わせることが何よりも重要でしょう。
関連記事:労働基準法による退職届は何日前までに必要?法的ルールを解説
労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。
そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法まで網羅的に解説しています。
「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08