フィードバック面談とは?流れや実施上の注意点を解説
更新日: 2025.2.14 公開日: 2023.5.26 jinjer Blog 編集部

人事評価の結果を上司から部下に伝え、そのうえで課題の解決方法や今後のキャリアプランを考える場をフィードバック面談といいます。人事評価の結果を一方的に書面などで伝えるのではなく、面談の機会を設けることで評価に対する納得感や、モチベーションの向上などの効果が期待できます。
本記事では、フィードバック面談で「何を話せばいいのか」お悩みの方のために、面談の進め方やポイント、注意点などを解説します。
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. フィードバック面談とは?

フィードバック面談とは上司が部下本人に対し、人事評価の結果を伝え返し、話し合いの機会を設けることです。本人に伝える結果は、どのような行動が評価できるかだけでなく、具体的な課題も共有し今後の行動計画(アクションプラン)の作成にも活用します。
人事評価の結果は書面だけで済ますことも可能です。しかし、フィードバック面談の機会を設けることで、コミュニケーションの活性化や、評価の納得感を高めることにつながります。
また、会社としては、従業員一人ひとりに対し、どのような働きを期待しているか伝えられる場でもあります。部下は自身の強みや弱みを知る成長の機会となり、上司のマネジメントスキル向上にも役立ちます。
なお、フィードバック面談は、就活生のエンゲージメント向上にも寄与することから、人事考課に加えて採用活動に取り入れる企業も増えています。
2. フィードバック面談の目的

フィードバック面談は、基本的に評価者もしくは上司が一人ひとりの従業員に対しておこないます。面談では、評価の内容説明や課題点、今後の仕事の進め方などを話し合うので、面談のための準備や時間調整などの業務負担が増えます。
業種や職務によっては、面談のために時間を割くのはもったいない、と思うかもしれません。
しかし、フィードバック面談は主に3つの目的のためにおこなうので、必要性をしっかり理解しておきましょう。
2-1. 人事評価への納得感を高めるため
人事評価結果を紙やメールで交付した場合、評価に至った理由を聞けない、結果に対し反論ができないなどの問題が生まれるため、従業員の不満につながります。不満を持ってしまうと、仕事への意欲の低下や評価を意識することを止めるなどの悪循環が生まれるかもしれません。
フィードバック面談を実施すれば、従業員はなぜ今回の結果に至ったのか、どのような点を改善すればよいのか、直接上司へ確認できます。人事評価結果自体は不本意であっても、理由を確認できたり、ポジティブな励ましを受けたりすれば、納得感を高めることが可能です。
人は、納得してこそ素直に指示に従ったり、目標を目指したりできるので、フィードバック面談はとても重要な業務になります。
2-2. コミュニケーションの活性化
日常業務では1日の業務やスケジュールの話しかしないことが多いため、上司と部下のコミュニケーションはどうしても希薄になりがちです。
しかし、フィードバック面談を導入すれば、上司と部下が一対一でコミュニケーションを取る機会を増やすことができます。部下は、日常業務ではできない相談や悩み事を話すことができ、上司も状況を把握した上でのアドバイスを伝えられます。
密度の高いコミュニケーションをおこなえるため、今後のキャリアプランなど、短時間では難しい話しもできます。本音で発言できる環境を整えることは、心理的安全性の構築にも役立つでしょう。
2-3. モチベーションの向上
フィードバック面談では、上司から自身の働きに対して直接返答を得られるため、「自分の仕事が評価されている」という意識が生まれやすくなります。結果が不本意な従業員に対しても、励ましや次期への期待を伝えることで、気持ちを前向きにする効果も期待できるでしょう。
また、課題を認識したうえで、次期への行動計画が立てられるため、ステップアップの意識にもつながります。
業績アップや企業風土の改革などには、従業員のモチベーションが大きく関わっています。フィードバック面談は、会社にとって重要な「従業員のモチベーションアップ」を図るための大事な役割も担っているのです。
3. フィードバック面談の効果
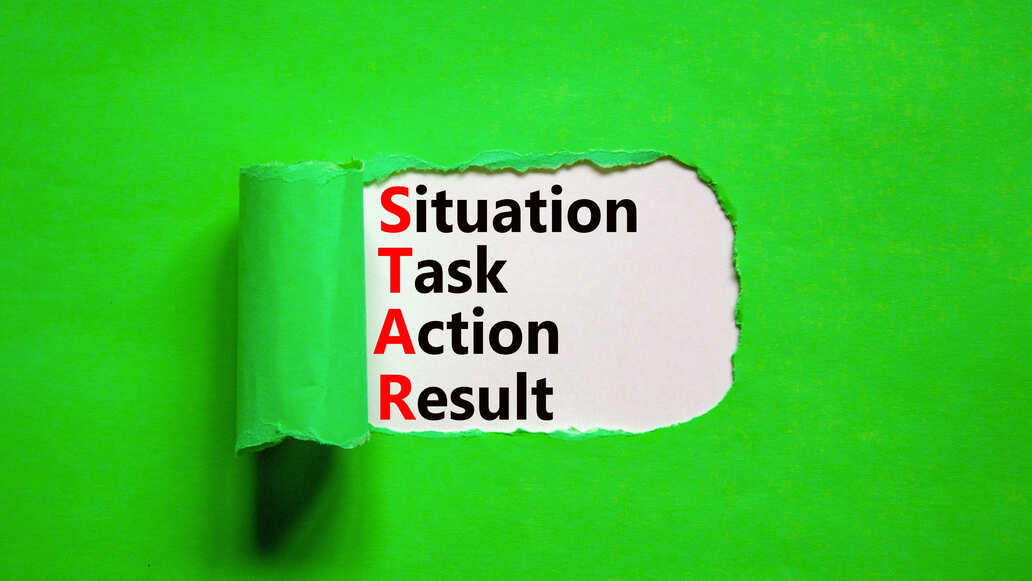
フィードバック面談は、人事評価への納得感やコミュニケーションの活性化、モチベーションの向上という目的を達成するだけでも、充分な効果が得られます。しかし、面談目的以外にも効果があるからこそ、導入する企業が増えているのです。
ここでは、フィードバック面談を実施することにより期待される3つの効果を紹介します。
3-1. 生産性を高められる
会社の成長や生産性を高めるには、従業員が発揮するパフォーマンスが大きく関わってきます。当然ですが、パフォーマンスが低ければ、業務効率も低下するので生産性はまったく上がりません。
フィードバック面談によって、仕事の効率化や課題解決などのアドバイスを個人レベルでおこなえば、必然的に従業員一人ひとりのパフォーマンスが向上します。従業員全体のパフォーマンスが向上するということは、会社全体の業務効率を高めることにつながるので、生産性を高める効果が期待できるのです。
3-2. 部下の課題を把握できる
人事評価の結果を話し合うことで、部下の抱える課題や問題点の発見にもつながります。
日常業務の中では、1対1で話し合う機会がないため、部下がどんな課題や問題を抱えているかを把握するのは難しいでしょう。この点がわからないまま、仕事のアドバイスをしても目標達成にはつながりません。
しかし、フィードバック面談で課題や問題点を把握できれば、適切なアドバイスができます。例えば、目標を達成できない部下の場合、自身では問題点に気が付かなくても、上司の視点からは解決策が見つかるかもしれません。
また、アドバイスを元に部下自身で解決方法を考えれば、能力やスキルの向上も期待できます。
3-3. 上司の成長につながる
フィードバック面談の実施は、管理職のマネジメントスキルやコミュニケーションスキルの向上にも役立ちます。
日々の業務では断片的な判断でしか指導ができず、上司も部下も忙しい状況では、上手くコミュニケーションを取るのも難しいのが実情です。いくらセミナーを受講しても、管理職のスキルは向上しません。そのため、マネジメントやコミュニケーションが苦手という管理職も少なくないようです。
しかし、面談を実施するために、日程調整や事前準備、人事評価結果の伝え方の工夫など、管理職は必然的にこれらに取り組まなくてはいけません。この数々の取り組みが、管理職としての成長を後押ししてくれるのです。
また、一人ひとりの部下と向き合う必要もあるため、傾聴能力やコーチング、ティーチングなどの能力開発にも役立ちます。
4. フィードバック面談の進め方

フィードバック面談を実施する前に、上司は評価結果の根拠や今後の課題など、部下に伝える内容を整理し準備しましょう。また、一方的に結果を伝えるのではなく、部下に話しをさせる時間を作ることも大切です。
ここでは、面談の具体的な進め方を解説していきます。
4-1. 事前準備
フィードバック面談を実施する前に、部下と日程調整をおこないましょう。上司が日程を決めるという方法もありますが、部下の業務に支障がでる可能性もあるので、できる限り調整して決めるのがベストです。
ただし、面談の人数が多い場合は、個々で日程調整をすることが負担になることもあるかもしれません。このような場合は、上司が面談できる日時を指定して、従業員がスケジュールを当てはめていくというやり方が良いでしょう。
部下には人事評価に対する自己評価と質問したい内容がないか、事前にまとめるように伝えるとスムーズです。
上司は、評価結果の根拠と今後の課題など、面談時に話す内容をある程度整理しておきましょう。
4-1-1. 面談シートを作成する
フィードバック面談の前に面談シートを作成して、話す内容や流れをまとめておくと、当日スムーズに面談を進めることができます。面談シートに記載する項目の一例は、次のとおりです。
- アイスブレイク
- 面談の趣旨
- 自己評価の際に尋ねたいこと
- 評価の結果と理由
- 時期の目標と行動計画
- 面談の締めくくり
それぞれの項目ごとに、話す内容を決めておくことで、限られた面談の時間を有意義なものにすることができます。また、フィードバック面談の前にシミュレーションをおこなう際にも、面談シートがあると便利です。
4-2. アイスブレイク
アイスブレイクとは、本題に入る前におこなわれる緊張をほぐすための雑談です。
面談は、単に結果を伝えたり仕事の話をしたりするだけの時間ではありません。部下の今の現状や心理的な問題などを聞き出すことも目的の1つです。部下が緊張していると、思うようにコミュニケーションできない恐れもあるので、上司から雑談をしてあげることが望ましいです。
天気や体調、趣味の話しなど、とりとめがなくとも楽しめる話しを取り入れ、場をなごませましょう。
4-3. 自己評価の確認
フィードバック面談では、まず、部下自身の自己評価とその根拠を確認します。ここで大切な点は、部下の話しを途中で遮ったり、否定したりしないことです。上司が途中で口を挟んでしまうと、部下は本音を言えなくなってしまいます。
本音で話してもらわなければ、的確なアドバイスができなくなり、問題も解決できないかもしれません。
自己評価を聞くときは、相槌をうつなどして話しやすい雰囲気を作り、本音を引き出しましょう。人事評価結果との乖離を確認するためにも、部下が話している内容はメモを取ることも大切です。
4-4. 人事評価結果を伝える
部下の自己評価が終わったら、人事評価結果とその根拠を伝えます。また、自己評価よりも人事評価の結果が低い部下の場合、なぜ現在の評価となっているか丁寧に説明することで納得感を得やすくなります。
部下から不満や反論などがあるときは、最初から否定するのではなく、一度主張を聞いてから、もう一度評価の理由を説明しましょう。
4-5. フォローアップ
人事評価結果を説明した後は、今後に向けたフォローアップ(話し合い)をおこないます。課題の解決やキャリアプランの実現に向けたスキルの取得など、内容は部下により異なります。
このとき大切なのは、やれそうなことを提案するということです。解決策でもスキルの取得でも、従業員にとってハードルが高すぎると、次も同じ結果になってしまうかもしれません。いきなり高みを目指すのではなく、少しずつでも課題をクリアできるように、従業員のスキルに寄り添った提案をしましょう。
なお、フォローアップでは上司が一方的に今後の内容を指示するのではなく、部下に考えさせることで能力の向上が期待できます。
5. フィードバック面談を実施するときのポイント

フィードバック面談は上司と部下の信頼関係の構築や、人材育成などの目的があります。そのため、部下のモチベーションを下げるような結果とならないよう注意しましょう。
ここでは、面談を実施する時の注意点を紹介します。
5-1. 部下を尊重する姿勢を持つ
部下の人格を否定する、発言を否定する、怒鳴って改善を促すなど、信頼関係を壊すような行動を取るのは絶対にやめましょう。結果が低いと、いらいらしたり否定したりしたくなってしまうかもしれません。しかし、人は叱責によってやる気を出したりモチベーションがアップしたりすることはなく、逆に自己否定感を強めてしまう恐れがあります。
面談の際は、上司が部下を尊重する姿勢を持つことで、高圧的な態度や意見の否定などは起きづらくなるでしょう。
フィードバック面談は、従業員のモチベーションアップや業績アップのためにおこなうものなので、評価を客観的に伝えて改善を促すことが大切です。
5-2. 行動の改善を自然に促す
部下の弱点や欠点の改善策を話し合ったら、部下自身が行動を変えるように促しましょう。ここで大事なのが、強制をするのではなく、「自然に」ということです。フィードバックの内容にもよりますが、人は強制をすると反発をすることが多いため、せっかくの面談が無駄になってしまいます。
自分から「改善していこう」という気持ちを引き出すのは、上司のマネジメントスキルでもあるので、自然にやる気が出るよう促しましょう。
また、性格に対する指摘は適切ではありません。例えば、遅刻の多い部下の場合、真面目な性格になるように促すのではなく、朝5分早く起きるなど行動を促すのが効果的です。
5-3. ポジティブなフィードバックを盛り込む
フィードバック面談では、評価する点と改善点の双方を伝える必要があります。しかし、欠点の指摘が多いとやる気を失う原因にもなりかねません。
そのため、ポジティブなフィードバックを盛り込むことを意識しましょう。例えば、営業成績が上がらない従業員の場合、ダメな原因を羅列するのではなく、ダメな部分を指摘しつつ、「自分ならこうしてみる」「こういった工夫をすればいいのでは」などポジティブなイメージを盛り込みながら話を進めるようにしてください。
欠点を指摘されても、面談がポジティブな内容であればやる気も高まるので、上手に盛り上げて次期に向けて成長を促すようにしましょう。
6. 効果的なフィードバックの手法

フィードバックの質を高める手法はいくつかありますが、ここでは代表的な3つの手法をご紹介します。それぞれ特徴が異なるため、状況に応じて組み合わせて活用するのがおすすめです。
6-1. サンドイッチ手法
サンドイッチ手法は、「褒める」→「改善点を指摘する」→「褒める」といったように、ネガティブな内容をポジティブな内容の間に挟んで伝える手法です。
マイナス評価だけを立て続けに伝えてしまうと、部下のやる気を削いでしまう可能性がありますが、この手法を使うことで、部下のモチベーション低下を押えられるのがメリットです。
ただし、この手法を使い過ぎると、プラスの評価しか部下の印象に残らなくなる恐れがあるため、他の手法も織り交ぜながら、適度に活用するようにしましょう。
6-2. SBI手法
SBI手法は、状況(Situation)、行動(Behavior)、影響(Impact)の順に話を整理しながら面談を進めていくフレームワークです。
「●月●日の顧客とのミーティングで(状況)」「○○の提案をしたことにより(行動)」「顧客に良い印象を与えることができた(影響)」というように、SBI手法では主観を入れずより具体的に事実を伝えていきます。
状況が把握できた状態で、具体的な行動の話に移るため、部下に自分自身の良いところや課題を客観的に振り返らせることができるのがポイントです。
なお、SBI手法は、ポジティブな評価またはネガティブな評価、どちらを伝える際にも使うことができます。
6-3. ペンドルトン手法
ペンドルトン手法は、心理学者であるペンドルトン博士によって提唱されたフィードバックの手法です。
フィードバックを通じて受け手の内省を促すことを目的としているため、ペンドルトン手法では部下の話を聞いてから、それに対し上司が応じるのが流れです。そのため、部下にまず自身の課題や改善点を考えてもらい、上司がそれを受けて一緒に話し合いながら解決策を模索します。
部下が自らの改善点を考えられるようになるため、今後の成長につながることが期待できます。
7. フィードバック面談は部下も上司も成長できる機会

フィードバック面談とは、人事評価の結果を上司から部下に伝える場です。しかし、ただ結果を伝えるだけではフィードバック面談とはいえません。
話し合いを通じて、仕事ぶりの評価だけでなく従業員が抱える問題をヒアリングしたり、課題の改善策を一緒に考えたりすることがフィードバック面談をおこなう意義になります。目標を丸投げして結果だけを伝えるより、管理者と部下でお互いの意見や考えを伝え合うことは、信頼関係の構築やモチベーションの向上などの効果が期待できます。
また、フィードバック面談は部下だけでなく、上司の能力向上も期待できるので、人材育成に役立つ手法です。
ただし、部下一人ひとりとの日程調整や結果の管理が難しい場合は、人事評価システムなどを導入して効率よく進めましょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-

派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-

賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-

賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18































