労働契約法3条に定められた「労働契約の原則」と注意点や罰則を詳しく解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2021.10.2
OHSUGI

労働条件は労働契約の基本原則に基づいて締結されるものです。 労働契約法3条で制定されている「労働契約の原則」は労働契約をおこなう際に留意すべき重要事項が記載されていたり、使用者と労働者の紛争を防ぐことを目的としています。 本記事では、労働契約法3条の労働契約の原則5つについてと、注意点や禁止事項について詳しく解説しています。
▼そもそも労働契約法とは?という方はこちらの記事をご覧ください。
労働契約法とは?その趣旨や押さえておくべき3つのポイント
目次
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
1. 労働契約法3条による「労働契約の原則」とは?

労働契約法は労働に関する条件や就業形態は時代とともに変化し、使用者と労働者の紛争を未然に防ぐことを目的として制定されました。労働契約法によって労働者を保護しつつ、使用者と労働者の良好な関係を築くことが期待されています。
なかでも労働契約法3条では労働契約における基本的な理念や以下のような5つの原則が記されています。
- 労使対等の原則
- 均衡考慮の原則
- 仕事と生活の調和への配慮の原則
- 信義誠実の原則
- 権利濫用の禁止の原則
1-1. 労使対等の原則
労働契約をおこなう際など個別での合意は問題ありませんが現実問題、事業主と労働者の間には力関係が存在するものです。
一般的に労働者は弱者であるため、労働者を守ることを目的として労働条件決定の場面では、お互いが対等の立場で合意すべきという「労使対等の原則」が規定されています。
この原則は労働契約の基本原則であり、労働基準法2条第1項と同じ意味合いがあります。
1-2. 均衡考慮の原則
労働契約(雇用契約)を締結及び変更するにあたっては、実際の就業状況に基づいて均等を考慮すべきものとする原則です。
具体的に「均衡を考慮する」とはどのようなことなのかというと、正社員、契約社員、パートタイマーなどの就業形態が違うからといって、処遇などの差別をしてはいけないという意味です。
しかし、就業形態が違うのに賃金が全く同じというわけにはいかないため、就業の実態に伴い、責任の重さやなどを踏まえ、均衡(バランス)を考えましょうという原則なのです。
1-3. 仕事と生活の調和への配慮の原則
現代社会では共働き家庭の増加や、子育て、介護など仕事と生活の両立が難しい現実があります。
このような背景から、厚生労働省からワークライフバランスが提唱されています。
ワークライフバランスとは、仕事と生活のバランスがとれて多様な働き方や生き方ができることを意味します。
労働契約法3条における第3項でも、仕事と生活の調和への配慮の原則が定められることになりました。
育児や介護などの状況に気遣って、仕事と生活の両立がしやすくなるよう労働契約の締結や変更をおこなうべきとする原則です。
1-4. 信義誠実の原則
民法第1条第2項では、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実におこなわなければならない」と規定されていますが、これは労働契約においても適用されるものであることを労働契約法3条でも表しています。
使用者及び労働者はどちらも契約を遵守しなければなりません。
労働契約が守られることは、労働紛争を防ぐことにもつながります。
信義誠実の原則は、労働基準法第2条第2項が定める内容と同じです。
1-5. 権利濫用の禁止の原則
権利濫用禁止の原則とは、事業主も従業員も労働契約に関する権利を濫用してはいけないということを規定したものです。
民法第1条の基本原則でも同様の内容が定められており、労働契約においても適用されることを確認しています。
権利を濫用したかどうかの判断は難しく、判断基準は明確に定められているわけではありません。
実際のところは事案に応じて主観的要件と客観的要件に分けて判断されます。
2. 労働契約法3条による「労働契約の原則」の注意点や禁止事項

労働契約法3条第2項の「均衡考慮の原則」では、就業形態の違いによって、給与などの待遇差だけでなく、福利厚生や教育訓練などにおいても不条理な差を付けることは禁止されています。
このような就業形態による条件の違いを禁じる旨は、2020年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」においても定められています。
一般的に正社員と非正規社員とでは給与や賞与に違いがありますが、基本的には同じ額の支給が必要です。
しかし、実際には業務の内容や異動の可能性、能力、経験、成果などさまざまな違いがあるため、待遇差に合理性があるかどうかが判断されることになります。
労使対等の原則では、労使が対等の立場で合意をすべきことが定められていて、これは契約の一般原則でもあります。そのため事業主が不利益変更を一方的におこなうことは許されません。
不利益変更とは、賃金や休暇などの労働条件が労働者にとって不利に変更されることを指します。
しかし現実問題、給料や退職金の減額、昇給停止、手当ての廃止など、不利益に当たる労働条件の変更は起こりうるものです。
このような不利益変更を企業がやむを得ずおこなう場合、従業員との合意がなければなりませんので注意が必要です。
不利益変更の内容が合理的かつ、変更後の就業規則を社員に周知した場合は、合意がなくても不利益変更をおこなうことが可能です。
2-1. 労働契約法は解雇についても規程している
労働契約の原則で禁止されていることや注意すべきことについて挙げましたが、これ以外にも労働契約法で禁止されている事項があります。
例えば「解雇」については、基本的に合理的な理由や、やむを得ない理由を会社が証明できない限り認められていません。
解雇とは労働者の合意を得ずに、事業主側の主張のみで労働契約を解消することを指します。
解雇においては労働契約法の第16条で規定されています。
不当な解雇などによる労働紛争やトラブルを防ぐために設けられた規約です。
労働契約の原則の第5項における「権利濫用の禁止の原則」とみなされた場合の解雇は無効となります。
解雇が認められる合理的な理由とはどのようなものなのか挙げると、「就業規則違反」「遅刻や欠勤を繰り返す」「能力不足」「人員削減の必要性」などです。
また、解雇をおこなう場合は30日前に予告をするか、もしくは30日分以上の賃金を支払わなければならない決まりとなっています。
これらの条件を満たしていれば、会社都合の解雇でも労働基準法違反に当てはまりません。しかし前提として、解雇に関する規定が就業規則に書かれている必要があります。
関連記事:パートタイム・有期雇用労働法の内容を分かりやすく解説
関連記事:労働基準法による解雇の方法や種類、円満解雇するための秘訣を解説
3. 労働契約法3条に違反した場合の罰則
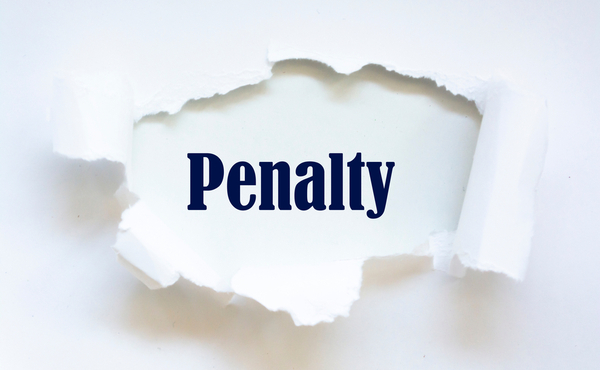
実は労働契約法は違反をしても基本的に罰則がありません。なぜなら労働契約法は労働に関する民事ルールを定めた私法だからです。
「労働基準法」は罰則について定められていますが、労働契約法においては法律的な効力がありません。
しかし、もし個別労働紛争が勃発し、それが民事訴訟まで発展してしまった場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。
また、雇用契約書は作成義務もないため、作成しない場合もあると思いますが、雇用契約書は労働条件の労使間トラブルの対策ともなりうるので、作成するのがおすすめです。 当サイトでは上述したような雇用契約の結び方や禁止事項、「毎年結ぶ必要があるの?」などのよくある疑問をまとめた「雇用契約マニュアル」のような資料を無料で配布しております。雇用契約に関して不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
4. 労働契約法3条は労働契約の基本原則となるもの

労働契約法3条に定められている「労働契約の原則」は全5項目あり、全てが労使契約を取り交わすうえで基本となるものです。
近年、人々の働き方は多様化し就業意識も大きく変化している中、労使関係において問題を抱えているケースも多いでしょう。
事業主と従業員はお互いに対等な立場で合意をし、契約を締結する必要があります。
労働契約の原則をしっかり理解しておくことで従業員とのトラブル防止にもつながります。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08



























