労働契約法7条を解説!労働契約の内容・就業規則との関係とは
更新日: 2024.3.22
公開日: 2021.10.3
OHSUGI
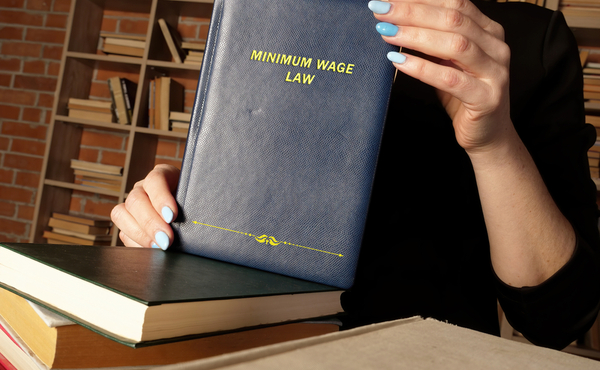
従業員を雇用して労働契約を結ぶ際に、労働条件として就業規則を代用することがあります。しかし、就業規則を労働条件とする場合、労働契約法7条に則って労働契約が締結されていないと、後々に無効とされる恐れがあります。こうしたリスクを回避するためにも、労働契約法7条について正しい知識を身につける必要があります。
本記事では、労働契約法7条の内容や就業規則との関係について詳しく解説します。
▼そもそも労働契約法とは?という方はこちらの記事をご覧ください。
労働契約法とは?その趣旨や押さえておくべき3つのポイント
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
1. 労働契約法7条による労働契約の内容

会社が従業員を雇う場合には、必ず労働契約を結ばなくてはいけません。労働契約法7条では、労働契約時の労働条件の内容について規定されています。
以下、詳しく見ていきましょう。
1-1. 労働契約法7条とは労働契約の成立に関する法律
労働契約法7条は、労働者と雇用契約を締結する際に、労働契約の内容となる労働条件を個別に決めていない場合には、就業規則で定めた労働条件をもって、労働契約の内容となる労働条件を補充してもよいと認めています。
日本においては、個別に労働契約を結ぶ際に、詳細な労働条件は定めずに就業規則をもって労働条件とすることが、昔から一般的に行われています。そのため、就業規則で定めた労働条件と、個別に締結する労働契約の内容となる労働条件との法的関係を明らかにしておく必要があるため、労働契約法7条によってこのような規定がされています。
1-2. 就業規則とは雇用に関するルールを定めたもの
就業規則には、労働条件や服務規程といった社内の規律に関する規定が定められています。
就業規則を作成するにあたっては、以下2つを必ず記載しなければなりません。
- 絶対的必要記載事項
- 相対的必要記載事項
絶対的必要記載事項には、賃金・就業時間・退職などに関する事項が含まれます。
相対的必要記載事項は、企業が制度を設ける際に記載しなければならないものです。具体的には、退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償といった事項が含まれます。
就業規則を作成する際は、労働基準法の内容を下回ってはいけないとされています。万が一、就業規則の内容が労働基準法より下回ってしまった場合、該当箇所に関しては無効となるため、注意が必要です。
なお、就業規則は全ての企業に作成が義務付けられているわけではなく、常時10人以上いる事業所が就業規則を作成しなければいけない決まりになっています。この方法で対応する場合、法律で定められた雇用契約時に通知が必要な項目が自社の就業規則にもれなく記載されているかを確認しておきましょう。
当サイトでは、雇用契約の結び方や「就業規則と労働条件通知書の内容はどちらが優先される」などよくある疑問をまとめた資料を無料で配布しております。労働条件の提示について不安な点があるご担当者は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:就業規則の届出方法と具体的な手順を分かりやすく解説
1-3. 労働契約法7条における合理性とは
労働契約法7条においては、労働条件の変更にあたって合理性が求められます。労働契約法7条における合理性とは、該当する労働内容に条件が認められるかどうかです。
対して、すでに締結している契約を変更するにあたっては労働契約法10条に則る必要があります。労働契約法10条であっても合理性が必要です。労働契約法10条における合理性は変更前の労働条件と比較して、急激、大幅な変化でないかを確認します。労働条件としては合理性があっても、以前の条件と比較して合理性に欠けると変更が認められません。例えば、変更前の労働条件から急激もしくは大幅に変化している場合、合理性に欠けると判断されて、変更が認められない可能性があります。
2. 労働契約法7条による就業規則との関係

労働契約法7条による労働契約と就業規則との関係は、労働契約を締結する際の状況によって変わってきます。
ここでは、状況ごとに労働契約法7条によってどのように労働契約の内容である労働条件が決まっていくのか解説します。
2-1. 労働契約時に詳細に労働条件を決めていない場合
労働条件を詳細に決めずに労働契約を結んだ場合は、労働契約の内容となる労働条件に就業規則を適用させることができます。ただし、就業規則を適用させるにあたっては、2つの条件を満たしていなければなりません。
1つ目は、就業規則の中で定められている労働条件が「合理的な内容」であることです。労働条件が合理的であるかどうかは、個々の労働条件と照らし合わせて判断されるとされています。
2つ目は、就業規則を従業員に周知させていたという事実があることです。ここでいう「周知」とは、従業員が就業規則をいつでも閲覧できるような状態にしておくことです。たとえば、就業規則を事務所内に掲示したり、社内のイントラネットで閲覧できるようにすることです。
この2つの条件を満たしていない場合には、就業規則を労働契約の労働条件とすることはできません。
関連記事:就業規則の閲覧を求められたらどうする?正しい対応方法を紹介
2-2. 労働契約時に個別合意により労働条件を決めていた場合
雇用主と従業員双方の合意に基づいて、労働契約時に個別に労働条件を決めていた場合には、その労働条件の内容が就業規則を下回っていなければ、個別に決めた労働条件の方が優先されることになっています。
しかし、個別に決めた労働条件の内容が、就業規則の内容を下回っているような場合には、就業規則の方が優先されます(労働契約法12条)。たとえば、就業規則には賞与の支給が明記されているにも関わらず、労働契約の労働条件では賞与は支給しないとなっているような場合です。このケースでは就業規則が優先されますので、雇用主は賞与を支給しなくてはなりません。
関連記事:労働契約法12条による就業規則違反の労働契約を分かりやすく解説
3. 労働契約法7条に関する注意点

労働契約を締結する際に、労働条件として就業規則を適用させるには、いくつか注意すべきことがあります。
ここでは、労働契約法7条に関する注意点を紹介します。
3-1. 労働契約の成立時にのみ適用ができる
労働契約法7条で、「労働契約の成立する場面において」と明言されている通り、労働契約時点で就業規則があった場合に、就業規則を労働契約時の労働条件として適用することができるとされています。
たとえば、個別に労働条件を提示して労働契約を締結した後に、就業規則を作ったような場合には、過去に遡って就業規則を労働条件として適用させることはできないということになります。
3-2. 就業規則の周知の範囲
先述でも説明しましたが、就業規則を適用できる条件のひとつに「就業規則を従業員へ周知させること」があります。周知とは、労働基準法では以下3つの方法が示されています。
- 事業所の見やすい場所へ常に掲示し、または備え付けること
- 書面を労働者へ配布すること
- デジタルデータ等で記録し、従業員がこのデータをいつでも閲覧できる機器を設置すること
労働契約法7条では、上記3つの方法に限らず、従業員が就業規則をいつでも確認できる状態であれば、周知と見なすとされています。たとえば、上司の机の引き出しに就業規則が管理されていて、従業員は上司を通じていつでも就業規則を閲覧できる状況であれば、「周知していた」と認められるでしょう。
4. 就業規則は労働契約法7条と照らし合わせて決めなければならない

労働契約法7条では、労働契約を締結するにあたって、前もって労働条件を詳細に決めていない場合は、就業規則で規定している労働条件の適用が認められています。
ただし、適用にあたっては、就業規則が「合理的な内容であること」と「従業員に周知されていること」が条件としてあります。この条件を満たしていない場合は、就業規則は労働契約時の労働条件として認められません。
また、労働契約時に雇用主と労働者双方が合意し、個別に労働条件を決めていた場合であっても、就業規則を下回るような労働条件の締結は無効となり、就業規則が優先されます。労働契約の内容となる労働条件に就業規則を適用する際は、十分な注意が必要です。
このように、就業規則は労働契約法7条と照らし合わせて作成しなければなりません。また、従業員にもしっかり周知しましょう。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08



























