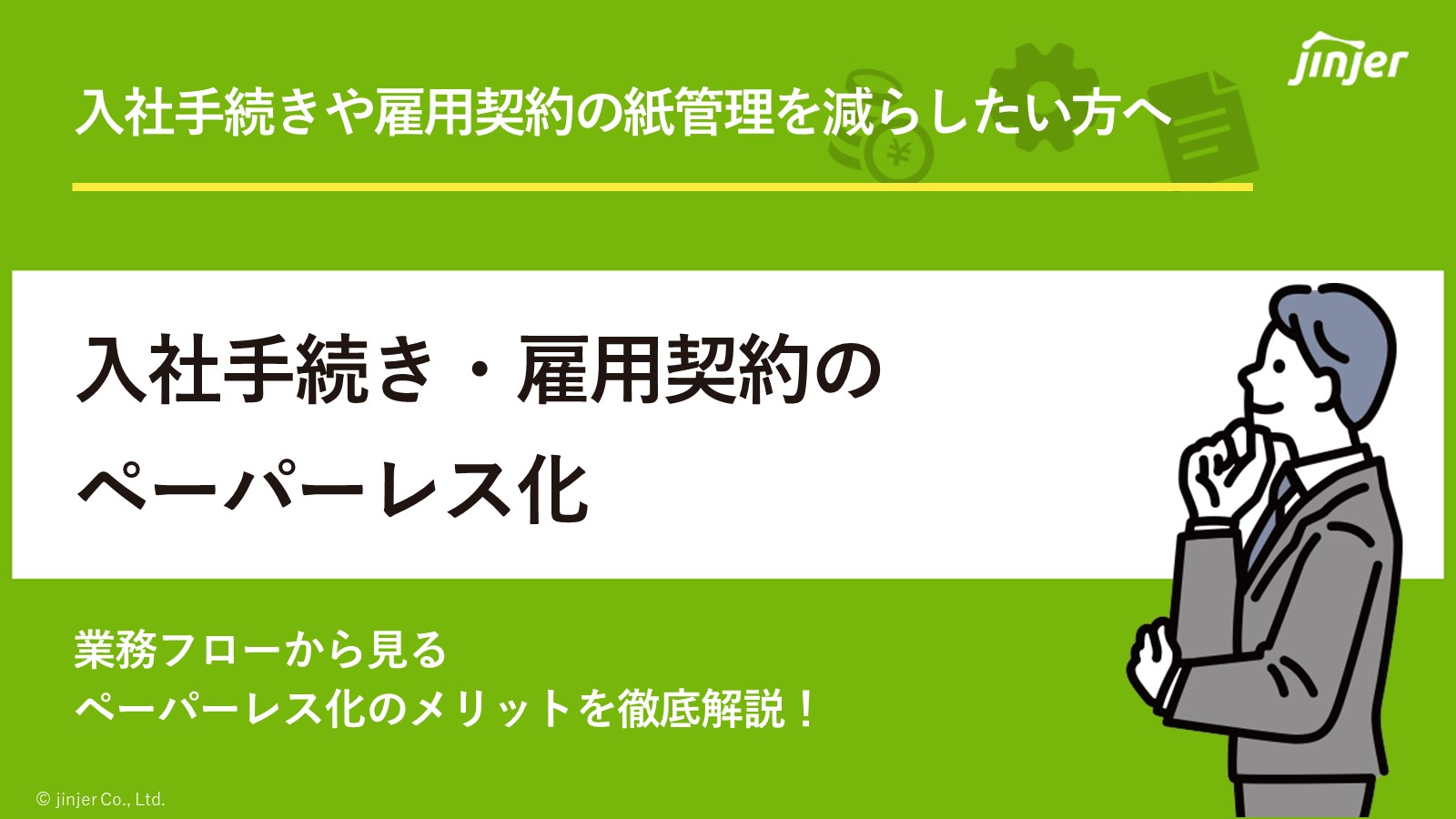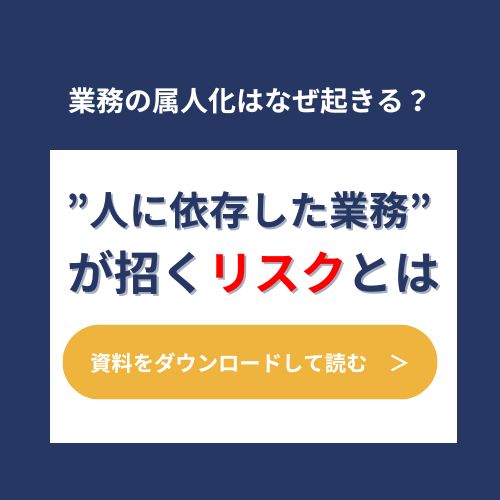就業規則の届け出をわかりやすく解説!労働基準監督署への届出方法と手順

常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則の届出が義務付けられています。
具体的な手順は以下の通りです。
- 就業規則の原案を作成する
- 労働者代表から意見書をもらう
- 「就業規則(変更)届」を添付して管轄の労働基準監督署に持参または郵送する
この記事では、就業規則の届出方法と具体的な手順、注意点を解説します。
▼就業規則について1から理解したい方はこちら
就業規則とは?人事担当者が知っておくべき基礎知識
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
目次
1. 就業規則の届出とは


就業規則の届出とは、事業主が就業規則を作成または変更した際に、労働基準監督署長に提出する手続きを指します。目的は、就業規則の不備を労働基準監督署がチェックし、不適切な内容について指導を行うことです。これにより、従業員の労働条件が適切に整備されることが期待されています。
1-1. 会社には就業規則の届出義務がある
就業規則の届出は、労働基準法89条で常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して義務づけられています。
新たに就業規則を作成した場合や、既存の規則を変更した場合も同様です。この「10人以上かどうか」の判断は事業場ごとに行われるため、事業場が複数ある企業では、各事業場ごとに労働者数を確認する必要があります。なお、従業員が10人未満の事業場においても、就業規則を作成し周知することは可能で、その場合でも労働基準監督署に届出ることが望ましいです。
2. 就業規則の届け出が必要なタイミング


就業規則の届出が必要なタイミングは2種類です。ひとつは就業規則を作成したとき、もうひとつは既存の就業規則を変更したときです。
それぞれどのような状況が該当するのか確認しておきましょう。
2-1. 常時10人以上の労働者を使用する事業場の就業規則を作成したとき
もともと就業規則がなかった事業場で就業規則を作成した場合は、その内容を届け出なければなりません。
よくあるのは常時雇用する労働者が10人未満の小さな事業場が、事業拡大により雇用人数が増えたタイミングです。事業拡大に伴って人員を増やし、常時雇用人数が10人以上になった際に法律に従って就業規則を作成するパターンです。
この場合も当然届け出が必要であるため、作成するだけでなく必ず正しい形で届け出をしましょう。
2-2. 常時10人以上の労働者を使用する事業場の就業規則を変更したとき
就業規則の作成が必要な常時10人以上の労働者を使用する事業場で、就業規則の内容を変更した場合も届け出が必要です。
これは失念してしまうことが多いため、十分に注意しなくてはなりません。
労働基準法の改正に合わせて就業規則を変更した場合も届け出が必要です。どのような理由による変更でも忘れずにおこないましょう。
3. 就業規則の届出に必要な3つの書類


就業規則を管轄の労働基準監督署に届け出る際は、下記3つの書類が必要となります。
- 就業規則
- 意見書
- 就業規則(変更)届
各書類について、詳しく解説します。
3-1. 就業規則
就業規則を作成する際は、必ず記載しなければいけない事項がある点に注意しましょう。
記載する事項は、下記の3つに分類されます。
- 絶対的必要記載事項:労働時間、賃金、退職 など
- 相対的必要記載事項:退職手当、懲戒 など
- 任意的記載事項:企業理念 など
このうち、1に関しては必ず記載が必要です。
2に関しては定めをする場合には記載しなければなりません。
3は任意のため、記載しなくても特に問題はありません。
また、就業規則は本則以外に、賃金規定などの「別規定」がある場合は、それらも合わせて全て届出が必要です。
3-2. 従業員代表者の意見書
労働基準法第90条により、就業規則の届出には意見書の添付が義務付けられています。
意見書とは、労働者に対して就業規則に対する意見を聞くための書類で、労働基準監督署のHPなどからダウンロードすることができます。
通常は、下記のどちらかに意見を記入してもらい、署名・捺印をします。
- 労働者の過半数で組織する労働組合
- 1がない場合は、労働者の過半数を代表する者
なお、管理監督者は労働者代表となることができないため注意しましょう。
関連記事:就業規則の意見書とは?作成に必要な内容と書き方のポイント
記載例
就業規則の意見書の記載例について説明します。
意見書は、労働者代表から会社への正式な文書ですので、まず宛名に会社名と会社の代表者名を記載します。
次に、労働者代表から意見を聴いた日付、実際に意見書を記入した日付、そして労働者代表の名前を明記する必要があります。意見の記載がしやすいように、「意見なし」と「意見あり」にチェックボックスを設けることが一般的です。意見がある場合は、余白に詳細を記載してもらうことで、提出された意見の内容を具体的に把握できます。
たとえば、「意見あり」にチェックを入れた場合、その内容が十分に反映されるように記載を促すことが重要です。
特になければ「異議なし。」「特にありません。」などと書いて問題ありません。また、もし意義が書かれたとしても、就業規則の効力には影響がないため、そのまま届け出ましょう。
これにより、会社と労働者の間で透明かつ公正な就業規則の策定が可能となります。
3-3. 就業規則(変更)届
就業規則の作成や変更の際、鏡として添付する書類ですが、法律上定められた書類ではありません。
決まった様式はないため自作しても問題ありませんが、労働基準監督署のHPよりダウンロードできるため、用いるとスムーズです。
なお、就業規則の「変更」の場合、上記様式の「主な変更事項」欄に変更内容を記載すれば、該当箇所の就業規則を添付するのみで届け出ることができます。
就業規則全文の印刷が不要となるため、経費削減方法としても効果的です。
就業規則の変更の届出は詳しい記事がございますので是非確認してみてください。
関連記事:就業規則の変更届出の方法と気をつけるべき4つの注意点
記載例
この届出書には、以下のポイントを確実に記載しましょう。まず、提出先である労働基準監督署長の名前を明記します。
次に、就業規則を新たに作成した、もしくは変更した旨を明示します。その後、事業場の所在地、事業所の名称、そして代表者の名前を正確に記入します。
また、就業規則変更の場合は、変更内容や変更理由も明確に示すことが重要です。
4. 労働基準監督署への就業規則の届出方法


就業規則の届出を行うには、下記の4つの手順が必要となります。
- 就業規則の作成(または変更)
- 意見書の作成
- 就業規則(変更)届の作成
- 必要書類を管轄の労働基準監督署へ提出する
1~3は、それぞれ注意事項を確認した上で、事前に作成しましょう。
また、各必要書類は、届出用と会社控え用の2部ずつ用意する必要があります。会社控え用は、労働基準監督署で受付印をもらったのち保管します。
4-1. 管轄の労働基準監督署に持ち込む
準備した書類を管轄の労働基準監督署に持ち込むことで手続きが可能です。
窓口で内容や添付書類を確認し、問題がなければそのまま受理されます。初めて就業規則を届け出る際は、その場で間違いを確認し、修正も可能なため、直接持参する方がスムーズでしょう。
4-2. 郵送で手続きをおこなう
もう1つは、郵送で届け出る方法です。
郵送の際は必要書類の他に、返信用封筒を同封しましょう。問題がなければ、後日、受付印が捺された会社控えが届きますが、不足している書類や情報がある場合は差し戻される可能性があります。
4-3. 電子申請で手続きをおこなう
労働基準監督署への就業規則の届出には、電子申請が便利で効率的な方法です。
電子申請は、以前は電子署名・電子証明書の添付が必須でしたが、令和3年4月以降、この要件が不要となり、さらに利用しやすくなりました。この変更により、書類の提出が迅速かつ簡便になりました。
電子申請は、e-Govの申請画面から行うことができます。申請手続きを進める際には、必要な書類をアップロードし、必須情報を入力するだけで完了します。また、提出後には受付印が付いた控えをダウンロードすることができるため、保存が容易で証拠としても有用です。
5. 就業規則の届出での注意点
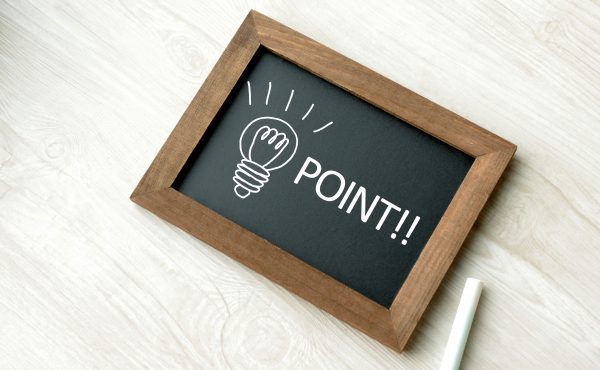
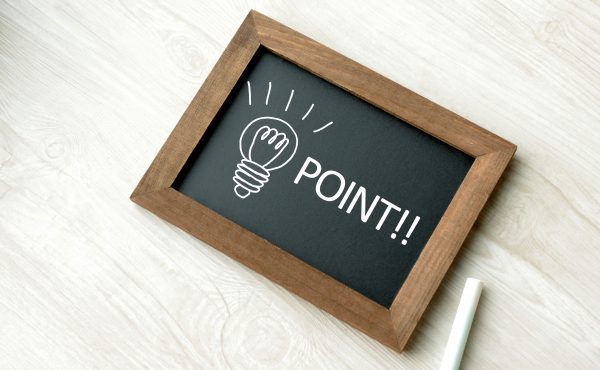
最後に、そもそも就業規則を届け出る必要がある会社の基準や、万が一届け出なかった場合の処罰など、就業規則の届出での注意点を解説します。
5-1.「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は就業規則の届出が必要
労働基準法89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成と届出を義務付けています。
「常時10人以上」とは、会社全体ではなく、各事業所単位での人数となります。そのため、下記のように各事業所の人数が10人未満の場合、届出は必要ありません。
【例】
| 事務所名 | 労働者数 | 届出の必要性 |
| 事業所1 | 11名 | 必要 |
| 事務所2 | 2名 | 不要 |
| 事務所3 | 5名 | 不要 |
また、労働者とは正社員だけでなく、パート・アルバイト従業員などの非正規雇用者も含めるため、注意しましょう。
なお、繁忙期などで臨時的に10名を超える場合はこの限りではありません。
5-2.就業規則(別規定含む)を届出ていない場合、罰金の恐れがある
労働基準法第120条1号により、就業規則の作成と届出が必要な会社で、万が一届出をしていなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
就業規則は新たに作成した時だけでなく、変更したときも届出が必要ですので注意しましょう。
また、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」は、別規定を新たに作成、または変更した際も、就業規則として届出が必要です。
5-3. 付属規程等について届出が必要な範囲に注意
就業規則の届出においては、付属規程等について届出が必要な範囲に十分注意を払う必要があります。まず、契約社員就業規則やパート社員就業規則、嘱託社員就業規則など、雇用形態に関係なくすべての就業規則を労働基準監督署に届け出る義務があることを確認してください。ただし、単に社内の参考資料や指針としての「規程集」のようなものは対象外です。
次に、賃金規程や育児介護休業規程、退職金規程、旅費規程など、就業規則の絶対的必要記載事項または相対的必要記載事項を含む規程もすべて届出の対象となります。これにより、従業員の権利保護と企業の法令遵守が確保されます。どの規程まで届け出るべきか迷った場合は、労働基準監督署に確認することをお勧めします。詳細な届出の手続きと説明を怠らないようにしましょう。
5-4.「就業規則・36協定の本社一括届出」の利用も可能
なお、複数の事業所のある企業では、本社にて「就業規則・36協定の本社一括届出」の利用も可能です。
本社を含む全事業場で同じ就業規則を利用していること、電子申請により届け出ることなどの条件がありますが、活用すれば経費の削減や届出漏れ防止に有効でしょう。
また、本社で一括届けを行っていれば、各事業所で個別に労働基準監督署に就業規則を届け出る必要はありません。
5-5.届出た就業規則は労働者に周知しなければいけない
就業規則は作成・変更し、届け出ればそれで終わりではありません。
労働者に周知して初めて効力を発揮し、これを「就業規則の周知義務」といいます。(労働基準法第106条1項及び、労働基準法施行規則第52条の2)
就業規則の周知義務に違反すると、30万円以下の罰金が科されるケースもありますので、届出だけでなく周知も忘れずに行いましょう。(労働基準法第120条1号)
周知方法も法律で定められており、下記のいずれかとなります。
- 事業所や作業場の見やすい場所に常時掲示し、または備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
3については、パソコンなどに保存したときを想定しており、全従業員が保存場所を理解し、なおかつ自由に閲覧できることが求められると解釈できます。
関連記事:就業規則の閲覧を求められたらどうする?正しい対応方法を紹介
6. いつまでに提出が必要?就業規則の提出期限


就業規則を作成または変更した場合、管轄の労働基準監督署への届け出は「遅滞なく」行う必要があります(労働基準法施行規則第49条第1項)。
参考:労働基準法施行規則|e-GOV法令検索
具体的な期限は明示されていないため、就業規則が完成した時点で速やかに届け出を行うことが推奨されます。施行日の前でも届け出は可能であり、条文の変更や追加を定期的に行っている企業であれば、1年や半年に1度のペースで運用ルールを設けると良いでしょう。
なお、常時10人の労働者を使用する場合には遅滞なく届け出が必要ですが、それ以下の規模でも職場のルールを明確にし、従業員とのトラブルを避けるために就業規則を整備しておくことが有効です。
6-1. 変更・改定・追加の場合の届出期限
就業規則の変更・改定・追加を行う場合も提出期限については法律上の明確な規定や通達が存在しないため、基本的には「遅滞なく」届け出ることが求められます。
具体的な期限が定められていないとはいえ職場の秩序維持や従業員との信頼関係を保つためにも、できるだけ迅速に対応することが重要です。速やかに提出することで不測のトラブルを避け、円滑な労務管理を実現しましょう。
6-2. 就業規則の提出が漏れていた・忘れていた場合は?
もし就業規則の提出が漏れていた、または忘れていた場合、まずは速やかに提出を行うことが重要です。しかし、就業規則の周知が企業内部で確実に行われているなら、その効力に直接影響を及ぼすことはありません。労働契約法7条も、就業規則の周知が重視されていることを明確にしています。
参考:労働契約法|e-GOV法令検索
とはいえ、就業規則の変更が従業員にとって不利益な内容を含む場合、その変更の「合理性」が求められます。この合理性の判断において、就業規則を届け出ていないことがマイナス評価となりうるため、特に不利益な変更がある場合は提出を確実に行うことが必要です。不利益な変更が届出の欠如により効力を持たないリスクを避けるためにも、就業規則の周知だけでなく、提出手続きも徹底することが賢明です。
7. 常時10人以上の従業員を雇う事業所は就業規則の届け出を!


就業規則は正しい作成・届出・周知が、労働基準法で求められています。常時10人以上の従業員を雇う事業所では就業規則の作成と届出が義務付けられており、失念した場合は30万円以下の罰金が科されるケースもあるため、注意しましょう。
また、就業規則は届け出ればそれでよいだけでなく、周知して初めて効力を発揮します。従業員全員が閲覧できる正しい運用により、労使間のトラブルを防止するためにも周知することが重要です。
参考:労働基準法|e-Gov法令検索
参考:労働基準法施行規則|e-Gov法令検索
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08