労働保険の加入手続き方法を徹底解説!加入条件や計算方法まで

労働保険は労災保険と雇用保険から成り立っています。労働者にもしものことが起こった場合、生活が維持できるようにサポートするための制度です。労働者を雇っている事業所であれば、加入しなければなりません。ここでは労働保険の加入手続き方法・計算方法を分かりやすく解説しています。
労働保険は、働く人々に万が一の事態が起こった際、生活が維持できるようにサポートするための制度です。
本記事では労働保険の特徴や加入手続き方法・必要な書類、保険料の計算方法などを詳しく紹介します。
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1.労働保険とは?


労働保険は、労働者災害補償保険と呼ばれる労災保険と雇用保険を総称したものです。労働保険において、労働者とは「事業に使用される者」のことを指します。職業の種類は関係なく、すべての事業で労働の対価として賃金が払われていれば「労働者」です。ここでは労働保険の加入義務について説明します。
1-1.労災保険と雇用保険の概要
・労災保険:労働者の業務中・通勤中の災害による傷病や障害に対して保険給付を行う保険制度
・雇用保険:雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行う保険制度
1-2.労働保険の加入義務とは
労働保険は、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、1人でも労働者を雇っている事業所に適用され、労働保険への加入義務が発生します。事業主が成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
2.労災保険と雇用保険の加入条件


企業として加入義務のある労働保険ですが、労災保険・雇用保険でそれぞれ対象となる条件が異なるため、労災保険・雇用保険別に加入条件を詳しく見ていきましょう。
2-1.労災保険の加入条件
労災保険の加入条件は、事業主が一人でも労働者を雇用している場合に適用されます。これは正規雇用だけでなく、通年雇用をしていなくても、1日でも雇用していればパートやアルバイト労働者も含まれます。会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主やその家族等は前提として「労働者」とみなされず加入できませんが、会社の取締役でも労働者として報酬を得ていることがわかれば、保険に加入することは可能です。したがって、事業所の規模や業種にかかわらず、すべての職場が基本的に労災保険の対象となります。
ただし、例外として、農林水産業を営む個人事業所で労働者が5人未満の場合は、労災保険の加入が任意となります。
労災保険で中小事業主が利用できる特別加入制度とは?
中小事業主や一人親方が利用できる特別加入制度は、自身の業務中の怪我や病気に対して補償を受けるための重要な制度です。本来、労災保険は現場で働く労働者を対象としていますが、中小事業主はこの特別加入制度を利用することで労災保険に加入できます。この制度により、リスクの高い業種に従事している中小事業主も安心して業務に従事できます。
労災保険でいう中小事業主は、労働者数が50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業を指します。さらに、卸売業やサービス業であれば100人以下、それ以外の業種では300人以下であれば中小事業主として認められます。特別加入を希望する場合、労働保険事務組合に事務手続きを委託しているといった手続きが必要となります。
2-2. 雇用保険の加入条件
雇用保険の加入対象者は、正規雇用者だけでなく所定の労働時間が週20時間以上で一定の条件を満たしている、パート・アルバイト・派遣社員などの非正規雇用の労働者です。
30日以内の期間を定めて雇用する日雇い労働者や季節的に雇用する短期雇用者も含みます。
また平成29年1月1日以降は65歳以上の労働者にも、雇用保険が適用となりました。令和2年度からは64歳以上の労働者からも雇用保険料を徴収しています。
このことから、適用事業に雇用される労働者であれば、学生を除いて「雇用保険法第6条各号に掲げる者」以外は、原則として被保険者となるのです。
関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について
3.労働保険の加入手続き方法
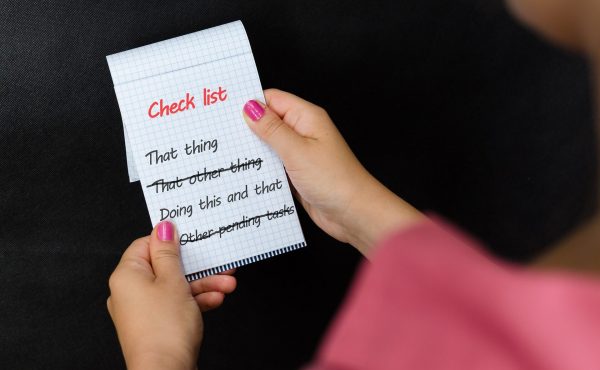
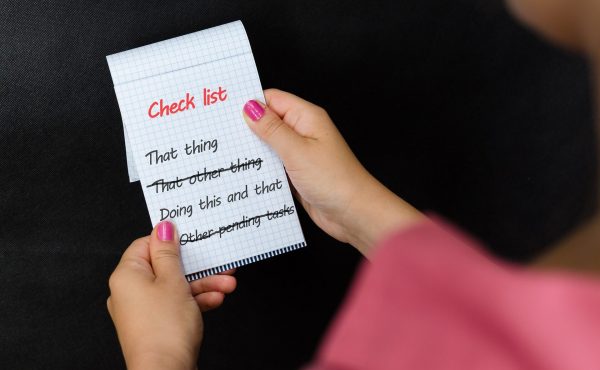
それでは実際の労働保険の加入手続きの方法として、手続きの流れと手続きの期限を解説します。
3-1. 労働保険の加入手続きの流れ
労働保険の適用事業となると、原則として以下の流れで労働保険への加入手続きを行います。
① 事業を行っている地域を管轄している労働基準監督署に対して「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出する
② 労働保険番号の交付を受けた後、同じく事業を行っている地域を管轄している公共職業安定所で、雇用保険の加入手続きを行う
以上の2ステップが主な加入手続きの流れです。書類の詳細は次の章で解説します。
3-2. 労働保険の加入手続きの期限
労災保険や雇用保険への加入は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に書類を提出しなければなりません。
ただし、労働保険概算保険料申告書のみは保険関係が成立した翌日から50日間ですが、納付も同じく50日以内です。書類に不備があると納付が遅れてしまうため、書類は10日以内に提出し、実際の納付は50日以内に行う、という流れをおすすめします。
4. 労働保険の加入手続きに必要な書類
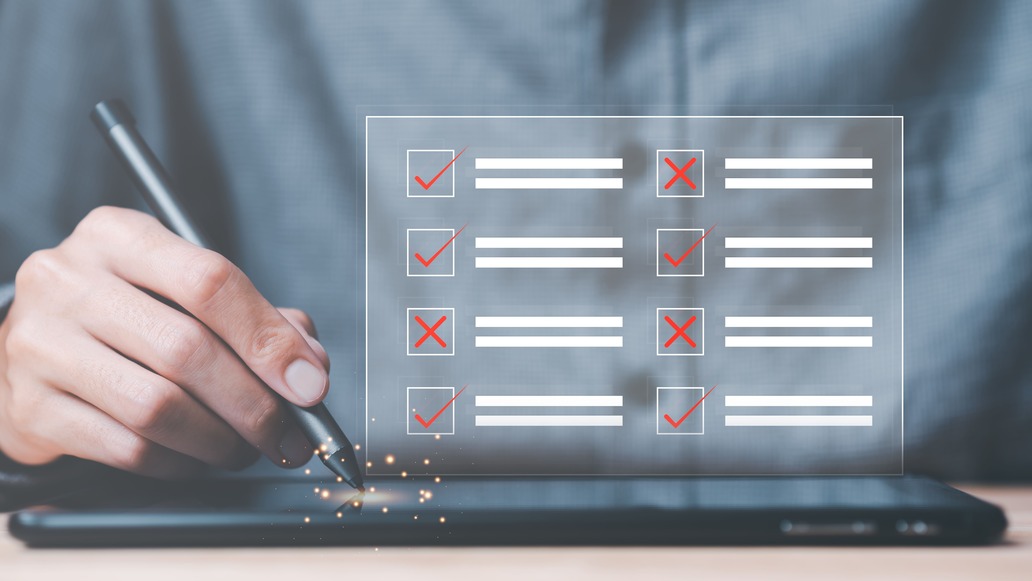
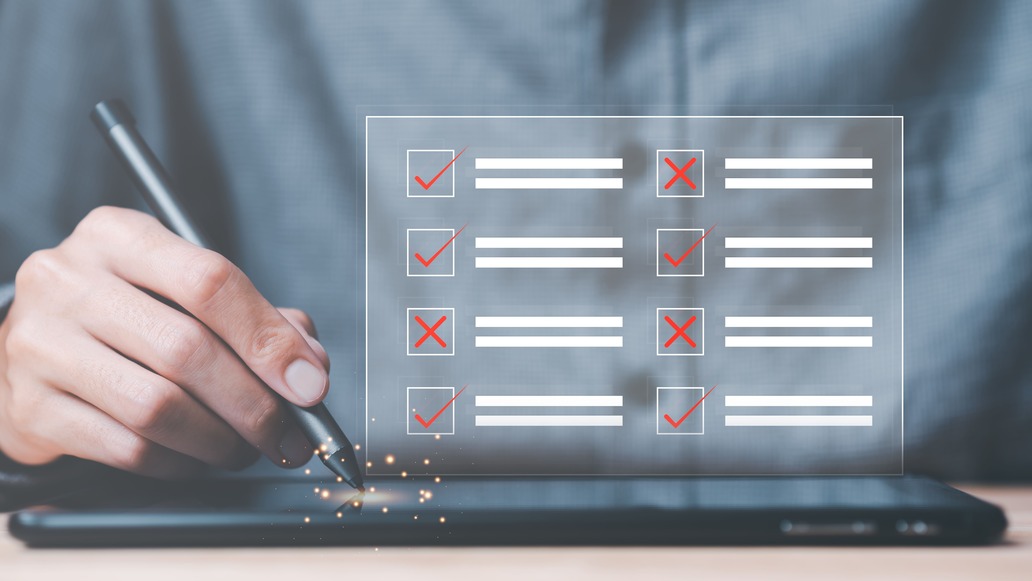
続いて労働保険の加入手続きとして、労災保険と雇用保険の手続きにおける必要書類について説明します。労災保険・雇用保険に加入する際は、以下の書類が必要です。
4-1.労働基準監督に書類を提出する
事業を行っている地域を管轄している労働基準監督署に対して書類を提出します。労災保険の手続きに必要な書類は以下です。
- 労働保険 保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書(写)1通
- 賃貸借契約書など ※謄本の住所と実際の勤務地が異なる場合のみ
4-2. 公共職業安定所に書類を提出する
労働保険番号の交付を受けた後、同じく事業を行っている地域を管轄している公共職業安定所で、雇用保険の加入手続きを行います。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届(加入する従業員分)
- 労働保険 保険関係設立届(控え)
- 労働保険概算保険料申告書(控え)
- 履歴事項全部証明書(原本)1通
- 賃貸借契約書など ※謄本の住所と実際の勤務地が異なる場合のみ
- 労働者名簿
5. 労働保険の加入手続きに関するよくある質問


労働保険の加入条件や手続きについて説明してきましたが、手続きに伴い関連してよく発生する質問をまとめました。回答を参考にスムーズに手続きを進めましょう。
5-1. 加入手続きに電子申請は可能?
労働保険の加入手続きには電子申請も可能です。労災保険や雇用保険の手続きをオンラインで行うためには、電子政府のポータルサイトであるe-Govを活用できます。ただし、電子申請を利用するためには事前に利用者登録が必要ですので、必ず準備を済ませてから手続きを進めてください。
5-2. はじめて労働保険に加入する場合の手続きは?
初めて労働保険に加入する場合、まず行うのは労働基準監督署での保険関係成立届と概算保険料申告書の提出です。保険関係成立届は保険成立翌日から10日以内に、概算保険料申告書は同じ日から50日以内に提出します。これらを同時に提出することで手続きがスムーズになります。
次に、労働保険番号を受領し、この控えを使ってハローワークで雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を手続きします。雇用保険適用事業所設置届は、事業所設置日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届は資格を取得した日の翌月10日までに提出する必要があります。
各手続きでの必要書類を事前に確認し、期限内に漏れなく提出することが重要です。これにより、円滑に労働保険の加入手続きを完了できます。
5-3. 雇用保険に未加入の場合の罰則はある?
雇用保険に未加入の場合、事業主に対して罰則が適用されることがあります。具体的には、労基法や雇用保険法に基づき、雇用している従業員が要件を満たしているにもかかわらず、雇用保険に加入させなかった場合、事業主には最大で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、雇用保険料の追徴金や延滞金が徴収されることもあります。
このような罰則や金銭的なペナルティだけでなく、未加入による社会的信用の低下や従業員からの信頼喪失など、経営に悪影響を及ぼすリスクも伴います。従業員を雇う際には、雇用保険の加入条件を確認し、必要な手続きを忘れずに行うことが重要です。
6.労働保険料の基本的な計算方法と支払方法


労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の総称です。労働保険料の中で、労災保険にかかる保険料は全額事業主が負担します。一方、雇用保険料は事業者と労働者それぞれで負担しなければなりません。労働者に支払っている賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)で決まることとなっています。
毎年4月1日~3月31日までの見込み賃金額と、業種ごとに決められている労働保険料率を用いて6~7月に計算されるのが一般的です。
関連記事:賃金総額とは?含まれるもの・含まれないものや計算方法を解説
6-1.労災保険料の計算と支払方法
計算式:労災保険の対象となる従業員の賃金(総額)×労災保険料率
労災保険料率は、事業の種類に応じて55種類(2.5/1000~88/1000)に分けられています。
例えば従業員の賃金総額が5000万円で食品製造業(労災保険率:6/1000)に分類される場合の計算式は以下の通りです。
5000万円×0.6%=30万円
この計算式で算出される金額を、4月~翌年3月の1年分まとめて事業所から支払います。継続事業の場合は、その年度に支払う予定である賃金総額に対して保険料率を乗じ、算出した金額を概算保険料として納付しなければなりません。実際の保険料との差額が発生する際は年度終了後に清算を行います。
もしも年度途中で初めて雇用したり、従業員が退職して一人も従業員がいなくなった場合、保険関係の成立もしくは消滅から50日以内に申告を行う義務があります。
6-2.雇用保険料の計算と支払方法
計算式:雇用保険の対象となる従業員の賃金(総額)×雇用保険料率
雇用保険料率は、一般の事業・農林水産と清酒製造事業・建設事業の3種類で15.5/1000~18.5/1000(令和6年度)に分けられています。算出された雇用保険料は、労働者の負担分と事業主の負担分に分けられ、それぞれが負担しなければなりません。
雇用保険料率表には「労働者負担」と「事業主負担」のそれぞれの保険料率が記載されています。この保険料率に基づき、お互いに雇用保険料を負担します。
7. 労災・雇用保険それぞれの手続きを正しく理解して労働保険へ加入しよう


働く人々を守るために、事業所が責任をもって加入しましょう。
またパートやアルバイト、派遣労働者などを新たに雇い入れた際、その労働者が雇用保険加入の条件を満たす場合は、手続きを忘れずに行ってください。
関連記事:労働保険の年度更新とは?手続き方法や注意点を詳しく解説
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
労務管理の関連記事
-


【2024年最新】労務管理システムとは?自社に最も適した選び方や導入するメリットを解説!
人事・労務管理公開日:2024.08.22更新日:2024.08.22
-


【2024年4月】労働条件明示のルール改正の内容は?企業の対応や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.10.18
-


社員の離職防止の施策とは?原因や成功事例を詳しく解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.09.03





















