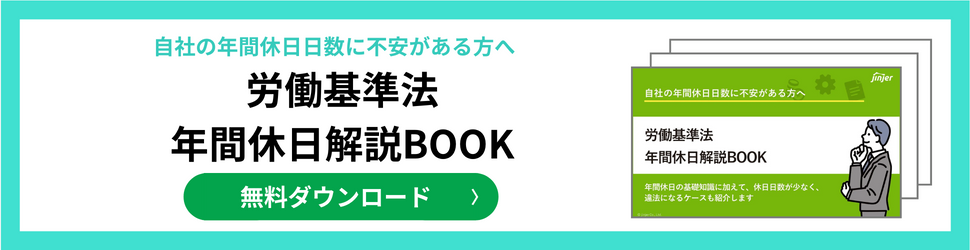労働基準法の年間休日最低ラインは105日?正しい日数と法律概要を解説
更新日: 2024.7.11
公開日: 2021.10.4
MEGURO

労働者を雇うときには、規定の休日を設ける必要があります。
労働者の雇用を守る法律として労働基準法があり、労働基準法には業務時間の上限や休憩の取り方とともに、休日に関する取り決めが盛り込まれているのです。
休日なしで働かせ続けることは労働基準法違反となるので十分に気をつけましょう。
この記事では、労働基準法が定める年間休日の考え方と数え方について詳しくご紹介いたします。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
「有給休暇は年間休日に含まれる?」
「世の中の平均的な年間休日数ってどのくらい?」
「自社の年間休日日数が法律に違反してないか不安」など自社の年間休日や有給休暇の日数に不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「労働基準法年間休日解説BOOK」を無料配布しております。
本資料では、労働基準法に則った年間休日数の基礎知識はもちろん、違反とみなされる可能性のある休日日数や、逆に違反にならないケースなど、休日日数に関して網羅的に解説しております。
これ一つで自社の休日日数が法律に反してないかや、年間スケジュールの組み立てる際の確認ができるため、法律に則った勤怠管理をおこないたい方は、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
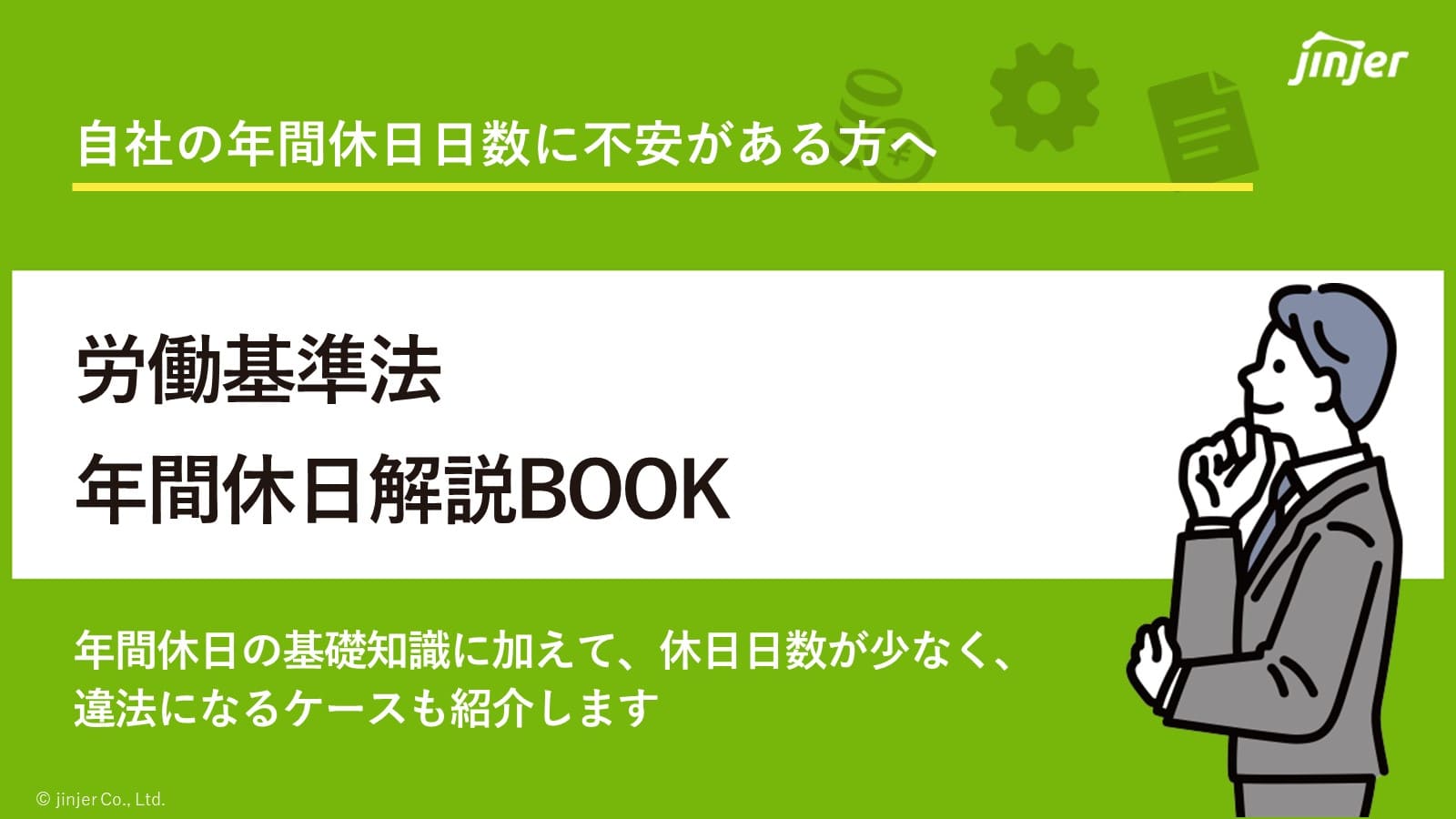
目次
1.労働基準法が定める年間休日とは

年間休日とは、労働基準法で定められている「法定休日」と、企業が自由に設定できる「法定外休日」を年間で合計した休日数のことをいいます。 年間休日を設定する目的は、従業員のワークライフバランスを充実させ、従業員の定着率も安定させることにあります。
1-1. 法定休日の意味
労働基準法では、企業は従業員に必ず週に1日、もしくは4週を通じて4日の休日を付与することが義務付けられており、この休日を法定休日と呼びます。法定休日は労働者の健康と安全を守るために重要ですが、この休日に曜日や日付に関する制約はありません。
週休が2日以上ある企業は、就業規則に法定休日の曜日を具体的に指定するのが一般的です。また、法定休日に労働させる場合、企業はその日労働した分に対して割増賃金を支払わなければなりません。労働基準法に準拠した適切な休日運用を行うことで、従業員の働き方改革にも寄与し、企業全体の労務管理の質を向上させることが可能です。
1-2. 法定外休日の意味
法定外休日とは、法定休日に加えて企業が自主的に設定する休日のことです。労働基準法では、労働時間を1日8時間、1週間40時間以内と定めており、これを超過する労働は基本的に認められていません。労働基準法に基づき、法定休日は毎週1日または4週間のうち4日以上与えることが義務付けられており、1日8時間・週5日働く労働者には、1週間に最低でも2日間の休日が必要です。そのうち1日は法定休日として、もう1日は法定外休日として企業が自主的に付与することが一般的です。これにより、労働者は適切な休息を取ることができ、労働環境の改善にもつながります。
1-3. 年間休日の最低ラインは105日
労働基準法の第35条には「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回、または4週間に4回の法定休日を与えなければならない」とあります。また労働基準法32条では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間までと定めています。
この2つの決まりを適用すれば、1日8時間の労働時間で年間に働かせることのできる日数の上限は260日程度となります。つまり、最低限必要な年間休日数は、365日-260日という計算により105日ということになるのです。労働基準法の35条に定められているのはあくまで法定休日の考え方です。
たとえば企業が労働基準法第35条の取り決めに応じて毎週1回の休日を設けた場合、年間の休日数は年間の週数と同じ52日前後にとどまります。これでは、年間105日という休日の基準には遠く及びません。
そのため多くの企業では、年間の休日数の基準を満たすために、法定休日とともに法定外休日を設けているというわけです。
2. 年間休日に関わる労働基準法のおさえておくべき概要

年間休日を設定する上で労働基準法の概要を理解しておくことは欠かせません。そもそも年間休日にある休日や休暇の違いがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。休日や休暇だけではなく、振替休日や代休などの休みもあります。改めて各項目の定義も細かく紹介していきます。
2-1. 休日と休暇の違い
休日とは、労働契約上、企業が必ず労働者に与えるべき労働義務がない日のことを指します。法定休日と法定外休日の2種類があり、週に1日以上または4週間で4日以上の法定休日を設定する必要があります。これに違反すると企業は罰則を受ける可能性があります。また、休日に労働を行わせる場合は、労使協定(36協定)を結び、割増賃金を支払わなければなりません。
一方、休暇とは、労働義務がある日を企業側の判断で免除された日のことを指します。主な休暇には、労働基準法で定められた年次有給休暇(年休)があり、6カ月以上の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤実績がある従業員に対して一定日数の年休を付与する義務があります。これも違反すると企業は罰則を受けます。
労働基準法では、「休日」と「休暇」を明確に区別しており、それぞれに適用されるルールや罰則も異なります。
関連記事:労働基準法に定められた休日とは?そのルールを分かりやすく解説
2-2. 振替休日の定義
振替休日は、あらかじめ休日とした日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。労働基準法では、振替休日を適用するには、事前に労働者へ通知が必要です。この日は労働日に振り替えられるため、休日労働への割増賃金を支払う必要がありません。しかし、振替休日が翌週以降になる場合や、振替勤務があった週の労働時間が法定労働時間の40時間を超える場合は、時間外労働による割増賃金が発生するので注意が必要です。
労働基準法に基づいて振替休日を運用する際には、以下の4点に気をつけることが重要です。
1. 振替休日に関するルールを就業規則に明記すること
2. 振替休日は特定の日を指定すること
3. 振替勤務日の前日までに振替休日を通知すること
4. 振替休日はなるべく振替勤務日に近い日に設定すること
これらのポイントを理解し、適切に運用しましょう。
2-3. 代休の定義
代休とは、企業が従業員に法定休日や所定休日に労働させた後に、その埋め合わせとして与える休暇です。これは振替休日とは異なり、事前の通知や休日の調整はなく、後日、休日が別途付与されます。労働基準法に基づく代休の制度を適切に運用することで、従業員の労働負荷を軽減し、労働環境の健全化を図ることができます。
なお、代休が適用される勤務日が振替勤務日に変更されていないため、法定休日に出勤させた場合は、法律に則った割増賃金の支払いが必要です。人事担当者や労務管理者は、労働基準法の規定に基づき、代休の付与と賃金の支払いを正確に管理することが求められます。
2-4. 年間休日に有給休暇は含まれる?
有給休暇は年間休日には含まれません。そもそも年間休日とは、社員全員に適用される休日休暇のことを指します。
それに対し有給休暇とは、条件を満たした労働者全員に付与される休日であり、全員が同じ日に取得することはありません。そのため、人それぞれ取得できる日数や取得する日程が異なる有給休暇は年間休日に含まれないのです。
2-5. 労働基準法で定めている「法定休日」は変更できる?
労働基準法では、事業場ごとに法定休日を任意に定めることができます。このため、企業はその都合に合わせて法定休日を変更することが可能です。ただし、就業規則を作成する際には毎週日曜日を休日と定めるように具体的に曜日を特定することが強く推奨されます。これは振替休日や代休の問題、休日労働や深夜労働の割増率の問題などを回避し、労使間のトラブルを防ぐためです。
労働基準法には1週間に1日の休日を与えるまたは4週間に4日の休日を与えると規定されていますが、これを具体的な日付や曜日に明示することで、裁判を含む労使間の紛争を未然に防ぐことができます。法定休日の規定が不明確なために企業が不利になったケースも少なくありませんので、法定休日については就業規則で明確にすることが重要です。
3. 年間休日の設定例


一般的な企業が労働基準法をもとに設定している年間休日の平均日数は120日程度となります。1年間には104日前後の土日があり、さらに祝日が16日あるのでこれを合計すれば120日ということになります。
つまり完全週休2日で土日を休日とし、さらに祝日やお盆、年末年始休暇を設定している企業であれば、年間休日数は120日以上になるのです。
3-1. 年間休日の平均は110.7日
厚生労働省の令和5年調査における令和4年1年間の年間休日総数の1企業平均は110.7日(令和4年調査 107.0日)、労働者1人平均は115.6日(同 115.3日)となっている。 1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、「1,000人以上」が 116.3日、「300~999人」 115.7日、「100~299人」が 111.6日、「30~99人」が 109.8日となっている。(第4表)
出典:令和5年就労条件総合調査の概況 |厚生労働省
厚生労働省の調査では、金融業や保険業、情報通信業、電気ガス・熱供給・水道業、学術研究・専門技術サービス業、製造業(メーカー)では年間の平均休日数が120日以上に達していたといいます。
3-2. 一部の業種では100日に満たないケースも
これに対し、外食や小売、サービス業、宿泊業などの接客業、運輸業、建設業などでは年間の平均休日数が100日に満たないケースも多いとされています。こういった事情が重なり法定休日を労働者に与えず働かせ続けてしまった場合には、労働基準法第119条の規定により6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることになります。企業は十分な休日を確保し労働者に提供する必要があります。
多くの労働者は、休日が少なく労働時間の長い企業に対して魅力を感じないものです。休日を少なく設定していると、労働者はより年間休日数の多い会社を選んで転職してしまうかもしれません。貴重な人材の流出を防ぐためにも、十分な休日数を設定するようにしましょう。
3-3. 労働基準法を守るために有効な対応方法
企業によっては十分な休日数の確保が難しいということもあるかもしれません。また、繁忙期などの関係で休日出勤をお願いしなければならない事情も出てくると思います。
こういった場合に、労働基準法に則って年間休日数を守るために有効な対応方法としては、完全週休2日という形で年間120日程度の休日を設定するほか、ゴールデンウイークや夏季休暇、年末年始休暇というかたちで長期休暇を導入する方法のほか、リフレッシュ休暇を設定して年間の休日数を調整するケースもあります。
4.労働基準法に置ける年間休日数の最低ラインでの働き方とは


労働基準法の1日8時間から考えると年間休日の、105日とされています。
たとえば土日を完全に休日とする場合には、土日のみで年間休日数の105日に達してしまうことになります。
この場合には祝日の出勤が必要となるほか、ゴールデンウイークや夏季休暇、年末年始休暇の取得もできなくなってしまいます。
祝日や長期休暇のタイミングで休みを取得したいのであれば、土曜日に隔週出勤するなどの工夫が必要となります。
いずれにしても、年間休日数105日というのはかなり休日の少ない働き方ということになります。
もちろん、出勤する日が多ければ給与額が高まる可能性もあるため、休日の少なさは労働者にとって必ずしもマイナスになるわけではありません。
しかし、休息時間やプライベートの時間を十分に確保できないことは、労働者にとって大きな損失となってしまいます。
そのため労働者と企業側とでよく話し合い、労働者の意見を最大限汲み取った上で、年間休日数を設定することが大切です。
5. 労働基準法で定められている休日に関しての罰則


労働基準法で定められている
・毎週少なくとも1回の休日
・4週間に4日以上の休日
上記を与えていないことが発覚した場合、労働基準法の違反となり罰則が科されます。違反することがないよう予め確認しておきましょう。
5-1. 休日を与えなかった場合の罰則
労働基準法に基づいて会社が従業員に適切な休日を与えない場合、企業には厳しい罰則が科されます。具体的には、企業が従業員に毎週少なくとも1回、または4週間に4日以上の休日を与えなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が規定されています。さらに、休日は同じ日付の0時から24時までの連続した24時間を設定する必要があります。たとえば、前日12時から24時までと翌日0時から12時までの合計24時間を休ませても、それは休日として認められないため注意が必要です。
5-2. 休日に出勤させる場合の対応
法定休日に従業員を出勤させる場合、企業はまず労働基準法に基づく適切な対応を取る必要があります。最初に、従業員の過半数を代表する者または労働組合と時間外労働・休日労働に関する協定(通称36協定)を締結することが必須です。この協定に基づき、法定休日の出勤に関する条件を労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、36協定に従った時間外労働や休日労働の指示が可能である旨を、就業規則や労働契約に明記することも重要です。加えて、協定の内容を掲示や書面配布などで従業員に周知する責任があります。労働基準監督署に届け出た後は、実際に休日に出勤させた従業員に対して、法定割増賃金を支払う義務があります。具体的には、法定休日に出勤した場合、通常賃金の1.35倍の割増賃金を提供する必要があります。
6.労働基準法の年間休日が105日を下回っても違法にならないケース


年間休日数の設定はあくまで基準ということになります。
状況によっては、年間休日数が105日を下回っても違法となりません。
年間休日数の少ない働き方には以下のような条件があります。
6-1.労働時間が短い場合
労働基準法における年間休日数の下限は105日とされていますが、これを下回っても必ず労働基準法に抵触するわけではありません。
労働基準法第35条の規定では労働者に毎週1回または4週間に4回以上の休日を与える必要があります。
また、労働基準法第36条には法定労働時間について、1日8時間、週40時間という定めがあります。
たとえば労働者の労働時間が1日6時間だった場合には、週6日勤務しても1週間の労働時間合計は36時間となります。
これは、労働基準法第36条の1日8時間、週40時間という取り決めの範囲内です。
この働き方を1年間続けた場合には、年間の休日数は52日前後となります。
しかし、週に1度休日を設定して週6日勤務という形式にしていれば、労働基準法には抵触しません。
つまり、労働時間を短く設定すれば年間の休日数が少なくても罰則の対象とはならないのです。
6-2.年間休日に有給休暇を含めて設計する場合
年間休日に有給休暇は含まれないとすでに説明したと思いますが、この特徴を活かして年間休日を100日で設定するケースがあります。
ではどうやって105日を満たすのかといいますと、年間休日100日と年次有給休暇を合わせて休日数を105日にするということです。
フルタイム労働者の場合、有給休暇は入社後6ヶ月働くと10日もらえます。フル消化は難しいかもしれませんが、2019年から有給義務化が始まったので年5日は必ず有給で休めるので、ちょうど105日になるというわけです。
ただ前提として労働基準法36条をクリアしていることが必須になるので、週6日出勤が必要になった際は該当者の出勤状況を注意深く確認するようにしましょう。
6-3.36協定を締結している場合
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことを指します。
これは労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超えて時間外労働をさせるときの取り決めです。
36協定では時間外労働の上限を月45時間、年360時間と定めています。
この範囲内であれば休日数が少なくなっても違法とはなりません。
ただし36協定は、社員の過半数で組織する労働組合との協定または社員の過半数を代表する人との協定が必要となります。
適用には所轄労働基準監督署への届け出が必須です。
また、36協定で時間外労働や休日労働をさせるときには、必ず所定の割増賃金を支給しましょう。
関連記事:労働基準法の第36条に定められた協定の内容や届出の記入法
6-4.特殊な労働形態を採用している場合
企業が変則労働制を採用しているのであれば、労働時間は1日単位ではなく月単位や年単位で換算されます。
変則労働制は、繁忙期に集中して働いてもらい閑散期に休日を設定したい場合などに向いています。
また、タクシー業界やホテル業界が変則労働制を採用する例もあります。
ほかに、フレックスタイム制や裁量労働制を採用している場合にも、労働基準法における年間休日の取り決めの適用外となるケースがあります。
本章で解説しているように年間休日が105日を下回っていても違反にならないケースもありますが、36協定を締結していない場合は法律違反になる可能性が高いです。そのため、用語の定義や休日・休暇の種類から正しく理解しなければなりません。
ここまで読んで、複雑な内容が多く、正しく理解できているか不安という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「労働基準法年間休日解説BOOK」とを無料配布しております。
この資料では本記事に記載されている年間休日の基礎知識や、年間休日が少なくても違反にならないケースの解説などを、図解をもちいてわかりやすく解説しており、正確に年間休日の基礎を理解することができます。
興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
7. 高度プロフェッショナル制度の年間休日のルールは104日を義務化


2019年4月から新設された「高度プロフェッショナル制度」で働く労働者に対しては、年間104日以上、かつ4週を通じて4日以上の休日を確保することが義務付けられています。高度プロフェッショナル制度とは、アナリストやコンサルタントなど高度な専門的知識をもち、高い年収を得ている労働者に適用される制度で、適切な健康・福祉措置をとったうえで労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日、割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
高度プロフェッショナル制度は適用するにあたって「高度な専門的知識をもっている」「業務範囲が明確」「年収が1,075万円以上」など高いハードルがあるため、適用される労働者はごくわずかです。
したがって、年間休日を104日以上とする義務化は、ほとんどの労働者には適用されないと考えてよいでしょう。
参考:「働き方」が変わります!!|厚生労働省
8.労働基準法の年間休日の考え方を把握し、十分に休日を与えましょう


労働基準法をもとに労働時間を1日8時間、週40時間に設定しているのであれば、年間休日数の下限は105日となります。
労働時間や労働形式によって、必要な年間休日の日数は異なるので、法令を十分に確認しておくことが大切です。
休日は労働者にとって貴重なリフレッシュの時間となります。
労働者が気持ちよく働けるよう、十分な休日を設定するなどの配慮をしましょう。
「有給休暇は年間休日に含まれる?」
「世の中の平均的な年間休日数ってどのくらい?」
「自社の年間休日日数が法律に違反してないか不安」など自社の年間休日や有給休暇の日数に不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「労働基準法年間休日解説BOOK」を無料配布しております。
本資料では、労働基準法に則った年間休日数の基礎知識はもちろん、違反とみなされる可能性のある休日日数や、逆に違反にならないケースなど、休日日数に関して網羅的に解説しております。
これ一つで自社の休日日数が法律に反してないかや、年間スケジュールの組み立てる際の確認ができるため、法律に則った勤怠管理をおこないたい方は、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
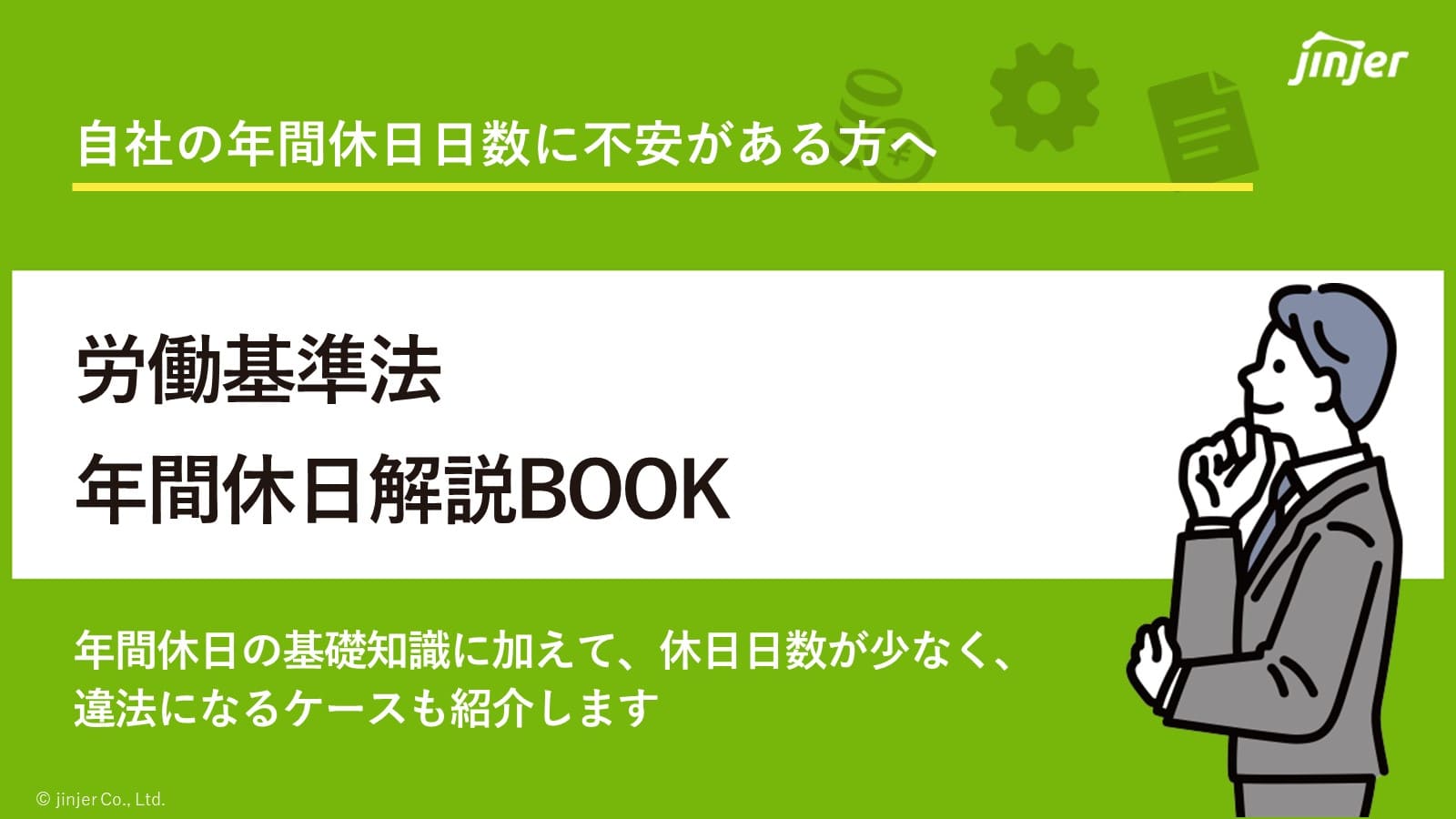
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08