人材データベースとは?人事業務全般に役立つ機能と作り方、活用法を解説
更新日: 2024.1.16
公開日: 2023.6.14
OHSUGI

企業が従業員の情報をまとめ、一元管理する人材データベース。人材データベースの活用は、人材の採用や配置、そして育成にも役立ちます。ここでは人材データベースを作成する目的や作り方、記載項目、メリットといった基礎知識を解説します。
目次
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 人材データベースとは

人材データベースとは、企業に属する従業員のさまざまなデータの集合体です。社員の氏名や住所、生年月日、入社年月日といった基本的な情報に加えて、人事評価やスキルなど、従業員に関するあらゆるデータが保存されています。
人材データベースは、基本的にExcelや人事データベースサービス、人事ERP(「Enterprise Resource Planning」の略で、経営に欠かせないヒト、モノ、カネの情報を集約し適切に分配する)システムなどによって電子的に作成します。システム的に管理をおこなうことで、従業員の増加や管理すべき情報の増加にも対応可能です。
人材データベースに登録された多くの情報を活かした人材戦略をとることが、経営計画の実現や目標の達成につながるでしょう。
2. 人材データベースを構築する目的と機能

人材データベースは、単に従業員の情報を確認するためだけに使うものではありません。人材データベースを構築する目的と機能、さらには具体的にどのように使っていくのかについて見てみましょう。
2-1. 人材データの可視化するため
人材データベースを構築する目的のひとつは、従業員の個人情報を一括管理して企業の人的資源を可視化するためです。人材データベースを可視化する機能を用いれば、年次、学歴、職歴、入社形態や保有スキルをまとめて確認できるだけではありません。情報の抽出も容易であることから、業務効率の向上につながるでしょう。また、残業時間や休職者の割合といった従業員の勤怠状況も容易に把握でき、労務管理も楽になります。
人材データの可視化は、現在の企業の経営状況を確認したり、将来的な人材戦略を検討したりするために欠かせません。また、現在の状況が明らかになることで、不足している人材についても把握できるため、人材採用においても役立つでしょう。
2-2. 適切な人材配置の実現するため
人材データベースを活用すれば、それぞれの従業員の特性に応じた人材配置が可能です。
人材データベースには、それぞれの従業員のスキルやこれまでに経験した業務、所属した部署での評価、本人の希望など、配置転換の参考になる情報がまとめて記載されています。また、住所などの基本情報も登録されているため、配置転換による転勤の有無なども合わせて確認できるでしょう。
少子高齢化による人手不足が進む昨今、従業員の特性を活かした適材適所の人材配置をおこなう必要性が高まっています。生産性の向上やエンゲージメントの強化のために、人材データベースをもとにした適切な人材配置を心掛けましょう。
2-3. 労働者名簿として活用するため
人材データベースをシステム的に作成し、そのまま労働者名簿として活用することも目的のひとつです。
労働者名簿とは、従業員を雇用している企業が必ず作成しなければならない法定三帳簿のひとつです。電子的に保存することも認められています。
記載項目は以下の通りです。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 履歴
- 住所
- 業務の種類(従業員30人以上の場合)
- 雇用年月日
- 退職年月日と理由
これらを人材データベースにも登録すると、労働者名簿としても利用できます。
3. 人材データベース構築時の記載項目

人材データベースは作成が法的に義務付けられているものではありません。そのため記載内容はそれぞれの企業に委ねられています。
とはいえ、従業員のデータ管理をおこなうにあたって、主に記載しておくべき項目はある程度パターン化されています。人材データベース構築時に記載すべき主な項目は以下の通りのため、人材データベースの作り方の参考にしましょう。
3-1. 基本情報
従業員の氏名、性別、生年月日、住所、入社日、電話番号、社員番号といった個人を識別するための基本的な情報です。
なお、性別についてはLGBTに配慮した対応をとっている企業もあります。ただし、労働者名簿には性別の記載が必須ですので、労働者名簿としても利用する場合は注意してください。
3-2. 職務内容
現在の職務内容や役職、等級などについて記載します。本人が希望する仕事がある場合は、併記しておきましょう。
3-3. スキル
保有資格、語学力、そのほか業務に必要なスキルの習熟度などについて定量的に記載します。特定のスキルを持った従業員の抽出や、配置転換を検討する際などに役立つでしょう。
3-4. 経歴・人事評価
学歴や職歴、入社後に所属した部署の履歴、研修などの受講履歴、表彰履歴などの情報です。過去に所属した部署における評価や実績についても記載しておくと、従業員の客観的な評価や、得意な業務、不得意な業務などが一目でわかります。
3-5. 勤怠状況
休職や遅刻、早退、欠勤履歴、月の残業時間といった、従業員個人の勤怠状況です。勤怠状況を人材データベースに書いておくことで、勤怠に関する問題の早期発見や、勤務態度の把握、勤怠状況と成果との関連性の確認などに役立てられます。離職率と合わせてチェックすることで、早期離職防止に役立てることもできるでしょう。
3-6. マインド
適性検査の結果や、将来目指すキャリア、上司との面談内容や面談履歴などについて記載します。本人のモチベーションやエンゲージメント、性格などを記載しておくことで、それぞれの従業員に適した配置やフォローをしやすくなるでしょう。
4. 人材データベース構築のポイント
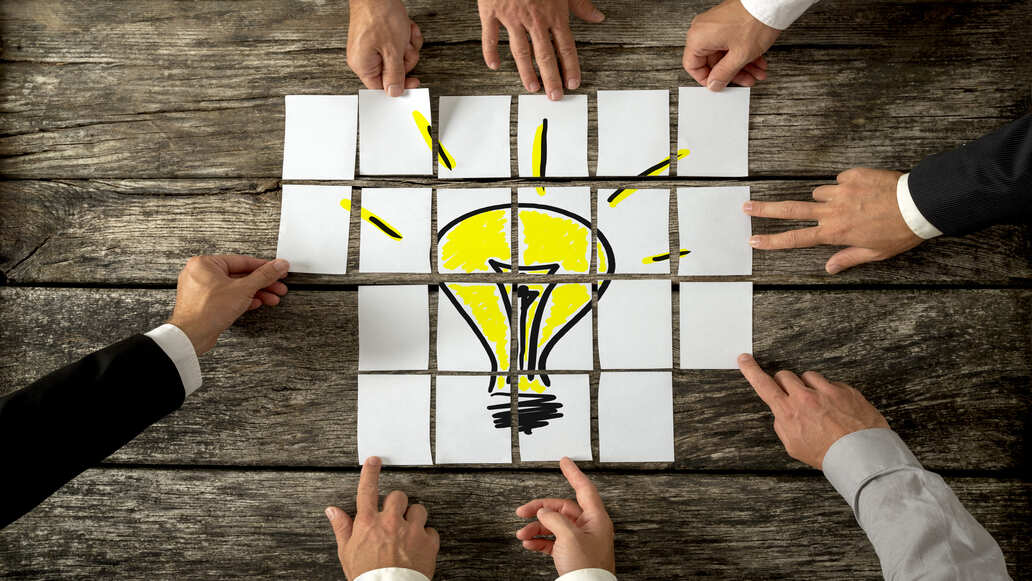
人材データベースを構築する際は作り方だけでなく、構築のポイントを把握しておくことが大切です。人材データベースを構築する際のポイントは次のとおりです。
4-1. 使用する目的を明確にする
人材データベースを構築する際はデータベースを使用する目的を明確にしましょう。どのようなデータが必要なのか、どのように分析するのかが不明瞭なまま人材データベースを構築してしまうと、運用に失敗してしまうかもしれません。
人材データベースを使用する目的として、トップダウン、ボトムアップの2種類を把握しておきましょう。それぞれの違いは次のとおりです。
トップダウン:事業戦略をベースにした人事戦略の達成に人材データを活用する
ボトムアップ:業務の課題を解決・改善するために人材データベースを使用する
4-2. データの定義と運用ルールを明確にする
人材データベースはただデータを収集すればいいわけではありません。人材データベースを有用なものにするには、収集するデータの定義を明確にしておきましょう。また、運用ルールを明確にしておくことも大切です。例えば最初から多くの項目をデータ化しようとすると、データ収集や更新に時間がかかってしまうため、スモールスタートを心がけるようにしましょう。
4-3. 従業員にも共有する
人材データベースは常に最新の情報を保っておく必要があります。そのため、データの変更や追加があった場合、すぐに対応できるようにしておかなければなりません。データの変更、追加にすぐに対応するためには従業員に人材データベースについて共有しておきましょう。
5. 人材データベースを人材育成に活かすメリット

人材データベースは、人材の育成にも多くのメリットを生み出します。具体的に何ができるようになるのか、4つの例をご紹介しましょう。
5-1. 人事情報の共有ができる
人材データベースを人事担当者や各部署の管理者などで共有することで、必要な情報を必要なタイミングですぐに手に入れられます。ただし、個人情報へだれもが簡単にアクセスできる状態は好ましくありません。閲覧できる範囲や対象者については、十分な考慮が必要です。
5-2. 人材配置や人材育成に活かせる
各従業員のスキルや経歴、希望などを整理することで、適材適所の配置をしやすくなるでしょう。従業員の持つ力を最大限に発揮できる配置を実現することで、人材の有効活用ができます。
また、それぞれの従業員の職位などに応じたスキルの有無や評価を確認することで、どのような教育が必要なのかも把握しやすくなるでしょう。これまでに受講した研修や取得したスキルが実務に活かされていることの確認も可能です。
5-3. 特定スキルを有した従業員の抽出が容易
システム的に管理されている人材データベースがあれば、特定のスキルや経歴を持った従業員を容易に抽出できます。業務内容の調査や、新しいシステムに関する意見交換といったさまざまなシーンで、適した人材をすぐに探せるでしょう。
5-4. 人事担当者の業務効率化につながる
従業員に関するデータを人材データベースで一元管理することは、人事担当者の業務負担軽減にもつながります。特に、人事担当者が個別の従業員を把握できない大企業においては、人材データベースが人材の管理やデータ分析など多くの場面で役立つでしょう。
関連サイト:リスキリングナビは、人材育成や社内のリスキリングの最新情報や事例を多く発信しております。
人材育成を考えるなら、リスキリングナビ
6. 人材データベース構築に適したシステム

人材データベースを構築するのに適したシステムとして、次の2つが挙げられます。
- エクセル
- タレントマネジメントシステム
6-1. エクセル
人材データベースはエクセルで構築可能です。エクセルを活用することで、無料で人材データベースが構築できます。エクセルであれば、一定のルールに則ってデータを蓄積することで、人材データベースが作れます。
6-2. タレントマネジメントシステム
人材データベースの作り方として、タレントマネジメントシステムを導入するという方法もあります。タレントマネジメントシステムであれば、従業員一人ひとりの情報を一元管理できるため、人材データベースとして機能します。
7. 人材データベースの活用で人事業務を効率化しよう!

人材データベースを活用して、人事業務の効率化を図りましょう。必要な情報を容易に抽出できる人材データベースがあれば、短時間で正確性の高い業務が可能になります。
ただし、人材データベースを効果的に利用するためには、リアルタイムでの更新や活用法の理解が必須です。人材データベースが形骸化しないよう、運用ルールなどを定めて周知していきましょう。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























