年末調整をしないとどうなる?考えられる5つのリスクを解説
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.11.2
OHSUGI

年末調整は従業員の所得税を正しく納税するために実施する手続きです。定められたルールに従い適切に所得税を納めなければ、法的な罰則を受ける可能性があります。場合によっては悪質な脱税とみなされ、資産の差し押さえにまで発展する危険もあるのです。
この記事では年末調整が適切におこなわれなかった場合のリスクについて解説します。年末調整をやらないとどうなるのか、年末調整をしなくてもよい場合はあるのかなど、気になる方はぜひ参考にしてください。
関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整は雇用主の義務

自社の従業員の年末調整は雇用主に課せられた義務です。年間の所得が確定する年末に手続きを実施し、各従業員の正しい所得税を算出しなければなりません。年末調整を実施しないと会社としても正しい納税ができないため、必ず手続きをおこないましょう。
1-1. 年末調整により源泉所得税と本来の所得税の差額を清算する
年末調整とは、各従業員の毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税(源泉所得税)と、その年に本来納税すべき所得税との差額を清算するための手続きです。従業員の年間所得が確定する12月頃に実施されることから年末調整と呼ばれます。
毎月の源泉所得税額はあくまで各従業員の想定される年間所得から概算される金額です。実際の所得税には各種所得控除が適用されるため、源泉所得税との間に金額の乖離が生じます。年末調整はその乖離を修正するための手続きです。「従業員の確定申告を会社が代行している」とも言えるでしょう。
1-2. 年末調整をしないと正しい納税ができない
年末調整を実施しないということは、会社も正しい納税ができていないということです。法律で定められた税金を納めることは私たち国民の義務ですので、対象となる従業員への年末調整は必ず実施されなければなりません。
そのため、故意に年末調整をおこなわなかった場合は国からの罰則が科せられます。また、人為的なミスによる手続きに不備であっても、罰則が発生する可能性はゼロではありません。年末調整は決められたルールに従い、適切に実施しましょう。
年末調整は決められたルールに従い、適切に実施しましょう。とはいえ、年末調整は提出書類や記載ルールが細かいため、抜け漏れがないか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて、年末調整のルールをわかりやすくまとめた資料を無料で配布しています。年末調整業務に不安がある方は、こちらの「年末調整のガイドブック」を見て確認しながら業務をすすめられることをおすすめします。
2. 年末調整をやらないどうなる?5つのリスクを解説

もしも年末調整が適切に実施されなかった場合、もしくは故意的にやらなかった場合、会社のリスクは以下の5つです。
- 余計な税金がかかる
- 過剰納税分の還付が受けられない
- 従業員に確定申告の負担が掛かる
- 雇用主に懲役もしくは罰金が科せられる
- 資産が差し押さえられる
それぞれのリスクについて詳しく解説します。
2-1. 余計な税金が掛かる
年末調整を実施したものの期日までに所得税が納税できなかった場合には「延滞税」が発生します。延滞税は納付期日の翌日から自動で課税され、特に納付期日を2ヵ月以上経過した場合は税率が上がるため注意が必要です。
延滞税で課税される1日当たりの金額は、以下の計算式(1)(2)で求める金額を合算して算出します。
(1)本来の納税額×延滞税の割合(※1)×期日からの経過日数÷365=金額
(2)本来の納税額×延滞税の割合(※2)×期日からの2ヵ月を超えた日数÷365=金額
※1:年「7.3%」もしくは「延滞税特例基準割合+1%」いずれか低い方が適用
※2:年「14.6%」もしくは「延滞税特例基準割合+7.3%」いずれか低い方が適用
また、納税した所得税が本来納めるべき金額よりも少なかった場合は「過少申告加算税」が発生する可能性があります。過少申告課税の税率は不足金額の10%(※3)です。ただし、税務署が調査する以前に自ら修正申告した場合は課税されません。
※3:当初の申告納税額か50万円いずれ多い額を超えている部分の税率は15%
2-2. 過剰納税分の還付が受けられない
年末調整を実施しなかった場合、会社は過剰に納税した源泉所得税の還付を受けることができなくなります。
先述したように、従業員の毎月の源泉所得税は概算であるため、本来の所得税より多く徴収していることが一般的です。会社が所得税の過払金を還付されなければ、当然ながら従業員へも還付をおこなうことができません。
2-3. 従業員に確定申告の負担が掛かる
会社が年末調整をおこなわなかった場合、従業員は自身で確定申告をおこなわなければなりません。確定申告の準備には時間を要し、また申請の手順も複雑です。年末調整に比べて圧倒的に手間が掛かることから、従業員への負担も増大してしまいます。
会社が正しく納税をしなかったということで、会社に対する従業員の信用も低下してしまうでしょう。仕事のモチベーションが低下し、退職者が増大することも考えられます。
2-4. 雇用主に懲役もしくは罰金が科せられる
故意に確定申告をおこなわなかった場合、書類を偽造し嘘の申告をした場合、従業員から徴収した所得税を納税しなかった場合、これらは全て「脱税」とみなされ法的な罰則の対象です。
所得税法においてこれらの行為が発覚した事業者には「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」、悪質な場合は「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」といった罰則が定められています。
2-5. 資産が差し押さえられる
税務署から税金の未納や脱税を指摘され、その後も納税をしなかった場合、最悪のケースとして資産が差し押さえられるケースも考えられます。
実際には税金を滞納してすぐに資産が差し押さえられることはありません。初めに税務署からの督促状が送付され、それに応じなかった場合は電話や書面で直接催促されます。税務署から再三の督促を受けにもかかわらず納税をしなかった場合に資産差し押さえに発展するのです。
資産の差し押さえは対外的な会社の信用にも関わります。税金は期限内に納付し、万が一税務署から税金未納の指摘を受けた場合は速やかに対応しましょう。
3. 年末調整をやらなくてもよい従業員の条件

原則として、年末調整は自社で雇用している従業員全員を対象として実施します。しかし、例外的に年末調整の対象外となる従業員もおり、該当する従業員への年末調整は実施しなくても罰則はありません。ここでは年末調整をやらなくてもよい従業員の条件を解説します。
3-1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない
自社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない従業員は年末調整の対象外です。該当する従業員は扶養控除申告書を提出している他の会社で年末調整をおこなうか、もしくは自身で確定申告をおこないます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年末調整をおこなうための前提条件となる書類です。従業員が扶養控除申告書を提出できるのは1社のみと定められているため、従業員もその1社でしか年末調整を受けることができません。
特にアルバイト社員の場合は該当するケースが多く、採用時には必ず他社での勤務の有無を確認しておきましょう。他社との掛け持ちをしているようであれば、どの事業所で年末調整を受けるかの確認が必要です。
3-2. 年収103万円以下で所得税の源泉徴収がない
その年の全ての収入を合計した年収が103万円以下で、自社で所得税の源泉徴収をしていない従業員であれば年末調整が不要です。
所得税は年収103万円を超えた時点で課税されます。所得税の源泉徴収がなければ還付も追加徴収も発生しないため、年末調整を実施する必要がないのです。
ただし、年収103万円以下でも、自社で源泉徴収をしていた場合は年末調整を実施しましょう。本来であれば所得税の納税は不要な年収ですので、一度徴収した税金を返金しなく手はなりません。
3-3. 給与所得が年間2,000万円を超えている
年間の給与所得が2,000万円を超えている従業員は、年末調整ではなく個別の確定申告で所得税を納めることが定められています。該当する従業員への年末調整はおこなわないようにしましょう。
3-4. 災害減免法が適用されている
大規模災害により経済的に大きなダメージを受けてしまった被災者に対しては災害減免法が適用される場合があります。災害減免法の適用者には所得税の納税猶予期間が設定されますので、該当する社員に対する年末調整の未実施には罰則はありません。
関連記事:年末調整の障害者控除とは?その範囲や金額を詳しく解説
4. 年末調整に間に合わなかった場合の対応
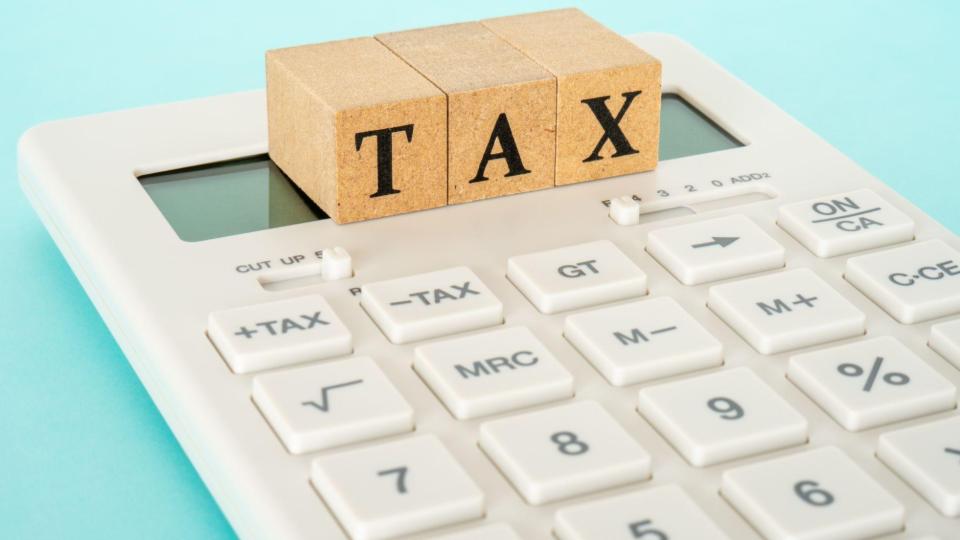
年末調整に間に合わなかった場合、どれだけ遅れたかによって対応が異なります。数日であれば事前に税務署に連絡しておくことで、受け取ってもらえるのが一般的です。しかし、大幅に遅れるのであれば、従業員自身で確定申告をしてもらいましょう。期限に間に合わあなかったといって年末調整を提出しないと、先述のとおり罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。
従業員自身で確定申告をおこなってもらう際は、確定申告の期限を伝えておきましょう。確定申告は原則として毎年2月16日から3月15日の間に完了する必要があります。確定申告の義務がありにも関わらず無申告だと延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生する恐れがあります。
5. 年末調整をスムーズに終える方法

年末調整をスムーズに終えるには次のような方法を検討してみましょう。
- 年末調整の代行サービスを活用
- スケジュールをたてておく
- 電子化を検討してみる
5-1. 年末調整の代行サービスを活用
年末調整は代行サービスを活用可能です。代行サービスを活用すれば、年末調整にかかる自社の負担を軽減できます。また、業務の負担だけでなく、人件費の削減も期待できるでしょう。
年末調整の代行サービスを利用する際は、依頼先の実績を確認することが大切です。依頼先のホームページや資料などを確認することで、実績を把握できます。また、自社からの問い合わせに対応できるカスタマーサポート体制が整っているかも確認しましょう。
5-2. スケジュールをたてておく
年末調整はスケジュールをたてておくことも、スムーズに進めるうえでのポイントです。例えば10月の下旬から年末調整の申告書を配布~説明を進め、11月に回収することで、法定調書の提出までに入念にチェック可能です。また、早めのスケジュールをたてておけば、不備があった場合でも余裕をもって修正に臨めます。
5-3. 電子化を検討してみる
年末調整は電子化することも可能です。年末調整を電子化すれば、書面で発生していた申告の不備を軽減できます。年末調整の電子化は経理担当者の事務処理の手間も軽減可能です。例えば、原票と申告書の内容を確認する作業が電子化されることで自動的にチェックできます。電子化によって年末調整の正確性が高まるため、経理担当者は修正対応の手間から解放されます。
6. 年末調整をやっていないと気付いたときは税務署に相談しよう

年末調整は従業員の収入に大きく関わる大事な手続きですので、ルールに従って間違いのないように実施することが大切です。特にスタートアップ企業では年末調整のノウハウがなく、正しい手続きができないことも考えられます。
会社の年末調整や所得税を所管しているのは税務署です。もしも年末調整の不備が発覚した場合や、年末調整をやっていないと気付いたときは管轄の税務署に相談しましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























