年末調整しないことによる罰則内容を詳しく紹介
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.9.27
OHSUGI

従業員へ賃金を支払う以上、雇用主は必ず年末調整を実施しなければなりません。年末調整は従業員の納税に深く関わるため、正しく実施されていない場合には雇用主に罰則が科せられることもあります。
この記事では年末調整をしないことによる罰則について詳しく解説します。人為的ミスで年末調整が正しくおこなわれなかった場合も罰則の対象となることがあるので、経営者の方は十分注意しましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 従業員の年末調整をしないと罰則がある
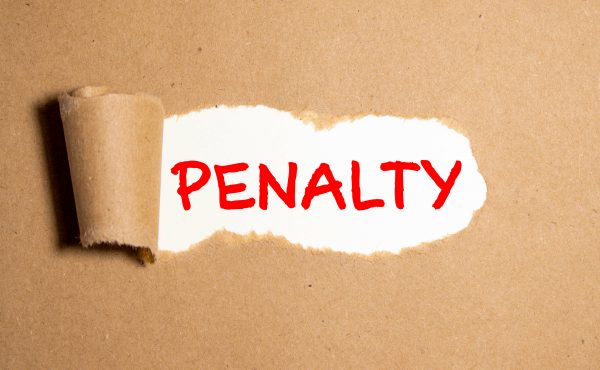
年末調整を故意におこなわなかった雇用主は罰則が科せられます。従業員の所得税を納めることは雇用主の義務です。対象者となる従業員には必ず年末調整を実施し、適切に所得税を徴収しなければなりません。
1-1. 雇用主には従業員の所得税を納める義務がある
会社は従業員に支払う賃金から所得税を源泉徴収し、従業員に代わって国に納めています。これは雇用主に課せられた義務です。
しかし、源泉徴収額は「従業員の賃金が1年間変動しない」という前提で概算されます。所得控除等が考慮される本来の所得税とは金額の乖離があるため、年末調整によって差額を清算しなければならないのです。
また、年末調整には、事業者単位で納税を取りまとめることでスムーズに税金を徴収するという国の目的もあります。仮に全ての労働者が個別で確定申告をおこなった場合、税務署が申告を処理しきれなくなるためです。
1-2. 年末調整を正しくおこなわないと罰則がある
雇用主が従業員の年末調整をしなかった場合、その会社は正しい所得税が納税できないということになります。税金の納付は国民の義務です。自らの利益のため故意に年末調整を実施しなかった雇用主には、懲役や罰金といった法的な罰則が科されます。
また、人為的なミスで手続きに不備があった場合も、適切に対応しなければ脱税と判断されてしまう恐れがあります。「税務署への書類提出を忘れていた」「計算を間違えてしまい納税額が少なかった」という可能性もゼロではありません。年末調整は計画的かつ正確に実施しましょう。
年末調整の業務を適切におこなわないことによる影響範囲は大きいです。抜け漏れのない対応をするために、年末調整の必要書類や提出期限を理解しておきましょう。当サイトでは、年末調整の流れや必要書類の書き方が理解できる資料を無料で配布しています。年末調整業務を抜け漏れなくおこないたい方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして、年末調整のミスや漏れの防止にお役立てください。
2. 年末調整をしないことによる会社(雇用主)の罰則を解説

年末調整を適切におこなわなかった雇用主には以下のような罰則が科せられます。
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科も可)
- 過少申告加算税と延滞税
それぞれの罰則が適用されるケースについて解説します。
2-1.「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されるケース
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられるのは以下のケースです。
- 年末調整を実施せず、従業員から適切な所得税を徴収していなかった
- 年末調整書類に嘘の記載や記録をし、税務署の承認を受けていた
なお、これらの行為は所得税法の第242条に抵触します。
2-2.「10年以下の懲役または200万円以下の罰金」が適用されるケース
以下のケースでは「10年以下の懲役または200万円以下の罰金(もしくはその両方)」が科せられる可能性があります。
- 従業員から源泉徴収した所得税を税務署に納付しなかった
このケースは所得税法第240条に抵触し、懲役刑と罰金両方が科せられる場合もあります。
2-3. 過少申告加算税や延滞税が課税されるケース
「過少申告加算税」は、所得税の納税後に納税額の不足を指摘された際に生じる税金です。新たに納める税金の10%相当額が課せられます。ただし、当初の申告税額と50万円のいずれか大きい方を超える部分については15%が適用されます。
一方で「延滞税」は納付期限を過ぎてしまった場合に、1日ごとに加算される税金です。納期限の翌日から2か月を経過する日まで年7.3%、それ以降は14.6%の税率が原則として適用されます。
故意的ではないにしても、これらのケースはちょっとしたミスから発生してしまうことも考えられます。年末調整の手続きは正確かつ計画的に進めることが大切です。
参照:No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁
参照:No.9205 延滞税について|国税庁
2-4. 多く支払った所得税の還付が受けられないケース
毎月従業員の給与から源泉徴収している所得税は、各種控除を加味していない税額のため、多く支払っているケースがほとんどです。
しかし、年末調整をしないと本来納めるべき税額が確定しないため、従業員たちが多く支払った所得税の差額分を還付することができません。
この場合、従業員たちが自ら確定申告をしなくてはならず、上述で解説した罰則に加え、従業員たちとの間にトラブルが生じるケースも想定されるでしょう。
3. 年末調整の期限遅れも罰則の対象になる

年末調整を正しくおこなっていたとしても、書類の提出や所得税の納付が遅れてしまった場合も罰則の対象となるケースがあります。ここでは年末調整のスケジュールや各種の期限、手続きが遅れてしまった場合の罰則を解説します。
3-1. 年末調整の所得税納付期限と書類提出期限
年末調整の手続きには以下の2つの期限があります。
- 源泉所得税の納付(年末調整後、翌年1月10日)
- 法定調書・住民税関連の書類提出(年末調整後、翌年1月31日)
年末調整で確定した所得税の税務署への納付期限は翌年1月10日です。なお、源泉所得税の納付に用いる「所得税徴収高計算書」には、年末調整で確定した所得税の過不足を記入する必要があります。
また、年末調整に伴う各種書類の提出期限は翌年1月31日です。期日までに「法定調書合計票」「支払調書」「源泉徴収票」を税務署に、「給与支払い報告書」を各従業員の居住する自治体宛てに提出します。
関連記事:年末調整はいつまでにやるべき?気になる提出期限とは
関連記事:年末調整の納付書とは?書き方や提出方法を詳しく紹介
3-2. 年末調整の基本的なスケジュール
一般的な年末調整のスケジュールは以下のようになります。
【11月下旬】
- 従業員の年間所得の確定
- 従業員に年末調整必要書類の記入を依頼
- 従業員から年末調整必要書類や各種証明書を回収
【12月】
- 年末調整の計算
- 従業員への所得税過不足の還付・追加徴収
【翌年1月】
- 源泉所得税の納付(1月10日期日)
- 年末調整関連書類の作成・提出(1月31日期日)
3-3. 従業員の提出遅れに法的罰則はない
従業員に記入を依頼する年末調整必要書類(扶養控除申告書・基礎控除申告書・保険料控除申告書)や各種証明書は、11月下旬~12上旬に提出期日を設けて回収します。
この提出期日は会社の都合で定めるものです。従業員の提出が遅れたとしても、社内での書類作成が1月31日までに終われば法的に問題はありません。しかし、社内の処理が滞る可能性があるため、余裕を持って作業ができるよう早めに提出期日を設定しましょう。
なお、1月31日までに書類を提出しなかった従業員は、年末調整をおこなうことができません。その場合は個人で確定申告をおこなうことになります。
▼遅れないように必要書類を集めるコツはこちら
年末調整の必要書類の集め方|スムーズに手続きするためには?
3-4. 税務署や自治体への書類提出が遅れる場合は罰則を受ける可能性もある
処理の遅れ等で必要書類の提出が遅れるとしても、すぐに罰則を受けることはありません。事前に管轄の税務署や自治体に連絡し、提出が遅れる旨を申し入れておけば大きな問題になることはないでしょう。
しかし、提出が大幅に遅れると話は別です。確定申告を実施していないとみなされ、最悪の場合は10年以下の懲役または200万円以下の罰則が適用される可能性があります。
また、従業員の納税も完了していないことになるので、各従業員が個別に確定申告をおこなわなければなりません。期日までに書類を提出することが原則ですが、万が一遅れるにしても事前に提出先に連絡し、早めに対応することを心掛けましょう。
3-5. 期日までに所得税を納税しなかった場合は資産の差し押さえもある
納付期日を過ぎても所得税が納税されなかった場合、最悪のケースでは資産の差し押さえまで発展することも考えられます。
そこまで至らなかったとしても、税金の滞納には延滞税が掛かり、1日ごとに金額が加算されてしまいます。会社の信用にも関わることなので、期日までに間違いなく納税するようにしましょう。
4. 年末調整をしなくても罰則がない従業員の例

年末調整を適切に実施していない企業には最悪の場合法的な罰則が適用されることもあります。しかし、中には年末調整の対象外となる従業員もおり、その人に対しては年末調整を実施していなくても問題ありません。ここでは年末調整が不要となる従業員の例を紹介します。
4-1. 「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出していない従業員
「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を自社に提出していない従業員に対しては年末調整をおこなうことができません。扶養控除申告書は、その労働者が年末調整をおこなう事業者に提出する書類です。
複数の職場を掛け持ちしているアルバイト社員で該当するケースが多く、既に他社で扶養控除等申告書を提出している場合は年末調整が不要です。
4-2. 年間の給与所得が2,000万円を超えている従業員
年間の給与所得が2,000万円を超えている従業員も年末調整の対象外です。この場合は年末調整ではなく確定申告により所得税を納めることが法的に定められています。
一般社員で該当する従業員は極一部ですが、会社役員クラスの従業員であれば該当するケースも珍しくありません。
4-3. 年間の合計所得が103万円以下かつ源泉徴収を受けていない従業員
年間の合計所得が103万円以下で、かつ源泉徴収を受けていない従業員は年末調整をおこなう必要はありません。年収103万円は所得税が非課税であり、また源泉徴収されていなければ還付する税金もないためです。
ただし、年収103万円以下でも所得税の源泉徴収がある従業員であれば、年末調整をおこなう必要があります。
関連記事:年収103万以下のアルバイトは年末調整しなくていい?
4-4. 災害減免法が適用されている従業員
大規模災害等で経済的に大きな負担を受けた場合、災害減免法が適用されることがあります。これにより所得税の納税に猶予期間が発生するので、該当する従業員は年末調整を実施しなくても問題ありません。
5. 罰則を受けずに年末調整をスムーズに進める方法

これまで説明してきたとおり、年末調整の提出期限に遅れた場合、罰則の対象となる場合があります。
しかし、年末調整は煩雑な手続きが多いため、どうしてもミスが起こりやすいものです。従業員数も多くなると年末調整の書類を回収するだけでも多くの時間を要し、結果として年末調整の提出期限に間に合わないという事態が起きてしまいがちです。
期日に間に合うよう年末調整をスムーズに進めるには、年末調整に対応した給与計算システムや人事労務管理システムを導入する方法があります。
システム上で保険料や控除額などの自動計算ができるため、ミスを減らして計算業務の時間短縮を図ることができます。また、年末調整の用紙をペーパーレス化ができるので、ミスがあった際の差し戻し作業も楽になり、書類を回収する必要もありません。
このように、年末調整の作業工数を大幅に削減できるので、年末調整の業務が課題となっている場合は、システムの導入を検討してみてもよいでしょう。
6. 年末調整は法令を遵守し期日内に手続きを済ませよう

会社による従業員の源泉徴収や年末調整は、国が効率的に所得税を徴収するための仕組みでもあります。雇用主は責任を持って自社の従業員の所得税を徴収し国へ収める義務があり、義務を果たさない雇用主には罰則も用意されているのです。
罰則を受けないためにも、年末調整は法令を遵守し期日内に手続きを終えることが求められます。特に年末調整に慣れていないスタートアップ企業は、事前にスケジュールを立て、必要な人員を配置して手続きに臨みましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























