年末調整の再調整は可能!方法やポイントをわかりやすく解説
更新日: 2024.3.8
公開日: 2021.2.26
OHSUGI
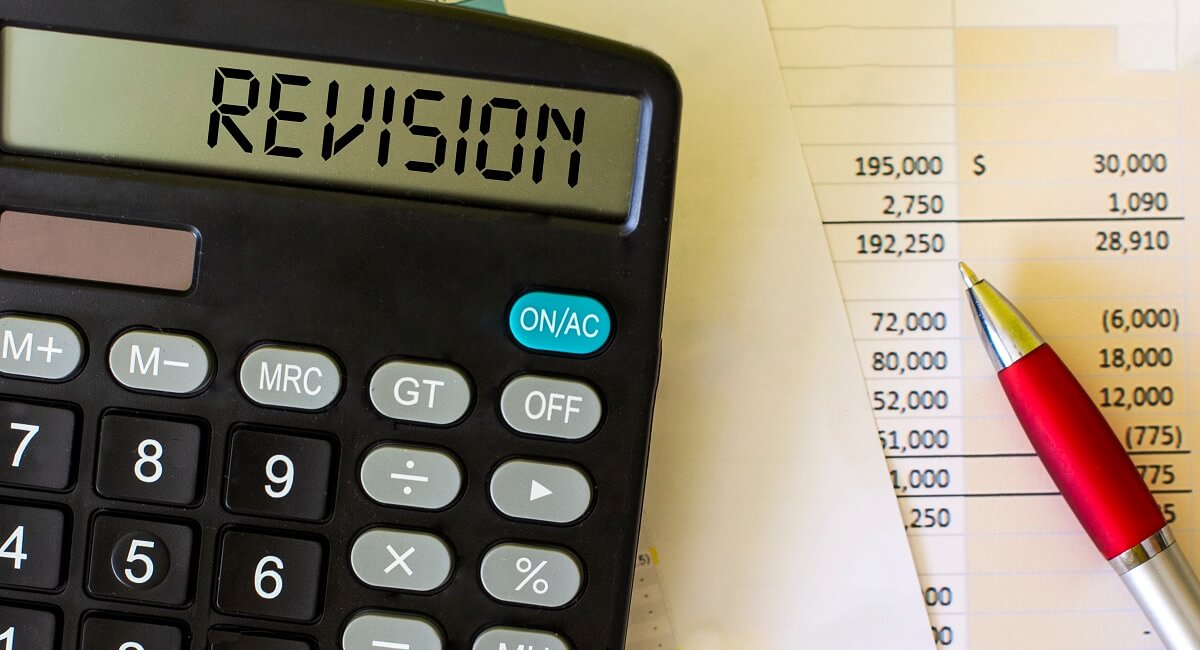
年末調整は、源泉徴収された税額と年税額一致させ、清算するために必要な重要な手続きです。そのため、年末調整で提出する合計所得は正確なものでなければいけません。
しかし、何らかの事情で合計所得が見積と異なることがあります。そのような場合は、年末調整をどのように処理するのでしょうか。
本記事では年末調整の再調整の方法やポイントをわかりやすく解説します。
目次
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」
「令和6年の年末調整における定額減税への対応方法が知りたい」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整の再調整は可能

従業員や、配偶者の合計所得額が見積りと異なり、配偶者控除あるいは配偶者特別控除額に影響がでることがあります。そのような場合は、配偶者控除等申告書を再提出し、年末調整を再調整をすることが可能です。
企業側は、年末調整の再調整が終了した時点で、従業員の給与所得に差が生じていないかどうか確認しなくてはいけません。年末調整の再調整が必要なケースとしては、下記の4つが挙げられます。
- 扶養親族等の人数に増減があったとき
- 配偶者控除や配偶者特別控除の対象である配偶者の年収に変化があったとき
- 年末調整の終了後、保険料などを支払ったとき
- 控除が適用となる申告を忘れてしまったとき
扶養親族等の人数の増減は、結婚して配偶者控除や配偶者特別控除が適用となったときや、子どもが扶養の対象外となった際などが該当します。
従業員の配偶者の年収が、年末調整で申告していた額よりも高い場合も、配偶者控除や配偶者特別控除の適用範囲を超過することがあります。
年末調整の終了後に、保険料控除の対象となる保険料を支払った際にも、再調整が必要です。
このほか、年末調整の申告自体を忘れてしまっていたときなども、やはり再調整の対象となります。
2. 年末調整の再調整が必要になるケース

年末調整の再調整が必要にも関わらず放置してしまうと、対象者は適切な所得税を支払えなくなったり、還付を受けられなくなったりします。そうした問題を発生させないために、年末調整の再調整がどのようなケースで必要になるのか、よくある例を知っておきましょう。
2-1. 年末調整後に扶養人数などに変更があった
扶養控除等申告書に記載されている扶養親族の数が、年末調整後に変更されることがあります。
扶養していた子どもが結婚して控除から外れたり、16歳未満の子どもが障がい者に認定されて扶養に入ったり、扶養人数が変わる条件はさまざまです。そのような場合は従業員本人から申告を受け、年末調整を再調整しなくてはいけません。
2-2. 年末調整後に配偶者や本人などの所得見積額に差額が生じた
配偶者控除と配偶者特別控除は、2020年から従業員本人と配偶者の合計所得によって控除額が決まる仕組みになりました。
そのため、従業員や配偶者の合計所得の見積額と、確定後の合計所得に差があり、その発覚が年末調整後であった場合は再調整をおこなわなくてはいけません。
2-3. 年末調整後に給与を支払った
年末調整をおこなったあとに、追加で給料を支払った場合も合計所得額に変更があるため、年末調整の再調整が必要になります。給与の追加支給がある場合にこのケースが発生しやすいです。
しかし、追加支給分を翌年度の改定分として支給する場合は、本年度の所得額の合計に変化はありません。そのため、年末調整の再調整は必要なくなります。
2-4. 年末調整後に保険料を支払った
年末調整では生命保険料や地震保険料も控除対象になります。そのため、年末調整後にこれらの保険料を支払った場合は、控除額を適正なものにするために年末調整の再調整が必要です。
従業員からの申告がないと企業側は気づけないため、従業員に保険料を支払うタイミングや年末調整後に支払った分の取り扱いについては事前に説明しておくとよいでしょう。
2-5. 年末調整後に住宅ローン控除の申請があった
住宅ローン控除は2年目からは年末調整で対応できます。従業員が申告を忘れていたり、遅くなって年末調整後に保険料控除申告書が提出されたりした場合は、年末調整の再調整で対応しなくてはいけません。
また、提出が住んでいる保険料控除申告書の控除額を修正する場合も、年末調整の再調整が必要です。
3. 年末調整の再調整をおこなう方法
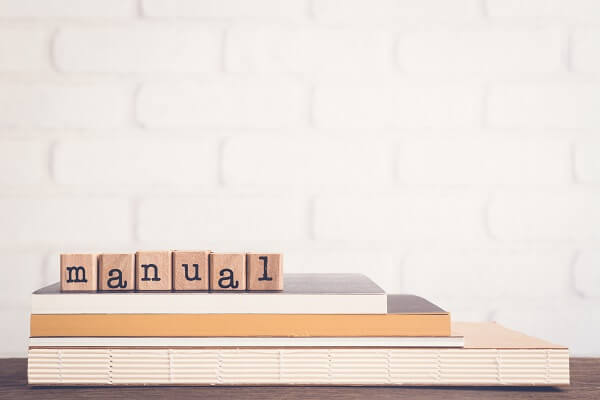
年末調整の終了後に記載内容の間違いに気が付いときや、明らかなミスがあった場合、あるいは申告内容と実態が異なるようなときには、年末調整の再調整が必要になることがわかりました。
どのように再調整をおこなうのか、再調整をおこなうタイミング別に確認していきましょう。
3-1. 「翌年1月31日以前」で「源泉徴収票発行前」の場合
下記の方法で再調整が可能です。
- 計算間違い:申告書の該当する部分に二重線を引き、二重線に重なる形で修正印を押し、正しい数字を記入する
- 扶養親族の人数の変化や保険料の申告漏れ:従業員より正確な内容を聞き取り、添付書類を確認後修正をおこなう
3-2. 「翌年2月1日以降」あるいは「源泉徴収票発行後」の場合
年末調整の修正期限(翌年1月31日)を過ぎてしまったとき、源泉徴収票発行後にミスが発覚したときには、企業側の修正は不可能です。
再調整するには、翌年2月16日から3月15日の間に、従業員自身が確定申告をおこなわなければなりません。
3-3. 過年度の年末調整に誤りがあった場合も再調整が必要
過年度分の年末調整に誤りがあったときにも、年末調整の見直しをする必要があります。過年度分の年末調整をおこなうのは、支払った税額が少なく追加徴収される場合か、もしくは支払った税額が多く還付される場合の2通りです。
- 追加徴収時は企業から税務署へ支払う:
追加徴収のケースでは、企業が税務署に従業員の不足税額を支払います。追加徴収分については、企業から従業員へ請求することになります。
- 還付については従業員自身が税務署に請求する:
支払った税額が多い場合は、従業員自身が税務署に請求をおこない、還付を受けます。
4. 年末調整の再調整に必要なもの

年末調整の再調整時は、記入後の書面を修正することになります。しかし、記載の誤りが多い場合は新たに書き直すことになり、その際には下記の書類が必要です。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票
- 源泉徴収票
- 支払調書
それぞれについて詳しく解説します。
4-1. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票
年間給与額の合計、給与から徴収した所得税額、弁護士や税理士などの外部に支払った年間報酬額や、その報酬より徴収した所得税額などを記載した書類のことです。翌年1月31日までに修正する必要があります。
4-2. 源泉徴収票
従業員や会社役員に支払った年間金額を個々にまとめた帳票です。提出が必要な源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」、もしくは「退職所得の源泉徴収票」となります。
4-3. 支払調書
支払調書にはいくつか種類がありますので、新たに提出が必要なときには、注意が必要です。
主なものは、下記の4つです。
- 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
以下、それぞれについて詳しく紹介します。
① 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
税理士や弁護士など、外部に支払った報酬等を記載したものです。一定金額を超過するものについては、支払調書を法定調書合計表に添付し、税務署へ提出する必要があります。
源泉徴収の対象となりうる報酬や金額などの支払いをした際に作成する支払調書で、1年間の報酬金額や、源泉徴収税の金額を記入します。1年間に5万円を超える場合に提出するのが一般的です。
② 不動産の使用料等の支払調書
地代や家賃など、不動産の賃借料を支払っているときに作成しなければならない支払調書で、借主や借りている不動産の情報、支払金額などを記入します。
家賃の場合、1年間の使用料の支払いが15万円を超過しており、個人に支払っている際に提出します。
③ 不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産を購入したときに作成する支払調書で、購入した不動産の情報や金額などを記入します。法人または一定の不動産業者である個人に対し、1年間の支払金額が100万円を超過する場合に提出するものです。
④ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産に関するあっせん手数料を支払った際に作成する支払調書で、支払先や料金を記入していきます。法人あるいは一定の不動産業者である個人に対し、1年間の支払金額が15万円を超過するときに提出が必要となります。
4-4. 市区町村に提出の必要な書類
年末調整で必要となるのは税務署に提出する書類だけではありません。
「給与支払報告書」は、住民税計算のため、従業員の住む市区町村に提出する書類です。総括表と個人別明細書の2種類があり、どちらも翌年1月31日までに提出します。
① 総括表
市区町村ごとに作成をおこなう、給与支払報告書の表紙のようなものです。給与を支払う企業名やその所在地、企業の全従業員のなかで、どのくらいの人数の従業員がその市区町村に住んでいるのかといった情報を記入します。
② 個人別明細書
給与や賞与等の年間金額や保険料控除等の金額情報を記載したもので、一般的に記載内容は源泉徴収票とほぼ同様です。
年末調整にかかわる必要書類の具体的な記載例は当サイトで無料でお配りしている「年末調整ガイドブック」でまとめてご確認することができます。年末調整の手続き方法も解説しておりますので、漏れなく年末調整を済ませたい方は、こちらからダウンロードして、ご確認ください。
5. 年末調整の再調整に期限はある?

年末調整の再調整はいつでもできるわけではなく、期日が決まっています。日数的な余裕はないため、再調整が必要な場合は早めに対応しましょう。
5-1. 企業内の再調整の期限は翌年1月31日まで
年末調整の再調整は、「従業員に源泉徴収票を発行する前」かつ「翌年1月31日まで」におこなうこととされています。
また、年末調整後であっても、翌年1月31日を過ぎていなければ、企業内での見直しは可能です。ただし、企業によっては、早い段階で締め切っているケースも少なくありません。
締切日をよくチェックしておくとともに、再調整が必要となる場合は早めに担当者に相談するとよいでしょう。
5-2. 従業員自身が確定申告する場合は翌年3月15日まで
「翌年2月以降」または「源泉徴収票発行後」に再調整する場合は、企業ではなく、従業員自身が翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をおこなう必要があります。
従業員が自身で確定申告する際は手間も多いため、期限内の再調整が望ましいでしょう。再調整の可能性があれば早めの連絡が肝心です。期限や必要書類などの情報についても、企業側から全従業員へしっかり周知しておきましょう。
6. 年末調整の再調整が必要なケースを把握して正しく提出しよう

年末調整の再調整は可能ですが、手続きが必要で期限も定められています。
翌年1月31日を過ぎておらず、源泉徴収票が未発行であれば、なるべく早めに担当者と従業員の間で連絡をおこない、再調整を進めましょう。
翌年1月31日を過ぎているか、源泉徴収票発行されたあとで再調整する場合は、翌年2月16日から3月15日の間に確定申告が必要です。
なお、過年度の年末調整に誤りがあった場合にも注意しましょう。追加徴収時は企業主体で動き、還付については従業員自身が請求しなければなりません。
年末調整をおこなったあとで再調整する場合、全ての内容を見直さなければなりません。年末調整の担当者や従業員本人にとって、非常に多くの手間と時間がかかることになります。
年末調整をおこなう際は、なるべく再調整が必要ないよう、事前に必要となる書類や期限についての情報を全従業員に周知することが大切です。もちろん、なかには扶養家族の増減など、仕方のないケースもあります。再調整の可能性があれば従業員に早めに申し出てもらう、担当者が従業員とその都度コンタクトを取るなどして、対処しましょう。
また、現在は年末調整の電子化が進んでおり、インターネットの活用によって、担当者・従業員の負担軽減が期待できます。積極的に導入するとよいでしょう。
▼電子化について知りたい方はこちら
年末調整の電子化はここまで進んでいる!気になる手続きの方法
年末調整手続きの電子化は義務?令和2年からの改正内容
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」
「令和6年の年末調整における定額減税への対応方法が知りたい」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
年末調整の関連記事
-

法定調書合計表とは?|書き方や提出方法、注意点を徹底解説
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.05.22
-

配偶者控除等申告書とは?書き方や提出義務について詳しく紹介
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.10.04
-

扶養控除等(異動)申告書の書き方や注意事項について解説
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.10.04































