年末調整で退職者がやるべき手続きを分かりやすく解説
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.2.5
OHSUGI
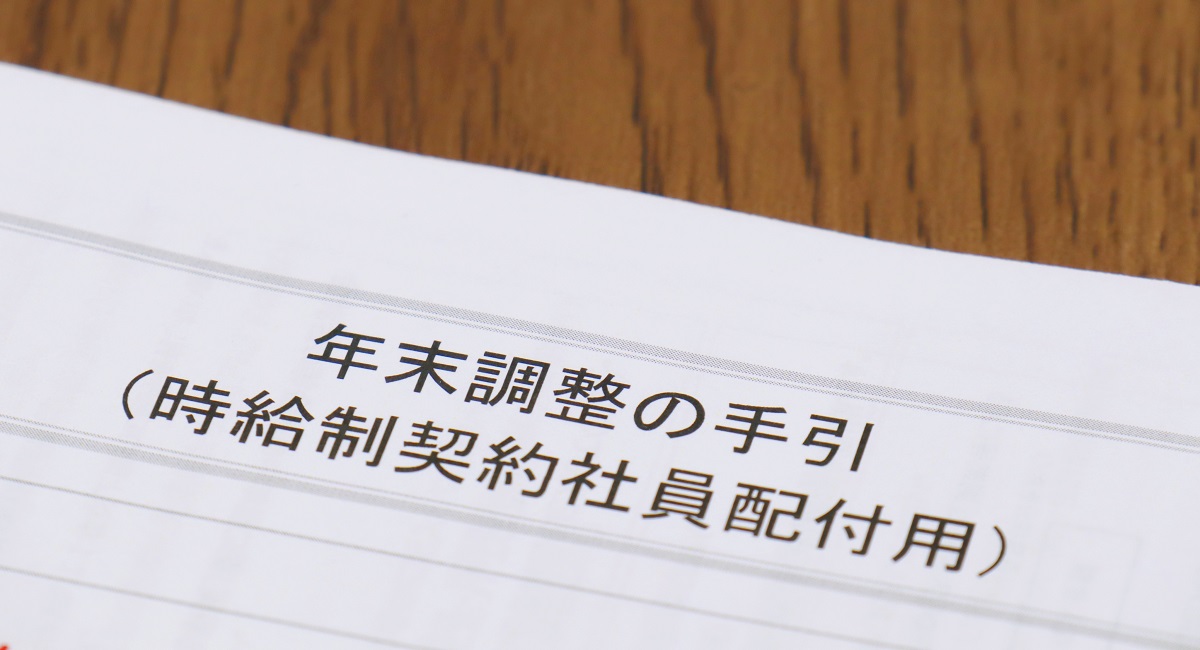
年末調整で退職者がやるべき手続きを怠ると、スムーズな年末調整をすることはできません。いつまでに提出するのか、必要書類は何かなど、正しい年末調整のためにおこなうべき手続と知識をしっかりと把握しましょう。今回は、年末調整で退職者がやるべき手続きについて説明します。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整とは
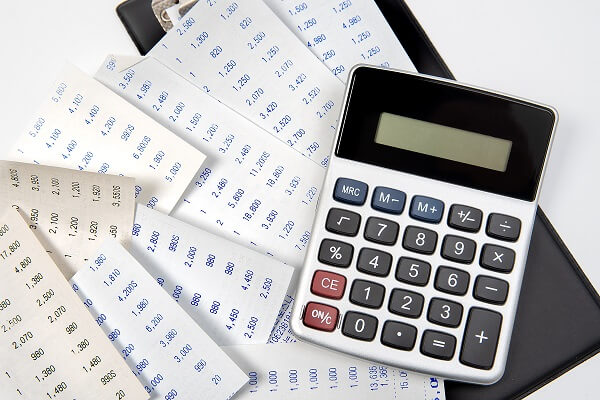
会社など給与の支払者は、役員又は従業員に対して給与を支払う際に、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をおこなっています。源泉徴収とは、所得税及び復興特別所得税を会社が給与からあらかじめ差し引くことです。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
源泉徴収は1年間に支払う給与の予定額によって決まりますが、その金額は会社が1年間に実際に支払うべき金額とは異なるケースがほとんどだからです。金額がズレる要因としては残業代や昇進などがあります。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。
関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説
関連記事:年末調整とは?その必要性や基本的な書き方について解説
2. 年末調整で退職者がやるべきこと

1年を通じて勤務している人のほか、1年の途中で退職して、同じ年内に新しい会社に勤めだし年末まで働いている人も年末調整の対象になります。この場合は、転職先で年末調整を受けます。例えば11月に退職し、12月に新たな職場に転職したのであれば、転職先での年末調整が必要です。
ただし、退職者が以下のケースに該当する場合は、年の途中でおこなう年末調整の対象となるため、元の会社で年末調整をおこなう必要があります。
- 死亡による退職
- 著しい心身の障害による退職(退職後に再就職の見込みがある場合は除く)
- 12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職
- パートで働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後、本年中に103万円の収入を超える見込みがない)
このように、年末調整業務は従業員全員がする必要があるわけではありません。一定の条件を満たした従業員が対象となるので、まずは誰が対象者で誰が対象外なのかを確認しておく必要があります。当サイトでは、年末調整の対象者を「はい」「いいえ」形式で確認することができる資料を無料で配布しています。そのほかにも年末調整に必要な業務がこれ一冊で理解できるようになっているので、年末調整業務に不安のある方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。
2-1. 退職者が退職した年の年末調整でやるべきこと
年末調整で退職者がやるべきこととして、新しい会社で働き始める前に、その年中に別の会社から給与の支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。
退職した会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認可能です。この確認ができないときには、年末調整をおこなうことはできません。
別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整をおこなう必要があります。
なお、年末調整をおこなう際に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は勤務期間に応じて月割りする必要はありません。例えば、5月に前の会社を辞めて、8月から新しい会社で働き始める人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は全額が認められます。
関連記事:年末調整で前職の源泉徴収票提出が必要なときの対応方法
2-2. 年をまたいで再就職する際は確定申告が必要
年をまたいで再就職する場合は、新しい勤め先で年末調整することができません。本人自らが確定申告をおこなう必要があります。再就職のタイミングが年内か否かによって、年末調整の扱いが異なるので注意しましょう。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。退職時に交付された源泉徴収票を基に、前年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、必ず期日内に確定申告をおこなうようにしましょう。
3. 年末調整を退職者がスムーズにおこなうポイント

1年の途中で退職して、同じ年内に新しい会社に勤めだして年末まで働いている場合、転職先では、退職した会社で得た収入と転職した会社で得た収入を合算して所得税を計算します。
そのために、退職した会社で退職するまでに源泉徴収された税額が記載された「源泉徴収票」が必要です。所得税法によって会社は退職日から1か月以内に源泉徴収票を交付する決まりとなっているため、退職した会社から源泉徴収票を受け取り、それを転職した会社に提出します。
源泉徴収票は、退職する日に受け取るケースと、あとから郵送されてくるケースがあります。給与所得の源泉徴収票をしっかりと用意しておくことが、年末調整を退職者がスムーズにおこなうポイントです。
年末調整では大きく分けて3種類の書類を提出する必要があります。またそれぞれに必要に応じて、添付書類も合わせて提出します。
3種類の書類とは以下のとおりです。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書
- 基礎控除申告兼給与所得者の配偶者控除等申告兼所得金額調整控除申告書
3-1. 扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは給与所得者が扶養控除、配偶者の控除などを受けるために用いる書類です。会社は従業員に対して、扶養控除等(異動)申告書を配布し、該当の年に1回目の給与を支払う前日までに回収する必要があります。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、年末調整時に翌年の申告書を提出してもらうのが一般的です。
3-2. 保険料控除申告書
給与所得者が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために提出する書類です。保険料控除申告書には次のような内容を記載します。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
3-3. 基礎控除申告兼給与所得者の配偶者控除等申告兼所得金額調整控除申告書
給与所得者が、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けるために提出する書類です。特に年間の合計所得額が2,500万円以下の場合、基礎控除が受けられるため、多くの従業員が提出する必要があります。従業員には年末調整時に提出してもらいます。
4. 年末調整で退職者がやるべき手続きをしっかりと押さえて正しい年末調整を

ここまで年末調整の概要、年末調整で退職者がやるべきこと、年末調整を退職者がスムーズにおこなうポイントなどについて説明してきました。年末調整で退職者がやるべき手続きについてよく理解できたという人もいらっしゃることでしょう。
年末調整を正しくおこなうと所得税の還付を受けられる場合もあります。年末調整で退職者がやるべき手続きをしっかりと押さえて正しい年末調整をおこないましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























