年末調整とは?その必要性や基本的な書き方についてわかりやすく解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2021.2.8
OHSUGI
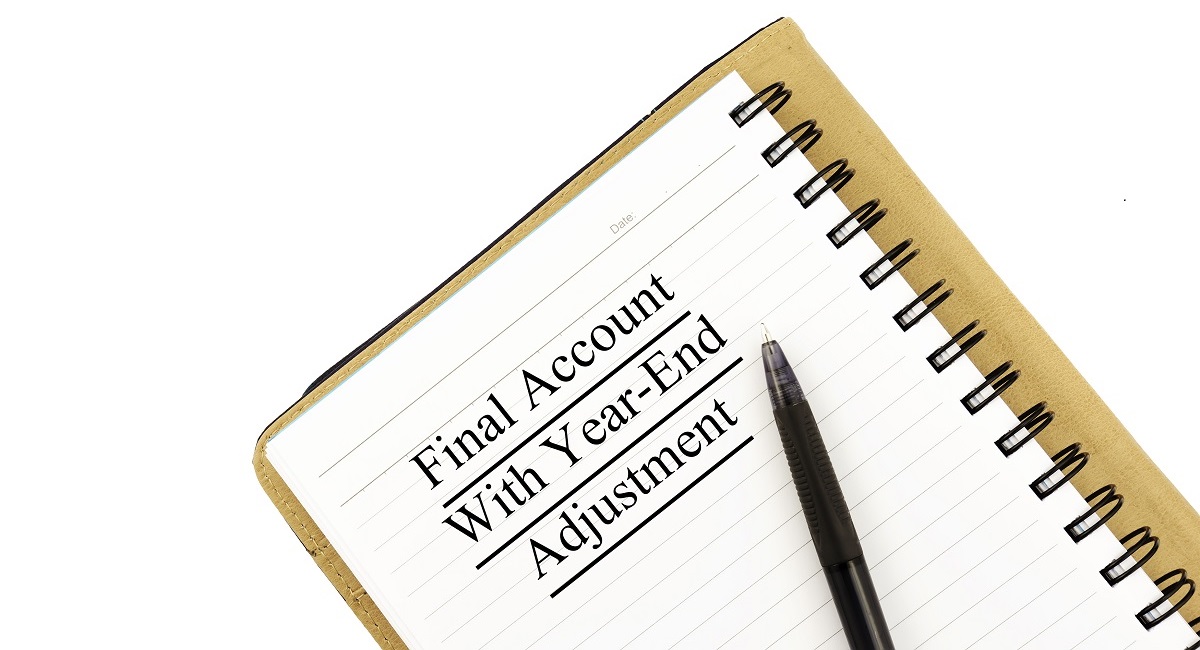
年末調整に関して正しい情報を知らないとどうなるでしょうか。正しく年末調整を行えば、所得税の還付を受けられる可能性もあるため、しっかりと情報を知るべきです。そこで今回は、年末調整に関して説明します。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整とは?

年末調整とは簡単に言うと、従業員が本来支払うべき所得税を計算し、その年の給与から徴収した所得税との差額を精算する手続きのことです
会社から給料を受け取っている役員や従業員は、基本的に年末調整をおこなう必要があります。
一般企業など役員や従業員に給料を支払っている事業体は、給料を支払う際に、所得税と復興特別所得税の源泉徴収をおこなっています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額は、必ずしも、その人が1年間に納めるべき税額とはなりません。源泉徴収する金額は、その1年間で払う給料の予定額を元に計算されているためです。
給料の支払いを受けた人は1年間に源泉徴収された所得税と復興特別所得税との合計額と、実際に支払われた給与に基づいて算出された1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額とを一致させる必要があります。この手続きのことを年末調整といいます。
1-1. 年末調整の対象となる人
年末調整は12月におこなう年末調整と年の途中でおこなう年末調整があります。
年末調整の対象となる人は、1年をとおして会社などに勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人です。
ただし、1年間に受け取る給与の総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により、その年の給料に対する所得税と復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人は、年末調整の対象となりません。
年末以外で年末調整をおこなう人は、以下のとおりです。
- 年の途中で海外支店などに転勤し、非居住者となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(一部除く)
- 12月中の給与の支払いを受けたあとで退職した人
- その年の給与総額が103万円以下の退職者(パート従業員など)
年の途中で退職した人でも、これらに当てはまっていない人は年末調整の対象になりません。
関連記事:年末調整の対象者になるケースとならないケースの違い
関連記事:外国人社員の年末調整手続きは必要?注意すべき3つのこと
関連記事:年収103万以下のアルバイトは年末調整しなくていい?
1-2. 確定申告との違いとは?
給与所得者に対しておこなうのが年末調整であるのに対し、確定申告はそれ以外の人に対しておこなう手続きのことを指します。主に、フリーランスや個人事業主、自営業など、会社に属さずに生計を立てている人が対象です。
毎年、1月から12月までに得た所得に対して、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をおこない、実際に納めた所得税の差額分を還付または納税します。
給与所得者でも、上述で説明した年末調整の対象外となる人は確定申告が必要です。また、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税等)受ける場合も、年末調整では控除できないため、確定申告で手続きしなくてはいけません。
1-3. 年末調整はいつまでに手続きが必要?
年末調整の書類は、翌年の1月31日までに税務署に提出する決まりとなっています。また、源泉徴収税の納付期限は翌年の1月10日までです。そのため、これらの期限に合わせて年末調整のスケジュールを組む必要があります。
一般的には、10月頃に従業員へ年末調整の書類を配布して記入してもらい、11月頃に書類を回収。12月には回収した書類に基づき年末調整の計算をおこなうという流れが多いです。
支店や営業所が複数あり回収に時間がかかるような場合は、前もってスケジュールに余裕をもたせておくのが望ましいでしょう。
2. 年末調整を正しくおこなう必要性

毎月の給与から控除される所得税は、あくまでも支払う給料の予定の額に基づいて計算されています。実際には、1年間で従業員の給与が変更になることケースや扶養家族などの数に変動が生じるケースもあるでしょう。
さらに、生命保険料を支払ったり、扶養家族が増えたりした場合には、所得金額から控除される制度があります。
これらの事情を反映させて計算した実際の所得税額と、毎月予定の給与額に基づいて控除された所得税額を比較すると、所得税の額にズレが生じることになります。そこで年末調整を行い、この税額のズレを調整する必要があるのです。
年末調整を正しく行わないと、多くの場合、所得税の過払いが生じたままになります。控除が可能でも控除がおこなわれず、源泉徴収された金額の方が多いケースが想定されるからです。
一方で、年末調整の業務には必要な手順が多く、正しくおこなおうとしても、不明点が発生しやすい業務でもあります。そのような年末調整に関する不明点を解決できるよう、当サイトでは、年末調整に必要な業務を一冊にまとめた資料を無料でお配りしています。年末調整業務に不安のある方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてミスのない年末調整業務にお役立てください。
関連記事:年末調整を忘れた場合に考えられるリスクと対処法を解説
関連記事:年末調整をしないとどうなる?考えられる5つのリスクを解説
3. 年末調整の基本的な書き方

年末調整にあたっては「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の3枚を記入して提出する必要があります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」については去年までとあまり変わっていないので、ここでは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の書き方を中心に説明します。
3-1. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書のひな形については、国税庁のサイトでご確認ください。
記載欄は少なくありませんが、会社が記載することになる箇所もあります。所轄税務署長、給与の支払者の名称、給与の支払者の法人番号、給与の支払者の所在地については、会社に記載を任せてもよいでしょう。
なお、給与の支払者の法人番号についてはこちらでは記載しないようにすべきです。また、押印するときは基本的にシャチハタを使用してはいけません。
3-1-1. 基礎控除申告書
給与所得の収入金額と所得金額は見積額を記載します。給与所得の金額は下の表に従って算出してください。
| 給与収入の金額 (a) | 給与所得の金額 |
| 1円以上 550,999円以下 | 0円 |
| 551,000円以上 1,618,999円以下 | (a)-550,000円 |
| 1,619,000円以上 1,619,999円以下 | 1,069,000円 |
| 1,620,000円以上 1,621,999円以下 | 1,070,000円 |
| 1,622,000円以上 1,623,999円以下 | 1,072,000円 |
| 1,624,000円以上 1,627,999円以下 | 1,074,000円 |
| 1,628,000円以上 1,799,999円以下 | (a)÷4(千円未満切捨て)…(b),(b)×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円以上 3,599,999円以下 | (a)÷4(千円未満切捨て)…(b),(b)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円以上 6,599,999円以下 | (a)÷4(千円未満切捨て)…(b),(b)×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円以上 8,499,999円以下 | (a)×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | (a)-1,950,000円 |
給与所得以外の所得の合計額については、給与所得以外の所得があれば合計額を記入してください。給与所得以外の所得がなければ、0と記載しましょう。本年中の合計所得金額の見積額については給与所得と給与所得以外の所得の合計を足した金額を記載します。
控除の額の計算は下の範囲のうち、自分の所得金額にあてはまるところをチェックしましょう。
● 900万円以下 (A)
● 900万円超~950万円以下 (B)
● 950万円超~1,000万円以下 (C)
● 1,000万円超~2,400万円以下
● 2,400万円超~2,450万円以下
● 2,450万円超~2,500万円以下
区分ⅠについてはA~Cを記載します。A~Cでなければ、何も記載しません。基礎控除の額は2,400万円以下であれば48万円以下、2,400万円超~2,450万円以下であれば32万円、2,450万円超~2,500万円以下は16万円と記載します。
3-1-2. 配偶者控除等申告書
配偶者控除等申告書については配偶者の氏名、配偶者のマイナンバー、配偶者の生年月日を記載します。また、配偶者と別居している際は、配偶者の住所を記入します。
もし配偶者が日本以外の国に住んでいる場合には、「非居住である配偶者」欄に〇を記入します。そして、「生計を一にする事実」の欄に配偶者にその年に送金等をした金額を記入します。
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の欄については、配偶者の給与所得の収入金額と所得金額は見積額を記載します。給与所得の金額は上の表に従って算出してください。
給与所得以外の所得の合計額については、配偶者に給与所得以外の所得があれば合計額を記入します。配偶者に給与所得以外の所得がなければ、0と記載しましょう。
区分2欄については下記の内のひとつを選んで記載します。
- 48万円以下かつ年齢70歳以上(昭26.1.1以前生)《老人控除対象配偶者に該当》
- 48万円以下かつ年齢70歳未満
- 48万円超95万円以下
- 95万円超133万円以下
配偶者控除・配偶者特別控除の欄は、控除額の計算の表に従って、自分に適用になるのは配偶者控除なのか・配偶者特別控除なのか、および、金額を確認して記載しましょう。配偶者控除・配偶者特別控除の内、当てはまらない方の欄は空欄で構いません。
▼結婚した場合にどんな手続きが必要かわからない方はこちら
年末調整は結婚したら何が変わる?書類の書き方のポイント
3-1-3. 所得金額調整控除申告書
申告書の「要件」欄に示された以下の4つの項目から、該当するものにチェックを付けます。
- あなた自身が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
- 扶養親族が特別障害者
- 扶養親族が年齢23歳未満(平10.1.2以後生)
「同一生計配偶者」とは、年末調整する人と同じ生計で生活する配偶者(一部除く。)で、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下)の人のことです。
要件のうち、同一生計配偶者あるいは扶養親族に関する項目にチェックを付けた際は、「☆扶養親族等」の各項目に、同一生計配偶者あるいは扶養親族の情報を記入します。同一生計配偶者については、「左記の者の合計所得金額(見積額)」が48万円以下であることが必要です。
要件欄でチェックを付けたのが特別障害者に関する項目である場合には、「★特別障害者」欄に、特別障害者に該当する事実を記載します。こちらは、障害の状態あるいは交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)といった情報を指します。
所得金額調整控除額は記入しません。
3-2. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
扶養の有無に関係なく、年末調整が対象となるすべての従業員に提出してもらう書類です。氏名、生年月日、住所、マイナンバー、配偶者の有無について漏れなく記載してもらいましょう。
詳しい書き方については、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:扶養控除等(異動)申告書の書き方や提出時期について解説
関連記事:年末調整の申告書の書き方を見本を用いながらわかりやすく解説
参照:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁
3-3. 給与所得者の保険料控除申告書の書き方
生命保険や地震保険など、各種保険の控除を受けるための書類です。
「給与所得者の保険料控除申告書」のほか、保険会社から送られてくる証明書の貼付も必要となります。証明書は、一般的に10月頃に送られてくることが多いので、従業員に忘れず貼付してもらうよう注意を促しておくと良いでしょう。
関連記事:年末調整の申告書の書き方を見本を用いながらわかりやすく解説
参照:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁
3-4. 住宅借入金等特別控除申告書の書き方
所定の要件を満たした人で、住宅ローンの控除を受けるために必要な書類です。住宅を取得したその年は控除を受けるのに確定申告する必要がありますが、2年目からは年末調整で手続きをおこなうことができます。
書類は対象となる従業員の元へ税務署から送られてくるため、その他の書類と合わせて提出してもらうようにしましょう。金額に関しては、金融機関が発行する残高等証明書に基づきながら記入してもらいます。
4. 納税の義務を果たすために年末調整を正しくおこなうことが重要です

ここまで年末調整の概要、年末調整を正しくおこなう必要性、給与所得者の基礎控除申告書兼 給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の正しい書き方について説明してきました。
年末調整の書類は、一つひとつの情報を正しく記載することが大切です。年末調整を経て適切な額の所得税を納付できます。担当者の方は、正しい書類の書き方を全従業員に共有しましょう。
▼書き方について知りたい方はこちら
年末調整の申告書の書き方をパターン別に詳しく解説
参考:
年末調整がよくわかるページ|国税庁
給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の記載例|国税庁
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























