年末調整の対象者とは?必要な書類や確定申告との関係も解説
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.9.14
OHSUGI
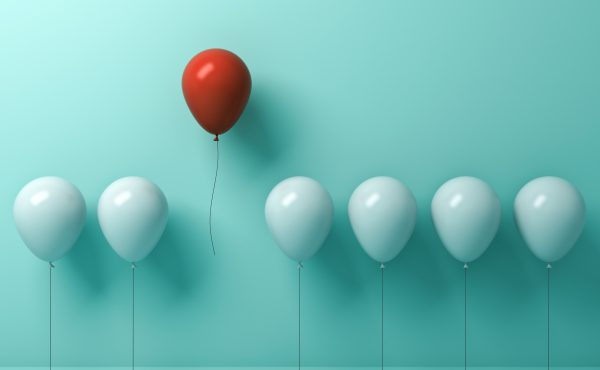
会社員であれば、基本的に全員が年末調整をおこないます。しかし、年末調整の対象にならない一部例外もあるため、両者の違いをしっかり理解しておきましょう。
本記事では、年末調整の対象者になるケースとならないケースの違い、年末調整をしても確定申告が必要なケースを解説します。年末調整をより確実に終わらせるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整の対象になるケース

まずは年末調整の対象者になるケースをみていきましょう。年末調整は原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している人すべてが対象です。正社員やパート、アルバイトなど雇用形態に関係なく実施しなくてはいけません。
年末調整の対象になる主な条件は下記のとおりです。
- 1年を通して会社に勤務している人
- 年の途中で就職して年末まで会社に勤務している人
- 年の途中で海外の転勤などによって非居住者となった人
- 死亡によって退職となった人
- 著しい心身の障害が原因で退職となった人
- 12月に支給されるべき給与等の支払いを受けたあとに退職した人
- パートやアルバイトで働いていた従業員が退職し、本年に支払われる給与総額が103万円以下である人
これらの条件に該当する場合は、年末調整をする必要があります。なお、4~7に該当する場合は、年末ではなく退職時に手続きする点に注意しましょう。
年末調整では、以上の条件を満たした人が対象者となります。ただ、これらの条件をテキストのみで確認するのは少しわかりづらいのではないでしょうか。当サイトでは、年末調整の対象者が図で理解できる資料を無料で配布しています。「はい」「いいえ」形式で答えるだけで対象者がわかるので、自社で誰が対象となるのかあいまいだという方は、こちらから「年末調整のガイドブック」をダウンロードしてご確認してみてください。
関連記事:年収103万以下のアルバイトは年末調整しなくていい?
関連記事:死亡退職した従業員の年末調整はどうする?手順や注意点
2. 年末調整の対象にならないケース

反対に年末調整の対象者にならないケースも解説します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している場合でも、年末調整の対象にならない一部例外が存在します。
年末調整の対象にならない条件は以下の通りです。
- 1年間の主たる給与の総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税と復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
- 2箇所以上の会社から給与の支払いを受けている人(ほかの会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している、もしくは年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合)
- 非住居者
- 同一の雇用主に継続的に雇用されない日雇労働者
以上に当てはまる人は年末調整の対象になりません。また、原則として12月31日時点で在籍していない従業員も年末調整の対象外です。例えば、転職によって退職した従業員が該当します。この場合は、転職先が年末調整を実施することになります。
3. 年末調整の流れ

年末調整の対象者がわかったところで、年末調整における作業の流れを解説します。
年末調整は1年間の給与所得にかかる所得税を算出する作業であり、扶養の人数や生命保険料などの金額を考慮して所得税額が決定する仕組みです。年末調整の大まかな流れは下記をご覧ください。
- 年末調整の準備をする
- 年末調整の計算をする
- 源泉徴収票を作成する
- 過不足の精算と源泉税を納付する
- 法定調書を作成する
毎年1月31日までに、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に源泉徴収票を添付して提出します。また、従業員全員の「給与支払報告書」を作成し、それぞれの住所に所在する市区町村ごとにまとめて提出します。
▼年末調整のやり方を知りたい方はこちら
年末調整のやり方・手引きをイチから分かりやすく解説
▼年末調整の期限を知りたい方はこちら
年末調整はいつまでにやるべき?気になる提出期限とは
4. 年末調整に必要な書類

年末調整に必要な書類は下記の4つです。
毎年11月頃に税務署から会社に送られ、その後従業員に配布します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(会社ではなく直接納税者へ送付)
このうち、「給与所得者の保険料控除申告書」は生命保険料控除を受ける対象者のみ、「住宅借入金等特別控除申告書」は住宅ローン控除を受ける対象者のみそれぞれ提出が必要です。
なお、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は令和2年の年末調整から新しく設けられた申告書です。
これら年末調整に必要な書類を事前に確認し、申請の抜けがないよう注意しましょう。ちなみに、年末調整で申請漏れがあった場合は自身で確定申告をしなければなりません。2度手間にならないよう慎重に進めていきましょう。
5. 年末調整をしても確定申告が必要になることがある

一般的な会社員の場合、年末調整を済ませればほかの申告等は必要ありません。しかし、雑損控除や医療費控除、寄付金控除については年末調整で適用されないほか、住宅取得等特別控除(初年度のみ)の還付も受けられません。そのため、会社に属していたとしても確定申告が必要となるケースもあります。
また、以下の会社員は確定申告をしなければならないため注意が必要です。
- 1箇所の会社から給与を受けており、給与所得以外の収入が20万円を超える人
- 2箇所以上の会社から給与の支払いを受けている人
- 1年間の主たる給与の総額が2,000万円を超える人
- 動産の貸付などで家賃収入がある人
- 災害による被害を受けて災害減免法の規定を用いて、源泉徴収の猶予や還付を受けた人
- 源泉徴収による規定が適用されない給与を受けている人
このように、会社員でも確定申告をおこなうケースがいくつか考えられます。その事実に気づかず放置していると、あとで取り返しのつかないことになりかねません。確定申告が必要となるケースについて、事前に従業員へ案内をしておいた方が良いでしょう。
6. 年末調整の対象者に手続きをしない場合のペナルティ
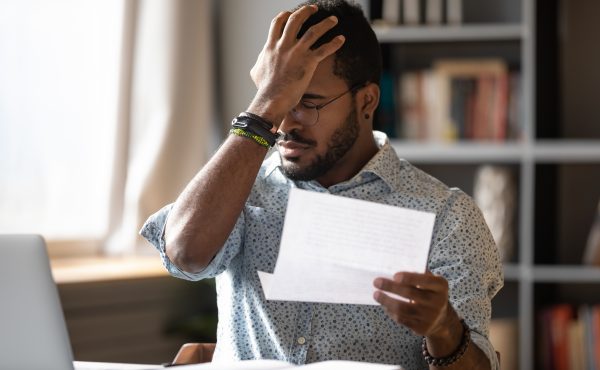
年末調整の対象者であるにも関わらず、手続きをしない場合にどのようなペナルティがあるのか解説していきます。ペナルティを科された場合、単に罰金を支払うだけでなく社会的な信用を失う恐れもあるので、くれぐれも注意が必要です。
6-1. 懲役または罰金刑が科される
年末調整は、所得税法によって会社に実施を義務付けている手続きです。
そのため、年末調整の対象者に手続きをおこなわなかった場合、所得税法の違反とみなされ「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される恐れがあります。
また、源泉徴収した所得税を故意に収めないなど悪質と判断された場合には「10年以下の懲役または200万円以下の罰金」といった重い量刑を科されることもあります。
6-2. 延滞税が発生する
年末調整の源泉税の納付期限は1月10日となっており、期限を過ぎると延滞税が発生します。
延滞税とは期限までに完納しない場合に課せられる税金であり、法定納期限の翌日から納付までの日にちに応じて利息が自動的に計算されます。
なお、国税庁が定める延滞税が発生する条件は下記のとおりです。
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
- 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
- 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
法定納期限の翌日から2か月を過ぎると延滞税の税率がさらに上がるため、納付漏れに気づいた際には速やかに税務署に連絡することが重要です。
▼罰則についてより詳しく知りたい方はこちら
年末調整しないことによる罰則内容を詳しく紹介
7. 年末調整が必要なケースと不要なケースを把握して正しい対応をしよう

年末調整はほとんどの会社員がおこなうものですが、例外も存在します。
また、年末調整に加えて確定申告が必要なケースもあるため、確認するとともに人事担当者は従業員から質問があった場合に答えられるようにしておく必要があります。
うっかりや知らなかったでは済まされない罰則が発生することもあるため、年末調整と確定申告の重要さを再確認し、間違いのない手続きができるようにしておきましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























