死亡退職した従業員の年末調整はどうする?手順や注意点とは

死亡により退職した従業員の年末調整は、源泉徴収や給与所得の源泉徴収票の発行方法が少し特殊です。本記事では、死亡退職した従業員の年末調整はどうするべきなのか、概要をご紹介します。発行方法や書き方についてしっかりと把握しておきましょう。
目次
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」
「令和6年の年末調整における定額減税への対応方法が知りたい」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 死亡退職した従業員の年末調整について

死亡退職した従業員は、死亡した時期によって対応方法が異なります。
また、年末調整は本来1年間の給与総額に対しておこないますが、年の途中に従業員が死亡した場合は、死亡した時点までに支払いが確定している給与総額を対象に年末調整をおこないます。
1-1. 給料の支給期を迎える前に死亡した場合
給料の支給日前に死亡した場合は、死亡後の給料は相続遺産として扱われるので、相続税が課税されます。そのため、源泉徴収はおこないません。
ちなみに支給期とは、「給与所得の収入金額の収入すべき時期」を指し、通常は支給期に給料が振り込まれます。よって支給期=支払日となります。
しかし、契約や株主総会の決議で支給期とは別に支払日が設定されている場合は、その支払日に合わせて給料が支払われるなら問題はありません。
給与の支給期前に死亡した場合、以下のようになります。
(例)
- 締め日→月末
- 死亡日→17日
- 給与の支給期・支給日→25日
この場合、死亡日以前に支払われる給与までが年末調整の対象となるため、会社は速やかに必要な手続きを行い、相続人に対して源泉徴収票を発行することが求められます。
1-2. 給料の支給期後に死亡した場合
給料の支給期を迎えてから死亡した場合は、死亡した従業員の給与所得になるので源泉徴収をおこないます。
先ほど触れた「支給期」が支払日と異なる場合でも、支給期を迎えてから死亡した場合は、源泉徴収の対象になります。
実際に支払われる前に死亡してもその従業員の給料になるので、混同しないように注意が必要です。
給与の支給期後に死亡した場合、以下のようになります。
(例)
- 締日→月末
- 死亡日→28日
- 給与の支給期・支給日→25日
このケースでは、給与が支給された後に死亡が発生したため、年末調整を行い、源泉徴収票を発行する必要があります。
1-3. 死亡退職者の年末調整はいつまでに行う必要がある?
相続手続きが発生した場合、死亡した従業員の年末調整は迅速に行う必要があります。給料は相続財産として扱われるため、正確な金額を算出し、円滑な相続手続きのために早めに年末調整を実施します。
特に、給与所得が2,000万円以上である場合や他の会社から給料を受け取っている場合は、準確定申告が必要になります。その際、源泉徴収票は申告に欠かせない書類となるため、申告期限である相続開始から4カ月以内に、会社は速やかに源泉徴収票を発行することが求められます。
2. 死亡退職した従業員の年末調整の手順
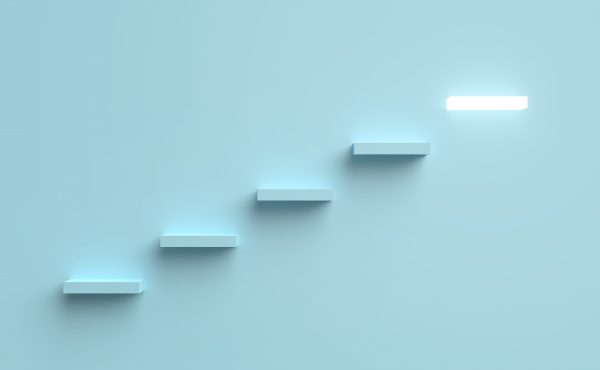
死亡退職した従業員の年末調整をおこなうにあたり、まずは相続財産となる給与の計算が必要です。その上で、年間の給与の総支給額から相続財産分を引いた額に対して年末調整しなくてはいけません。
ここからは、死亡退職した従業員の年末調整手順を具体例を交えながら解説します。
2-1. 相続財産になる給料を把握する
まずは給与のうち、相続財産として扱う給料を計算します。
少し分かりにくいので、会社Aと従業員Xを仮定してみましょう。会社Aでは給与を末日締翌月25日支払いにしており、従業員Xは9月17日に死亡したと仮定します。
- 会社A:末日締翌月25日支払
- 従業員X:9月17日に死亡
この場合だと、会社Aが従業員Xに給所得として支払うべきなのは、8月25日に支払が完了した7月までの分。8月分は9月25日に支払われ、死亡日が支給期を超えていないので相続財産として扱います。
2-2. 年末調整の対象になる給与を計算する
通常は1年間の給料に対して年末調整をおこないますが、年の途中で死亡した従業員の分はその時点までの給料で年末調整をおこないます。
8月の給料は相続財産になることがわかったので、年の始まりから7月分までが従業員Xの「年間所得」です。
- 1月1日~7月31日までの給与=従業員Xの年間所得(年末調整の対象)
- 8月1日~9月17日までの給与(死亡日)=遺族の相続財産
ちなみに臨時で支給される賞与(ボーナス)も死亡日よりも前に支給期が来ていれば給与所得になり、死亡日の後であれば相続財産となります。
従業員が死亡退職した場合も年末調整の対象となる場合は、対象金額を算出した後の年末調整の方法は通常と同じです。ただし、年の途中に年末調整が発生する可能性があるため、注意が必要です。
ほかにも年末調整を年の途中でしなければならないケースはいくつかあります。
年末調整のご担当者様の中には、年末調整を年の途中でしなければならないケースがどのような場合か、あいまいな方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、年末調整の対象者と年の途中で年末調整が必要なケースを図解でまとめた資料を無料で配布しています。年末調整の対象者があっているか確認したい方は、こちらから「年末調整のガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。
関連記事:年末調整の計算方法5ステップや注意点を分かりやすく解説
2-3. 遺族に給与所得の源泉徴収票を交付する
遺族は納税者が死亡した場合の確定申告「準確定申告」をおこなわなければならないので、遺族に対して「給与所得の源泉徴収票」の交付が必要です。
なお源泉徴収票の中央から下部分に「死亡退職」のチェック欄があるので、死亡退職に〇を付けて交付します。
なお、遺族は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をする必要があるため、速やかに年末調整をおこなって給与所得の源泉徴収票の交付を済ませましょう。
3. 死亡退職した従業員の年末調整をおこなう上での注意点

死亡退職した従業員の年末調整をおこなう上での注意点は次の3つです。
- 給与所得と遺産相続の区分
- 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除の対象範囲
- 配偶者控除・扶養控除の判定基準
また、以下のように給与の取扱いや各種手続きにも細心の注意が必要です。
- 遺族による相続税の申告漏れ
- 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の支払義務
- 給与の振り込み方法
- 退職金に関して
3-1. 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除の対象範囲
年末調整では、以下の保険料の支払額に応じて控除を受けることができます。
- 生命保険控除
- 地震保険控除
- 社会保険料控除
上記3つの場合は、死亡日までに支払った保険料が控除の対象額になります。
▼社会保険料控除について詳しく知りたい方はこちら
年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険の種類まとめ
3-2. 配偶者控除・扶養控除の判定基準
配偶者控除と扶養控除は少し特殊で、死亡日の現況によって計算されます。このとき月割計算はおこなえないので、注意が必要です。
具体的には、控除を受けるためには、死亡日までの合計所得金額を基に判断されます。たとえば、配偶者の総所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
また、扶養控除についても同様に扱われ、死亡日の時点で扶養しているかどうかが評価されます。たとえ年の途中で死亡した場合でも、死亡日までの全額を控除できるため、相続人にとっては重要な点です。このように、控除の判定基準には特有の条件があるため、正確な情報を把握することが求められます。
▼配偶者控除について詳しく知りたい方はこちら
年末調整は結婚したら何が変わる?書類の書き方のポイント
3-3. 遺族による相続税の申告漏れ
企業に勤める従業員が死亡した場合、給与分の年末調整をおこなったら、遺族に準確定申告のための引継ぎをしなければなりません。
遺族は給与所得の源泉徴収票をもとに準確定申告をおこなって納税する義務があるので、給与所得の源泉徴収票は確実に交付します。
なお、給与所得に含まれる範囲は、責任をもって年末調整の手続きをおこないましょう。
3-4. 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の支払義務
見落としがちな項目ですが、死亡した従業員の社会保険料は通常の退職と同じように扱います。
死亡した従業員は原則死亡の翌日に資格を喪失するので、5月21日に死亡した場合はその翌日5月22日が資格喪失日になります。
保険料は被保険者資格を取得してから、資格喪失の前月までの分を納めなければなりません。そのため、5月21日に死亡した従業員の保険料は、喪失した前月の4月分までの保険料を納めなければならないのです。
また、死亡日以降に発生する保険料は不要となりますが、雇用保険料については少し異なります。雇用保険料は、死亡日当月の給与に対して計算されるため、死亡後の給与からも天引きされることが求められます。
3-5. 給与の振り込み方法
死亡した従業員が受け取れなかった給与は遺族に支払いますが、振り込み方法で戸惑う方が多く見受けられます。
死亡した従業員の銀行口座は本人の死亡によって凍結されてしまうので、確実なのは手渡しか、相続人の銀行口座への振込です。
3-6. 退職金の取り扱い
従業員の死亡日を退職日とみなし、その1ヵ月後に退職金を支払う場合は、給料と同じく相続財産として扱われます。
退職金の支給期が1ヵ月後と考えると、わかりやすくなります。よって「退職所得の源泉徴収票」は提出せず、源泉徴収もおこないません。
4. 死亡退職した従業員は年間所得分のみで年末調整をおこなう

死亡した従業員の年末調整は、死亡日前に支給された給与のみでおこないます。死亡が発覚した時点で年末調整をおこなわなければならないので、年の途中でも手続きをおこないます。
支給期前に死亡したのか、支給期後に死亡したのかによって、給与所得と相続財産の区分が変わるのがポイントです。支給期が死亡日後にある場合、給料は相続遺産として扱うため、源泉徴収はおこないません。
また、年末調整と同時に、社会保険料の納付についても少し知識が必要となります。それぞれの手続きが間違いなくおこなえるよう、基本的な手順は繰り返し確認しておきましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」
「令和6年の年末調整における定額減税への対応方法が知りたい」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
年末調整の関連記事
-

法定調書合計表とは?|書き方や提出方法、注意点を徹底解説
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.05.22
-

配偶者控除等申告書とは?書き方や提出義務について詳しく紹介
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.10.04
-

扶養控除等(異動)申告書の書き方や注意事項について解説
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.10.04































