帳簿の正しい書き方は?仕訳手順や注意点、保存期間も解説
更新日: 2024.5.29
公開日: 2022.5.10
jinjer Blog 編集部

帳簿は決まった書き方があり、これを守らないと後から正しい金額を知ることができない可能性があります。
確定申告で税務署に提出する必要はないですが、税務調査の際は提出を求められることもあります。
本記事では帳簿の書き方について網羅的に解説していきます。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 帳簿の書き方やポイントとは?


帳簿は、事業にまつわるお金の動きを記録した書類です。
帳簿を作成することで、企業はその1年間の財務状況や経営状態を正確に把握することができます。帳簿は主要簿と補助簿の2種類に分類され、それぞれの帳簿に特徴や独自の記帳方法が定められています。
法人の場合、会社法で帳簿の作成が義務付けられています。これに違反した場合、30〜40%の重加算税が課される可能性があります。また、もし記帳のミスが虚偽の隠蔽とみなされた場合、100万円以下の罰金も課せられます。
個人事業主が帳簿を作成していなかった場合、所得税法第150条の規定により、青色申告の特別控除を取り消される場合があります。
また、帳簿を作成しないとペナルティが課せられるだけでなく、正しく経営方針を策定できません。全ての事業者は必ず帳簿を作成しましょう。帳簿書き方のポイントは自社だけではなく外部の目から見てもわかるように記載することが大切です。手書きであってももし税務署の調査が発生した場合であっても第三者が把握できるようにしておきましょう。
関連記事:帳簿を作成する理由や各種の特徴・違いをやさしく解説
2. 単式簿記(簡易簿記)と複式簿記とは
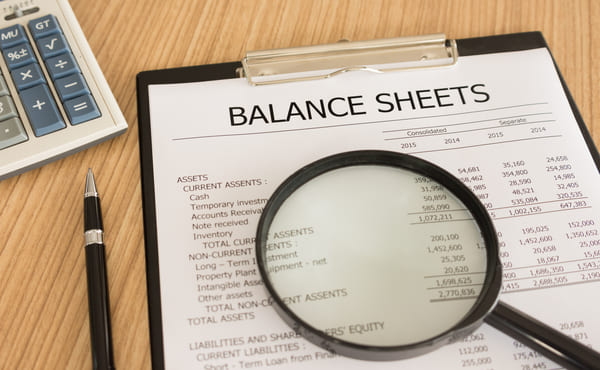
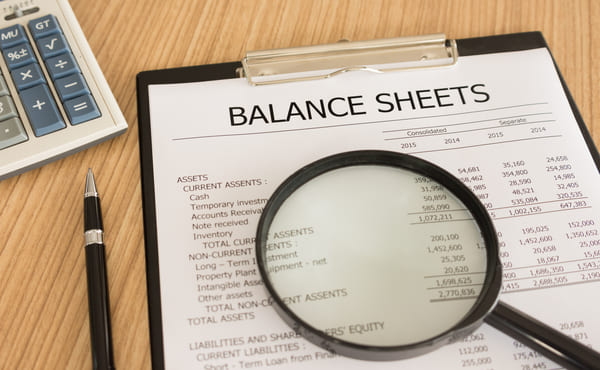
帳簿をつける際の記帳方法には、単式簿記(簡易簿記)と複式簿記の2種類があります。
単式簿記は収支のみを記帳するため、簡単でシンプルな記録になります。
一方の、複式簿記は、取引を複数の勘定科目で記載する記帳方法です。取引を借方、貸方という概念に分け、取引の結果、財政状況がどのように変化したのかを記録します。
2-1. 青色申告の場合
65万円の青色申告特別控除を受けるために、青色申告をおこなう個人事業主は、帳簿を複式簿記で記帳し、申告の際に貸借対照表と決算報告書を提出する必要があります。
総勘定元帳や仕訳帳、現金出納帳等の各種帳簿は提出義務はありませんが保管が義務付けられています。
単式簿記で記帳してしまったり、帳簿の保管義務を守っていないと、控除が受けられなくなってしまうため注意しましょう。
10万円の青色申告特別控除の場合は単式簿記の記帳で問題ありません。
2-2. 白色申告の場合
10万円の白色申告特別控除を受ける個人事業主は、単式簿記の帳簿をつければ問題ありません。法定帳簿と任意帳簿は保管が義務付けられているため、規定年数に応じてきちんと保管しておきましょう。
帳簿の種類には主要簿と補助簿があります。
ここでは、それぞれ書き方やポイントについて紹介します。
3. 主要簿の書き方と手順


主要帳簿は総勘定元帳と仕訳帳の2つで構成されています。それぞれ書き方が異なるので、詳しく紹介していきます。
3-1. 仕訳帳
仕訳帳とは取引の仕訳を記載したものです。
フォーマットはいろんな種類がありますが、すべて日付順で記載をするというルールがあります。
書き方はまず取引日を記載します。
現金や売上などの勘定科目を記載し、どの会社と取引をしたかもわかるようにしなくてはいけません。
この仕訳帳は損得勘定表に転記することになるので、それが完了しているかがわかるように元丁という項目に損得勘定表のページを記載します。
ページが記載されていれば、転記が完了したということです。
次に貸方、借方を記載します。
最後に取引ごとの区切りがわかるように区切線を引けば完了となります。
一つの取引はページを跨ぐことができないので注意してください。
関連記事:仕訳帳の扱い方とは?基本的な部分を5つの分類から詳しく紹介
3-2. 総勘定元帳
仕訳帳を元に作成するのが総勘定元帳です。
仕訳帳の内容から転記して作成します。
書き方ですが、まず取引日を記載します。
仕訳帳に相手勘定科目となっている科目を記載してください。
2つ以上ある場合は、諸口と記載します。
仕丁という項目に、仕訳帳のどのページの取引を転記しているのかを記載します。
借方、貸方のどちらなのかも記載し、残高の種類によって貸なのか、借なのかがわかるようにしてください。
最後に残高を計算して記入すれば完了です。
記載をする際には、勘定科目別におこなってください。
総勘定元帳は勘定科目ごとの記録をする帳簿なので、勘定科目別に記載をしないと情報の整理が難しくなってしまいます。
関連記事:総勘定元帳とは?作成する理由や転記方法、保存期間や形式など網羅的に解説
4. 補助簿の書き方と手順


次に補助簿の書き方についてです。
補助簿は主要簿よりも種類が多いですが、書き方はそれほど複雑ではありません。
補助簿を記載する目的さえ理解していれば、何を記載すればいいかがわかりやすいです。
補助簿の目的と併せて書き方を理解してください。
また、補助簿とは主要簿で記載していない情報がわかるものです。
そのため、主要簿を見れば内容がわかる項目に関しては、記載をしなくても問題ありません。
しかし、主要簿と項目が重複しても補助簿に記載しないと内容がわかりづらいという場合は、記載することをおすすめします。
会社ごとのフォーマットに差はあるので、ここで紹介した以外の項目を記載しなくてはいけない場合があるかもしれません。
その場合は、会社のルールにあわせて必要な項目を記載してください。
以下で紹介するのは、それぞれの帳簿に最低限記載が必要な内容についてです。
4-1. 現金出納帳
現金出納帳とは、毎日の現金の支出と収入から流れを把握するために利用するものです。
現金出納帳によって、それぞれの取引において残高がどれくらいあるのかを知ることが可能です。
現金出納帳の書き方は、まず日付を記載します。
そして取引の概要について、どの会社と、どんな取引をしたかがわかるように記載してください。
そしてこの取引で発生した支出や収入を記載し、残高を記載します。
この残高は手元にある預金残高と必ず一致します。
月を跨いで繰り越す際は、残高と支出金額、収入金額を次月繰越と記載をして現金出納帳の末に記載してください。
現金出納帳は取引が発生した順に記載をおこないます。
手元の残高と現金出納帳の残高が一致しなくてはいけないので、取引順に記載をしないと内容にずれが生じてしまいます。
現金出納帳に限らず、帳簿はまとめて記載をするという方がいるかもしれません。
しかし、まとめて記載をすると、取引の発生順がわからなくなってしまいます。
取引が発生するたびに、帳簿を記載するのを習慣にしておくことをおすすめします。
4-2. 仕入帳
仕入帳は商品の仕入れの詳細を知るために利用します。
総勘定元帳は仕入勘定を用いてまとめているので、仕入れの総額については知ることが可能です。
しかし、総勘定元帳では仕入れの個数や単価がわかりません。
そのため、仕入帳では仕入れの個数や単価を記載します。
仕入れの数に変化があったときに記載をするため、仕入れたタイミングだけではなく返品したときや商品の単価が変わったときにも記載する必要があるので注意をしてください。
総勘定元帳では網羅しきれない内容を記載しているのが、仕入帳と考えるとわかりやすいです。
4-3. 売上帳
売上帳とは売上の明細を記録するために利用されるものです。
総勘定元帳における売上の項目の補足をするのが主な目的です。
売上帳は売り上げ数や売り上げ単価を記載し、売り上げが発生した際に記入をおこないます。
先ほどの仕入れ帳と同じく、返品や値引きがあった場合でも同様に記載しなくてはいけません。
4-4. 経費帳
経費帳には、必要経費のうち仕入以外の費用を記帳します。(仕入については仕入帳に記載します。)
経費帳に記載するものとして修繕費、従業員に支払った給与、税金、交通費、文房具等の消耗品などがあります。
4-5. 固定資産台帳
固定資産台帳とは、減価償却が必要な資産について記録するものです。
自動車や建物など、販売目的ではなく、自社が事業で使用している資産のうち、1単位あたりの取得価格が10万円以上で使用想定期間が1年以上の資産が減価償却資産に該当します。
減価償却資産は原則として、法定耐用年数で取得時の費用を分割し、経年に応じて1年ごとに資産から経費に仕訳計上していきます。
固定資産の償却には、「定額法」と「定率法」があり、あらかじめ税務署に申請している償却方法で計算します。また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については改定前の基準である「旧定額法」「旧定率法」のいずれかを用いて計算しましょう。
各資産の耐用年数や償却率は国税庁のホームページで確認できます。
参考:国税庁 | 減価償却のあらまし
関連記事:帳簿の締め切りとは?4つの手順を徹底解説
4-6. 支払手形記入帳
支払手形記入帳とは、約束手形の振り出しや為替手形の引き受けの際に発生する支払手形の増減を記載するものです。
支払手形記入帳を確認すれば、支払手形の状況が把握できるようにしておかなくてはいけません。
支払手形は現金の代わりに利用されるため、支払手形記入帳には手形の受取人、振出人、取引内容、決済に利用する金融機関などを記載しなくてはいけません。
4-7. 売掛金元帳
売掛金元帳とは掛けで取引をおこなった際に、売掛金の残高がわかるように記載をする帳簿です。
売掛金は取引先によって異なるので、取引先ごとに項目を作成して記入をしなくてはいけません。
総勘定元帳では、どの取引先にどれくらいの売掛金があるのかは把握できません。それを把握するために利用するのが売掛金元帳です。
5. 簡易簿記と複式簿記の違い


簡易簿記と複式簿記とは記載する内容に違いがあります。簡易簿記の場合、増加した要因や減少した要因を記録していく帳簿です。お小遣い帳のようなイメージです。一方、複式簿記はひとつの取引を2つの要素にまで分解して取引を記録します。例えば固定資産を購入したのであれば固定資産の増加、現金の減少という2つの要素を総勘定元帳に記します。
簡易簿記と複式簿記は確定申告における控除額にも違いがあります。複式簿記を選択しているのであれば青色申告特別控除額は最大65万円です。これは青色申告特別控除額55万円に加えて、電子申告もしくは電子帳簿保存いずれかの要件を満たしている場合の控除額です。一方、それ以外の青色申告者の控除額は10万円にとどまります。
6. 帳簿の会計処理は3種類


帳簿の会計処理の方法は次の3種類です。
- 発生主義
- 現金主義
- 実現主義
6-1. 発生主義
発生主義とは費用、収益などが発生した際に帳簿に記す会計処理方法です。例えば5月31日に発生した取引の同日に請求書を発行した場合、6月30日に入金されるケースがあります。このような際、発生主義における売上日は5月31日です。
6-2. 現金主義
現金主義はお金のやり取りが実際に発生した際に帳簿に記す会計処理方法です。例えば5月31日に発生した売上の入金が6月30日にあった場合、入金日である6月30日に記帳します。現金主義は現金のやり取りが多い飲食店や小売店に適した記帳方法です。
6-3. 実現主義
実現主義とは費用、収益などが実現した際に記帳する方法です。例えば50万円の受注を受け、うち5万円を手付金として受け取るとします。この際、発生主義では契約が締結された時点で記帳します。一方、実現主義の場合、商品を納めて売り上げが確定してから記帳します。
7. 帳簿を記入する際の注意点


帳簿を記入する際は、数字の記入ミスがないようによく確認をしてください。
一度ミスをしてそれに気づかないと、後からミスを見つけるのは困難です。
帳簿を使って確定申告をおこなう際に、計算ミスがあると誤った金額を税務署に申告することにつながりかねません。
税務署から注意をされたり、場合によっては悪質なものと判断されたりすると、追加で税金をとられたりする可能性があります。
計算ソフトを利用すれば、計算ミスを防ぐことはできます。
しかし、数字の入力ミスをソフト上で発見するのは難しいです。
そのため、手入力で帳簿を作成するという方は、ミスが起こらないように慎重に確認をしながら記載してください。
また、帳簿ごとの目的も理解しておいてください。
帳簿は種類が多いので、どの帳簿にどんな内容を記載すればいいのかがわからなくなる場合があります。
帳簿ごとの目的を理解していれば、記載する内容に迷うことは少なくなります。
8. 帳簿のつけ方が分からない時の対応


帳簿のつけ方が分からない場合は公共機関や一般団体を頼る方法もあります。
白色申告の場合、税務署のホームページで配布されている記帳練習帳を参考に練習してみましょう。また、税務署では個人課税部門主催の記帳説明会が無料で開催されています。
青色申告に対しては、小規模事業者を中心に組織された非営利団体である青色申告会が、青色申告の提出方法や帳簿のつけ方等の指導をおこなっています。
また、自分で作成せずに会計ソフトを使うというのも有効な手段です。簿記の知識が無い方でも、質問に答え、項目を選択していくだけで自動で記帳や各種計算ができるものもあります。
9. 帳簿の保存期間


帳簿は一定期間保管することが法律で義務付けられています。法人税法では、帳簿の保存期間は7年、会社法では、決算書類や総勘定元帳等の帳簿の保存期間が10年と定められています。
法人の場合、帳簿の保存は10年と思っておくと良いでしょう。
また、個人事業主の場合は青色申告の場合は7年、白色申告の場合は法定帳簿は7年、任意帳簿は5年が保存期間となっています。
関連記事:法人における帳簿の正しい保存期間や適切な保存方法とは
10. 帳簿を書く際には主要簿と補助簿の違いや書き方を理解しておこう


主要簿と補助簿をあわせると帳簿の種類は非常に多いため、記入するのは大変と感じる方がいるかもしれません。
しかし、複雑なことはあまりなく、売り上げなどの数字を記入するだけなので、さほど難しくはありません。
単純な作業だからこそ、慣れてくるとミスが起こりやすくなります。
帳簿の作成ミスで、大きなトラブルにつながるケースもあります。
ミスを起こさないように、帳簿の作成は慎重におこなうようにしましょう。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















