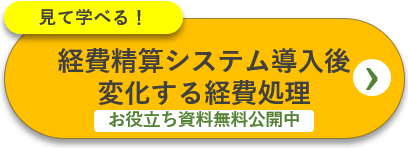経費処理時に請求書で経費計上できる?領収書との違いや経費精算の基礎知識
更新日: 2024.9.30
公開日: 2020.10.7
jinjer Blog 編集部
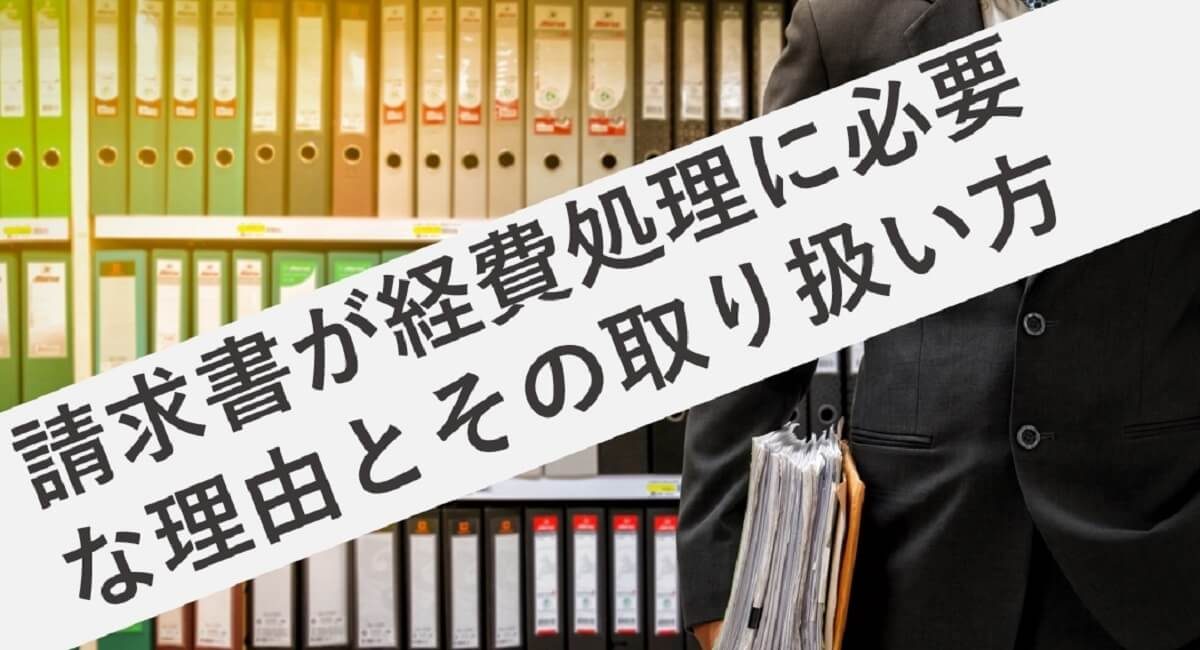
会社の経理部では日々たくさんの請求書が処理されています。
ほかの企業から商品を購入したり、サービスを提供してもらったりした場合には請求書が発行され、処理が必要になります。しかし時折請求書がないというケースも起こり得ます。
経費処理に請求書が必要な理由と、正しい取り扱い方について見ていきましょう。
目次
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説!
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 今更聞けない請求書と領収書の違い


まず経理処理を正しく理解するために、基礎知識としてそもそも請求書と領収書との違いを解説します。
1-1. 請求書とは
請求書とは、取引において代金の支払いを求めるための重要な書類です。請求書には、商品やサービスの提供に対する発生金額が具体的に記載されています。通常、請求書は取引が完了した後、支払いを受ける前の段階で発行されます。支払いを行う側は、この請求書を基に取引内容や金額を再確認し、適切な支払いを行います。
1-2. 領収書とは
領収書とは、代金の授受が完了したことを証明する重要な書類です。これは、支払われる側が支払う側から代金の受け取りを完了したことを確認するものであり、その金額が具体的に明記されています。
領収書はレシートでも代用できる?
レシートは領収書の代わりとして経費精算に使用できる場合が多いです。レシートは基本的に宛名なしでも問題なく使用できますが、法的に有効な証拠書類とするためには特定の条件を満たす必要があります。
具体的には、レシートに以下の5つの項目が記載されていることが重要です。1つ目は日付、2つ目は商品名、3つ目は取引の内容、4つ目は金額、そして最後に発行者の住所氏名です。これらが揃っていないと、経費として認められにくくなります。そのため、レシートを受け取った際には、これらの詳細がしっかりと記載されているかどうかを確認し、大切に保管するよう心掛けましょう。
1-3. 請求書兼領収書とは
請求書兼領収書とは、請求書と領収書の両方の役割を兼ねた書類です。通常、請求書は支払い前に発行され、領収書は支払い後に発行されますが、この書類は請求と同時に支払いが行われる取引の場合に利用されます。
そのため、実際の支払い時に発行されることが一般的です。中小企業の経理担当者は、この書類を受け取る際に支払いが完了していることを明確にするため、「了」「代済」「相済」といった表記があるかどうかを確認することが重要です。
2. 経費処理時に請求書で経費計上できる?
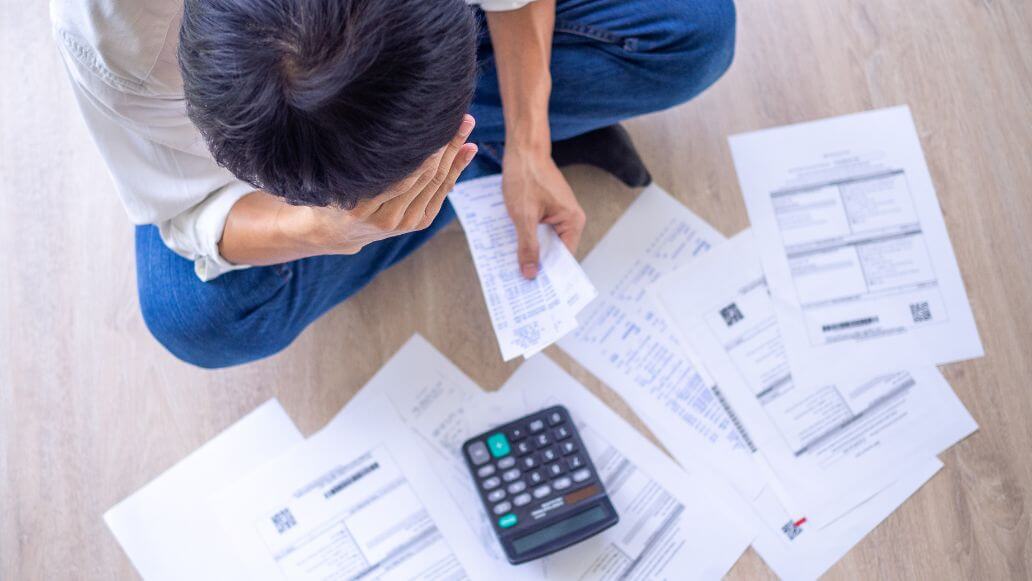
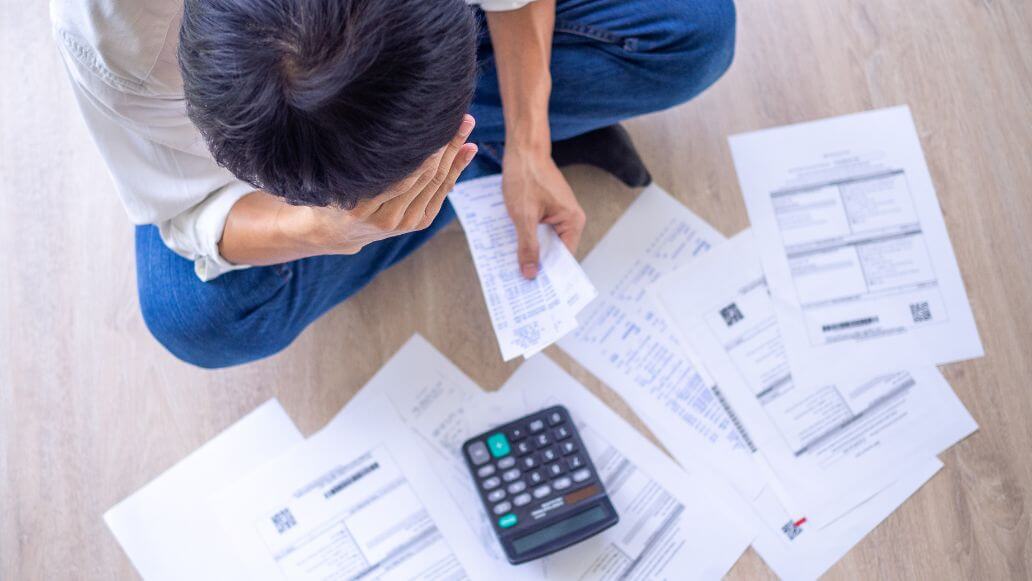
経費計上の際、請求書を使った経費処理は可能なのでしょうか。
請求書とは、支払い前に発行される書類であり、領収書とは支払い後に発行される書類です。これらの目的と発行時期は異なるため、通常、請求書は領収書の代わりにはなりません。しかし、銀行振込みやクレジットカード払いの場合には、請求書と明細書をそろえることで、領収書がなくても経費精算に使用できます。
また、先ほど説明した「請求書兼領収書」という「了」や「代済」と明記され、請求と支払いが一体になった書類であれば、領収書として経費処理に活用することが可能です。
関連記事:経費処理の重要性や効率的におこなうための5つのポイント
3. 請求書を領収書代わりにして経理処理する際の注意点


それでは実際に請求書を利用して経理処理に出す場合の注意点を解説します。誤った対応がないよう予め確認しておきましょう。
3-1. 収入印紙が必要
請求書を領収書代わりに経理処理する際には、特に収入印紙の貼付に注意する必要があります。
具体的には、5万円以上の取引に対しては収入印紙を貼付し、印紙税を納付しなければなりません。これは、金銭や有価証券の受領を証明する書類が対象となるためです。経理担当者として、この点を誤ると、後に税務署から追徴課税を受ける可能性があります。
したがって、請求書を領収書代わりに使用する際には、取引額をしっかり確認し、適切に収入印紙を貼付することが極めて重要です。
3-2. 電子請求書の場合は収入印紙が不要
一方で電子請求書を発行し、電子データのみで管理する場合、収入印紙は必要ありません。また、クレジットカード払いの場合、請求書と明細書が領収書代わりに使用できることも覚えておきましょう。
ただし、店舗で領収書が発行された場合には、請求書や明細書ではなく、実際の領収書を経費精算に用いる必要があります。正しい知識を持って経費処理を行うことで、トラブルを避けることができるでしょう。
4. 経費処理上での請求書の適切な取り扱い方

請求書は経理部が受け取り経理処理をしますが、適切な取り扱い方をしなければなりません。では法律上適切に請求書を取り扱うための3つのポイントを見ていきましょう。
4-1. 必要事項が記載されているか確認する
請求書には必須の記載項目がいくつかあります。これらの項目が欠けていると、適切な経費処理がおこなえなくなってしまうので注意が必要です。
請求書の必須記載項目は、
- 取引の日付
- 取引先の社名
- 取引内容
- 金額
- 取引をした相手の名前
- 振込先
- 支払い期限
などが挙げられます。もし足りない項目があれば、すぐに取引先に連絡して請求書を再発行してもらう必要があるでしょう。
インボイス制度に対応した請求書のポイント
さらにインボイス制度に対応した請求書を作成する際には、3つの重要な項目を正確に記載する必要があります。
まず、インボイス発行業者の登録番号を明記しましょう。これは事業者が正規のインボイス発行業者であることを証明するため、欠かせない情報です。次に、税率ごとに区分された消費税額を記載します。これにより、消費税の計算が明確になり、経費処理がスムーズに行えます。最後に、税率ごとに区分された合計金額と適用税率を明示してください。この情報は、各税率の総額を確認するために必要です。
従来の区分記載請求書と異なり、適格請求書では税率ごとの税抜金額と税率ごとの税額も求められるため、細部に注意を払いましょう。
4-2. 請求書の正しい保管方法
請求書は数年間にわたって保存しなければならないので、できるだけ管理しやすい方法を考える必要があります。もっとも一般的なのは紙のままファイルに保存する方法です。ただし保存環境によっては劣化したり、文字が見えなくなってしまったりする恐れがあるので注意が必要です。
続いてマイクロフィルムで保管する方法があります。規定のマイクロフィルムリーダーやプリンターといった機材が必要になりますが、より効率的に請求書を保管できます。ただしマイクロフィルムが使用できるのは保存期間の最後の2年間だけと定められています。
3つ目の方法が電子データです。2005年に施行されたe-電子法により、請求書を電子データとして保存できるようになりました。ハードディスクなどに請求書を保存でき、効率よく請求書を管理できます。ただし真実性の確保や可視性の確保、税務署長の承認などいくつかの条件をクリアしなければなりません。
4-3. 請求書は保管義務がある
請求書は商取引が確かにあったことを証明する証憑書類であるため、法人税法・所得税法・消費税法に基づき一定期間の保管義務があります。法人の場合には保存期間は7年、個人事業主の場合には5年と定められています。ただし個人事業主の方も帳簿は7年保存する必要があるので、請求書もあわせて7年保管しておくと安心かもしれません。
ここで注意が必要なのが、請求書を保存し始める日付、つまり「起算日」です。請求書の日付が起算日になるわけではありません。起算日は、事業年度の確定申告書の提出期限が終わった翌日となります。
たとえば9月決算の法人があったとします。すると確定申告の期日は11月30日となるので、請求書を保管する起算日は12月1日、保存期間は7年後の11月30日までということになります。ただし欠損金が発生した事業年度に関しては、平成20年4月1日以降の請求書を9年、平成30年4月1日以降の事業年度で10年の保管義務が生じます。
5. 経理処理後の請求書や領収書の保管期限
 請求書や領収書の保管期限は、経理処理後の適切な書類管理において非常に重要ですので詳しく解説します。
請求書や領収書の保管期限は、経理処理後の適切な書類管理において非常に重要ですので詳しく解説します。
5-1. 請求書の保管期限
法人税法に基づき、請求書は原則として7年間の保管義務があります。個人事業主の場合には5年と定められています。これは、税務調査などの際に企業の取引の正確性を証明するためです。
ただし個人事業主の方も帳簿は7年保存する必要があるので、請求書もあわせて7年保管しておくと安心かもしれません。
ここで注意が必要なのが、請求書を保存し始める日付、つまり「起算日」です。
請求書の日付が起算日になるわけではありません。起算日は、事業年度の確定申告書の提出期限が終わった翌日となります。
たとえば9月決算の法人があったとします。すると確定申告の期日は11月30日となるので、請求書を保管する起算日は12月1日、保存期間は7年後の11月30日までということになります。
ただし欠損金が発生した事業年度に関しては、10年(平成30年4月1日以前に開始した事業年度は9年間)の保管義務が生じます。
5-2. 領収書の保管期限
領収書の保管期限は申告の種類によって異なり、正しい処理を行うための基礎知識です。具体的には、青色申告を行う場合、領収書は7年間保管する義務があります。これは税務調査に対する備えであり、正確な経営状況を示すためにも重要です。一方で、白色申告の場合は、領収書の保管期限は5年間です。どちらの申告方法を選択する場合でも、法的な要件を確実に満たすために、定められた期間中は領収書を適切に保管することが求められます。また、効果的な経費処理を行うために、領収書を分類し、整理して保管することも欠かせません。このように、領収書の保管期限を正確に把握し遵守することが、中小企業における健全な経理運営につながるのです。
5-3. 保管方法
さらに、保存方法としては、紙媒体での保管が基本ですが、適切にスキャンして電子データとして保存することも認められています。電子保存を選択する場合は、当局の要件を満たすことが重要です。期限内に破棄しないよう定期的な確認と管理を徹底することで、経費処理の信頼性を高めましょう。”
6. ルールを理解して計上から仕訳まで正しい経費処理を!

請求書があれば、経理処理を適切におこない、どのような取引がおこなわれたかを明確にできます。税務調査や今後の取引をスムーズにおこなえるよう、取引先の企業に対して毎回請求書の発行を依頼するのが望ましいでしょう。
経費処理したあとも、法律に則って請求書をしっかり保存しておけば、税務上のトラブルも未然に防ぐことができます。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説!
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
経費処理の関連記事
-

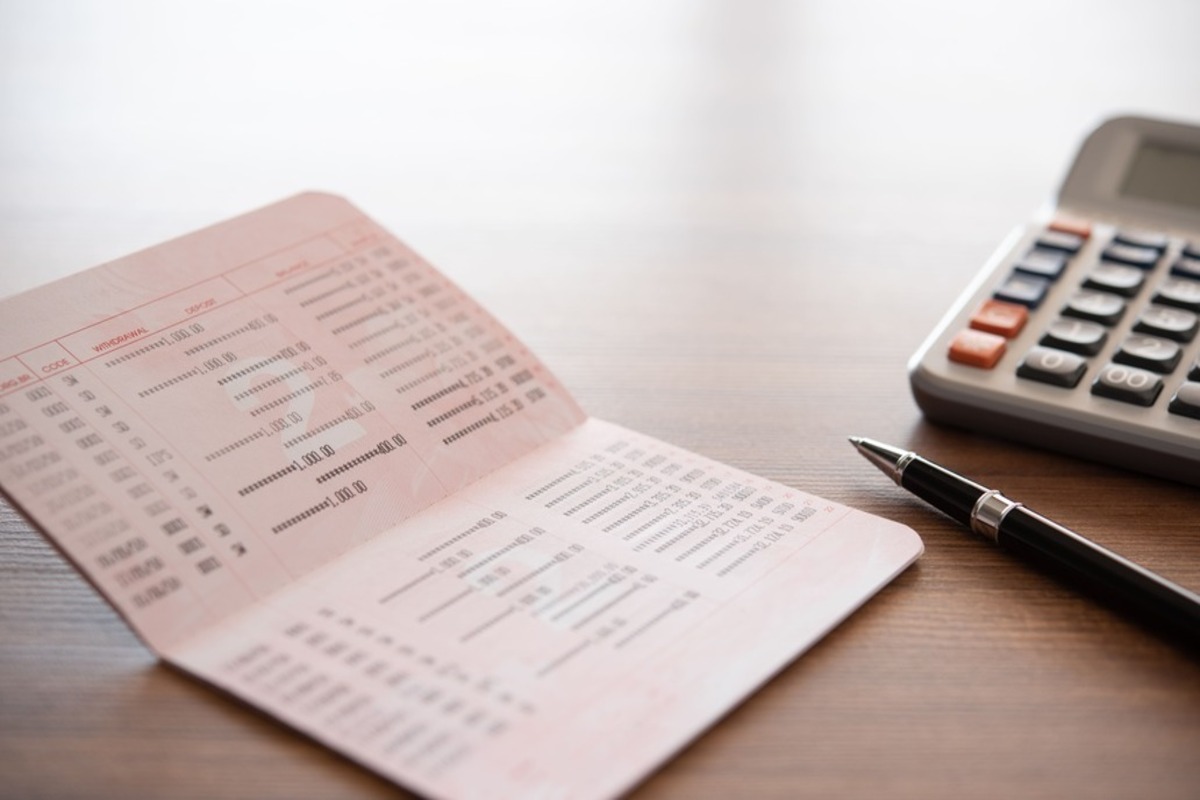
経費立替の注意点は?業務負担を減らす方法も合わせて解説
経費管理公開日:2023.05.10更新日:2024.01.30
-

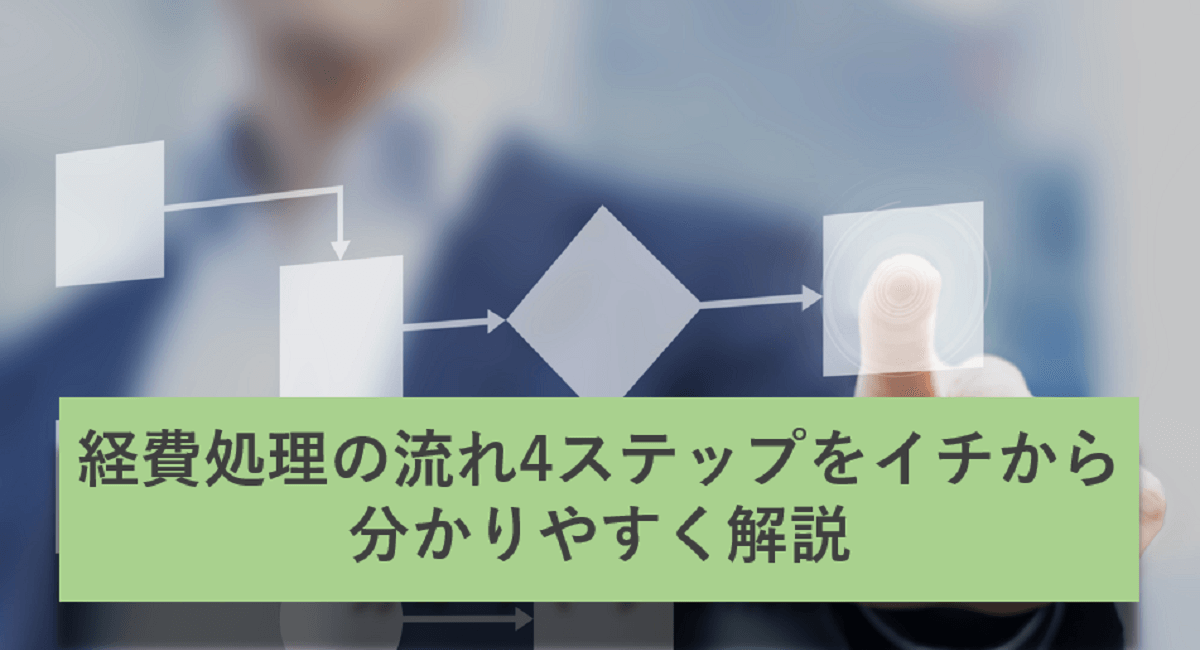
経費処理の流れを効率化するポイントとよくある問題点を解説
経費管理公開日:2020.10.23更新日:2024.10.10
-

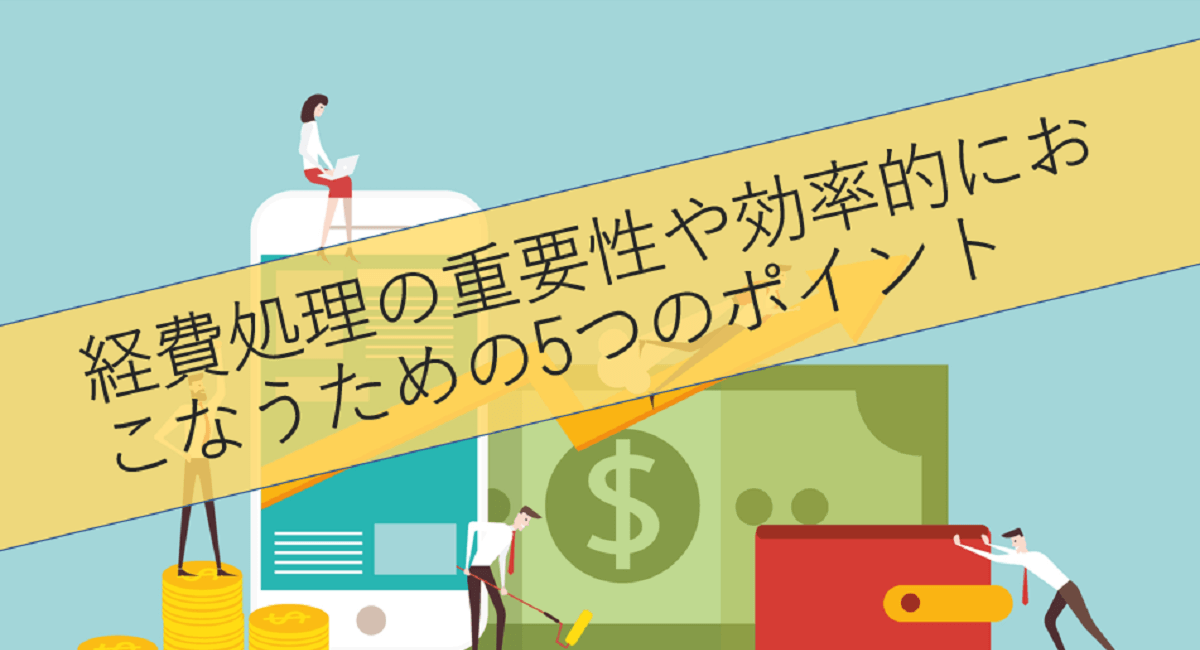
そもそも経費処理とは?効率的におこなうためのポイントをわかりやすく解説
経費管理公開日:2020.10.21更新日:2024.10.07