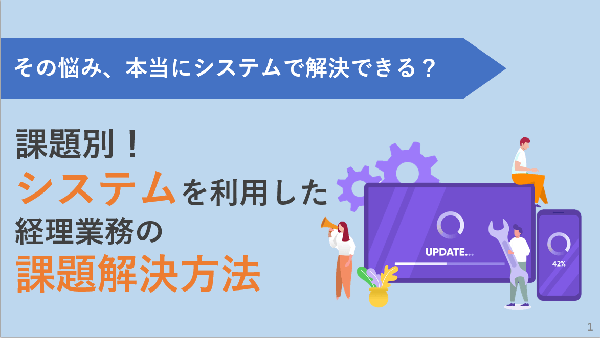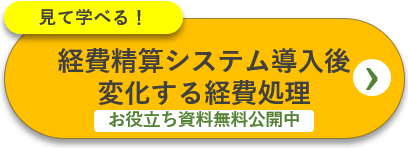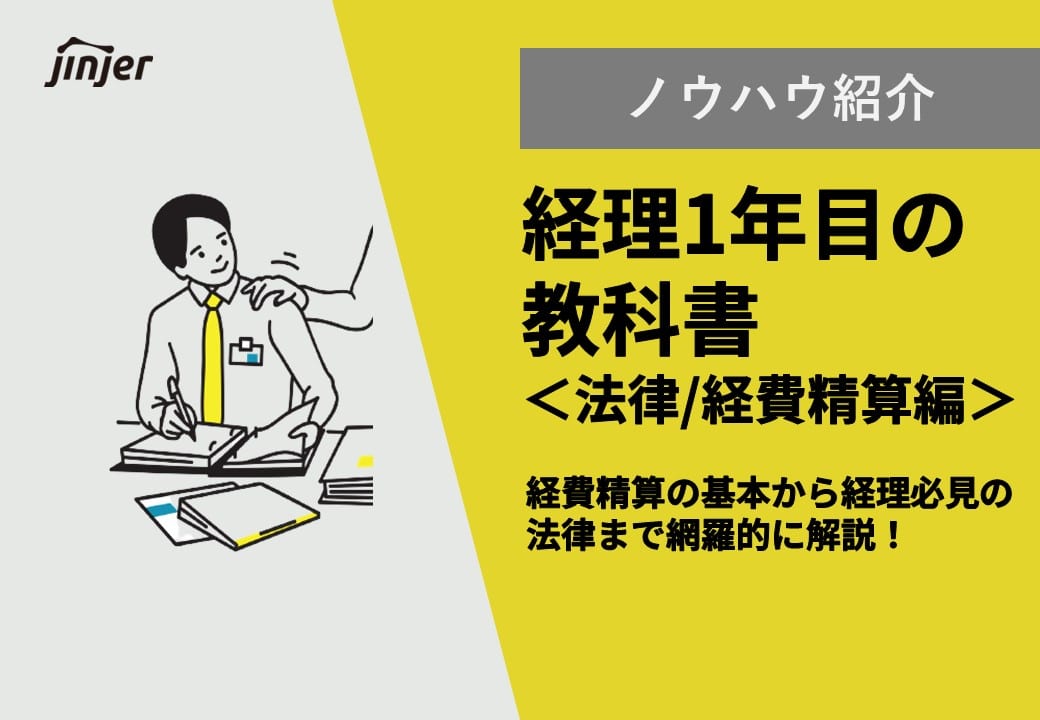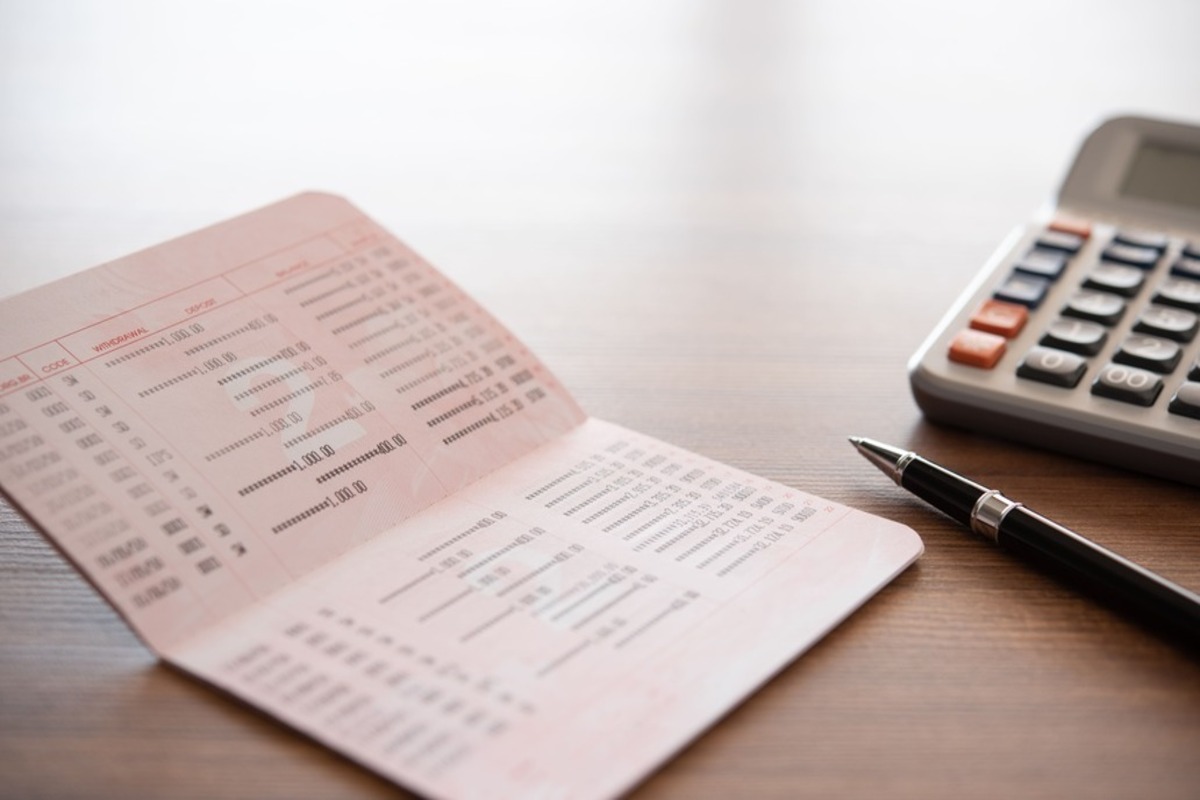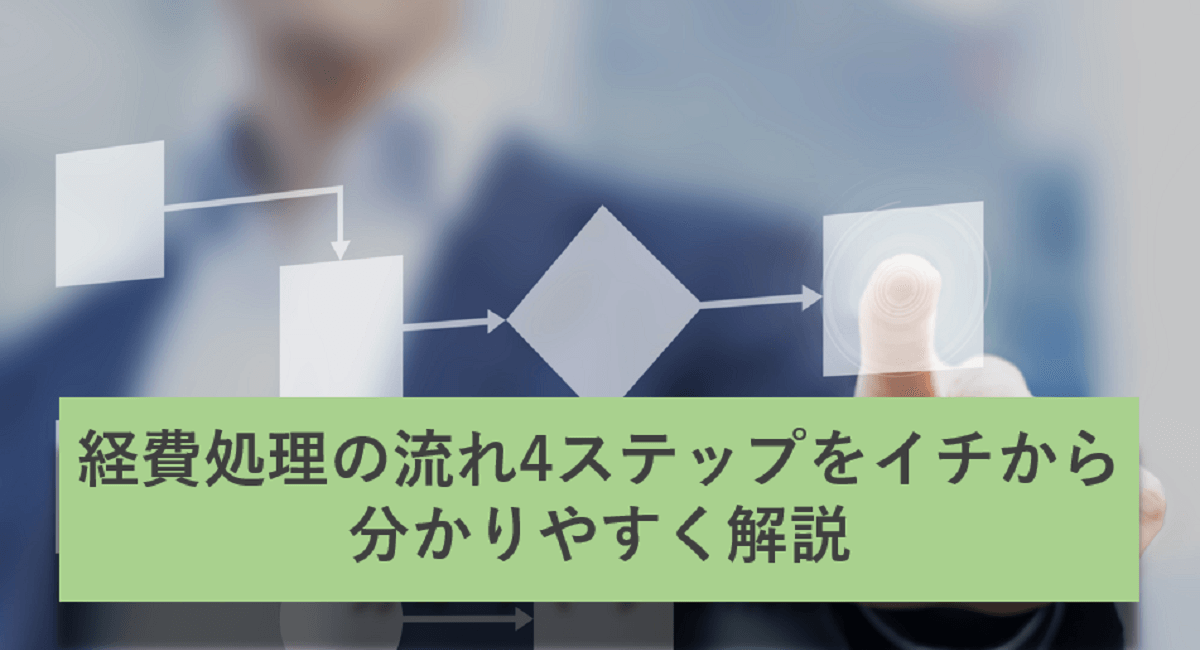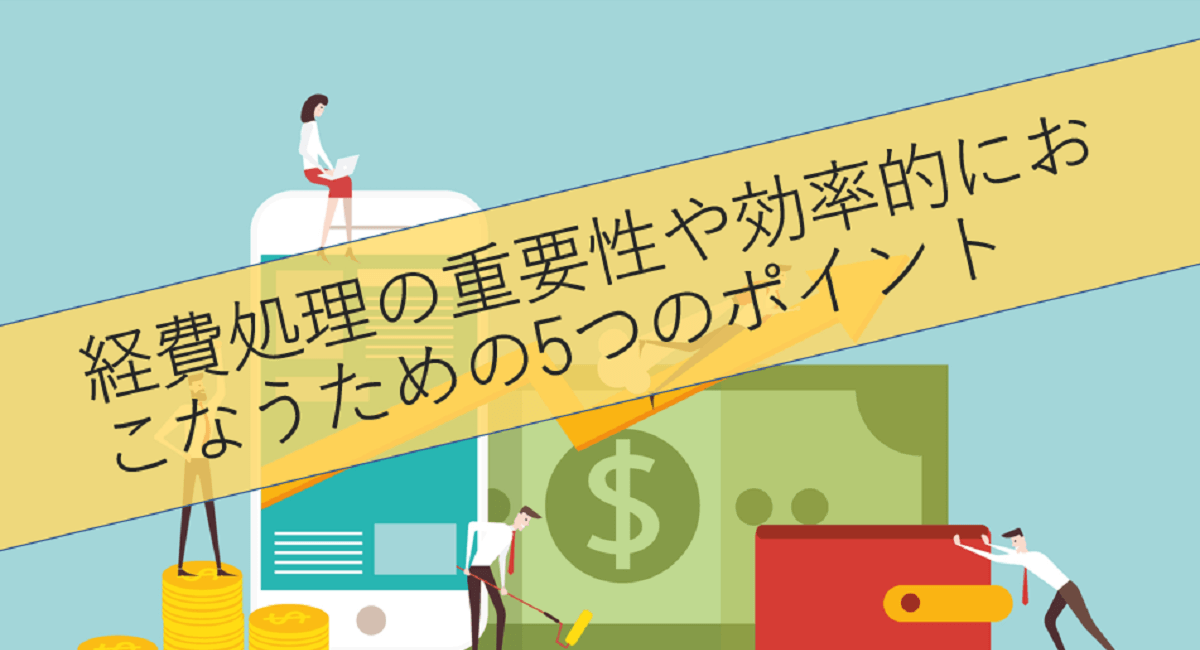そもそも経費処理とは?効率的におこなうためのポイントをわかりやすく解説
更新日: 2024.10.7
公開日: 2020.10.21
jinjer Blog 編集部

経費処理は会社で働くうえで避けて通れない業務ではありますが、手続きを面倒に感じている方も多いと思われます。
しかし、経費を正しく処理することは節税につながるため、経理担当者は業務上避けて通れないでしょう。
本記事では、経費処理の目的や経費処理を効率的に行うためのポイント、経費処理を効率的におこなうために活用できるツールについて、解説します。
「経理担当者になってまだ日が浅いため、基本知識をしっかりつけたい!」
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安になることがございませんでしょうか。
特に経費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひこちらから資料をダウンロードして有効にご活用ください。
目次
1. 経費処理についておさらい

経費処理を説明する前に、まずは費用、経費、損金の違いについておさらいしておきましょう。
1-1. そもそも経費とは?
経費とは、明確に定義することが難しいですが、一言でいうと資産の消費のことをいいます。
よく、社内では「経費で落とす」や「経費で処理する」と使われます。会社が事業を運営していく中で支出した費用、あるいは損金のことをいいます。
経営費用とも呼ばれ具体的には、出張の旅費や通信費、宣伝広告費、さらに事務所の家賃などが含まれます。
これらはすべて収益を得るために支出された費用であり、税金計算の根拠となる事業所得を決定する際に重要な役割を果たします。経費を適切に計上することで、事業所得を減少させ、納付すべき税額を抑える効果が得られます。
そのため、正確な経費管理は節税対策において欠かせない要素と言えるでしょう。
費用
費用とは「会社が事業を運営していく中で支出した金銭」のことを表します。他にも、減価償却費のような金銭の支出がないものも費用として認められています。会社が事業を運営していく上で関係のない支出は費用として認められませんので、注意が必要です。
損金
損金とは、法人の「経済的価値の減少」の原因となる原価や費用、損失などの額をいいます。
損金は、法人税を計算するときに収益から控除できる経費が損金です。損金の考え方で注意しておかなければならないことは、「事業を運営していく中で支出した金銭」は費用として認められるのに対して、損金の場合は、経費として扱うために一定の条件が必要です。
1-2. そもそも経費処理とは?
経費処理とは、会計処理の一部であり、企業や個人事業主が経費を適切に計算し、評価し、記録するためのプロセスを指します。
経費は日々の業務の中で発生し、正確に記録することが求められます。特に、請求書や領収書、納品書などの書類を適切に作成し保管することが重要です。これにより、経費として計上する際の透明性が確保され、税務調査においても安心して対応できます。
経費処理を効率的に行うためには、会計ソフトを活用し、日々の処理を怠らず行うことが鍵となります。
2. 経費処理と間違えやすい言葉との違い

経費処理の言葉の意味について詳しく説明してきましたが、関連する言葉で経費処理と間違えやすいものとの違いを説明します。
2-1. 経費精算とは
経費精算とは、従業員が一時的に立て替えた事業関連の費用を会社が払い戻す手続きを指します。
例えば、業務のために外出した際に発生した飲食費や出張にかかる交通費などが該当します。従業員は、これらの費用に対して領収書や明細書を用意し、申請を行います。経理部門はその提出された書類を確認し、経費として適切に処理した後、払い戻しを実施します。申請には期限が設けられていることも多く、正確な処理が求められます。
2-2. 経理処理とは
経理処理とは、企業の財務活動におけるお金の動きを管理する業務全般を指します。具体的には、日々の帳簿の記録や領収書の管理に加え、商品在庫の管理、さらには貸借対照表や損益計算書、決算書の作成など、多岐にわたる業務が含まれます。
税金の申告や納付、従業員の給与計算、年末調整も経理処理の一環であり、日常業務に加えて、月次業務や決算に関連する書類作成も必須です。経理処理は企業の健全な財務運営において欠かせない役割を果たします。
2-3. 会計処理とは
会計処理とは、経理処理の一環として、日々の取引の金銭の出入りを記録し、整理する業務を指します。
具体的には、帳簿への記入や決算書の作成を含み、定期的に行われる月次業務や年決算処理が中心となります。会計処理を通じて、各月の取引結果を明確にし、売掛金の管理や請求書の発行を行うことで、企業の財務状況を透明化します。
このように、会計処理は経費処理が適切に実施されるための基盤となる重要なプロセスです。
3. 経費処理が可能な費用の判断基準

会社を運営していく中で経費は切っても切り離せません。事業活動をおこなう際は、さまざまな経費が発生します。
経費として処理をすることは、節税にもつながるため、できるだけ多くの費用を経費として処理したいと考えている経営者の方も少なくありません。
しかし、経費として処理できるものには制限があります。
ここでは、経費処理が可能か不可能か判断するために押さえておきたいポイントを解説いたします。
3-1. 支出金額が常識の範囲であること
支出金額が常識の範囲内であることは、経費処理ができるかできないかを判断するために考えるポイントです。
事業の運営に必要な経費であっても、一般的な常識から外れた高額の食事代や旅行代は、基本的に経費として処理することができません。
3-2. 事業運営に必要な支出であると証明できること
事業運営に関係のないプライベートの食事や旅行の費用などは、基本的には経費として処理することができません。
事業運営に関係のある取引先との食事や旅行などは、証明できれば経費として処理することができます。
3-3. 費用収益対応の原則に準拠していること
会計処理は収益期間計算をおこないます。そのため、収益と費用が発生した月に正しく割り当てられている必要があります。
このように、会計期間を区切って損益期間計算をおこなうという、費用収益対応の原則が存在します。
費用がいくら事業運営にかかわる支出であっても、費用収益対応の原則に当てはまらなければ費用は計上できません。
4. 経費処理が不可能な費用に注意

経費処理は、事業に関連する支出を正しく計上する重要なフローですが、経費として計上できない項目も存在します。
まず、私生活に関わる支出は経費として認められません。例えば、職場専用の制服は経費になりますが、一般的なスーツは私的な利用もあり、経費には含まれません。また、一部の税金や、法人税、法人住民税、社会保険料は経費計上の対象外です。
さらに、個人事業主が家族に支払う給与も経費とはならない点に注意が必要です。ただし、特定の条件を満たした専従者給与は例外となるため、正確な知識が求められます。
5. 経費処理を効率的に行うための5つのポイント

経費処理は会社において重要な業務ではありますが、同時に煩雑な業務でもあるので、できる限り効率的にこなすことが重要です。
経費処理を効率的に行うためのポイントとしては、主に以下のようなことが挙げられます。
- 経費処理のフローを見える化する
- できる限りキャッシュレスで対応するようにする
- 法人カードを利用する
- クラウド会計ソフトを利用する
- アウトソーシングを活用する
ここでは、それぞれについて説明いたします。
5-1. 経費処理のフローを見える化する
経費処理では複数の部署をまたいで複数人の担当者が関与することもあるので、どのようなフローで経費が処理されているのかがわかりにくいことも多々あります。
経費処理に関わっている人、利用されているシステムなどを見える化することで、より効率的に経費処理をおこなえる可能性が高まるでしょう。
とくに経費処理が属人的な業務になってしまっている場合は、担当者が離職・転職してしまうことによって、業務がうまく回らなくなってしまうかもしれません。
担当者が変わってもつつがなく経費処理をおこなえる程度まで、見える化することを心がけましょう。
関連記事:経費処理の流れ4ステップをイチから分かりやすく解説
5-2. できる限り電子マネーで対応するようにする
経費を現金で支払っている場合、会社には必ず小口現金を用意しておかなければなりません。
経費を支払った後は必ず、帳簿上の金額と手元の金額が合っているかを確認しなければなりませんし、普段の現金の管理も面倒なものです。
経費を現金で支払うのではなく、口座引き落としや口座振り込みなどで支払うようにすれば、経費処理の手間が省けてお金の管理もグッと楽になります。
最近では電子マネーやQR決済で支払えるものも増えてきているので、そういったものを有効活用することも重要です。
関連記事:この電子マネー、どうやって経費処理する?種別ごとの処理方法を解説
関連記事:キャッシュレスポイント還元値引き、経費処理はどうすればいい?
5-3. 法人カードを利用する
社員が立て替えた経費を現金で精算する場合、領収書の発行や提出が必要となり、非常に非効率的です。
また、関与する人が多い分だけ、金額の請求ミスや事務手続きのミスなどといったミスが起きてしまう可能性も高いといえます。
経費の支払いに法人カードを利用するようにすれば、社員個人の持ち出しがなくなり経費精算の手間が省けるので、経費処理がより効率的におこなえるようになります。
キャッシュフローの改善のように、経費処理の効率化以外にもメリットがあることも見逃せません。
5-4. クラウド会計ソフトを利用する
社内に経費処理に詳しい人があまりいないのであれば、クラウドの会計ソフトを利用するのもひとつの手です。
専門的な知識がなくても請求書や見積書の作成が可能ですし、操作も簡単で感覚的に理解しやすいです。
クラウド型なのでパソコンにインストールすることなく利用可能で、インターネットに接続できる環境さえあれば、どこでも誰でも経費処理が行えます。
金融機関の口座や法人カードとの連携も可能で、口座から引き落とされたお金や法人カードで支払ったお金が自動的に登録されるので、経費処理の手間を大幅にカットできます。
5-5. アウトソーシングを活用する
経費処理は会社の売上に直接関わるわけではないバックヤードの業務なので、業務を丸ごとアウトソーシングしてしまうというのもひとつの選択肢です。
経費関連の業務を専門に請け負っている会社もありますので、いくつかの会社で費用対効果を検討しつつ、アウトソーシング先を決めるとよいでしょう。
アウトソーシングするためには経費処理のフローをわかりやすくする必要があるので、経費処理のフローを見える化できるという副次的効果も期待できます。
アウトソーシングによってノウハウを少し学んだあとに、そのノウハウをもとにしてあらためて社内で業務を行うようにするという流れも、アウトソーシングの費用によっては十分考えられるでしょう。
6. 経費処理を迅速にするためのツール3選

経費処理は、業務の中でほぼ毎日おこなわなければならないものなので、できる限り効率的に迅速におこなうことが望ましいといえます。
経費処理を迅速におこなうためのツールとしては、主に以下のようなものが考えられます。
- クラウド会計ソフト
- 経費精算システム
- チャット・掲示板形式のプロジェクト管理ツール
ここでは、それぞれについて説明いたします。
6-1. クラウド会計ソフトで経費処理をペーパレス化
先ほども少し触れましたが、クラウド会計ソフトを利用すれば経理に関する詳しい知識がなくても経費の処理をおこなうことができます。
指示されたとおりに入力をおこなっていけば、必要な作業を自動的におこなってくれるようなものもあるので、効率的に業務をこなすことが可能です。
操作がわからない場合などのサポート体制もしっかりしていますし、インストール型とは異なり、ソフトを更新する必要がないのも大きなメリットといえるでしょう。
関連記事:経費処理のペーパーレス化はここまで進んでいる!最前線を紹介
6-2. 経費精算システムで経費処理を電子化する
営業の人などが社外で経費を利用した場合、帰社してから領収書を渡して必要な手続きをおこなうことが多いですが、ほかの仕事に追われているうちに経費の精算をすっかり忘れてしまう、というようなケースはよくあります。
経費精算システムの中には、スマートフォンなどを利用して社外から利用できるものもあるので、帰社している最中の空き時間にでも経費精算を済ませてしまうことができます。
月末になってから、当月の経費精算の書類をまとめて経理担当者のところに持っていくことのないように、経費精算システムを有効活用しましょう。
関連記事:経費処理時の領収書を電子化しよう!法律・メリット・方法を解説
6-3. チャット・掲示板形式のプロジェクト管理ツール
経費を精算する必要のある社員と経理担当者の間のやりとりには、チャット形式や掲示板形式のプロジェクト管理ツールがあると便利です。
経費精算がらみのメッセージを送ることはもちろん、todoを設定して経費精算のリマインドをおこなうこともできます。
やりとりの形跡が残ることで、いったいわない・聞いた聞いていないといった水掛け論もなくなり、経費精算を後回しにするのでなくなるべく早く終わらせてしまおうという気持ちが社員に生まれることも、期待できます。
7. 経費処理はシステムを導入して効率的におこなおう

経費処理は、支払う法人税を減らすためや会社のお金の流れを把握するために重要です。
経費処理をおこなう際は煩雑な手続きもありますが、経費処理のフローを見える化したりクラウド会計ソフトを利用したりすることで、なるべく効率的におこなうようにしましょう。
クラウド会計ソフト以外に経費精算システムやプロジェクト管理ツールなども、経費処理の助けとなるので、費用対効果を考慮に入れたうえで導入を検討してみるのもひとつの選択肢といえます。
「経理担当者になってまだ日が浅いため、基本知識をしっかりつけたい!」
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安になることがございませんでしょうか。
特に経費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひこちらから資料をダウンロードして有効にご活用ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
効率の関連記事
-

領収書の貼り方のコツ!領収書保管や整理を効率化する方法を紹介
経費管理公開日:2024.03.18更新日:2024.10.07
-

差引支給額とは?計算方法や注意点、計算を効率化する方法を解説
勤怠・給与計算公開日:2024.01.12更新日:2024.06.21
-
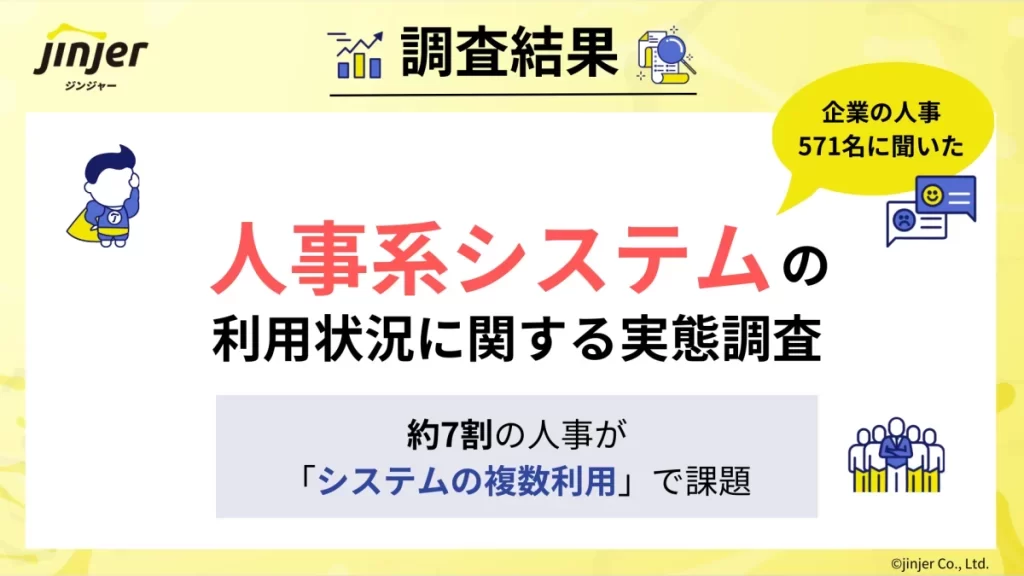 バックオフィスDX
バックオフィスDX7割の人事が「システムの複数利用」で課題あり。効率的なシステム利用に「同一ベンダー、同一データベース」が最適な理由は?人事系システムの利用状況に関する実態調査
公開日:2023.09.05更新日:2024.05.08
7割の人事が「システムの複数利用」で課題あり。効率的なシステム利用に「同一ベンダー、同一データベース」が最適な理由は?人事系システムの利用状況に関する実態調査
バックオフィスDX公開日:2023.09.05更新日:2024.05.08
経費処理の関連記事
-

経費立替の注意点は?業務負担を減らす方法も合わせて解説
経費管理公開日:2023.05.10更新日:2024.01.30
-

経費処理の流れを効率化するポイントとよくある問題点を解説
経費管理公開日:2020.10.23更新日:2024.10.10
-

そもそも経費処理とは?効率的におこなうためのポイントをわかりやすく解説
経費管理公開日:2020.10.21更新日:2024.10.07