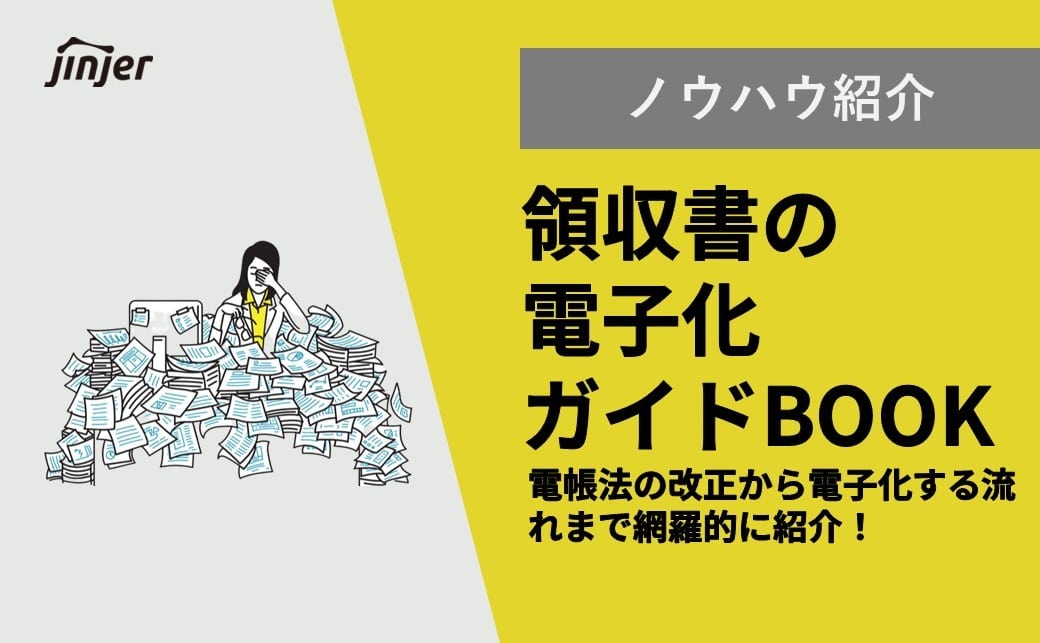経費精算で領収書を電子化する方法は?法律や疑問点をくわしく解説
更新日: 2024.10.7
公開日: 2020.10.14
jinjer Blog 編集部

経費処理の作業量はときに膨大になることがあり、多くの人員が必要とされてきました。
しかし現在ではリモートワークが急速に浸透するにつれ、請求書や領収書もペーパーレス化・電子化が進んできています。
現在、領収書をはじめとした書類の電子化が大変注目を集めております。
しかし、法律や手続き、電子化の方法など、初めて書類の電子化を進める企業にとっては難しいことが多く、不安がある方も多いのではないでしょうか。
今回は、領収書の電子化に関する法律や手続き、方法についてわかりやすく解説いたします。
そもそもの「経費精算」について知りたい方はこちらの記事で解説しているので、ご確認ください。
関連記事:経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
「精算時に領収書を貼り付けない人がいて、領収書を紛失することがある…」
「領収書と請求内容の突き合わせが大変」
「経費精算業務を効率化する方法が知りたい」とお悩みの方必見です。
経費精算業務は領収書と請求内容の突き合わせや、使用用途の確認など、確認作業が多い業務です。そのため「めんどう…もっと楽にできないかな?」「効率化できるのでは?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは、経費精算業務の負担を減らすための方法として、領収書を電子化する方法を紹介する資料を用意しています。電子帳簿保存法の改正点についても紹介しているので、業務を効率化する方法と法対応の2つをまとめて理解することが可能ですので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 領収書の電子化を進める際に確認する必要のある法律


まずは、領収書の電子化を進める際に確認しておいた方がよい「電子帳簿保存法」について解説していきます。
法律をしっかりと理解して、安心して電子化を進められるようにしましょう。
1-1. 2016年の電子帳簿保存法の改正
2016年にスキャナによる保存要件が緩和されました。
概要をまとめると、「スマートフォンでの電子化保存」と「領収書のサイズがA4以下の場合に、大きさに関する情報が不要」の2点があらたに加わりました。
つまり、法律上、スマートフォンで撮影した領収書の電子化保存が認められ、経費精算時の領収書をはじめとした、日常的に発生する業務により深く電子化が活用できるようになったのです。
1-2. 電子帳簿保存法で認められている帳簿書類
経理業務に関連する書類の電子化を考えるときには、どの書類が電子化できるのかを理解しておくとよいでしょう。
電子帳簿保存法によって電子化保存が認められている書類は以下のとおりです。
| 電子保存が認められている書類一覧 | 分類 |
|---|---|
| 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金・買掛金元帳固定資産台帳、売上・仕入帳など | 国税関係帳簿 |
| 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、その他決算に関して作成した書類 | 国税関係書類 (決算関係書類) |
| 領収書、契約書、請求書、納品書など | 国税関係書類 (その他の証憑類) |
| 見積書、注文書など | 一般書類 |
2. 領収書を電子化する方法を確認しよう


経費処理を電子化するためには「どのツールを使用するか」も非常に重要です。自社に合ったツールを採用すれば、電子化をスムーズにおこなうことができるでしょう。
2-1. スマートフォンに対応した経費精算システムの活用
経費処理を電子化するためによく用いられるのが、「経費精算システム」です。
最近ではスマートフォンやタブレットを通して経費処理がおこなえる、スマートフォンアプリ型のシステムも販売されています。
領収書を電子保存するだけでなく、申請時から領収書や申請書類を電子化して業務を効率化していきたいとお考えなのであれば、経費精算システムは有効な手段であると言えるでしょう。
① 領収書はスマートフォンで撮影するだけ
従業員が経費精算申請をおこなう際は、スマートフォンで申請内容を入力して、撮影した領収書を添付すれば申請は完了します。
写真を撮影しておけば、従業員が月末まで領収書の原本を管理しておく必要もなくなりますし、同時に領収書のない申請が発生することもほぼなくなります。
このようにシステムを導入すれば経費申請のミスが起こりにくくなります。実際のシステム導入イメージを当サイトではまとめて資料にしておりますので、中長期的にシステム導入を検討している方は参考としてお使いください。
「課題別!システムを使用した経費精算の課題解決BOOK」はこちらから無料でダウンロードできます。
② 経理担当者は領収書の保管・管理作業から解放
領収書が電子化することによって、領収書の原本をファイリングしたり、整理して保管したりする必要はなくなります。
見たい書類や領収書があれば、システム内で検索すればすぐに見ることができるため、手間をかけて探す必要はありません。
③ 申請者・承認者・管理者に多くのメリット
また、経費精算システムは領収書の電子化だけでなく、申請書や承認依頼、仕訳、処理などの経費精算に関わる一連の業務をオンラインで完結させることができます。
そのため、申請者、承認者、管理者を含む会社全体としてメリットが大きいのも特徴です。
関連記事:経費精算システムのメリット・デメリット・選び方をまとめて解説!
関連記事:交通費精算のDXとは?注意点や導入時のポイントを解説
関連記事:経費精算ワークフローとは?導入するメリット・デメリットを解説
3. 領収書の電子化を進める際の手続き


経費処理時の請求書や領収書の電子化を進める際は、さまざまな準備が必要になります。
経費処理の電子化には3つのステップがありますので、理解しておきましょう。
3-1. 会社内でのルール作り
経費処理を電子化する前に、会社内でのルールを作ります。
どのような経費を精算できるのか、どのような写真でなければならないか、経費処理を申請する流れなどを含めたフローを策定します。
このフローも簡単に決められるものではなく、国税庁が定める要件に基づいて社内で十分検討することが必要です。
ルール作りがしっかりおこなわれていないと、莫大な費用をかけて経費処理を電子化しても効果が出ない可能性があります。
交通費精算におけるルールは下記の記事で解説しています。
関連記事:交通費精算とは?精算書の書き方やルールをくわしく解説
3-2. 自社にあったソフトの導入
社内のルール策定が終わったら、ソフトを導入します。
このとき、自社のニーズに合った製品を探して導入しなければなりません。
価格も重要ですが、どのような書類を扱えるのか、どのくらい使いやすいのか、サポートは充実しているか、クラウド型かオンプレミス型か、セキュリティ対策は万全かなど、考慮すべき点はたくさんあります。
自社のニーズに合ったものを採用できれば、経費処理の手間も時間も大幅に削減できるはずです。
経費精算業務のペーパーレス化を進める方法や成功させるポイントは以下の記事でも詳しく解説しています。
当サイトでは「領収書の電子化! 電子化のルールとシステムを使用した経費精算の電子化」という資料を無料配布しております。本資料では、領収書を電子化する際の注意点や手順、また電子帳簿保存法への対応方法など領収書の電子化に関して網羅的に解説しております。経費精算に関する業務を行っている担当者にとっては大変参考になる内容なっているので興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
関連記事:今から始める、経費精算のペーパーレス化!やり方と導入方法を徹底解説
関連記事:経費精算システムの導入を成功させる7つのポイントを徹底解説
関連記事:経費精算のDX化とは?電子化のメリットや導入方法もくわしく解説
4. 領収書や申請書を電子化するメリット・デメリット


経費処理の電子化を進めるかどうかを決定する前に、電子化のメリットやデメリットについて考えておく必要があります。
ここでは、経費精算・経費処理で使用する書類を電子化するメリットとデメリットを解説します。
4-1. 経費処理時の書類を電子化するメリット
経費精算業務では、領収書や申請書、稟議書などが必要です。これらを紙で管理する場合、ファイリングに手間がかかる、保管場所を用意しなければならないなど、面倒な点があります。
業務に必要な書類を電子化することで、面倒をなくすことができるので、確認しましょう。
①管理スペースの削減が可能
紙を使って経費処理をしている場合、多くの領収書などを保管する必要があります。。いくつも棚を置いて、その中に山のように書類を保管している企業は少なくありません。
年度末になれば、非常に多くの書類を整理して、ファイリングする必要があります。
しかし経費処理を電子化すれば膨大な量の書類を電子データとして整理できるため、スペースが節約できます。
②データ検索が可能になり探す手間が省ける
紙で書類を管理していると、特定の領収書を見つけることに手間取ることもあるでしょう。
経費処理が電子化されていれば、必要とする領収書などの書類をパソコンで瞬時に検索できます。
内部監査で特定の書類や請求書・領収書が必要になっても、電子データをメールなどで送信するだけで済むでしょう。
③業務の効率化が図れる
経費処理は社員にとっても経理担当者にとっても負担の多い作業です。社員は領収書と経費の申請書類を合わせて上司に提出し、上司から承認印をもらって経理部に提出しなければなりません。
その後、経理担当者が領収書と申請書類を精査し、精算した後に書類をファイリングして最低でも7年間保管する必要があります。
もし領収書が適切なものでなかったり、申請書類に誤りがあったりした場合には、差し戻して修正してもらうことが必要です。しかし、経費精算システムを導入していれば、領収書をスマートフォンやタブレットで撮影してアップロードしたら自動で入力することができます。従業員が個別に入力する必要がないので、入力や計算ミスによる差し戻し回数を大幅に減らせるでしょう。
加えて、申請者や承認者は、経費精算業務のために、わざわざ会社に出社することがなくなります。経費処理を電子化すれば、申請書類と領収書をアップロードして、上司が時間のあるときにそれをチェックすることができるからです。
④コスト削減
経費処理を電子化することにより、紙を使う機会が減ります。
申請書類を印刷する必要はなく、ファイリング作業も不要です。
経理全般に必要となるコストを削減できるのは、電子化の大きな利点といえるでしょう。
⑤保管が容易
企業などの法人において、領収書は法人税法に基づき7年間の保存期間が設けられています。
しかし、領収書が劣化して読み取れなくなってしまったり、書類を紛失してしまったりする恐れがあるため、保管する環境に気を遣わなければなりません。
領収書の劣化や紛失は、税務上のトラブルになることもあるのでできる限り避けるべきでしょう。
経費処理を電子化しておけば、領収書を電子データとして保管できるので劣化・紛失の恐れがありません。また、バックアップを取るのも容易なので、万が一ハードディスクが壊れたりした場合でも安心です。
関連記事:経費処理の重要性や効率的におこなうための5つのポイント
4-2. 経費処理時の書類を電子化するデメリット
経費処理を電子化することは、メリットだけではありません。デメリットについてもよく考慮したうえで経費処理の電子化導入を検討しましょう。
ここでは、3つのデメリットを解説いたします。
①コストがかかる
最初に挙げられるデメリットは、電子化するためのコストです。
経費処理を電子化するためには、専用のソフトやアプリケーション、パソコン、複合機などが必要になります。1台しかない場合、税務調査のときは使えなくなるため、注意が必要です。追加購入する場合、初期費用とランニングコストを考慮すると、数百万円程度の支出となる可能性もあります。
また、必要な知識の習得や業務手順の見直しなど、担当者の負担が増えることは避けられないでしょう。そのため、現場と上層部双方の理解が必要なのです。
②データの分類を詳細にする必要がある
経費処理の電子化に伴う2つ目のデメリットは、データの分類が必要という点です。
たとえば部署ごとに、あるいは月ごとにフォルダを作って領収書を管理したり、命名規則に則ったファイル名で領収書を保管したりする、といった工夫が必要となるでしょう。
これらの検索機能は電子帳簿保存法による要件にも含まれています。「領収書の枚数が少ないから不要」ということはないため、注意が必要です。
電子化のメリットを最大限に引き出すためには、ただシステムを導入するだけでなく細かなデータ管理までおこなえる人材がいなければなりません。
③すべてを電子化できるとは限らない
経費処理を電子化する3つ目のデメリットは、すべてのデータが電子化できるわけではないということです。
電子データとして保存するためにはいくつもの要件を満たさねばならず、結局紙ベースで残しておかなければならないことも少なくありません。
そのためせっかくシステムを導入しても紙のデータと電子データが混在してしまう恐れがあります。
「完全に電子化できないのであれば、電子化するメリットがない」と判断して経費処理の電子化自体を断念する企業もあるでしょう。
また、企業の規模別によっても導入メリットは異なります。中小企業向けの経費精算システムの選び方はこちらの記事で解説しているので、合わせてご確認ください。
関連記事:中小企業向け経費精算システムとは?選び方や課題別おすすめ機能を紹介
5. 領収書の電子化に関するよくある質問
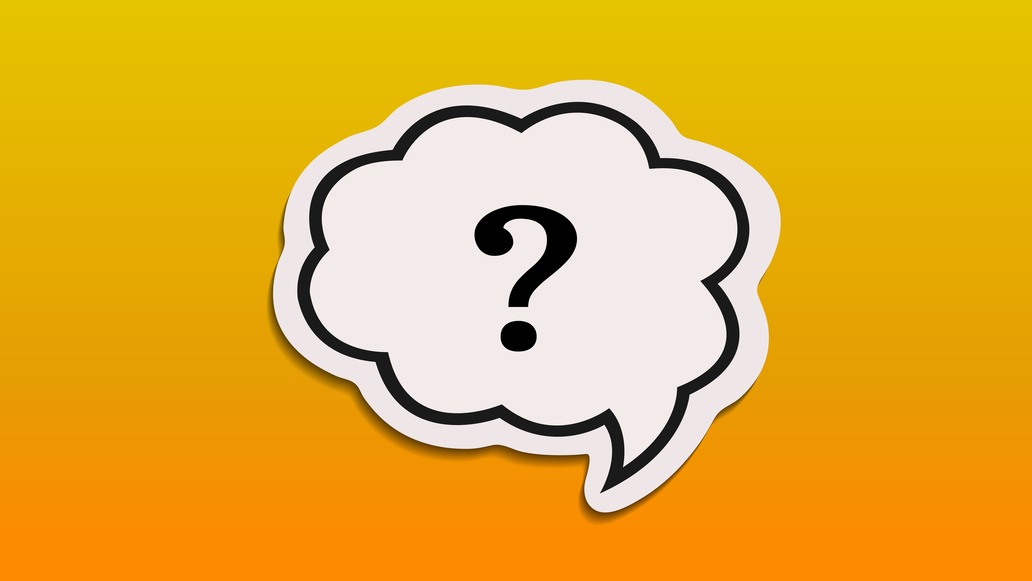
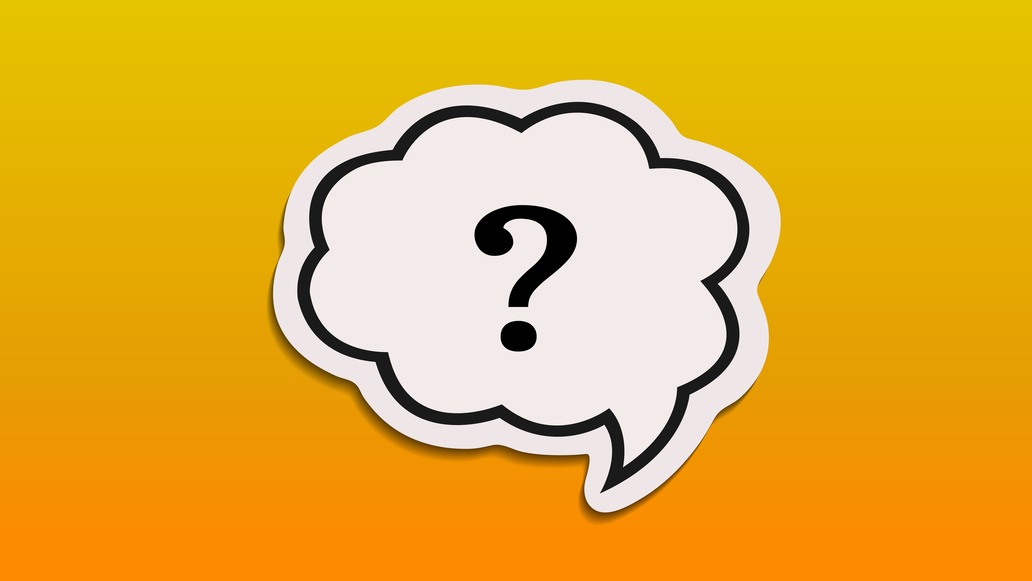
領収書は、経費精算業務をおこなう際にほぼ必ず必要となる書類です。経費処理のペーパーレス化を進めるためには、紙で受領した領収書のスキャナ保存について理解しておく必要があるでしょう。本章では、領収書を電子化するときの疑問点について解説します。
5-1. スキャナ保存した領収書は破棄して良い?
2022年1月の改正で、適正事務処理要件が廃止されました。それにより、スキャナ保存した領収書を即時破棄できるようになっています。
ただし、裁判などになった場合に、スキャナ保存した領収書を原本と同様に扱うかどうかは不明です。過去の判例などを参考にしつつ、判断するのが良いでしょう。
5-2. 領収書のスキャナ保存は誰でもできる?
領収書を受領した本人以外でも、スキャナ保存をおこなうことは可能です。ただし、保存する際に領収書の大きさに関する情報を記録する必要があるため、注意しましょう。
参照:Ⅰ 通則【制度の概要等】|国税庁
5-3. スキャナ保存するとき、タイムスタンプは必要?
以下の2つの要件を満たしている場合のみ、タイムスタンプは不要です。
- 削除・訂正の履歴が残るシステムを利用していること
- 入力期間内にスキャナ保存していることを確認できること
以前は必ずタイムスタンプを付与する必要がありましたが、2022年1月の改正で変更されました。
交通費精算や経費精算のDX化を進める方法について、こちらの記事でも詳しく解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。
関連記事:交通費精算のDXとは?注意点や導入時のポイントを解説
6. まとめ


経費処理の電子化は費用がかかると考えて敬遠する企業もあれば、費用をかけて導入したのにあまり使わなくなってしまう企業もあります。
そうならないためにも、経費処理の電子化のメリットやデメリット、導入費用とその効果などを十分に考慮する必要があります。
自社に合ったシステムを採用しメリットを十分に享受しましょう。
「精算時に領収書を貼り付けない人がいて、領収書を紛失することがある…」
「領収書と請求内容の突き合わせが大変」
「経費精算業務を効率化する方法が知りたい」とお悩みの方必見です。
経費精算業務は領収書と請求内容の突き合わせや、使用用途の確認など、確認作業が多い業務です。そのため「めんどう…もっと楽にできないかな?」「効率化できるのでは?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは、経費精算業務の負担を減らすための方法として、領収書を電子化する方法を紹介する資料を用意しています。電子帳簿保存法の改正点についても紹介しているので、業務を効率化する方法と法対応の2つをまとめて理解することが可能ですので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
法律の関連記事
-


「二段の推定」の意味や根拠法律について詳しく解説
電子契約公開日:2023.04.13更新日:2024.05.08
-


法律上の上限はなし?福利厚生費の限度額を解説
経費管理公開日:2022.05.10更新日:2024.05.29
-


消費税なしは法律上問題なし?記載がない請求書の扱い方について
経費管理公開日:2022.05.10更新日:2024.05.08
電子化の関連記事
-

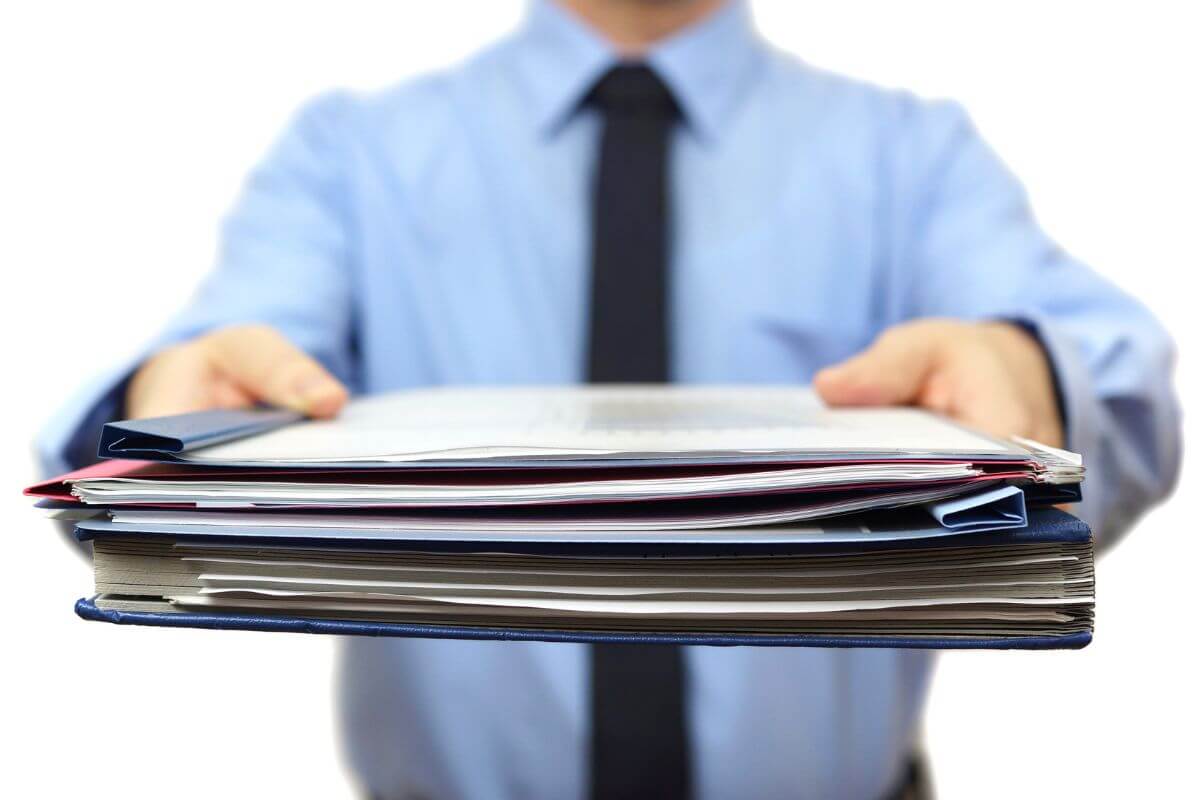
押印申請とは?申請書の書き方やテンプレートを紹介!電子化するメリットも
人事・労務管理公開日:2024.04.24更新日:2024.05.31
-


【今更聞けない】決裁と稟議の違いとは?意味や承認の流れを徹底解説
人事・労務管理公開日:2024.04.18更新日:2024.05.24
-


人事労務業務は電子化できる?電子化できる業務や手順を解説
人事・労務管理公開日:2023.06.06更新日:2024.06.24
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減のアイデアとは?基本的な考え方や注意点について解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2024.10.08
経費処理の関連記事
-

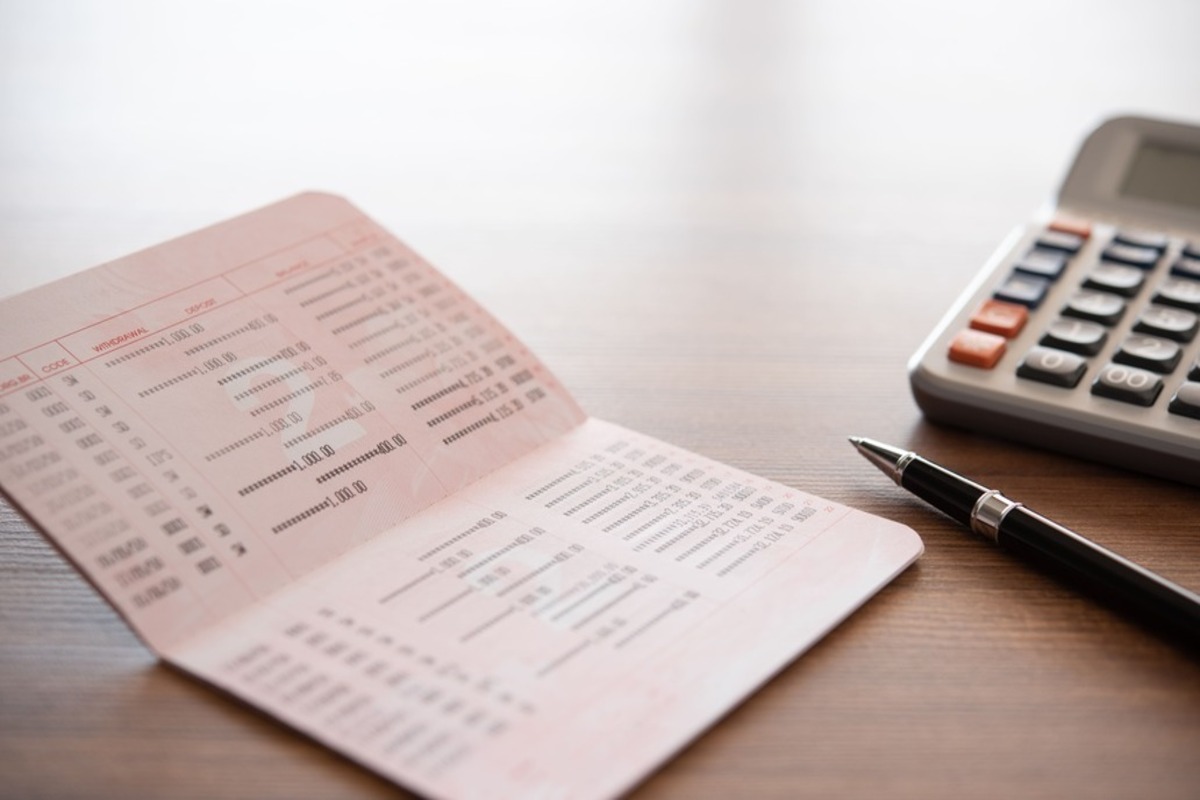
経費立替の注意点は?業務負担を減らす方法も合わせて解説
経費管理公開日:2023.05.10更新日:2024.01.30
-

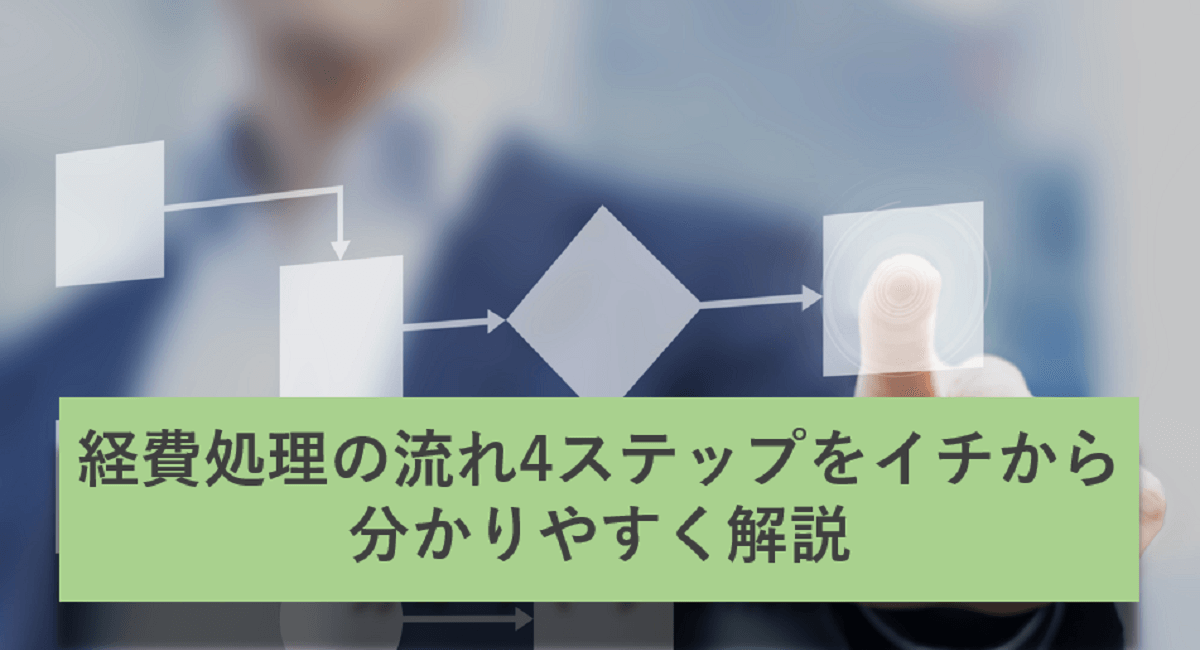
経費処理の流れを効率化するポイントとよくある問題点を解説
経費管理公開日:2020.10.23更新日:2024.10.10
-

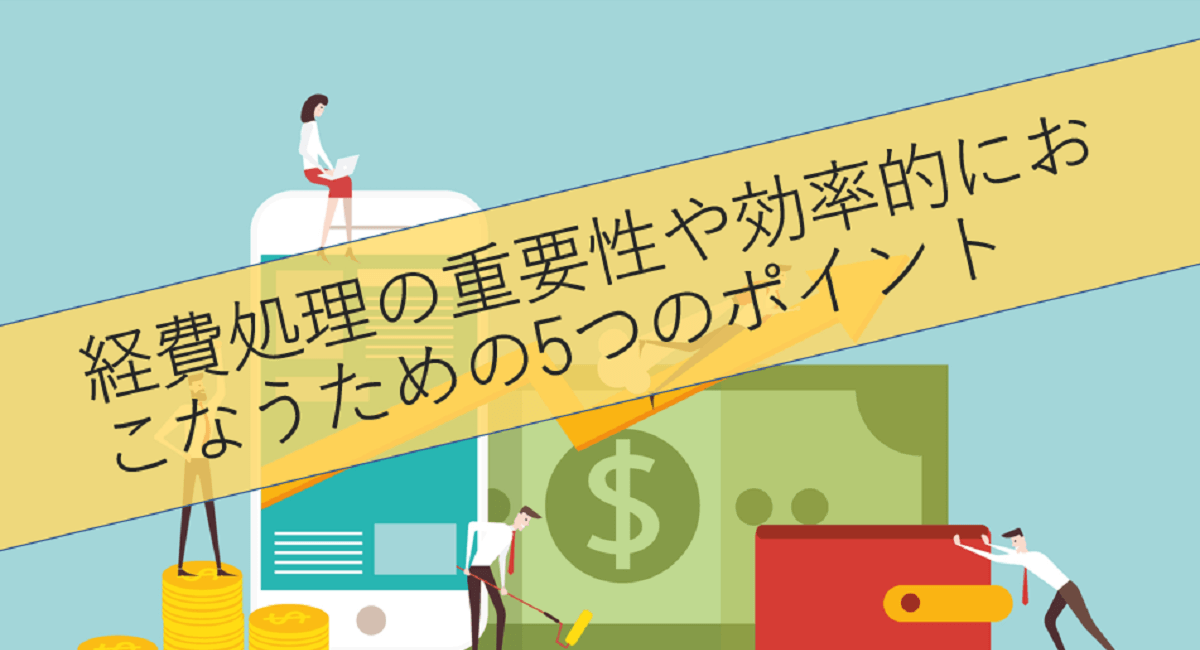
そもそも経費処理とは?効率的におこなうためのポイントをわかりやすく解説
経費管理公開日:2020.10.21更新日:2024.10.07