交通費精算とは?精算書の書き方やルールをくわしく解説
更新日: 2024.10.7
公開日: 2020.11.18
jinjer Blog 編集部

従業員が交通費精算をする場合、意外と間違いも多く、修正や差し戻しをすることにストレスを感じている経理担当者も多いでしょう。
交通費精算については事前にルールを設定し、従業員に周知しておくことが大切です。
ここでは、交通費精算に関するルール設定のポイントや周知のコツを紹介します。業務効率化のために、ぜひチェックしてみてください。
「通勤手当の非課税限度額っていくらから対象?」
「交通費精算で領収書が必要な場合と不要な場合って何が違うの?」
「接待に使ったタクシー代ってどの勘定科目になるの?」
「ガソリン代って交通費に含まれるの?」
などなど交通費に関してちょっとした不安や疑問を感じたことはないでしょうか。
交通費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。そこで今回は交通費に関するよくあるQ&Aや経理担当者が知っておくべき交通費の基本知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
交通費精算に関する情報をいつでも確認できる教科書のような形の資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひこちらからダウンロードの上、有効にご活用ください。
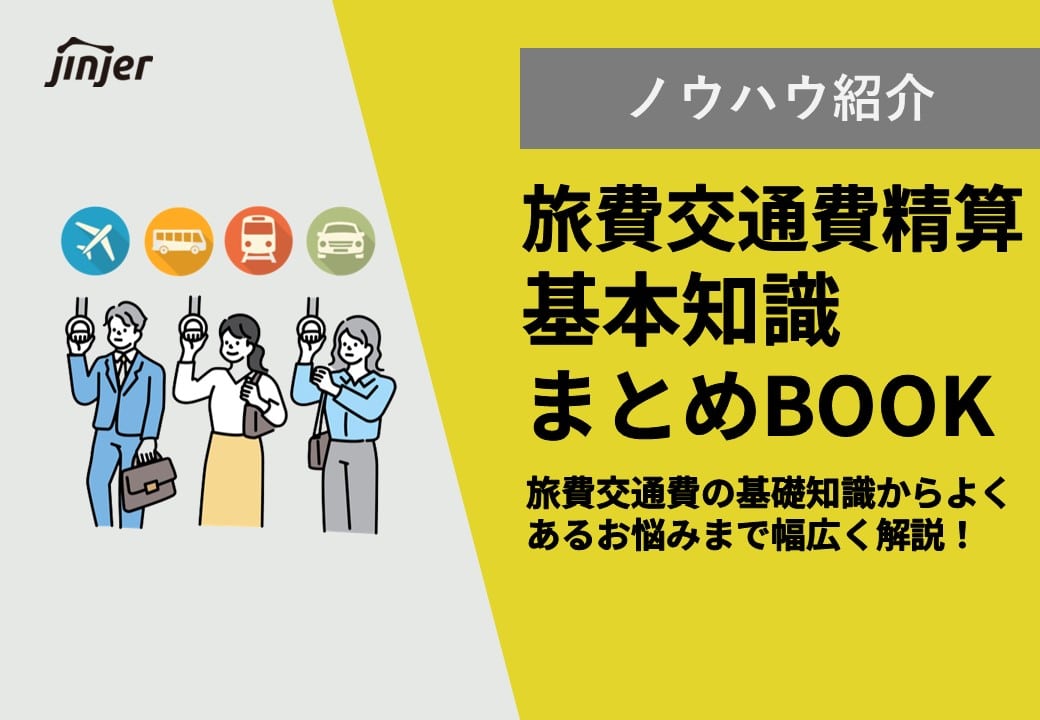
1. 交通費とは?


交通費とは、日々の営業活動や出張などで従業員が移動する際に発生する移動費用を指します。電車やバスなどの公共交通機関の利用が主ですが、規程に定められていれば、タクシーや特急料金も交通費で精算することが可能です。
また、このような交通費を経費精算システムなどを用いて実費精算することを「交通費精算」といいます。
1-1. 通勤手当との違い
先述のとおり、交通費とは「従業員が移動する際の移動費用」を指します。そのため「通勤手当」と混同されやすいでしょう。しかし、この二つには明確な違いが存在します。
違いは以下のとおりです。
| 項目 | 用途区分 | 用途 |
| 通勤手当 | 給与 | 従業員の自宅と会社を往復するための交通費。支給の有無や金額は会社規程による。 |
| 交通費 | 経費 | 営業活動や出張などの移動費用。実費に対して、個別に精算する。 |
このように、明確な違いがあるため、二つの費用は分けて管理する必要があるでしょう。また、交通費は全額非課税ですが、通勤手当は月額15万円以上の場合は課税対象になるため、注意が必要です。
参照:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
1-2. 旅費(旅費交通費)・出張費との違い
交通費と似た言葉で、旅費(旅費交通費)や出張費があります。これらは経理業務において「分けなければならない」という明確な決まりはありません。そのため、営業活動のための交通費や視察のための出張費用などをまとめて「旅費交通費」や「交通費」といった勘定科目で仕訳することができます。
1-3. 取引先の交通費を負担する場合
接待などで取引先の方にお車代を渡したり、タクシーで送迎したりするなど、取引先の交通費を負担することもあるでしょう。その場合、移動にかかった費用であっても「交際費」で仕訳します。
交通費は損金になりますが、交際費は基本的に損金不算入となる費用です。勘定科目を間違えた場合、脱税につながるおそれもあるため、注意しましょう。
1-4. 就活生や求職者の交通費を負担する場合
企業の説明会参加や面接のため来社した求職者に、交通費を渡している企業も少なくありません。その場合、どのように仕訳すれば良いのでしょうか。一般的には「採用教育費」として仕訳します。「交通費」に含めても税務上の問題はありませんが、採用コストがわかりにくくなるでしょう。また、いずれの場合も「求職者に受領証を書いてもらう」「領収書の提出を求める」など、税務調査への対応も必要です。
2. 交通費精算のルールはなぜ必要?


多くの企業では、交通費精算においてルール(規程)が存在します。これらはなぜ必要なのでしょうか。
目的は大きく2つあります。
- 無駄な費用を発生させない
- 業務負担を減らす
それぞれ詳しく解説します。
2-1. 無駄な費用を発生させない
電車やバスなどは複数の路線があるため、同じ目的地でも経路は複数存在します。このとき、不必要に遠回りする経路を選択したり、グリーン車などを利用したりすると、無駄な費用が発生してしまいます。また、税務調査などで「合理的ではない」と判断された費用は経費として認められない可能性もあるでしょう。
先述のとおり、合理的な経路で移動することは、会社の利益を守ることに繋がります。
2-2. 業務負担を減らす
交通費精算のルールには、移動経路や手段だけでなく、利用時の申請や精算方法についての規定も含まれます。もし申請や精算の決まりがなければ、会社が許可していない費用の精算や、月次や年次の決算後に精算を依頼されるおそれもあります。
会社として健全に運営していくためにも、交通費精算のルールを定めることが必要です。
3. 交通費精算のルール設定における3つの重要ポイント


先述のとおり、あらかじめ交通費精算のルールを設定しておくことは大切です。
わかりやすいルールを作っておけば、精算する従業員の間違いも減り、チェックする経理担当者の負担も軽減できるでしょう。
ここでは、交通費精算のルール設定における重要ポイントを3つ紹介します。
2-1. 可能な限り領収書を提出させる
「3万円未満の交通費精算については領収書不要」などと決めている会社も多いでしょう。この「3万円」という基準は、消費税法に基づいています。
消費税法施行令第49条には、3万円未満の取引については領収書不要と記載されています。[注1]
新幹線や飛行機で移動する場合は、高額の交通費となるため、3万円未満であっても領収書を提出させたほうがよいでしょう。
できる限り領収書を保管しておくことで、税務調査が入ったときに指摘を受ける可能性も少なくなります。
少額のバス移動などとは異なり、窓口で簡単に領収書を発行してもらえるため、従業員に周知しておくのがおすすめです。
交通費精算において領収書の提出が必要となる条件や、領収書を電子化する方法については下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:経費精算で領収書を電子化する方法は?法律や疑問点をくわしく解説
関連記事:今から始める、経費精算のペーパーレス化!やり方と導入方法を徹底解説
[注1]消費税法施行令|e-Gov
2-3. 移動手段別の利用規定を設ける
移動手段には、電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、新幹線や自家用車、タクシーなど様々なものがあります。それぞれの利用規定を設けることで、従業員との無用なトラブルを避けられるでしょう。
2-3-1. タクシーを利用する場合の基準
タクシーを利用すると電車やバスより高額になりやすいため、従業員に頻繁に利用させるのは避けたほうがよいでしょう。
「目的地が駅から何km以上離れている場合は利用してもよい」「利用する場合は領収書をもらう」などのルールを決めておくことが大切です。
2-3-2. 従業員が自分の車で移動する場合の規定
従業員が自家用車で移動する場合の精算方法も決めておく必要があります。社用車であれば、ガソリン代は全額経費として精算できるので、とくに問題はありません。
ただ、自家用車の場合は、プライベートで使用する部分もあるため、ガソリン代をすべて経費として精算するのは難しいでしょう。
そこで多くの会社では、ガソリン1リットルあたりの金額を決めておき、仕事上での走行距離をもとに精算するという方法がとられています。
ガソリン代は社会状況によって変わることもあるため、従業員、会社にとって大きな不利益がないように決めておくことが大切です。
このように交通費はガソリン代や税金の対応など細かい要件が多く、他の経費と比べて対応するのが難しいです。また毎回WEBで検索したり、人に聞いたりするのも工数がかかります。そのような方に向けて当サイトでは交通費精算に関する基礎知識から税金の対応、またよくあるQ&Aなど網羅的に解説した「旅費交通費精算基本知識まとめBOOK」を無料配布しております。
これひとつで気になった時にすぐ確認して解決できるので、普段の業務でも大変役立つ内容となっております。資料は無料ですのでぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
関連記事:交通費精算で気になるガソリン代について基本的な考え方を解説
3. 交通費精算業務を効率化する方法


ここまで紹介した重要ポイントを参考に交通費精算のルールを作ったら、そのルールを従業員に周知して徹底させることが重要です。ここでは、交通費精算のルールを徹底させる4つのコツを紹介します。
3-1. 交通費精算のルールを就業規則に記載する
まず、交通費精算についてのルールは、しっかりと就業規則に記載しておくことが大切です。領収書の取り扱いや交通費精算書の作成方法など、できるだけ細かく記載しておきましょう。
また、就業規則の存在を従業員が知らなければ意味がありません。社内ネットワーク上で公開したり、各部署に1冊ずつ常備したりして、いつでも閲覧できる状態にしておきましょう。
就業規則は会社ごとに異なるため、新しく入社した従業員へは丁寧に周知することも重要です。
3-2. 交通費精算書の承認ルートを明確に決めておく
従業員が交通費精算書を作成した際の承認ルートを決めておくと、不正防止や間違い防止につながります。
一般従業員の交通費精算書は、上司が確認のうえ、経理担当者がチェックするという流れを採用している会社も多いでしょう。
ダブルチェックをすることで、目的の不明な交通費や金額の間違いなどを見抜けます。
上司や経理担当者が間違いを見つけたときは、その従業員へ差し戻したり、精算書の作成方法を再教育したりすることで、ルールが浸透していくでしょう。
また、上司の立場である従業員の交通費についても、別の担当者が確認することは重要です。自分の経費を自分だけで承認する流れをとると、不正や水増し請求などが起こりやすくなります。
3-3. ルールの例外は認めない
交通費精算のルールを従業員に徹底させるためには、基本的に例外は認めないようにしましょう。
移動経路や金額が間違っている、就業規則に記載された決まりに従っていない、といった場合は承認せず、差し戻して修正させることが重要です。
交通費に限らずですが、ルールの例外を認めてしまうと、何度もその例外を利用しようとする従業員も出てきます。
せっかく作ったルールが無駄になってしまいますので、厳しく対応しましょう。
3-4. 経費精算システムを導入する
経費精算システムを導入することも、ルールの徹底につながります。システム上でルールを設定しておけば、ミスや不正を防ぎやすいでしょう。
たとえば、各従業員の通勤定期の経路をシステム上で設定しておけば、交通費精算の際、重複区間がある場合は自動的にその部分の交通費を除いた金額で精算できます。
精算する側の従業員にとっては計算する手間が省けますし、チェックする側の上司や経理担当者の負担も軽減できるでしょう。
当サイトではこのような交通費のルールや規定に関する課題の解決策を紹介したり、経費精算システムを用いた業務効率化の方法まで幅広く解説した「旅費交通費精算基本知識まとめBOOK」を無料配布しております。
実際のシステム画面を用いて経理業務がどのように効率化されるかのイメージも紹介しているので、中長期的にシステムを検討している方にも大変参考になる内容となっております。資料は無料ですので、気になる方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
システム導入を含めた、経費精算業務のDX化については、こちらの記事でも解説しています。
関連記事:交通費精算のDXとは?注意点や導入時のポイントを解説
4. 交通費を正しく理解して精算ルールを策定しよう


今回は、交通費の定義やルール設定における重要ポイント、従業員にルールを徹底させる方法について解説しました。
全従業員に対して平等でわかりやすいルールを設定しておけば、精算時の間違いも減らせて、確認する経理担当者の負担も軽減できるでしょう。
交通費精算のルールを作成したら就業規則に記載するなどして、従業員に周知することが大切です。
承認ルートを設定して、不正を防止することも検討しましょう。また、経費精算システムを導入して、精算書チェックやルール徹底の手間やコストを減らすことで業務の効率化ができます。面倒な計算やチェックはシステムに任せて、効率的に仕事を進めていきましょう。
「通勤手当の非課税限度額っていくらから対象?」
「交通費精算で領収書が必要な場合と不要な場合って何が違うの?」
「接待に使ったタクシー代ってどの勘定科目になるの?」
「ガソリン代って交通費に含まれるの?」
などなど交通費に関してちょっとした不安や疑問を感じたことはないでしょうか。
交通費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。そこで今回は交通費に関するよくあるQ&Aや経理担当者が知っておくべき交通費の基本知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
交通費精算に関する情報をいつでも確認できる教科書のような形の資料になっております。
資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひこちらからダウンロードの上、有効にご活用ください。
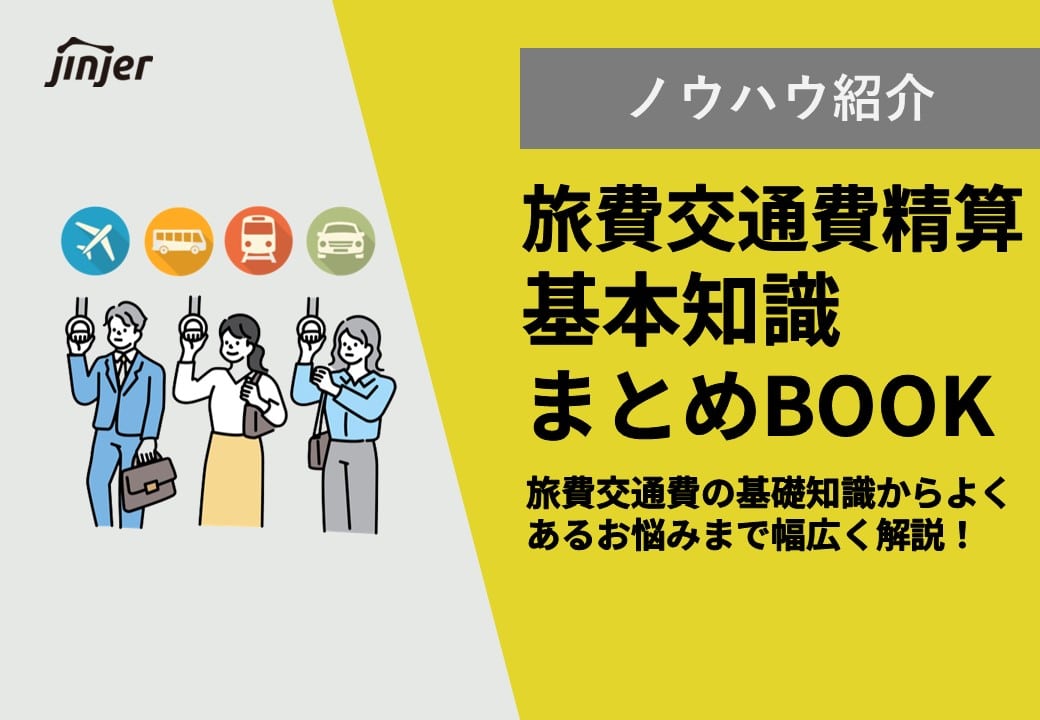
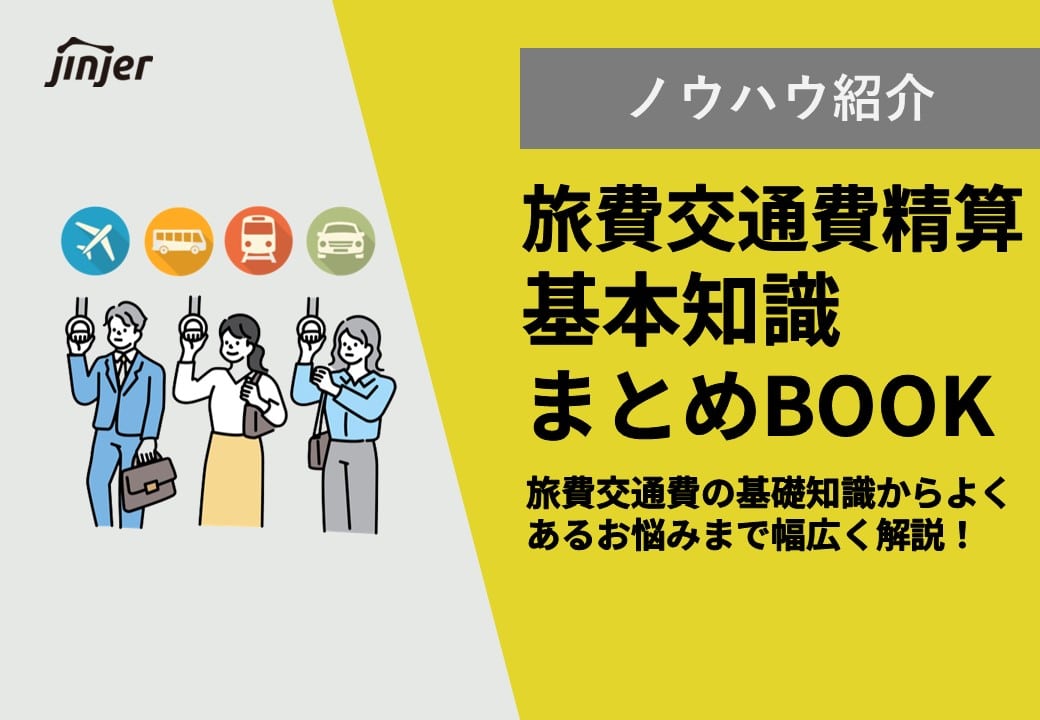
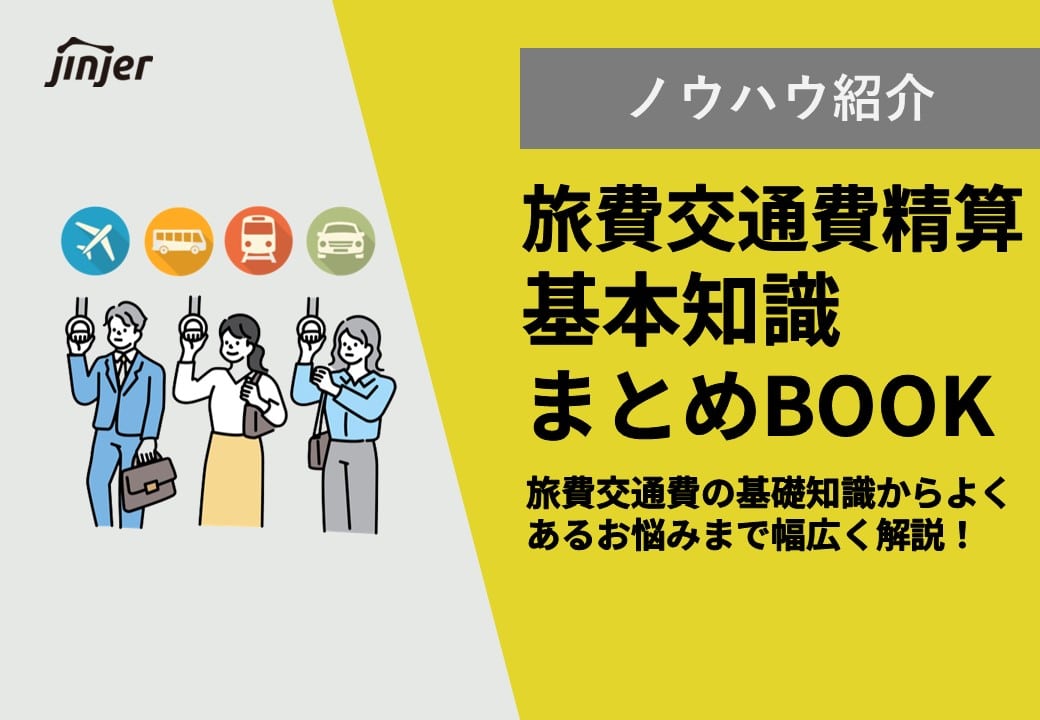
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
書き方の関連記事
-


報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説
人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24
-


顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介
人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24
-


回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26
交通費精算の関連記事
-


交通費精算のDXとは?注意点や導入時のポイントを解説
経費管理公開日:2023.06.02更新日:2024.10.07
-


交通費精算の電子化は必要?メリットやルールを解説
経費管理公開日:2023.06.01更新日:2024.10.07
-


ETC料金は経費精算できる?勘定科目や必要書類を紹介
経費管理公開日:2023.05.09更新日:2024.10.07




















