労働保険料を仕訳する際のポイントや具体例を紹介
更新日: 2024.7.2
公開日: 2022.5.11
jinjer Blog 編集部

事業主には、事業税や法人税などの負担義務がありますが、社会保険料も支払わなければなりません。社会保険にも種類がありますが、職種や業務にかかわらず負担義務となっているのが雇用保険や労災保険に対して支払う「労働保険料」です。
労働保険料というのは仕訳方法によって使用する勘定科目が異なりますが、基本的には福利厚生の費用に分類されるため法定福利費という科目になります。法人税や所得税とは異なるので、租税公課には当たらないため注意が必要です。
ここでは、労働保険料の制度内容や支払時期、仕訳方法などについて解説していきます。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 労働保険とは


労働保険とは、雇用保険と労災保険のことを指し、社会保険の一種です。労働保険について正確に理解をしておかないと、仕訳の際に間違えてしまうことがあるので、具体的な役割と費用分担を確認しましょう。
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進を目的として失業者などに対して失業等給付を支給する制度(保険料は事業主と労働者が折半)
労災保険は、業務または通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために給付を行う制度(保険料は全額事業主負担)
雇用保険や労災保険などの労働保険は、例え従業員が1人であったとしても、事業主には加入義務があります。労働保険に加入することで失業や勤務中の事故などに備えることができ、従業員が安全に安心して働くためには必要不可欠な制度です。
2. 労働保険料の仕訳とは


労働保険は事業主負担と従業員負担があり、複数回に渡って仕訳をする必要があります。
一見すると制度内容は経理担当者に関係ないように思えますが、制度について理解することが適切な仕訳をするための近道です。
ここでは、労働保険料の支払時期や仕訳方法、個人事業主の仕訳について解説します。
関連記事:仕訳とは?借方・貸方の考え方や仕訳の手順をわかりやすく解説
2-1. 労働保険料の支払時期
労働保険料の支払は、前年度に支払っている保険料を精算する「確定保険料」と新年度の保険料を概算で支払う「概算保険料」に分かれています。そして毎年6月〜7月に、この2つの手続きを行うことを労働保険の「年度更新」と言います。また、労働保険料が40万円以上の場合3回に分けて納付することができます。
労働保険料の支払においては、前払いであることと過不足分は後で清算するスタイルであることがポイントです。
2-2. 労働保険料の仕訳方法
労働保険料の仕訳の方法としては大まかに3種類あります。
・概算保険料の支払いや確定保険料の過不足など一貫して法定福利費で仕訳をする方法(従業員数の少ない中小企業が利用する)
・概算保険料を前払費用として支払い、毎月の従業員の給料から差し引く保険料を預り金とし、確定保険料での過不足を法定福利費で調整する方法
・概算保険料の納付を前払費用とし、会社負担分を毎月法定福利費として仕訳し、決算時に不足分を未払費用として計上する方法(従業員数の多い大企業が利用する)
仕訳方法は従業員数の規模で判断されることが多いですが、従業員数が多い中小企業もありますので、心配になったときは早めに税理士に相談しましょう。
2-3. 個人事業主の労働保険料の仕訳について
個人事業主が支払う労働保険料は、会計処理においては「保険料」という勘定科目に仕訳されます。
しかし、税法上では「経費」に該当するため、支出側の取引として記載しなければならない点に注意しましょう。また、概算保険料を納付するときに払う費用は「仮払保険料」という勘定科目になり、保険料が確定して差額が発生した場合は差額を調整する勘定科目への変更するという点にも注意してください。
このように、個人事業主の労働保険料の仕訳は面倒な点が多いのですが、保険料を経費として計上すれば税金の負担を軽減できます。経費として計上し事業の利益を抑えることは節税効果につながるので、税法をしっかり理解して、適切なタイミングで経理処理をすることが重要です。
3. 労働保険料の勘定科目


労働保険料を仕訳する際に必要になる勘定科目は、下記の3つが主流になります。
- 法定福利費
- 前払費用
- 預かり金
ここでは、それぞれの勘定科目について解説します。
3-1. 法定福利費
法定福利費とは、法律で定められた福利厚生に関わる費用のことで、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災)のことです。
法定福利費は福利厚生費と混同しやすいですが、異なる勘定科目となるので仕訳の際には注意しましょう。
3-2. 預り金
預り金とは、従業員などから一時的に預かった金額を処理する科目のことです。
源泉徴収した所得税や社会保険料、雇用保険料のことを意味します。
雇用保険で支払う費用は、事業主と労働者で折半すると決められているため、仕訳では「預り金」に分類されます。
3-3. 前払費用
前払費用とは、一定の契約に従って継続して役務の提供を受ける場合に、未提供の役務に対して支払った対価を意味します。
労働保険料は前払いが原則となるので、保険料の支払いでは「前払費用」の勘定科目を使用します。
4. 労働保険料を仕訳する際のポイント


労働保険料を仕訳するときのポイントは、下記の3種類の仕訳方法のどれを採用するかによって勘定科目が異なるという点です。
- 全て同じ勘定科目で仕訳する場合は、法定福利費を使用する
- 確定保険料納付時に法定福利費として仕訳する場合は、法定福利費の他に概算保険料を前払費用、従業員の給料から差し引いた分に預り金を使用する
- 事業主負担分を毎月法定福利費として仕訳する場合は、法定福利費以外に概算保険料を前払費用、従業員の給料から差し引いた分を預り金、決算時に未払費用を使用する
これらの仕訳方法に沿って、適切な勘定科目を使用するようにしましょう。また月ごと、年ごとに処理をする費用となるので、ばらばらにならないように一貫した仕訳方法を徹底してください。
また、仕訳方法を判断するには、「どのような支払いフローの時」に「どのような仕訳が必要なのか」を詳しく知っておく必要があります。
普段なかなか使わない勘定科目だと、どのように仕訳をするか忘れてしまったり、間違いがないか心配になったりすることもあるのではないでしょうか。
そんなときには、当サイトでお配りしている「勘定科目と仕訳のルールブック」をご覧ください。80種類以上の勘定科目とその仕訳例が記載されており、不安を解消しながら仕訳をすることができます。こちらから無料でダウンロードして頂けますので、勘定科目や仕訳方法の確認にご活用ください。
関連記事:仕訳帳とは?決算書でも使用される5つの分類と注意点を解説
5. 労働保険料の仕訳例
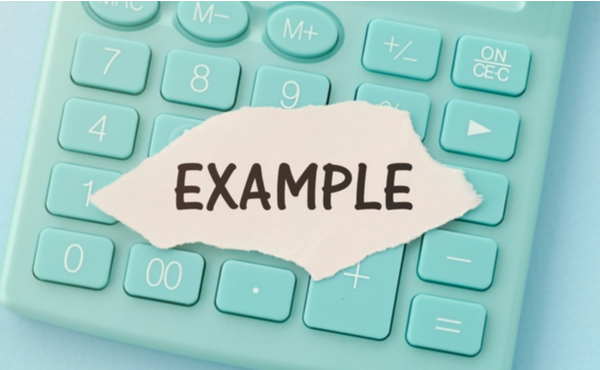
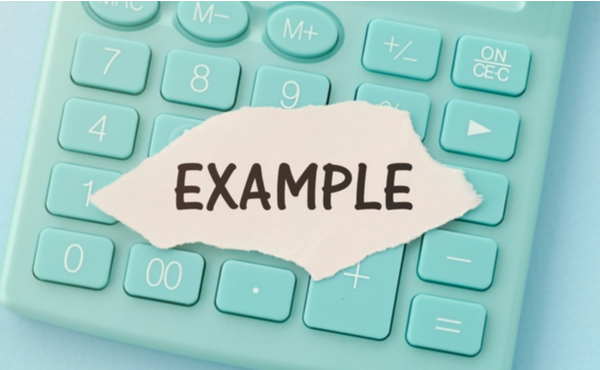
労働保険料の仕訳方法は、主に下記の3種類になります。
- 一貫して法定福利費で仕訳をする
-
清算時に法定福利費で調整して仕訳する
- 事業主負担分を毎月法定福利費で仕訳する
ここでは、これらの仕訳方法を下記の例に沿って解説していきます。
【具体的な例】
概算保険料1,800円を3回に分割して納め、確定保険料2,500円とし、不足が700円出る設定で仕訳をする
また、概算保険料の内、年間600円を従業員負担とする
5-1. 一貫して法定福利費で仕訳する場合
労働保険料を全て法定福利費で仕訳する場合は、以下のようになります。
1.概算保険料支払時には、借方が法定福利費/600円、貸方が現金/600円として年3回の納付時に仕訳する
2.従業員の給料から差し引いた保険料分を借方が給料/50円、貸方が法定福利費/50円として毎月仕訳する
3.確定保険料の精算時に不足分の700円を法定福利費/700円、貸方が現金/700円として仕訳する
全てを法定福利費として仕訳をすると、分かりやすく簡単に仕訳することが可能です。他の勘定科目を使用することなく、決算での処理も必要ありません。
ただし、従業員数が増えてくると、法定福利費が増加するので気をつけましょう。
5-2. 清算時に法定福利費で調整して仕訳する場合
確定保険料の清算時に、不足分を法定福利費で調整して仕訳する場合は以下のようになります。
1.概算保険料支払時には、借方が前払費用/600円、貸方が現金/600円として年3回の納付時に仕訳する
2.従業員の給料から差し引いた保険料分を借方が給与/50円、貸方が預り金/50円として毎月仕訳する
3.途中で従業員が増えたため、預り金の年間総額が150円増えて750円となった
4.確定保険料の精算時に、借方を預り金/750円、法定福利費/1,750円、貸方を前払費用/1,800円、現金/700円として仕訳する
確定保険料の精算時に法定福利費を調整するのがポイントです。決算での対応もないため、シンプルに仕訳することが可能です。
5-3. 事業主負担分を毎月法定福利費で仕訳する場合
事業主負担分を、毎月法定法定福利費で仕訳する場合は以下のようになります。
この方法は不足分を決算時に未払費用として処理するので、注意しましょう。
- 概算保険料支払時には、借方が前払費用/600円、貸方が現金/600円として年3回の納付時に仕訳する
- 従業員の給料から差し引いた保険料分を借方が給与/50円、貸方が預り金/50円として毎月仕訳する
- 事業主負担分を借方が法定福利費/100円、貸方が未払費用/100円として毎月仕訳する
- 年度末において確定保険料を清算するため、借方を未払費用/1,200円、預り金/750円、法定福利費/1,750円、貸方を法定福利費/1,200円、前払費用/1,800円、未払費用/700円として仕訳する
この仕訳方法は、毎月会社負担分を計上する必要があるので、概算保険料1,800円から従業員負担の600円を差し引き、会社負担は年間で1,200円であることを最初に明確にする必要があります。
また、不足分の700円は確定保険料を納付するタイミングで支払うため、決算では未払費用として計上します。
6. 仕訳の考え方に沿って労働保険料を処理しよう


労働保険料は原則として前払いなので、概算時と確定後に差額が出ることがあるため仕訳が複雑です。特に、「前払費用」や「未払費用」などの勘定科目は、現金が動いた時期と費用を計上しなければならない時期にズレが生じた場合、ズレを調整するための勘定科目なので注意が必要です。
しかし、仕訳方法だけでなく、制度の内容を理解しておくとより仕訳がしやすくなります。仕訳の考え方に沿った適切な勘定科目を使用すれば、労働保険料も適切に仕訳をおこなうことが可能です。
従業員数の規模や考え方によって仕訳方法が異なりますが、担当者の方は制度の内容をしっかり理解してどのパターンでも正確に仕訳できるようにしておくと良いでしょう。
関連記事:仕訳帳の項目ごとの書き方や仕訳する際の考え方を紹介
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















