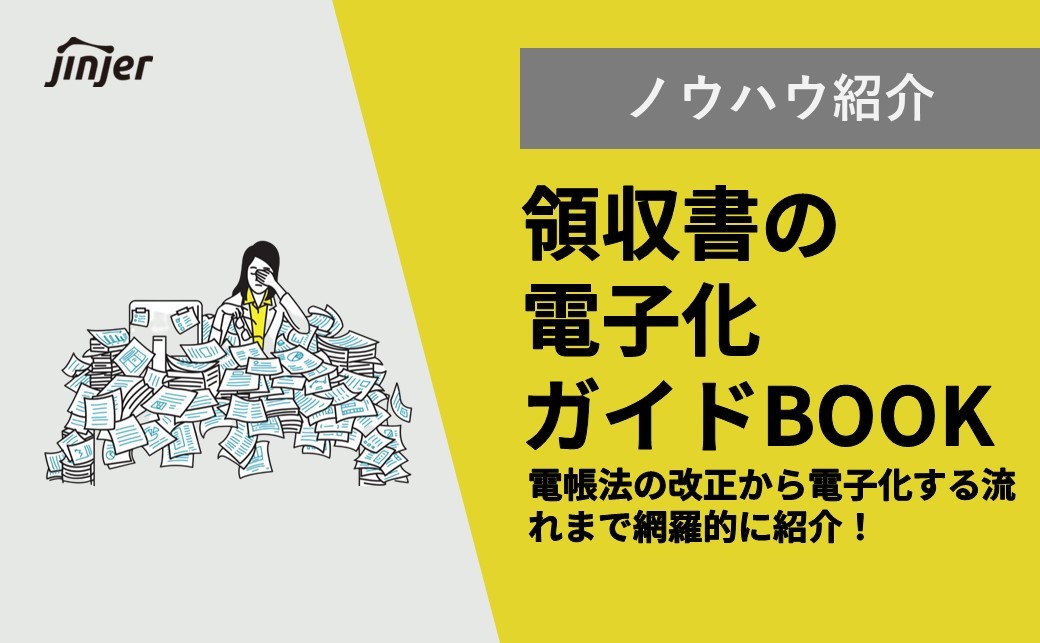領収書発行は現金決済とクレジット決済ではどう変わる?
更新日: 2024.3.8
公開日: 2021.1.12
OHSUGI

商品やサービスを提供した場合、代金を受領したことを証明するために領収書を発行します。
現在では支払い方法が多様化しているため、領収書の書き方もやや変わってきます。
そこで現金決済とクレジット決済それぞれの領収書発行方法の違いについて解説します。
「領収書がたくさんあって、管理しきれずに困ってる」
「経費精算の際に、申請書類と領収書のチェックに時間がかかる」
「電子化するためにシステム検討を始めたが、何からはじめたらいいかわからない」
「電子化したいが、電子帳簿保存法をしっかり理解できず困っている」
など領収書管理に関してお悩みではないでしょうか。
法改正もすすみ、中長期的には領収書を電子化することがのぞましいでしょう。領収書を電子化するためには電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを導入することが最も効率的です。当サイトでは電子帳簿保存法に対応したシステムでどこまで業務が効率化できるかをまとめた資料をご用意しております。資料は無料でダウンロードできますので、中長期的にシステムを検討したい方は是非ご覧ください。
1. 現金決済とクレジット決済それぞれの領収書の書き方

現在ではクレジット決済も推奨されているため、現金決済だけでなくクレジット決済による支払いも増えてきました。
クレジット決済では実際に現金をやり取りするわけではないものの、購入者が領収書を依頼すれば発行可能です。
では現金決済とクレジット決済それぞれの領収書の書き方について見ていきましょう。
1-1. 現金決済の領収書の書き方
現金決済の領収書にはいくつか書き方のポイントがあります。
領収書は支払いの証明となる重要な書類なので、必要な項目の記載がなければ領収書として認められなかったり会社として信用を失ってしまったりするかもしれません。
領収書の書き方は以下のとおりです。
まず「領収書」と中央上部もしくは上部左側に大きく記載します。
続いて宛名を記載します。取引相手が株式会社や有限会社である場合、(株)や(有)と略さず正式に書いた方がよいでしょう。
宛名が空白の場合には領収書が無効であると判断されることもあるので注意しましょう。
さらに金額にも細かいルールが決められています。
まず先頭には「¥」を書き、末尾には「-」や「※」と書きます。
加えて数字は3桁ごとにコンマを打って金額の改ざんを防ぎます。
領収書には但し書きも記入しなければなりません。
どんな商品やサービスに対して支払われた代金なのかをできるだけ具体的に記載します。
もし但し書きに記載しきれない場合には、納品書などを添付して第三者からも何の目的で領収書を発行したかが分かるようにします。
さらに領収書の発行者、発行した日付を記入し、領収書の金額が5万円を超える場合には収入印紙を貼ってから消印を押します。
関連記事:領収書の金額の書き方|内訳や但し書きの記載方法を解説
1-2. クレジット決済の領収書の書き方
クレジット決済で領収書を求められた場合、現金決済の領収書とはやや異なります。
そもそもクレジット決済ではレシートやお客様控えが領収書の代わりとなるので、領収書を必要とするケースは多くありません。
しかしもし代金を支払った企業や個人から領収書の発行を依頼された場合、領収書を発行することは可能です。
基本的な書き方は現金決済の領収書と同じですが、一つだけ異なるポイントがあります。
それは「但し書き」の部分です。
但し書きには、「クレジットカード払いによる」といった記載をして、支払い方法がクレジット決済であったことを明記しなければなりません。
これは代金を支払った企業や個人と、クレジットカード会社の両方から二重に支払いを受けたのではないかという疑いをかけられないためです。
1-3. 現金決済・クレジット決済を併用した領収書の書き方
現金決済とクレジット決済を併用した支払いが発生するケースもあります。現金、クレジットを併用した決済であっても領収書の発行は可能です。クレジット決済であれば収入印紙を貼り付ける必要はありません。しかし、現金とクレジットを併用した場合、現金の支払いが5万円以上であれば収入印紙の貼り付けが必要です。
2. 現金決済とクレジット決済の領収書相違点

現金決済とクレジット決済の領収書にはいくつかの相違点があります。
領収書を発行することがある場合は、その相違点についても覚えておく必要があるでしょう。
現金決済とクレジット決済の領収書相違点を3つ解説します。
2-1. 現金決済の領収書は義務、クレジット決済の領収書は義務ではない
まず大きな相違点といえるのは、領収書の発行が法的な義務かどうかという点でしょう。
そもそも領収書とは、代金の支払いが確実に行われたことを証明するものです。
そのため現金決済で代金が支払われたのであれば、領収書を発行するのは法的な義務となります。
これは民法第486条に定められており、もし代金を支払った企業や個人が請求書の発行を請求したなら、代金を受け取った側は必ず領収書を発行しなければなりません。
もし領収書の発行を拒否する場合、代金を支払う側は支払いを拒否することも可能です。
一方クレジット決済の領収書の場合はそうではありません。
クレジット決済では現金のやり取りがないため、通常領収書の発行が行われません。
領収書が発行されない代わりに、レシートや利用明細書などが領収書の代わりになります。
もちろん代金を受け取った側がサービスとして領収書を発行することはあり得ますが、現金決済の領収書とは違い、正式な書類とはならないことを覚えておきましょう。
参照:民法|e-Gov法令検索
2-2. クレジット決済の領収書では必ず但し書きが必要
現金決済では但し書きの部分にどんな商品やサービスが提供されたかを具体的に記載しなければなりません。
例えば「お品代」といった但し書きは具体性がないため、税務署から指摘される恐れがあります。
「印刷用紙代」や「書籍代」などのようにできるだけ詳しく記載しましょう。
第三者から見てどのように経費が使われたか明確にわかるように記載することが重要です。
一方でクレジット決済の領収書では必ず但し書きにクレジット決済であることを記載する必要があります。
但し書きを忘れると、税務署から指摘される可能性があるので注意が必要です。
2-3. 収入印紙の有無
収入印紙とは、税金を納めるために納付者が購入する証票です。
現金決済の領収書の場合、金額が5万円以上になると課税文書となるため収入印紙を貼らなければなりません。
5万円未満の領収書の場合には、現金決済であっても非課税文書になるため収入印紙は必要ありません。
- 5万円以上100万円以下の領収書:200円分の収入印紙
- 100万円以上200万円以下の領収書:400円分の収入印紙
と金額によって税額が決められています。
一方クレジット決済の領収書は正式な書類ではないので、金額にかかわらず収入印紙は不要です。
関連記事:領収書に貼付する収入印紙に割り印が必要な理由を詳しく解説
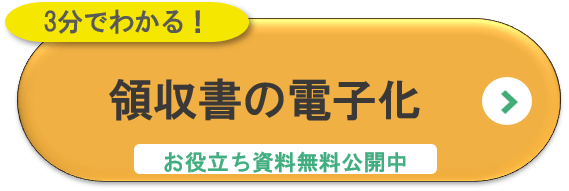
3. 現金決済とクレジット決済の領収書発行の注意すべき2つのこと

現金決済であれクレジット決済であれ、領収書を発行する際には注意すべき点があります。
では領収書発行の際の注意点について見ていきましょう。
3-1. 領収書の再発行は基本的に不可
現金決済やクレジット決済で領収書を発行したにもかかわらず、受け取った側が紛失してしまうことがあります。
そのような場合、領収書の再発行を依頼されるかもしれませんが、基本的に領収書の再発行はできません。
現金決済では領収書の発行は法的な義務ですが、再発行はそうではありません。
複数の領収書を発行させて経費を水増しするといった不正が行われる恐れもあります。
共犯の疑惑をかけられないためにも、領収書の再発行には応じないようにしましょう。
ただし領収書が汚損・破損してしまったという理由で、元の領収書を持参のうえ再発行を依頼されたのであれば、再発行が可能な場合もあります。
関連記事:領収書の再発行は可能?依頼された際の対応や注意点を解説
3-2. 領収書の控えを保管しておく
領収書は企業や個人が、代金を支払ったことの証明として発行を依頼するものです。
そのため領収書を渡してしまうと、領収書を発行した側は取引を行った記録となるものが何もなくなってしまいます。
領収書を受け取った側は最大7年間保管する法的義務がありますが、発行した側はそうではありません。
お金の流れを証明する書類を残すためにも、領収書の控えを保管しておくことが賢明です。
しかし領収書を保管するのも限界があり、単純に管理するコストや経費精算の際の経費申請書と領収書の突合作業など、紙で管理すると面倒なことが多くあります。そのため中長期的には領収書を電子化して業務を効率化することがのぞましいでしょう。
当サイトで無料配布しております「領収書の電子化ガイドブック」では、システムを通して領収書を電子化し、経費精算業務を効率化する方法を解説しております。領収書管理を楽にしたいとお考えの方には大変参考になる情報がございますので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
関連記事:領収書の保管期間は5~10年!知らないとまずい基礎知識
4. 現金決済とクレジット決済の領収書の違いを把握して正しい使い方をしよう

現金決済とクレジット決済とでは、領収書の書き方などに違いがあります。
この点をしっかり把握しておかないと、取引先や税務署とトラブルになる恐れがあるので注意が必要です。
それぞれの決済の方法による領収書の書き方の知識を身に付け、正しく領収書を発行できるようにしましょう。
関連記事:クレジットカード決済で領収書が必要なときの発行手順を紹介
「領収書がたくさんあって、管理しきれずに困ってる」
「経費精算の際に、申請書類と領収書のチェックに時間がかかる」
「電子化するためにシステム検討を始めたが、何からはじめたらいいかわからない」
「電子化したいが、電子帳簿保存法をしっかり理解できず困っている」
など領収書管理に関してお悩みではないでしょうか。
法改正もすすみ、中長期的には領収書を電子化することがのぞましいでしょう。領収書を電子化するためには電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを導入することが最も効率的です。当サイトでは電子帳簿保存法に対応したシステムでどこまで業務が効率化できるかをまとめた資料をご用意しております。資料は無料でダウンロードできますので、中長期的にシステムを検討したい方は是非ご覧ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04