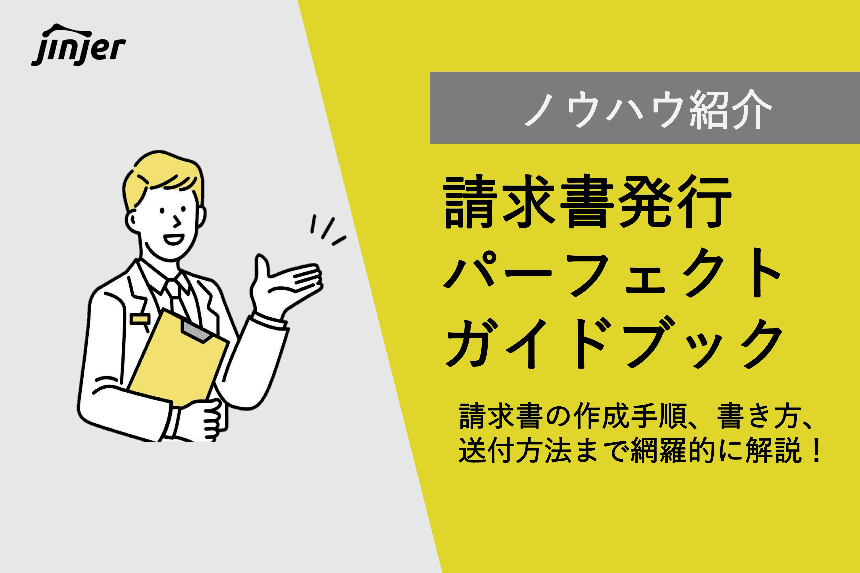領収書に貼付する収入印紙に割り印が必要な理由を詳しく解説
更新日: 2024.10.8
公開日: 2021.1.12
jinjer Blog 編集部
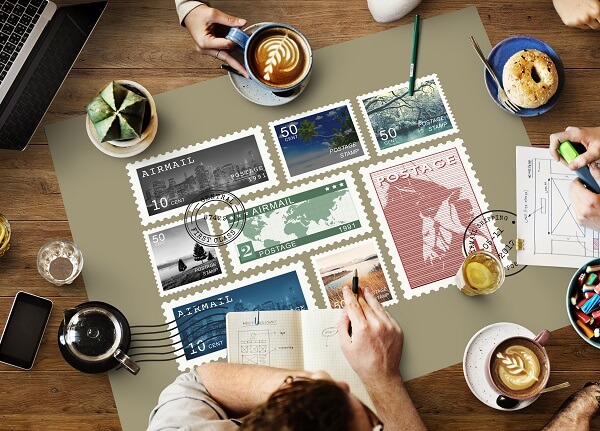
領収書には「収入印紙」を貼付し、その上から「割り印」を押印する必要のある場合があります。
収入印紙や割り印がないと「過怠税」が課されることがあるので注意が必要です。
本稿では、どのような場合に領収書に収入印紙と割り印が必要なのかと、正しい割り印の方法を解説します。
「なぜ割印を押す必要があるのか知りたい」
「失敗したら印紙代がもったいないので、割印を押すときは緊張している」
「割印に失敗したときの対応方法がわからない」など、収入印紙の扱いや割印について理解を深めたい方におすすめの資料です。
課税文書は、作成時に収入印紙を貼る必要があります。このとき、割印を押さなければなりません。押し忘れた場合、「過怠税」が課せられる可能性もあるため、注意しましょう。
当サイトでは、本記事の内容をわかりやすくまとめた「収入印紙における割り印を解説」という資料を無料配布しています。収入印紙における割り印に関しての基礎知識やよくあるQ&Aなどをまとめており、大変参考になる資料です。ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 領収書の収入印紙はいくらから必要?

国税庁の「金銭又は有価証券の受取書、領収書」と「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」によると、受領金額が5万円以上の受領証書(領収書)には、次の金額一覧に記載されている額に応じた印紙税(収入印紙)の支払いが義務付けられています。
| 受領金額 | 印紙税額 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円越え200万円以下 | 400円 |
| 200万円越え300万円以下 | 600円 |
| 300万円越え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円越え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円越え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円越え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円越え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円越え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
なお、上記の代金は商品やサービスなど、売上に関する領収書を発行する場合の印紙税額です。借入金や保険金など売上以外のものに関しては、受領金額5万円以上は一律200円の印紙税額が適用となる点に注意しましょう。
参照:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
参照:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
1-1. 収入印紙は郵便局やコンビニなどで購入可能
収入印紙は郵便局や各種コンビニのほか、一部ですが、法務局内の売店、看板に「印紙」が記載されているような酒屋やたばこ屋でも購入できます。
なお、コンビニでは200円の収入印紙しかないことが多いので、受領金額が大きな場合には郵便局や法務局で購入するのがおすすめです。
1-2. 印紙税は受領者と作成者がどちらが負担する?
印紙税(印紙代)は、書類の作成者(領収書の発行者)が負担するものです。なお、作成者が複数人いる場合には代表者が負担してもいいですし、全員で折半することもできます。
契約は全員が対等に関わるものなので、作成者が複数人いる場合には折半するのが一般的です。
関連記事:領収書における収入印紙の金額や貼り方、購入方法を解説
2. 領収書に収入印紙が不要な場合もある

先述したように、受領金額が5万円以上の領収書は、収入印紙の貼付が義務付けられています。
しかし、以下のような場合には、例外として5万円以上でも領収書に収入印紙は不要です。
2-1. クレジットカード払いで取引した場合
国税庁の見解では、受領証書(領収書)は「金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的」のものとされています。
そのため、クレジットカード払いのような信用取引では、金銭や有価証券の受領事実を証明できないことから、領収書に収入印紙を貼付する必要はありません
ただし、領収書には受領方法が「クレジットカード」であることを明記する必要があります。
明記していないと通常の受領方法とされ、収入印紙の貼付が求められるため要注意です。
関連記事:領収書発行は現金決済とクレジット決済ではどう変わる?
関連記事:クレジットカード決済で領収書が必要なときの発行手順を紹介
2-2. PDFデータなど電子データで取引した場合
国税庁の見解では、課税文書の作成について「PDFファイル等の電磁的記録に変換した媒体を電子メールを利用して送信した時は、課税文書を作成したことにはならない」とされています。
つまり、PDFデータなどの電子データで取引した領収書には収入印紙は必要ないのです。
ただし、一度は電子データで作成した課税文書であっても、これを印刷などをして現物(紙媒体)として発行した場合には、通常の領収書と同様に収入印紙の添付が求められます。
参照:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-1)|国税庁
3. 領収書に貼付した収入印紙に割り印が必要な理由
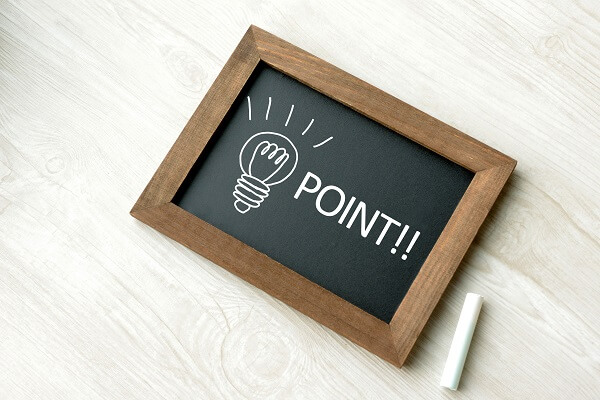
領収書に貼付される収入印紙は「割り印」を押印することで納付されたとみなされます。
割り印とは2種類の書類にまたがるように押印されたもので、これによりそれぞれの書類に関連性があることが証明されます。
つまり、領収書と収入印紙の関連性があると、内容の改竄や不正コピーの可能性がないと証明するためにも、収入印紙には割り印を押印する必要があるわけです。
関連記事:領収書に印鑑がない。経理上、税法上で問題はある?正しい領収書のつくり方
4. 領収書に貼付した収入印紙に割り印がないとどうなるの?

先述したように、領収書される収入印紙には「割り印」が必要とのことでした。
では、仮に割り印を押印し忘れたとして、発行側と受取側でどのような問題が発生するのかご説明します。
4-1. 発行側には印紙税法違反で「過怠税」が課せられる
発行側が領収書に貼付した収入印紙に割り印を押し忘れると印紙税法違反となり、本来の印紙税額に相当する金額の「過怠税」が課せられます。
本来の印紙税額が200円なら、過怠税も同額の200円です。
また、割り印の押し忘れだけでなく、そもそも収入印紙を貼付し忘れた場合には、本来の印紙税額とその額の2倍に相当する金額の過怠税を支払わなくてはいけません。
本来の印紙税額が200円だとしたら、過怠税は200円+200円×2=600円です。
ただし、領収書を作成したあと、収入印紙の貼付し忘れに気づいた際に所轄の税務署長にその旨を申し出ることで、過怠税を本来の印紙税額の1.1倍に減額ができます。
4-2. 受取側は領収書に収入印紙がなくても問題はない
収入印紙の貼付、割り印の押印はあくまで発行側の義務であるため、発行された領収書に収入印紙がない、または割り印が押印されていない場合でも、受取側には何の問題はありません。
また、収入印紙がなくとも、割り印がなくともその領収書の法的効力は有効とされます。
ただし、発行者との今後の関係を考えるのなら、気づいたときは指摘しておくのが望ましいでしょう。
5. 領収書の収入印紙の貼り方と正しく割り印する4つのポイント

領収書に収入印紙を貼付して、その上に割り印する際に正しく押印しないと効力が発揮されない可能性があります。
そこで、以下に収入印紙の貼り方と割り印の正しい押印のポイントを4つにまとめました。
5-1. 領収書に収入印紙を貼る場所は余白でOK
領収書に収入印紙を貼る場所については、税法上の決まりはありません。領収書であれば、あらかじめ貼り付け欄のあるものが多いため、そのまま貼り付け欄に貼付しましょう。
貼り付け欄が無い領収書の場合は、空いているスペースに貼っても構いません。収入印紙が複数枚あるときは、上下または左右に並べて貼るのが一般的です。
5-2. 領収書と収入印紙にまたがるように押印する
先述した通り、割り印とは2種類の書類の関係性を証明するためのもので、それぞれの書類にまたがるように押印する必要があります。
つまり、領収書の所定の位置に収入印紙を貼付したら、割り印は「領収書と収入印紙をまたがるように」押印するのが正しい方法なのです。
なお、押印の位置ですが、法的にどちら側と定められてはいないため、領収書と収入印紙をまたがるのであれば、収入印紙の上下・左右のどちらの方向に押印しても問題ありません。
5-3. 割り印には角印や名前入りの日付印を使う
割り印は発行者が誰なのかを把握できるようにする必要があります。
そのため、法人であれば社名が記載されたもの、個人事業主であれば屋号や代表者の名字が記載されたものを使用しましょう。
なお、印鑑の種類は角印や名前入りの日付印が一般的ですが、丸印やシャチハタ印でも問題はありません。
さらに「油性のボールペン」を使用して手書きでサインするのも、割り印として有効です。
5-4. 鉛筆でサインやボールペンでも斜線は無効
先述したように、割り印は手書きでも有効ではありますが、鉛筆のように簡単に消えてしまうものは認められません。
その他に、ボールペンでも斜線二重線を引いただけや、印鑑でも単に「印」とだけ印字されるような、発行者が誰なのか把握できないものも無効です。
とはいえ、領収書管理に関して毎回収入印紙の対応が必要なわけではないため、ふと収入印紙や割り印の対応が必要になった際にどう対応すれば良いかわからなくなることもあるでしょう。そのような方に向けて当サイトでは本記事の内容をスライド形式でわかりやすくまとめた「収入印紙における割り印を解説」という資料を無料配布しております。収入印紙や割り印における基本知識からよくあるQ&Aなどを網羅的にまとめており、気になった時にいつでもご確認いただけます。資料は無料ですのでこちらからダウンロードしてご覧ください。
関連記事:領収書を「手書き」で作成する際の7つの手順とポイントを徹底解説
6. 収入印紙の割り印に失敗したときの3つの対処法

領収書に収入印紙を貼付していると割り印の印影が欠けたり、必要以上に高額な収入印紙を貼付したりと失敗することがあります。
そのような場合は、以下の方法で対処できます。
6-1. 印影が欠けたときは位置をずらして再度押印する
割り印の印影が欠けたり、ズレたりして発行者が誰なのか不鮮明なときには、位置をずらして再度押印すれば修正できます。
失敗した割り印はそのままにしても、とくに問題ありません。
6-2. 押印前の収入印紙は郵便局で交換してもらえる
受領金額に応じたものよりも高額な収入印紙を誤って購入したり、5万円以下の貼付が必要ない領収書に貼付したりした場合は、手数料を支払って郵便局で交換してもらうことが可能です。
6-3. 押印後の収入印紙は印紙税の還付手続きができる
収入印紙にすでに割り印をしているものでも、領収書の書き損じや損傷などの理由で発行できない場合には、税務署で「還付手続き」をすることで印紙税の還付を受けることができます。
7. 金額によって印紙税額は変わる!割り印は忘れずに押そう

本記事では、領収書に貼付する収入印紙の金額や、正しい割り印の方法について解説しました。
収入印紙は領収書の受領金額が「5万円以上」の場合には貼付する必要があり、貼付した際には領収書と収入印紙にまたがるように割り印することで納付されたとみなされます。
ただし、取引をクレジットカード払いでした場合や、領収書をPDFデータのような電子データで発行した場合には、収入印紙は必要ありません。
そのため、収入印紙代を少しでも節約したいのであれば、クレジットカード払いや電子データで取引するのも1つの手です。
関連記事:領収書の金額の書き方|内訳や但し書きの記載方法を解説
「なぜ割印を押す必要があるのか知りたい」
「失敗したら印紙代がもったいないので、割印を押すときは緊張している」
「割印に失敗したときの対応方法がわからない」など、収入印紙の扱いや割印について理解を深めたい方におすすめの資料です。
課税文書は、作成時に収入印紙を貼る必要があります。このとき、割印を押さなければなりません。押し忘れた場合、「過怠税」が課せられる可能性もあるため、注意しましょう。
当サイトでは、本記事の内容をわかりやすくまとめた「収入印紙における割り印を解説」という資料を無料配布しています。収入印紙における割り印に関しての基礎知識やよくあるQ&Aなどをまとめており、大変参考になる資料です。ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
領収書の関連記事
-


領収書の役割とは?いつ使うもの?意味や定義、書き方を解説!
経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.07
-

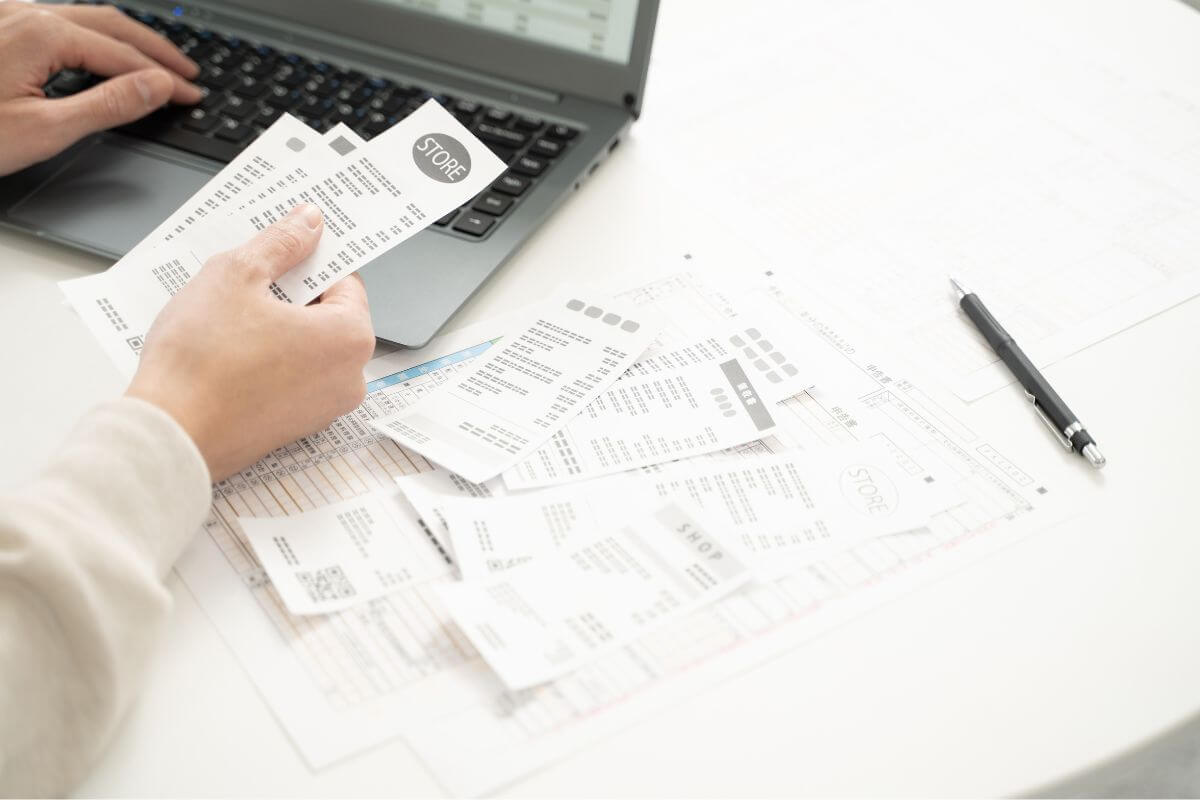
領収書の作成でおさえておくべきポイントは?必要なものや項目を解説
経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.07
-


領収書はPDFでも有効?PDFでの発行方法やメリット、原本の保存について解説
経費管理公開日:2024.03.18更新日:2024.10.07