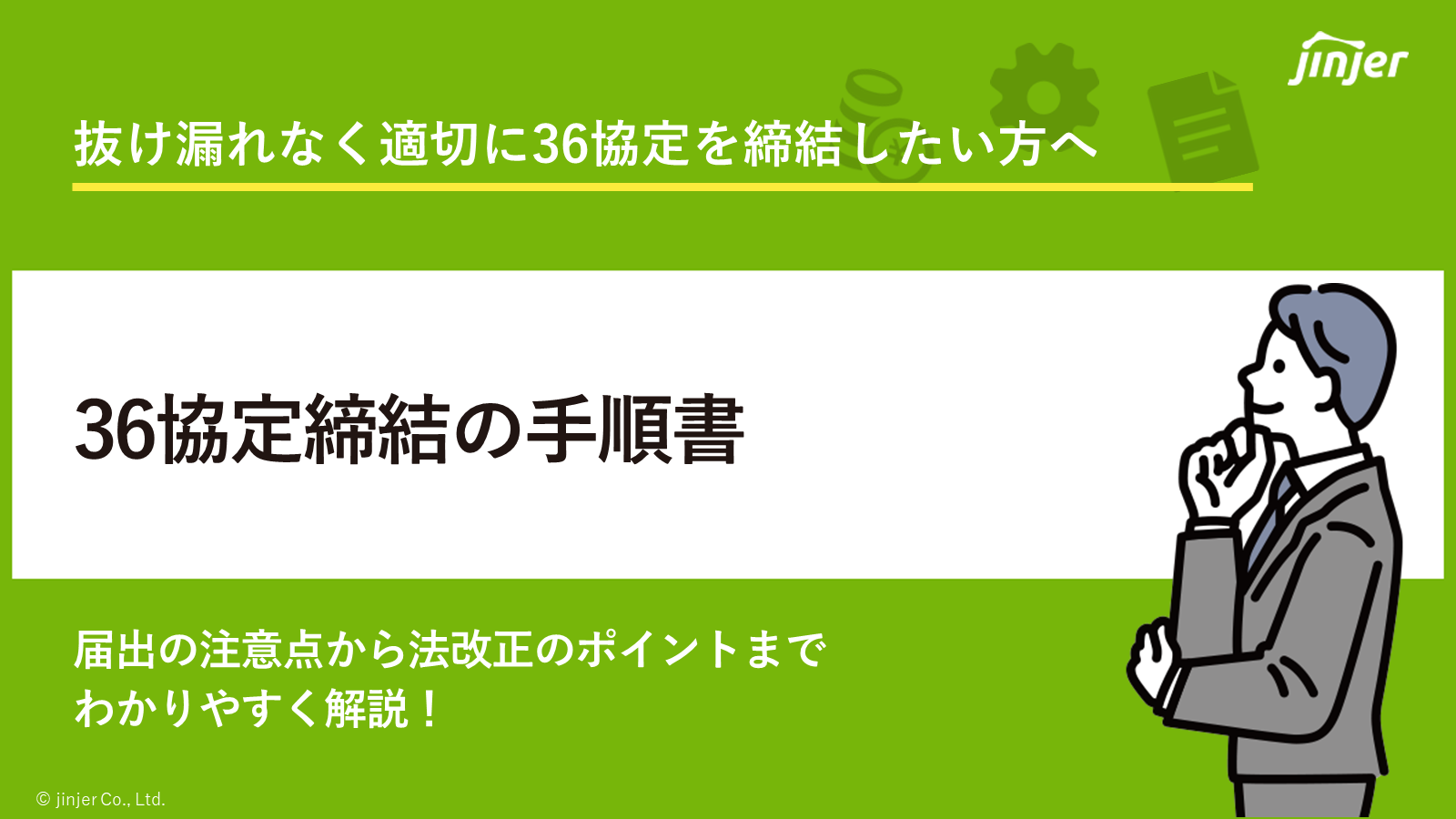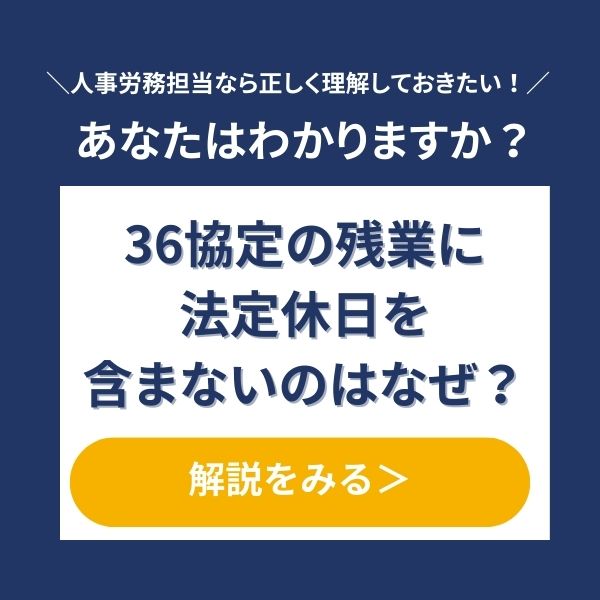副業時の36協定の考え方や事前に確認すべきポイント

日本では長らく「副業禁止」のルールが定着していましたが、平成30年1月に政府が副業・兼業を推進するためのガイドラインを策定・公表したのを皮切りに、近年は副業を容認する企業も増えてきました。[注1]
副業・兼業は労働者だけでなく、企業側にとっても「従業員のスキルアップにつながる」「人手不足を解消できる」といったメリットがありますが、本業のほかに副業をおこなうと労働基準法で規定する法定労働時間を超えてしまうおそれがあります。36協定を締結すれば法定労働時間を超えて働くことも可能ですが、協定の内容は本業先と副業先で異なる場合がありますので注意が必要です。
今回は、副業時の36協定の考え方や事前に確認すべきポイント、副業先の企業が知っておきたい注意点について解説します。
[注1]副業・兼業|厚生労働省
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
1. 副業時の36協定の考え方

副業を容認している企業であれば、従業員が副業をおこなうことは特に問題ではないものの、1つ注意しなければならないのが労働基準法で定められた「法定労働時間」です。
労働基準法第32条では、労働者の労働時間について、原則として休憩時間を除く1日8時間、週40時間を超えることを禁じています。[注2]
一方で、同法第38条では「事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定義しているため、本業先と副業先の法定労働時間は通算しなければなりません。
例えば、本業で休憩時間を除く1日8時間の労働を週5日おこなう場合、週の労働時間は40時間(8時間×5日間)に達するため、1時間でも副業をおこなうと法定労働時間をオーバーします。
労働基準法第32条に違反すると、同法119条の規定により、使用者(企業)は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられるおそれがあるほか、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性もあります。
こうしたトラブルを回避するためには、あらかじめ同法第36条で規定された36(サブロク)協定を締結し、法定時間を超えて労働する(させる)ことを労使間で合意しておく必要があります。
[注2]労働基準法|e-Gov法令検索
関連記事:36協定の違反になるケースや違反時の罰則について解説
1-1. 36協定の内容が本業先・副業先で異なる場合は?
36協定は労使間の話し合いのもと、事業場ごとに締結するものなので、同じ36協定でも本業先と副業先では内容が異なる可能性があります。
例えば、36協定では時間外労働について、1ヵ月45時間・1年360時間までという上限規制を設けていますが、その範囲内なら自由に時間外労働の時間を設定できるので、本業先(A社)の時間外労働の上限は1ヵ月45時間、1年360時間である一方、副業先(B社)では1ヵ月40時間、1年300時間を上限に設定しているというケースもあり得ます。
この場合、どちらの上限規制を適用するべきか迷ってしまうところですが、厚生労働省がまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によると、36協定(特別条項付き含む)によって延長できる労働時間の限度時間については、事業場間で通算しないこととしています。[注3]
なぜなら、36協定によって延長できる労働時間や上限規制は、あくまで個々の事業場における36協定の内容を規制するものであり、他の事業場の規制に何ら影響を与えるものではないと考えられるためです。
上記に挙げたケースなら、A社では「1ヵ月45時間、1年360時間」を上限とする時間外労働のルールが、B社では「1ヵ月40時間、1年300時間」を上限とする時間外労働のルールがそれぞれ適用され、各々の時間外労働の時間は事業場をまたいで通算されないことになります。
関連記事:36協定の特別条項とは?注意点と働き方改革関連法との関係
1-2. 変形労働時間制を採用している場合の36協定の考え方
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間(休憩時間除く)の法定労働時間を超えて労働させる場合、36協定を締結することを義務づけています。
ただし、法定労働時間を月単位・年単位で調整する変形労働時間制を採用している場合は、1ヵ月あるいは所定の範囲内の総労働時間が法定労働時間を超えない限り、従業員を1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働させても違法になりません。
具体的には、1ヵ月単位の変形労働時間制なら1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以内であれば問題ありません。それ以外の単位(1ヵ月を超え1年以内)の変形労働時間制は、対象期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以内なら36協定の締結は不要としています。[注2]
ただし、変形労働時間制を採用する場合は、労働基準法第32条の2および4の規定に基づき、労使間で協定を締結する必要があります。
また、変形労働時間制を採用していても、対象期間の1週間あたりの労働時間が40時間を超える場合は、労使間での36協定の締結が必須となるので注意しましょう。
2. 副業する前に確認すべきポイント

従業員の副業を容認する場合は、知らない間に労働基準法に違反することがないように注意しなければなりません。違反が発覚した場合、「知らなかった」では済まないこともあるので、当該従業員に対して、あらかじめ以下のポイントを確認するよう指導するのがベストです。
2-1. 副業先の36協定の有無を確認する
36協定は、あくまで法定労働時間を超えて労働させる際に必要となる協定ですので、法定労働時間を超える見込みがない会社では36協定を締結していない可能性があります。
労働契約を締結するにあたっては、他の事業場で労働しているか否かをあらかじめ確認するのが一般的です。副業によって法定労働時間を超えることがあっても、その責務を負うのは後から労働契約を締結した事業場、すなわち副業先となります。
そのため、本業先が責任を負うことはないので、確認は不要と思うかもしれません。しかし、36協定を締結していない企業で働くと、時間外労働や休日労働した場合の割増賃金を支払ってもらえない可能性があります。
自社の従業員が不当な条件で副業に従事することがないよう、副業先に36協定があるかどうか必ずチェックするようアドバイスしておきましょう。
2-2. 副業先の残業時間を確認する
36協定で規定する残業時間の上限は、勤務先によって異なります。残業時間は事業場をまたいで通算されないため、場合によっては副業先で長時間の残業を強いられることも考えられます。
兼業は労働者にかかる心身の負担が大きいので、副業での残業時間がかさむと、体調不良などを引き起こす原因となります。副業が原因で本業の業務に支障が出るというのは、企業の損益になってしまうので、従業員の健康管理のためにも残業時間の確認は必要事項といえるでしょう。
副業をおこなう従業員に副業先の残業時間を確認し、無理なく兼業できるかどうか、担当者が管理をすることが必要となります。
3. 副業先の企業が注意すべきポイント

他に本業を持つ労働者を雇用する際、必ず確認しておきたいのが本業先での労働時間です。
前節でも触れましたが、本業を副業の通算労働時間が法定労働時間を超えてしまった場合、その責務は後から労働契約を締結した副業先が負うことになります。
そのため、副業を希望する労働者を雇い入れる場合は、事前に本業での所定労働時間を申告してもらい、それに合わせて副業先での労働時間を設定する必要があります。
本業先の労働時間のみで法定労働時間の上限に達している場合、副業先の労働時間はすべて時間外労働となり、労働基準法第37条の規定により、所定の割増賃金を支払うことになるので要注意です。
また、時間外労働させる場合には労使間で36協定を締結していなければなりません。
もし自社で36協定を結んでいない場合は、本業の労働時間が法定労働時間に達していない労働者を雇用し、法定労働時間内で働かせるか、あるいは採用を機に労使間で36協定を締結するか、いずれかの方法を選ぶ必要があります。
関連記事:本業と副業で可能な労働時間とは?割増賃金や注意点についても解説
4. 副業を容認する場合は従業員の労働時間管理に注意

労働基準法では、事業場が異なる場合でも、労働時間は通算することと定めています。
同法では労働者の法定労働時間を、原則として1日8時間、週40時間(休憩時間除く)と規定していますので、本業と副業の通算労働時間がこれを超える場合、36協定を締結し、時間外労働について割増賃金を支払う必要があります。
本業と副業の労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えた場合の責務については副業債が負うことになりますが、本業先でも自社の従業員が安全に労働できるよう、副業先の36協定の有無や残業時間の規定の確認を促すなど、適切な指導をおこなうことが大切です。
副業先の方では、本業の労働時間を確認し、法定労働時間を超えていないかどうか、1日あるいは週に何時間労働させると時間外労働にあたるのか、正確に把握したうえで労働時間管理の徹底に努めましょう。
残業時間の法改正!ルールと管理効率化BOOK
働き方改革による法改正で、残業時間の管理は大幅に変化しました。
当初は大企業のみに法改正が適応されていましたが、現在では中小企業にも適用されています。
この法律には罰則もあるので、法律を再確認し適切な管理ができるようにしておきましょう。
今回は「残業時間に関する法律と対策方法をまとめたルールブック」をご用意いたしました。
資料は無料でご覧いただけますので、ぜひこちらからご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25