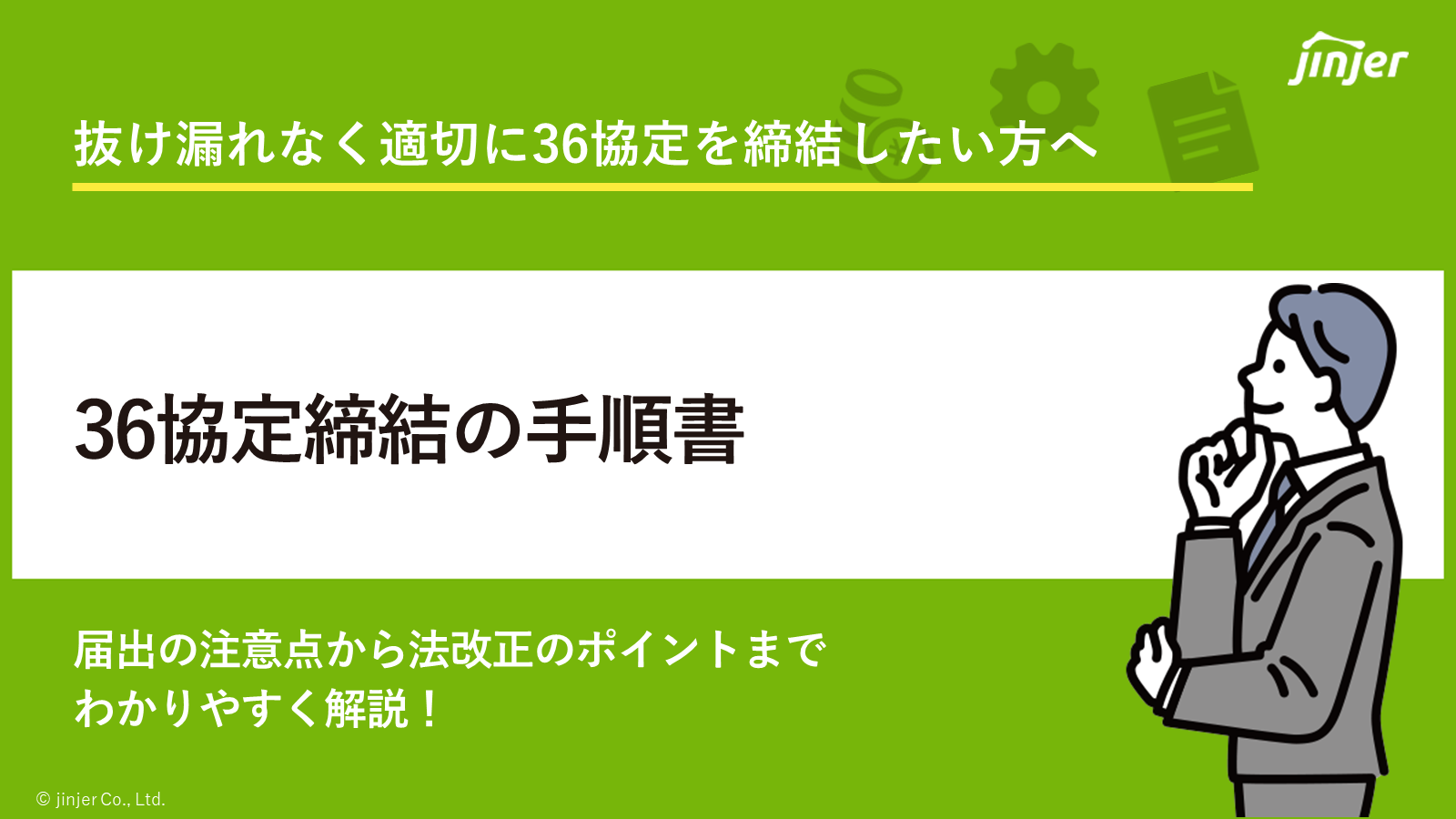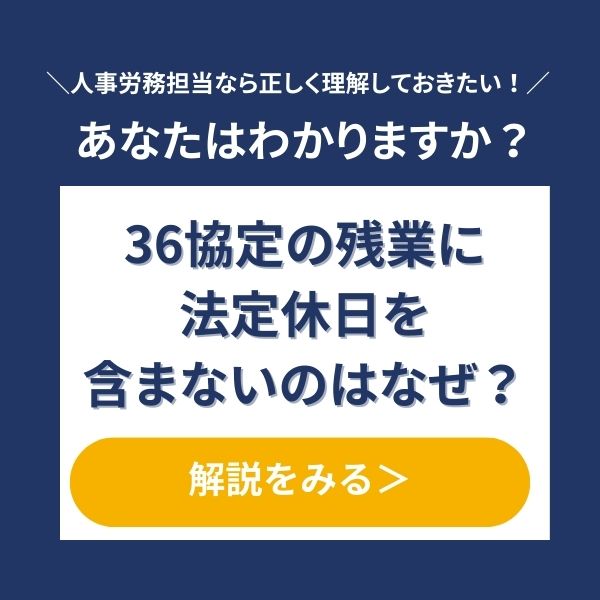36協定の違反になるケースや違反時の罰則について解説
法定労働時間を規定した労働基準法第32条に違反しないためには、同法第36条にもとづき、労使間で36(サブロク)協定を締結する必要があります。[注1]
36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働させることが可能となりますが、36協定にも一定の規制があり、それに反すると罰則の対象となります。
そのため、36協定を締結する際は、条項の内容をよく確認すると共に、労働基準法違反になるケースについて把握し、これを防ぐための措置を講じることが大切です。
今回は、36協定の違反になるケースや、違反した場合の罰則、違反を防ぐために企業が注意すべきポイントについて解説します。
[注1]労働基準法|e-Gov法令検索
目次
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
1. 36協定の違反になるケース

労働基準法第36条に基づく36協定に違反する主なケースを4つご紹介します。
ケース①:必要な届出をしないまま時間外労働をおこなわせる
労働基準法第36条では、使用者が労働者に同法第32条で規定された法定労働時間(休憩時間を除く1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合、労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定をし、行政官庁に届け出ることを義務づけています。[注1]
こうした届出や手続きをおこなわないまま、労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、労働基準法違反とみなされます。
たとえ労使間で合意があったとしても、書面で協定し、行政官庁(各地に設けられている労働基準監督署)に届け出なければ36協定が締結されたとはみなされませんので注意が必要です。
なお、36協定届が効力を発揮するのは、行政官庁にて書類が正式に受理された日となります。
36協定届には協定の有効期間を記載しますが、届出日より前の月日を記入していても、さかのぼって効力を発揮することはできません。
仮に2024年1月31日に協定し、36協定届の有効期間に「2024年2月1日より1年間」と記載したとしても、行政官庁に届け出た日が2024年2月4日だった場合、2月1日~3日までの3日間は無効となります。そのため、この期間中に時間外労働をおこなわせると違反になってしまうおそれがあるので注意しましょう。
ケース②:36協定の上限規制を超えて働かせる
36協定を締結すると、法定労働時間を超えて労働させることが可能となりますが、時間外労働の限度時間は原則として1ヵ月45時間、1年360時間が上限となります。[注1]
これを超えて時間外労働させると36協定違反となり、使用者は罰則の対象になるので注意しましょう。
なお、実際の時間外労働の上限は、労使間で締結した36協定の内容に準じます。
例えば、36協定で「1ヵ月40時間、1年300時間まで」と規定した会社で、1年間に310時間の時間外労働をおこなわせた場合、労働基準法上の上限(1年360時間)は超えませんが、その会社の36協定の内容には違反するため、労働基準法に抵触します。
ケース③:特別条項該当外なのに上限を超えて働かせる
36協定における労働基準法上の上限規制は1ヵ月45時間、1年360時間ですが、特別条項付き36協定を締結した上で、臨時的な特別な事情がある場合は、通常の36協定の上限規制を超えて労働させることが可能となります。[注1]
臨時的な特別の事情について、労働基準法第36条5項では「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」と定義しており、単純に「業務上必要と判断したから」「業務上やむを得ない事情があったから」といった理由は「臨時的な特別の事情」とは認められません。
特別条項付き36協定届(様式第9号の2)を提出する際も、「時間外労働(休日労働)をさせる必要のある具体的事由」の記載が必須となっており、あいまいな内容では受理されませんし、特別条項の適用による時間外労働の上限延長も不可となりますので要注意です。
なお、臨時的な特別の事情の一例としては、「予算、決算業務」「ボーナス商戦に伴う業務の繁忙」「急遽変更された納期のひっ迫」「大規模クレームへの対応」などが挙げられます。
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov法令検索
ケース④特別条項の上限を超えて働かせる
臨時的な特別の事情がある場合でも、時間外労働させる際は以下4つの項目を遵守する必要があります。[注2]
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2~6ヵ月平均で1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月まで
いずれか1つでもルールを破った場合、36協定および労働基準法違反となり、罰則の対象となります。
関連記事:36協定の特別条項とは?注意点と働き方改革関連法との関係
2. 36協定に違反した場合の罰則とは

36協定は、単に企業と従業員が結ぶ協定ではなく、労働基準法第36条に示されている協定なので、違反が発覚した場合は罰則が科せられる可能性があります。罰則は違反の悪質性などによって判断されますが、労働者に「ブラック企業」のイメージを持たれてしまうこともあり、優秀な人材確保が難しくなるかもしれません。
ここでは、どのような罰則があるのかを解説していきます。
3-1. 懲役もしくは罰金が科せられる
36協定に違反した場合、法定労働時間を規定した労働基準法第32条や、36協定について定めた同法第36条に抵触することになり、同法119条のもと、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。[注1]
注意したいのは、罰則の対象は36協定で定めた上限を超えて働いた労働者の方ではなく、その使用者であることです。
労働基準法上の「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義されており、主に以下が該当します。
法人・個人事業主
事業経営者(社長や取締役)
会社から一定の権限を与えられている人(中間管理職など)
一般的に、労働者の労働時間は労務管理が担当していますが、36協定の上限を超えて働かせるなどの違反が発覚した場合、直接の担当者である労務管理だけでなく、それを事業経営者も罰則の対象となります。
3-2. 企業名が公表されることがある
36協定違反の罰則は、懲役や罰金だけではありません。悪質性が高く、書類送検をされた場合は「企業名の公表」というケースもあります。
公表されるのは以下のような内容です。
-
企業名
-
所在地
-
企業概要
-
事案、違反した法律など
これらの情報が、厚生労働省や労働局のホームページ内に公表されます。企業名が公表されると、社会的な信用の下落やイメージが大きく損なわれることになります。
4. 36協定違反が発覚する3つのケース

36協定に違反をすると、懲役や罰金などの罰則だけでなく、社会的信用に関わる「企業名の公表」などのリスクがあるため、基本的には絶対に違反をしないように徹底することが重要です。しかし、担当者の業務が忙しかったりすると、管理が行き届かず違反してしまう可能性があるため注意が必要です。
ここでは、違反が発覚する3つのケースを紹介するのでチェックしておきましょう。
4-1. 従業員の通報による発覚
発覚するケースの一つとして、従業員自らが労働基準監督署に通報・相談するケースが挙げられます。
故意に違反していることもあれば、人事労務の担当者や直接の上司が気づかず違反してしまっていることもあるかもしれません。
いずれにしても、通報があれば労働基準監督署の調査が入るため、違反があれば発覚してしまいます。
特に、特別条項付き36協定を結んでいる場合は、条件項目が多すぎることで、勤怠の管理責任者が管理しきれていないこともあります。限度を超えた時間外労働をさせていないか、すぐに確認できる仕組みづくりも大切です。
4-2. 臨検監督による発覚
臨検監督というのは、実際に労働現場で36協定や労使協定で定めている労働条件が守られているかを確認する調査です。臨検監督は「申告監督」と「定期監督」があります。
申告監督は、前述した「従業員からの通報」を受けた場合、臨時で調査をおこないます。定期監督は、監督計画に基づいておこなわれる定期調査です。
「臨時」と「定期」という違いはあるものの、どちらも違反がないかを厳しくチェックするため、違反がある場合は発覚します。
4-3. 労働災害による発覚
就業時間中に事故や災害が発生したり、精神的、肉体的な病気になる従業員が多かったり、最悪の場合亡くなったりするなどの労働災害による発覚も少なくありません。こういったケースでは、労働災害の原因を追及する調査がおこなわれます。
その際に、従業員の長時間労働や過重労働などが原因と判断されると、違反が発覚することになります。労働災害による発覚は、例え故意でないとしても悪質性が疑われるため、「管理不足」や「協定の締結内容の問題」なども追求される可能性があります。
4. 36協定に違反しないための対策

36協定に違反しないために、企業が日頃から注意しておきたいポイントを3つご紹介します。
4-1. 労働時間の管理を徹底する
36協定を締結したとしても、時間外労働の時間には上限規制があります。
「気付いたら1ヵ月の上限を超えてしまっていた…」といったケアレスミスが起こらないよう、従業員ひとりひとりの勤怠管理を徹底することが大切です。
企業によっては、従業員の勤怠管理をExcelなどの表計算ソフトを使って手入力しているところもあるでしょう。しかし、手入力というのは、従業員が多いほど労務管理担当者の負担が増える上、ヒューマンエラーも発生しやすいので勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。
勤怠管理システムを導入すると、PCやスマホ、タブレット、ICカードなどから打刻できるほか、勤怠データが自動的にシステムに取り込まれて自動集計される仕組みになっています。そのため、人的ミスが発生しにくく、労務管理の負担も軽減されるので高い費用対効果が期待できます。
4-2. 従業員への周知
従業員の労働時間を管理するのは会社(労務管理)の役目ですが、従業員自身にも36協定における時間外労働の上限規制を把握してもらい、働き過ぎないよう留意してもらう必要があります。
36協定はもともと、労働基準法第106条の規定により、その内容を従業員に周知することが義務づけられていますので[注1]、作業場の見やすい場所への提示や備え付け、書面の交付といった必要な措置をおこなうのはもちろん、内容確認の呼びかけも徹底することが大切です。
4-3. テレワーク時のルール整備
近年は、働き方改革や新型コロナウイルスの影響により、自宅などで仕事に従事するテレワークやリモートワークを導入する企業が増えてきています。
完全テレワークの場合、従業員はオフィスに出社せずに働くことになるため、従来のようなタイムカードを使った打刻は不可能になります。
そのため、テレワーク導入にあたっては、「いつ仕事を開始・終了したのか」「どのタイミングで、どのくらい休憩を取ったか」など、労働時間に関する情報を正確に把握できるルール・環境を整えなければなりません。
具体的には、PC・スマホ・タブレットで打刻できる勤怠管理システムの導入や、就業ルールの見直しなどを行い、企業が労働時間を客観的に把握できる体制を整備しましょう。
関連記事:テレワーク・在宅勤務導入後の労働時間管理におすすめな方法3選
5. 36協定は違反になるケースの確認と防止策の徹底を!

36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働させることが可能になりますが、時間外労働の労働時間には上限規制があり、それを超えて働かせると36協定違反となります。
36協定に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられる可能性があります。このようなことにならないために、36協定で定めたルールに違反しないよう、日頃から労働時間の管理や従業員への周知、テレワーク時の環境整備などをしっかりおこなっておきましょう。
残業時間の法改正!ルールと管理効率化BOOK
働き方改革による法改正で、残業時間の管理は大幅に変化しました。
当初は大企業のみに法改正が適応されていましたが、現在では中小企業にも適用されています。
この法律には罰則もあるので、法律を再確認し適切な管理ができるようにしておきましょう。
今回は「残業時間に関する法律と対策方法をまとめたルールブック」をご用意いたしました。
資料は無料でご覧いただけますので、ぜひこちらからご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25