勤怠申請とは?概要や勤怠届(申請書)のフォーマットを紹介

「従業員の勤怠を抜け漏れなくチェックしないといけないのはなぜだろう?」「勤怠管理を正確かつ効率的におこなう方法はないか?」など会社を運営していく上で、従業員の勤怠の状況を適切に把握しなければならない理由や、効率的に勤怠管理する方法について悩んだことがある方は多いのではないでしょうか。
本記事では、勤怠管理がなぜ重要なのか知識を得た上で労務管理できるよう、勤怠管理の目的や申請書に記載してもらう必要事項、申請に必要な申請書の種類を紹介します。
関連記事:勤怠とは?管理方法や管理項目など人事が知っておきたい基礎知識を解説!
法律に則った勤怠管理をしていきたい方に向け、当サイトでは、法律で定められた勤怠管理の方法について解説した資料を無料で配布しております。
資料では2019年に改正された労働基準法に則った勤怠管理の方法も解説しているため、自社の勤怠管理が法的に問題ないか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。
1. 勤怠申請とは
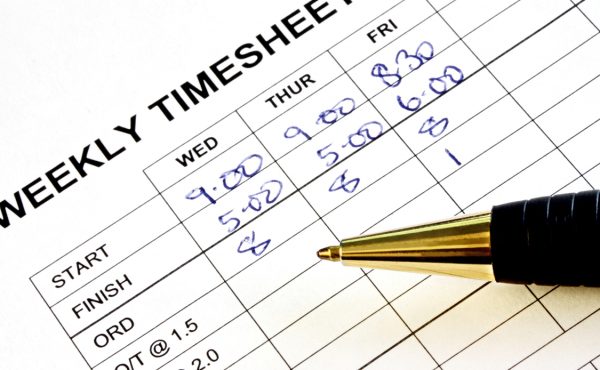
勤怠申請とは、時間外労働時間や深夜労働時間、休日出勤をした日数や遅刻欠勤があった日数などを申請することを指します。勤怠申請により、それぞれの項目に合わせた計算方法で給与計算をおこなったり、法定労働時間の範囲内になっているかを確認することができます。
また、勤怠とは出勤や退勤、休暇などの社員の「出勤状況」を示すものになっています。そして、社員の出社頻度や実労働時間などを把握し、就労規則など会社で決めたルールを遵守しているかを管理することを勤怠管理とよびます。
勤怠管理は従業員の労務状況を正しく把握するものであり、、正しく管理しておくことは健全な会社運営のために非常に大切です。
1-1. 勤怠申請で把握すべき時間の結論
企業の社内ルールによっても異なりますが、勤怠申請は従業員の労働時間がわかるようにおこなう必要があります。
たとえば、時間外労働(残業)をおこなう際や深夜労働、休日出勤や遅刻早退・欠勤など、給与計算のもとになる事項はすべて把握しておく必要があります。
さらに、有給休暇や代休・振休、特別休暇なども申請制にする企業は多く、従業員の勤怠情報を漏れなく把握するために勤怠申請が必要となります。
2. 勤怠申請をおこなう必要性
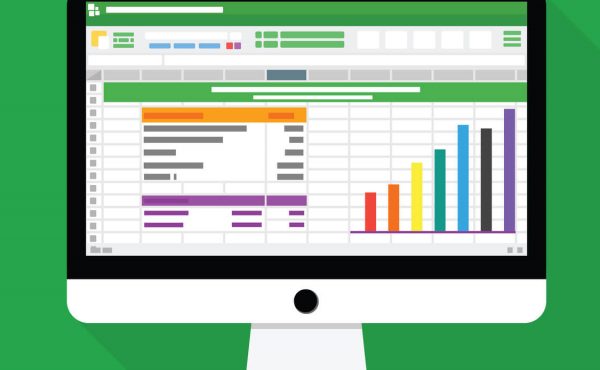
正しく従業員の勤怠を管理できなければ、後から修正するのも困難ですし監査があった際に指摘されても適切に返答できません。
ここからは、勤怠申請の必要性について解説します。
2-1. 会社側は従業員の労働時間を正確に知る必要がある
従業員の勤怠状況をしっかりと管理する目的は従業員がどれくらい働いているか、休んでいるかという勤務状況を正しく把握するためです。労働基準法にも客観的に労働時間を把握する旨が記載されています。
事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
会社の従業員といっても、正社員やパート、アルバイトや時短社員など様々な雇用形態があります。適切に従業員の勤務や休暇の状況を把握することで正確な労働日時が計算できていれば、客観的に見て正しく運営されている会社だと証明できるのです。
ただし、労務管理の主な目的は従業員の健康管理や給料計算のためにおこなうということが前提になることを忘れないようにしましょう。
関連記事:勤怠管理で気をつけるべきルールとは?見落とせない法律も解説!
2-2. 従業員の給与を間違いなく計算する必要がある
さまざまな勤務時間や雇用形態が増えてきている中で従業員の勤怠の状況を正しく把握できていれば、従業員の給与を正確に計算できます。
従業員がそれぞれがどの程度勤務したのかを把握しなければ、正しく給料を支払うことができなくなるばかりか、法律に則った労働時間の管理ができなくなってしまいます。
2-3. 思わぬトラブルに?勤怠を正しく申請しない危険性とは
勤怠状況を適切に管理できていない会社では、後になってトラブルが発生することもあります。
会社によっては退勤のタイムカードを押してから時間外勤務を開始するように命令していたり、法定労働時間に収まるように労働時間を調整しているところもあるようです。
このような会社は後で指摘されて勤務時間や給与を計算し直す労力がかかるのみでなく、労働基準法違反で厳しい処罰を受けることにもなりかねません。
当サイトでは働き方改革などの法改正によって新たに求められるようになった勤怠管理とその対策をまとめた資料「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」を無料配布しております。「自社の勤怠管理が違法でないか確認したい」「違法になりかねない勤怠管理を改善したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
関連記事:勤怠管理をしていない企業が抱える問題点と対処法とは
3. 勤怠管理に必要な勤怠届(申請書)フォーマット種類

近年では在宅ワークやリモート勤務といった、場所や時間を選ばずに仕事をするという働き方も増えてきました。時代の変化に合った働き方を推進させるためには、就業規則や勤怠管理の申請書を柔軟に更新していかなければなりません。
従業員の勤怠を適切に管理するためには、使いやすい申請書が必要な種類だけ用意されていることが不可欠です。
多様な働き方が推進されている中でも、勤怠管理を正しくおこなえるような申請書の種類を紹介します。
3-1. 勤務時間や出勤日数の申請書
勤務時間や出勤日数の申請書には、勤務日報や勤務変更届、勤怠届や超過勤務申請書などがあります。
例えば、勤務日報や勤務変更届は働く時間が変わったり、仕事が多く残業をすることになったりなど、勤務時間や出勤日数の変更の際に提出する必要があります。働く日数や時間に柔軟性を持たせている会社では、フレックス勤務申請書といった会社独自の申請書を設けることも適切に勤怠管理をする上で重要です。
勤務日報のフォーマットは、以下をご参照ください。
| 【勤務日報】
■今日の作業 本日の作業内容を簡潔にまとめます。複数の作業がある場合は、それぞれを列挙します。 ■今日の進捗・結果 行った作業の進捗状況や結果を具体的な数値を使って示します。感覚的な表現ではなく、具体的な数値を記載しましょう。 (例)商品の発送作業:12件の商品を発送しました。残り4件となります。 プレゼン作成:〇〇向けプレゼン作成の進捗率は70%です。 ■課題・改善点 作業を行う中で発生した問題点やお客様からの指摘事項、それに対する改善策を記載します。 ■明日の作業 明日に予定されている作業内容を簡潔に記載します。具体的で明確な情報を記入することが重要です。 |
勤務変更届・勤務時間変更申請書のフォーマットは、以下をご参照ください。
| 【勤務変更届・勤務時間変更申請書】
■部署、氏名: 氏名と所属部署を必ず記載しましょう。 ■期日: 変更希望日を指定します。1日の場合は「○月○日○曜日」とし、複数日にまたがる場合は「○月○日○曜日~○月○日○曜日 計○日間」と記載します。 ■時間: 遅刻や早退、半休(午前休や午後休など)の場合に必要です。また、勤務時間をスライドする際も漏れなく記載し、「○○:○○~○○:○○」と明確な時間を記述します。 ■事由: 病気・通院・慶事・弔事・介護などの理由を記載します。ただし、有給休暇取得時に事由を記入することに抵抗がある場合は、無記入でも構いません。 |
3-2. 休暇に関する申請書
休暇には様々な種類があるので、休暇の種類ごとに申請書のフォーマットを用意する必要があります。
有給休暇と特別休暇の申請書はもちろん、裁判員休暇取得申請書やボランティア休暇申請書、特別休暇申請書など、めったに使用する機会のないような申請書も就業規則に合わせて用意しておくことが大切です。
年次有給休暇申請書は、厚生労働省による参考様式が公開されています。必要に応じて、以下のフォーマットをご活用ください。
3-3. 特殊な場面で使用する申請書
基本的には会社で勤務しているものの、育児や介護などの理由で自宅で仕事をした方が時間を有効活用できるという従業員は、自宅作業許可申請書を使用して勤怠を申請してもらいましょう。
会社以外で仕事をする場合は、労働時間が変化しやすいので、従業員の作業時間や日数が労働基準法で定められている法定労働時間数を超えないよう、より厳密に把握しておく必要があります。
テレワーク勤務申請書を作成する際には、テレワークの定義や規定を明確にすることが重要です。就業規則の規定や、申請書作成には厚生労働省が公開している以下の資料をご活用ください。
4. 勤怠申請を楽にするなら、勤怠管理システムがおすすめ!

勤怠申請を紙ベースでおこなっている場合、申請書を印刷し、手書きで記入して提出先に渡しにいくなど、申請をするだけでも様々な工数が発生します。
また、提出された申請書を確認してタイムカードやエクセルに労働時間を反映することにも手間がかかるうえ、転記ミスや申請書の紛失リスクなども発生します。
勤怠管理システムであれば、PCやスマートフォンなどから従業員が申請書に必要事項を入力し、ワンクリックで申請が完了します。申請された内容は管理者が確認し、承認された後は自動で勤務実績に申請内容が反映されるため、人的ミスが発生しにくくなります。
システムの導入にはコストが発生しますが、自社に適した製品を導入できれば、費用以上の効果が期待できるため、導入すべきシステムといえます。特に従業員数が多い企業ほど人事担当者の負担は大きくなるので、導入による効果をより実感できるでしょう。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
5. まとめ

今回の記事では勤怠を正しく申請する必要性や、多種多様な働き方に対応できるような勤怠管理のフォーマットを紹介しました。紙ベースで勤怠管理をしていく方法に慣れている方は、就業規則に則った申請書を準備しましょう。
関連記事:適切な勤怠管理でトラブルを防ぐ | 承認時に注意すべきポイント
\\ 申請・承認ができる勤怠管理システムなら「ジンジャー勤怠」がおすすめ//
有給や残業など勤怠まわりの申請が手間で困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
勤怠管理システムの「ジンジャー勤怠」であれば勤怠まわりの申請業務を効率化することが可能です。
ジンジャー勤怠を導入すれば、
- パソコン・スマホアプリから有給休暇の申請・承認が可能
- 申請承認のワークフローも柔軟に調整できる
- シフトの申請や作成が可能
など勤怠まわりの申請・承認をシステム化したいと考えている方は、以下のフォームよりお気軽にご相談ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25




















