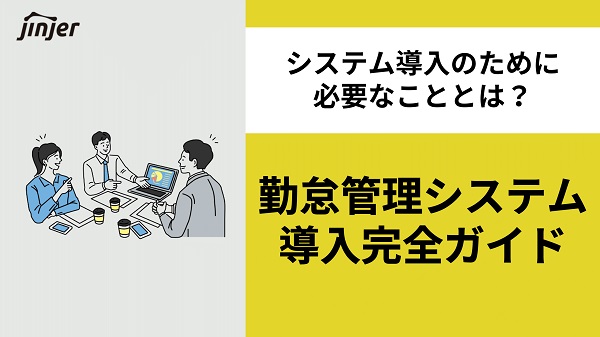勤怠管理で気をつけるべきルールとは?見落とせない法律の観点からみる注意点
更新日: 2024.6.4
公開日: 2020.2.21
OHSUGI

勤怠管理は人事担当者にとって重要な業務です。誤った管理をおこなうと、従業員に対して給与の未払いや基準を超えた労働をさせてしまう可能性があります。したがって、管理者は適切な管理をおこなうためにも法律上のルールを抑えておかなければなりません。
今回は、法令に基づいた勤怠管理の方法や、正確に管理する手段について紹介します。
勤怠管理システム提供会社が徹底解説!
働き方改革による業務効率化やDX化を背景に、クラウド型勤怠管理システムを利用する企業が増加しています。
しかし、システムといっても「そもそもどんなもので、何ができるの?」とイメージがつかない方も多いでしょう。
そこで当サイトでは、勤怠管理システムとは何か、どのようなことができるのかやシステムの選び方までを解説した「勤怠管理システム導入完全ガイド」を無料で配布しております。
「システムが便利なのはなんとなく分かるけど、実際にどのようなことができるのかを見てみたい」という方は、こちらからガイドブックをダウンロードしてご覧ください。
1. 企業には従業員の勤怠を管理する義務がある

勤怠とは、従業員が会社に在籍している間の勤務状況を意味しています。誰が何時に出社し、何時に退社し、いつ休み、いつ休憩をとったのか、それら全てが勤怠です。
人事担当者は、従業員が働いている時間も働いていない時間も、勤怠状況を把握して「管理」をおこなう必要があります。
ここでは、勤怠管理をする目的を解説します。
関連記事:勤怠とは?管理方法や管理項目など人事が知っておきたい基礎知識を解説!
1-1. 従業員の勤務状況を正しく把握する目的
使用者には、勤怠管理をおこなう義務があります。
労働安全衛生法第66条の8の3
事業者は第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
引用:労働安全衛生法第66条の8の3
すなわち、従業員が「働いた時間」「休んだ日」など勤務状況の全てを管理する必要があります。管理すべき項目として、以下の5つが挙げられます。
- 従業員が出勤した時間と退勤した時間
- 実際に労働した時間
- 残業した時間
- 有給休暇を取ったか否か
- 欠勤はあったか否か
以上の点を、正確にチェックしましょう。
1-2. 正しく給与計算をおこなう目的
会社は、従業員に対して働いた時間相応の給与を支払わなければなりません。例えば、1日8時間、22日働けば176時間分の給与が発生します。残業や休日出勤によって働いた時間が増えれば給与の加算が必要です。
しかし、正確な勤怠管理をせず、「実際は1ヶ月で200時間働いたのに残業代が一切入っていなかった」など、従業員にとって損害が生じる場合、トラブルに発展する場合があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、人事担当者は従業員の勤怠を細かくチェックし、正当な給与計算をおこなわなければならないのです。
1-3. 従業員の勤務状況を把握してトラブルを防ぐ目的
「法律で定められた労働時間を従業員が守っているかどうか?」人事担当者には、勤怠チェックをおこなう義務があります。
基準を大きく超えた労働時間を強いられた従業員は、心身ともに健康を損なうおそれがあり離職してしまうリスクも考えられます。人事担当者が勤務状況をチェックし、基準を超えた従業員やその上司に対して「なぜ時間超過しているのか」など相談を持ち掛ければ、未然にトラブルを防げるでしょう。
関連記事:勤怠管理とは?目的や方法、管理すべき項目・対象者など網羅的に解説!
2. 勤怠管理における法律上のルールと注意点

勤怠管理をする上で、法律を守ることは最も大事なポイントです。万が一、労働基準法に抵触する事態にならないためにも、おさらいしていきましょう。
2-1. 働く時間にまつわるルール
雇った従業員に労働させる場合には、労働基準法第32条において定められた「労働時間」を守る必要があります。第32条には、以下の項目が記されています。
1日8時間、1週間40時間が、法定労働時間(法律で定められた労働時間)の限度です。40時間を超えた場合は、残業としてみなされます。
2-2. 残業時間にまつわるルール
残業は、給与を支払うなら「何時間でも時間超過してよい」というわけではありません。36協定という労働者と結ぶ協定によって、時間外の労働や休日出勤は制限がかかっています。ポイントは以下の点です。
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間である
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合、以下の時間以内とする必要がある
時間外労働・・・年720時間以内
時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間
- 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
- 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断される
現在は、働き方改革の影響によって法令遵守が重要視されており、残業時間をキープする企業も多いです。どうしても残業が必要なときは、上司に申請した上で残業する社内ルールを導入するとよいでしょう。
※36協定の上限時間に関しては『特別条項』があり、臨時的、一時的な”特別な事情”が発生した場合のみ上限時間を延長することが可能となります。
関連記事:『法律改正で変わる勤怠管理・2019年度より改正された労働基準法を徹底解説‼』
3. 勤怠管理をおこなう方法とは
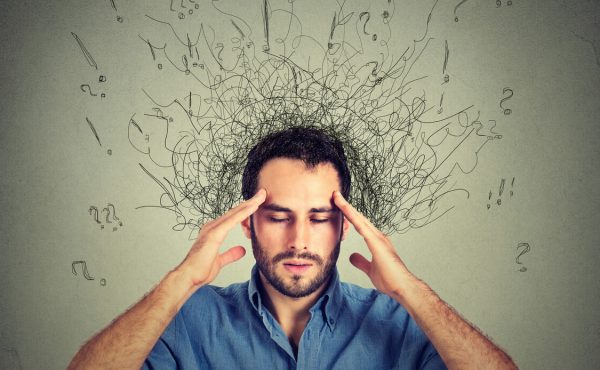
勤怠管理の方法を3つ紹介します。会社にどの管理方法がマッチするか、参考にしてください。
3-1. 人事担当者が出勤簿をチェックする
勤怠管理には、用意した出勤簿に従業員一人ひとりが出勤退勤時間を記入し、それを人事担当者がチェックをして管理するという管理方法があります。勤務中は、部署ごとの使用者が従業員の労働時間を確認し、出勤簿にその日の労働時間を記します。
この方法では正確な勤務時間を計算できますが、チェックするためにはそれなりの時間と労力が必要です。人事担当者が確実にチェックできることが前提であり、従業員数の少ない会社におすすめの方法です。
3-2. タイムカードを使用した勤怠管理方法
こちらは、従業員にタイムカードで打刻をさせて勤怠状況を管理する方法です。タイムカードを機械に通すだけで従業員の出勤・退勤・休憩時間の記録がとれます。人事担当者や従業員は打刻時間を確認するだけで1日の労働時間を計算できるので、従業員と管理者双方の手間が少なくて済みます。
ただし、タイムカードによる打刻は、正確な労働時間のチェックが難しいといった側面を持っています。打刻の瞬間を確認していれば別ですが、確認していなければ不正打刻や改ざんが容易にできてしまうのです。
関連記事:勤怠の改ざんが発覚!不正予防と対処法について徹底解説
3-3. 勤怠管理システムを使用する
人事担当者の手作業によって勤怠状況を管理することが困難な場合、勤怠管理システムを導入することをおすすめします。タイムカードなどで勤怠状況を目視で確認する方法では、不正があってもそれを見逃してしまう可能性があります。従業員数が多ければ多いほど正確なチェックは難しく、またチェックに必要な時間と工数は増える一方です。
勤怠管理システムでは、AIが従業員の勤務状況を自動でチェックしてくれるので、正確に勤怠状況を管理しつつミスの防止にもつながります。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
4. 社内で導入する勤怠管理のルール例


それでは法律上の観点から注意すべきルールを確認したうえで、具体的にどのような勤怠管理のルールに落とし込むべきなのか例を紹介します。
4-1. 出勤打刻のルール
従業員は出勤時に打刻や出勤時間の申告をする必要があります。法律上、始業時間とは使用者の指揮命令下に入った時刻(労働を開始した時刻)を指します。したがって、出勤時には会社に到着次第速やかに打刻を行うべきです。ただし、始業時間前に制服の着替えやラジオ体操がある場合、そのルール設定が重要です。例えば、制服の着用が必須な場合、その着替え時間も労働時間とみなされます。同様に、ヘルメット着用など業務に直接関係する準備も労働時間に含まれます。一方、ラジオ体操が自由参加であれば労働時間には含まれませんが、全員参加が事実上の慣習となっている場合は労働時間に含まれると考えるべきです。これらのルールを明確に設定・運用することで、一貫性と公正さを確保することができます。
4-2. 退勤打刻のルール
退勤時にも必ず打刻を行うことが求められます。業務終了時に直ちに打刻することで、勤務終了時間が明確になり、正確な労働時間の把握が可能となるためです。もし退勤後に上司から急な業務が命じられた場合は、再度打刻を行うか、残業申請書を提出するなどの対応が必要です。不正打刻を防止するために、打刻は必ず本人が行うこと、忘れや誤りがあった場合はすぐに上司に報告するルールを設定することも重要です。訂正が必要な場合には、タイムカードの備考欄を活用し、修正理由を記入することで労働基準監督署の調査時にも迅速に対応できる仕組みを整備できます。従業員の労働時間を正確に把握することは企業の義務であり、これにより適法な労働環境を維持することが求められます。
4-3. 休憩時間のルール
法律で定められた休憩時間を確実に取ることが求められます。休憩時間のルールは労働基準法第34条に明記されており、企業は労働時間が6時間を超える場合45分以上、8時間を超える場合1時間以上の休憩時間を付与しなければなりません。また、休憩時間は原則として一斉に付与する必要があり、労働者はその時間を完全に自由に使える状態であることが求められます。
このため、休憩時間中に電話番や会議などの業務を課すことは違法となります。さらに、休憩を適切にとったかを確認するには打刻で記録することもでき、労働時間と同様に確実な管理が求められます。これにより、勤怠管理におけるトラブルの防止と労務管理の質の向上が期待できます。企業の人事担当者や労務管理責任者は、これらのルールを正確に理解し、実践することが重要です。
4-4. 割増賃金に関するルール
法定労働時間内の労働と法定労働時間外の労働を明確に区別するためのルールを設定しましょう。法定内残業は所定労働時間を超え、法定労働時間の範囲内で労働することを指し、法定外残業は1日8時間または1週40時間を超えた労働を指します。労働基準法により、法定外残業には25%の割増賃金が義務付けられています。
勤怠管理システムにこれらの割増賃金率を設定することで、残業代を自動計算し、適切に給与計算に反映できます。このルールを明確にすることで、適切な勤怠管理が行われ、残業手当の支払いに関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。
これにより、企業は労働法を遵守し、従業員も公正な労働環境で働くことができます。
4-5. 残業時間の上限を定めるルール
残業時間には上限を設け、従業員の過労を防ぐための適切な管理が求められます。労働基準法では、時間外労働の上限が月45時間、年間360時間までと定められており、企業はこれを遵守する必要があります。このため、残業時間がこの上限を超えないようにルールを設定することが重要です。
効果的な管理のために、従業員に対して残業時間の上限を超えた労働を一切認めないルールを設けることが推奨されます。また、残業が避けられない場合は、必ず上司の承認を事前に得るよう指導することが必要です。これにより、計画的な労働時間管理が可能になります。
4-6. 年次有給休暇に関するルール
従業員は年次有給休暇を取得する権利があります。労働基準法では労働者に対し有給休暇を付与することが義務付けられており、1年に10日以上付与される場合は、年5日については使用者側が時季を指定して取得させることが求められています。これは会社の規模を問わず、全企業が守るべき法律です。
従業員が休みたい当日に突然有給申請をする場合、業務の進行に支障が生じることがあります。そのため、多くの企業では有給申請の期限を事前に定めています。具体的には、休暇を取る社員の代替体制が整うまでの所要日数を考慮し、事前に有給申請を行うルールを設定します。これにより現場の混乱を防ぎ、スムーズな業務運営を確保することができます。
4-7. 年間休日日数に関するルール
企業は従業員に毎週少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日を与える必要があります。
労働基準法35条
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
引用:労働基準法35条
労働基準法に則るためには最低年間105日の休日が必要とされていますが、これを超える休日数を設定する企業も少なくありません。法定労働時間で計算すると、年間に働かせることが可能な日数の上限は260日程度です。厚生労働省の調査によると、2021年の労働者1人当たりの年間休日数の平均は115.3日でした。こうしたデータを活用して自社の年間休日数を検討することは、従業員の満足度や生産性の向上に繋がります。したがって、年間休日数を明確にし、従業員全員に分かりやすく提示することは非常に重要です。
4-8. 雇用形態や勤務形態を管理するルール
雇用形態や勤務形態に応じた適切な勤怠管理は、中小企業において非常に重要です。正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど、それぞれの雇用形態に合わせた勤怠ルールの設定が求められます。特に、フレックスやシフト、時短などの柔軟な勤務形態を採用する場合は、その特性に応じた管理方法が必要となります。
まず、各雇用形態や勤務形態に適用される労働法や労働規則を確認し、それに基づいた勤怠管理の要件を把握しましょう。また、テレワークのような変則的な勤務形態に対する出社報告のルールも検討することが重要です。これにより、従業員の働きやすさを確保しつつ、法的な義務を満たすことができます。
特定の雇用形態や勤務形態に不利益が生じないよう、労働環境を柔軟に調整することが求められます。適切な勤怠管理を行うことで、企業全体の効率と従業員の満足度を向上させることが可能です。
5. 勤怠管理をおこなう方法とは


勤怠管理の方法を3つ紹介します。会社にどの管理方法がマッチするか、参考にしてください。
5-1. 人事担当者が出勤簿をチェックする
勤怠管理には、用意した出勤簿に従業員一人ひとりが出勤退勤時間を記入し、それを人事担当者がチェックをして管理するという管理方法があります。勤務中は、部署ごとの使用者が従業員の労働時間を確認し、出勤簿にその日の労働時間を記します。
この方法では正確な勤務時間を計算できますが、チェックするためにはそれなりの時間と労力が必要です。人事担当者が確実にチェックできることが前提であり、従業員数の少ない会社におすすめの方法です。
5-2. タイムカードを使用した勤怠管理方法
こちらは、従業員にタイムカードで打刻をさせて勤怠状況を管理する方法です。タイムカードを機械に通すだけで従業員の出勤・退勤・休憩時間の記録がとれます。人事担当者や従業員は打刻時間を確認するだけで1日の労働時間を計算できるので、従業員と管理者双方の手間が少なくて済みます。
ただし、タイムカードによる打刻は、正確な労働時間のチェックが難しいといった側面を持っています。打刻の瞬間を確認していれば別ですが、確認していなければ不正打刻や改ざんが容易にできてしまうのです。
関連記事:勤怠の改ざんが発覚!不正予防と対処法について徹底解説
5-3. 勤怠管理システムを使用する
人事担当者の手作業によって勤怠状況を管理することが困難な場合、勤怠管理システムを導入することをおすすめします。タイムカードなどで勤怠状況を目視で確認する方法では、不正があってもそれを見逃してしまう可能性があります。従業員数が多ければ多いほど正確なチェックは難しく、またチェックに必要な時間と工数は増える一方です。
勤怠管理システムでは、AIが従業員の勤務状況を自動でチェックしてくれるので、正確に勤怠状況を管理しつつミスの防止にもつながります。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
6. 労働基準法に則った勤怠管理のルールを設定しよう

勤怠管理は従業員の勤務から休憩、欠勤に至るまで、給与計算や労働基準のチェックをおこなう上で必要な業務です。的確なチェックをおこなうためにも、法律上の基準をおさえておきましょう。
勤怠管理には、出勤簿を使用して使用者や人事担当者が細かくチェックする方法やタイムカードでの打刻を使用した方法、あるいは勤怠管理システムを使用して管理する方法があります。それぞれメリット・デメリットがあるので、自分の会社にマッチした方法で管理しましょう。
勤怠管理システム提供会社が徹底解説!
働き方改革による業務効率化やDX化を背景に、クラウド型勤怠管理システムを利用する企業が増加しています。
しかし、システムといっても「そもそもどんなもので、何ができるの?」とイメージがつかない方も多いでしょう。
そこで当サイトでは、勤怠管理システムとは何か、どのようなことができるのかやシステムの選び方までを解説した「勤怠管理システム導入完全ガイド」を無料で配布しております。
「システムが便利なのはなんとなく分かるけど、実際にどのようなことができるのかを見てみたい」という方は、こちらからガイドブックをダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25